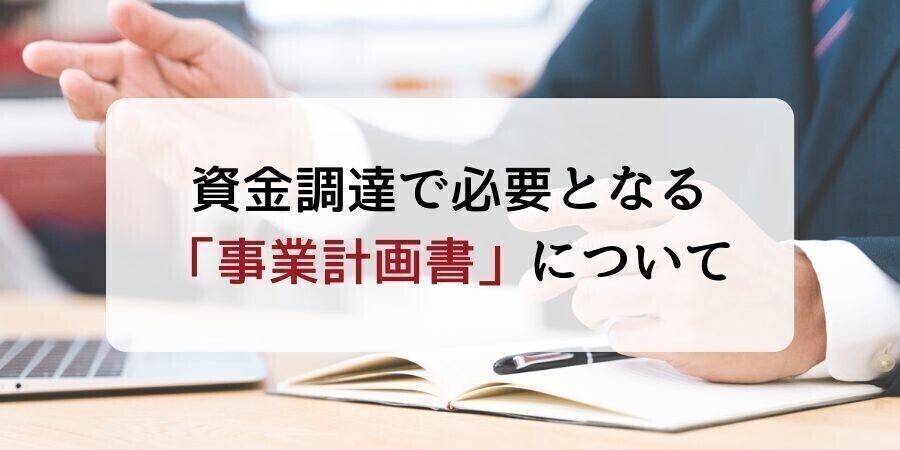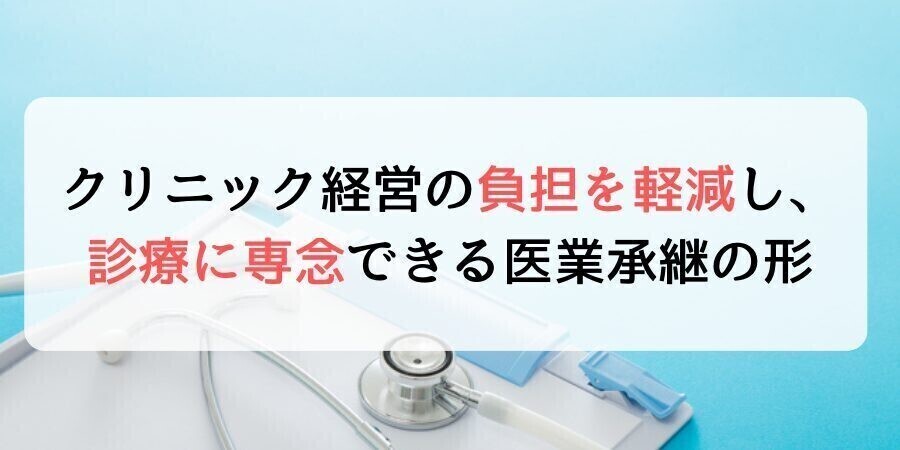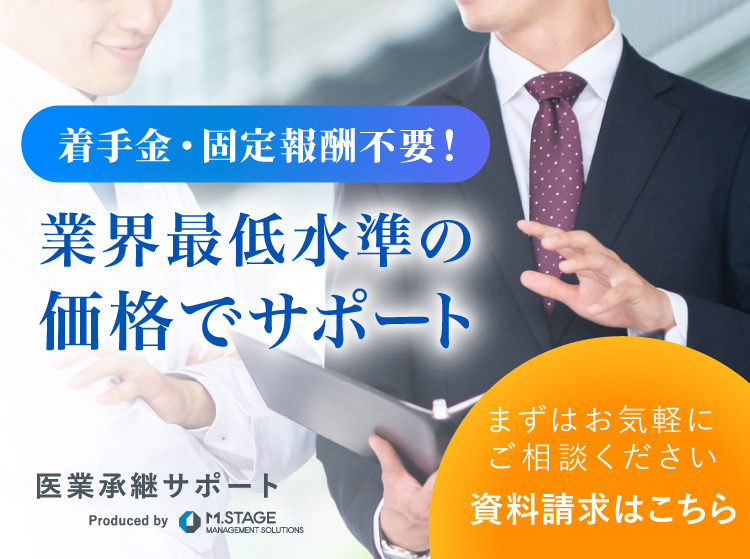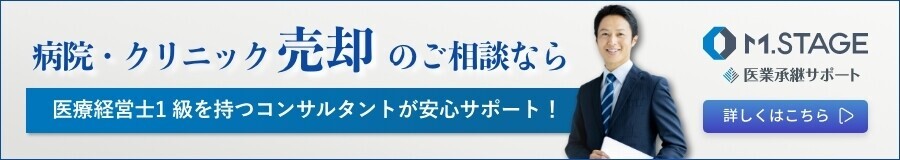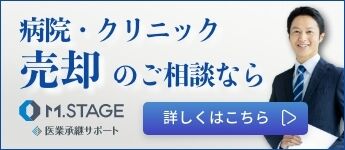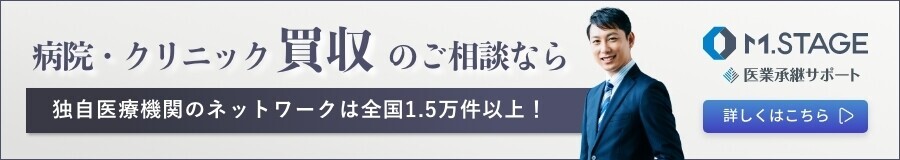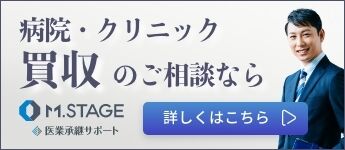診療所・病院の売却における譲渡価格の決め方
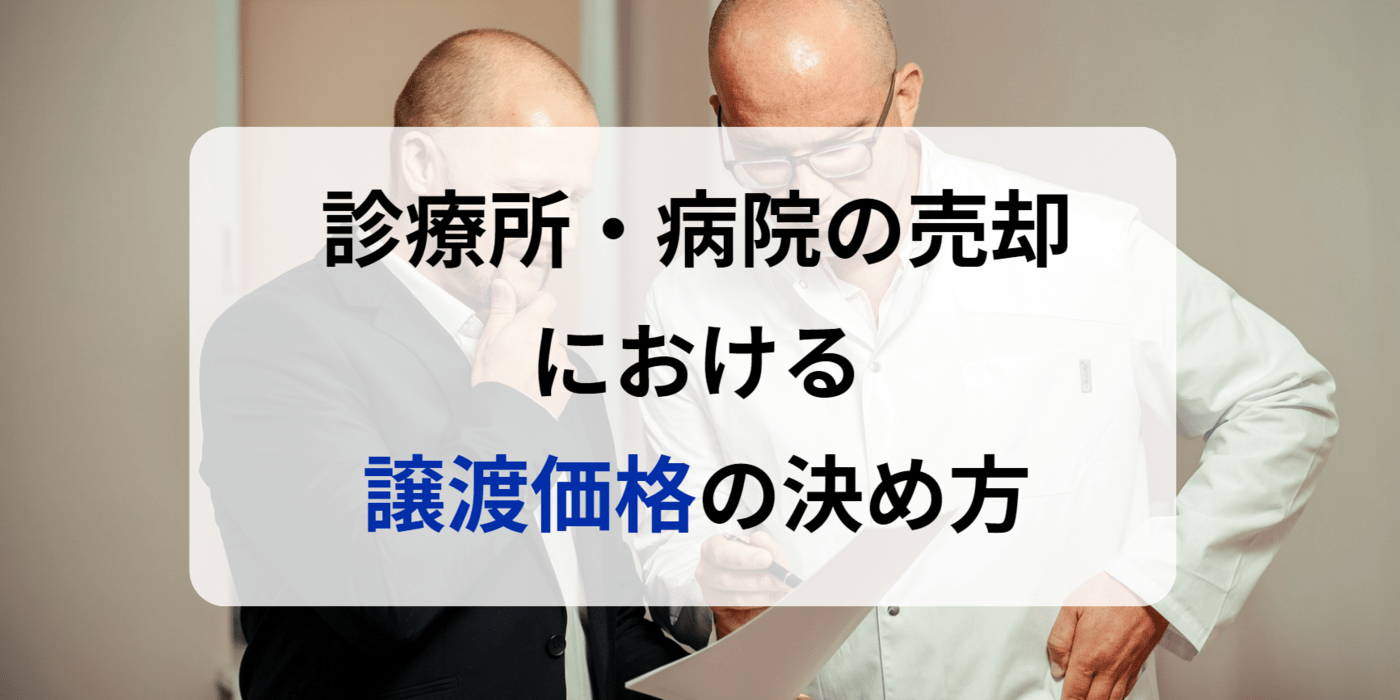
目次
医療機関のM&Aにおける譲渡価格の決定は、一般企業のM&Aと基本的に同じプロセスです。まず、医療機関の価値をバリュエーションにより算定し、その後、売り手と買い手の事情を考慮して最終的な譲渡価格を決定します。評価方法には、資産に着目するコストアプローチ、市場価格を基にするマーケットアプローチ、収益予測から逆算するインカムアプローチがあります。小規模な医療機関では時価純資産+営業権方式がよく用いられます。
本記事では、それらの概要を確認し、代表的な方法である「時価純資産+営業権」方式の内容について詳しく説明していきます。
病院・クリニックの承継をご検討中の方はプロに無料相談してみませんか?
エムステージグループの医業承継支援サービスについての詳細はこちら▼
診療所・病院の譲渡価格を決める基本の考え方
医療機関のM&Aにおける譲渡価格の決定プロセスは、一般的な営利企業(株式会社)のM&Aの場合と基本的に同じです。
もちろん、医療業界ならではの収益構造など注意すべき要素はありますが、譲渡価格算定のロジックそのものが営利企業のM&Aと大きく異なるわけではありません。その譲渡価格の決定プロセスは、大きく2段階に分けられます。
第1段階は、譲渡対象となる医療機関あるいは医療法人などの価値を算定することです。これは「価値算定」あるいは英語で「バリュエーション」と呼ばれます。(株式会社のM&Aの場合は、「企業価値算定」と呼ばれるものです)。
バリュエーションが算定された上で、そのM&Aにおける売り手と買い手の個別事情が反映されて、最終的な譲渡価格を決めるのが、第2段階となります。
譲渡価格を決めるためのバリューション(価値算定)
M&Aにおいて企業の価値を評価する方法については、企業の何に着目して評価をするのかによって、「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」の3つの方法が確立されています。
これらは医療機関にも通用するものですので、それぞれを簡単に見ていきましょう。なお、記述を簡素化するために、以降は「譲渡されるのは医療法人」という想定で説明しますが、法人化していない個人経営の場合であっても考え方の多くの部分は共通です。
1. コストアプローチ(代表は「時価純資産+営業権」方式)
コストアプローチは、売却対象となる資産に着目する方法です。具体的には、貸借対照表の「純資産の部」の金額を基準にしますが、その際に時価評価し直した「時価純資産」を用います。時価純資産については、後ほど詳しく説明します。
また、売り手法人の価値には、貸借対照表に計上されていないものなども含まれます。
それらはまとめて、「営業権」として評価され、時価純資産の価格にプラスされることが一般的です。つまり「時価純資産+営業権」となります。
この「時価純資産+営業権」方式が、コストアプローチの代表的な方式です。理屈がわかりやすく計算も比較的シンプルなため、小規模から中規模のM&Aでよく用いられる方法です。
2. マーケットアプローチ
マーケットとは、株式市場やM&A市場のことです。
株式市場に上場されている企業は、「市場で形成される株価×発行済み株式数」で、企業価値を客観的に算定することができます。
そこで、M&Aの被買収企業と同業の上場企業の、それぞれ共通の経営指標数値(営業利益やEBITDA(※)など)を比較し、その倍率を上場企業の株価に比準させて、被買収企業の価値を算定する方法がよく用いられます。(EBITDA=利子・税・減価償却費控除前利益)
また、M&A市場において、過去に行われた同業・同規模企業のM&A事例における譲渡価格を参考にする方法も、マーケットアプローチと呼ばれます。ただし、医療法人の場合は上場企業が存在しないため、上場企業との比準は困難です。
3. インカムアプローチ
インカムとは、事業から得られる収益のことです。
通常、M&Aにおける買い手は、将来に得られるはずの収益を期待して買収を行うので、その期待収益のキャッシュフローから逆算して譲渡価格を算定しようというアプローチです。
具体的には、将来の5年程度の期間にわたって得られると予測されるフリーキャシュフローを算定し、それを現在価値に割り引いた金額を基準にして企業価値を算定するDCF(ディスカウント・キャッシュフロー)方式が代表的です。
将来の予想収益を算定の基準にしますので、それが比較的安定していると思われる場合に用いられます。考慮しなければならない仮定が多く、計算が複雑になるため、比較的大規模なM&Aで用いられることが多い手法です。
医療機関では、「時価純資産額+営業権」方式が用いられることが多い
1~3の方法は、アプローチが違うだけで排他的なものでありません。そのため、実際には複数の方式で譲渡対象の価値を算定して、より妥当な譲渡価格を推定しようとすることもあります。
一般的な診療所や、比較的規模が小さな病院・医療法人などの場合は、1のコストアプローチ、「時価純資産額+営業権」方式が用いられる場合が多いでしょう。
そこで、以下では、よく用いられている「時価純資産額+営業権」方式を詳しく解説していきます。
「時価純資産額+営業権」方式の計算①資産を確認する
最初に、計算書類(決算書)の貸借対照表に基づいて資産額の評価を行います。
貸借対照表の「資産の部」に計上されている資産を確認します。医療法人なら当然決算書を作成していますが、個人事業でも青色申告をしている方なら、原則として貸借対照表を作成しているはずです。
診療所か病院かによって多少違いはありますが、下記のような資産が計上されていることが多いでしょう。
- 現金・預金
- 事業未収金
- 棚卸資産(医薬品、診療材料等)
- 不動産(土地、建物)
- 車両
- 医療機器
- リース資産
- ソフトウェア
- 差入保証金
一方、「負債の部」には、通常、下記のような科目が計上されています。
- 事業未払金
- 未払費用
- 預り金
- 短期・長期の借入金
そして、「資産の部」に計上されている資産額から、「負債の部」の負債額を差し引いた差額が「純資産の部」です。この純資産の部の金額は、決算期末時点でその医療機関が保有している純粋な財産額ということになります。
「時価純資産額+営業権」方式の計算②貸借対照表を洗い直して、時価純資産を求める
貸借対照表は、必ずしもその時点での資産の実態を正しく表しているわけではありません。
その理由の1つは、「簿価」で計上するという会計ルール自体が、実態を正確に表すものになっていないということ、もう1つは、資産・負債が会計ルール通りに正しく計上されているとは限らないということです。
そこで、貸借対照表の内容をチェックして、現時点での正しい評価額に洗い直します。
会計ルールの「簿価」と資産価値を評価する際の「時価」との違い
会計ルールにしたがって、会計帳簿や決算書に記載されている資産価格を、「簿価」といいます。
一方、「時価」は、仮に現時点で、その資産を買ったとしたら、いくらになるのかという「再調達価格」で表される価格です。M&Aでは、売買する時点での時価ベースで、正確に資産が評価されなければなりません。
しかし、貸借対照表に計上されている資産には、簿価と時価とに乖離が生じているものも多数あります。
例えば、会計ルールでは、土地などの資産は取得原価(購入時の価格など)で計上されることになっています。何十年も前に購入した土地でも、その購入時の価格で計上されているということです。そのため、現時点での評価額(時価)と大きな乖離がある場合があります。
また、建物や医療機器などは、利用期間に応じて購入時より価値が減っていきます。会計上は、その価値の減少を「減価償却」という操作によって帳簿に反映させるルールがあります。しかし、その減価は必ずしも市場価格の減価通りではないので、やはり時価との乖離が生じます。
さらには、将来受け取る未収金や将来に支払う未払金などの場合は、将来価値と現在価値とに乖離があるため、金利を考慮して現在価値に割り引く必要があります。
簿外債務などを調整する
負債の部においては、将来確実に支払わなければならない退職給与債務や、賞与債務などが簿外債務になっていることが、しばしば問題になります。
将来確実に支払わなければならない「債務性」を持つ項目は、本来は預金等で資金準備をする一方、引当金という負債項目として、貸借対照表に計上しておかなければなりません。
ところが、そのような債務が存在するにもかかわらず、実際には引当金が計上されていないことがよくあります。これを「簿外債務」といいます。M&Aにおいて簿外債務は将来、買い手が負担しなければならない債務となるため、正しく貸借対照表に計上して価値評価の対象としなければなりません。
時価貸借対照表を作成する
以上のように、M&Aの譲渡価格算出においては、貸借対照表をベースとしながら、実態との乖離をもたらすさまざまな論点を洗い出して確認・修正します。
そして現時点での正確な資産の価値がわかる「時価貸借対照表」を作成し、時価純資産額を算出します。
この時価純資産額が、M&A時点で、帳簿上に記載されている資産の価値ということになります。
債務超過の場合は、純資産はゼロと評価される
なお、経常収支のマイナス(赤字)が長年続いている医療機関の場合、「負債の部」の金額が「資産の部」の金額を上回り、結果として純資産の部の金額がマイナスになっていることがあります。このような状態を、「債務超過」といいます。
債務超過の場合、実態としては、買い手が売り手の負債を肩代わりするというイメージなので、譲渡価格を求める際の純資産の評価は、通常「ゼロ」となります。
「時価純資産額+営業権」方式の計算③営業権(のれん代)を算定する
以上で時価純資産額についてはわかりました。次は「営業権」について説明します。
営業権(のれん代)とは、貸借対照表には計上されない「収益を生む要素」
時価純資産額は、貸借対照表に計上されている資産の時価を表すものです。診療所や病院はそれらの資産を用いて業務を行い、収益を生んでいます。
しかし、診療所や病院が収益を生むために用いている資産は、貸借対照表に計上されているものだけではありません。
例えば、地域に長年根付いて活動してきたことによる信用や知名度(ブランド力)があることや利便性の高い立地であること、難度の高い症例を扱ってきた医師の技術、スタッフの採用や教育ノウハウ、すでに患者さんがついていること(カルテがあること)などです。これらはすべて、収益を生む源泉になっていると想定されますが、貸借対照表には計上されていません。
このように、貸借対照表には計上されていないけれども収益の源泉になっていると想定される要素は「無形資産」と呼ばれます。そして、無形資産の価格を表すものとして「営業権」という考え方が用いられます。なお、営業権は、「のれん代」と呼ばれることもあります。
M&Aにおいては、無形資産も重要な価値を持つものとして評価します。それを譲渡価格に反映させるべく、営業権の金額を時価純資産額にプラスするのです。
営業権の算定でよく用いられる年買法(年倍法)
営業権をプラスする際に問題となるのがその評価額です。ブランドやノウハウといった要素は、貸借対照表に計上されている不動産や設備のように、その評価額を客観的に測定することが難しいものです。
そのため、実際のM&Aでは通常、営業権を厳密に評価しようとすることは行われていません。実務上、よく用いられている営業権の評価方法は、「年買法」(または「年倍法」)という考え方です。
これは、「標準経常利益」をもとにして、その2年分とか3年分という具合に、倍数化した数値を営業権の評価額とするものです。標準経常利益とは、利益調整(節税など)のために用いられることが多い役員報酬額や、減価償却費などを調整した経常利益です。つまり「節税などを考えなければ、これくらいの利益になるはずだ」と想定される金額です。
年買法において、営業権を標準経常利益の何年分にするのが妥当なのかという点については、慣習的に数年(1~5年)程度が用いられることが多いようです。
買収側の立場からすると、営業権に対する投資を、将来得られる標準経常利益で回収していくことになります。その投資回収期間が何年であれば投資が妥当であるかという視点から、営業権を標準経常利益の何年分と評価するかを考えます。
最後の段階で、売り手と買い手の個別事情が反映される点
以上、「時価純資産額+営業権」方式の場合の、価値算定(バリュエーション)について、見てきました。このような算定によって求められた価格は、標準的な「相場価格」と言い換えてもいいでしょう。
相場価格は基準になりますが、それだけで譲渡価格が決まるわけではありません。相場を基準としながらも、最終的には、売り手と買い手それぞれの個別事情が反映された譲渡価格が決定されるのです。
例えば、複数の買い手候補がいる状況で、ある買い手に「そのエリアでどうしても病院が欲しい」という強いニーズがあれば、相場よりも高い買収価格を支払ってでも譲り受けることもあるでしょう。また、売り手の事情で、どうしても1か月以内にM&Aを実現したいという希望があったとします。
すると、価格よりも時間が優先されるので、相場よりも低い価格で譲渡されることになる可能性が高くなります。極端にいえば、「買い手の先生を気に入ったから、安く譲ってもいい」といったことも、実際にあるのです。
譲渡価格決定の事例1
九州のWE美容整形クリニックを経営する院長は、期日までにクリニックが入っているビルとのテナント契約を解約しなければなればならないという事情で、売却を急いでいました。そのため、時間を優先して相場よりも低い価格での売却を提示しています。その代わり、M&Aが途中で破談にならないように、買い手には違約金を求めるといった形で負担のバランスを取り、無事にM&Aが成功しました。
譲渡価格決定の事例2
首都圏にあるCP泌尿器科クリニックは、主要駅前の一等地に建つビルに入居していたことから、患者が絶えませんでした。しかも家賃が相場よりも格安という好条件でした。そのため、院長は相場よりもやや高い価格での売却を希望していました。一方、買い手となった医師は、ご家族の事情からその地区での開業を望んでいました。クリニックの経営環境が良いことも理解されて、売り手の院長が希望する価格での譲渡が実現しました。
譲渡価格の見積もりに注意
自分のクリニックや病院がいくらで売れるのか、気になった場合はM&A仲介会社に依頼をすれば概算の見積もりを出してもらえます。その価格が高ければ、売り手としては嬉しいでしょう。
しかし、注意しなければならないのは、必ずしも、見積価格が高ければ良いというわけではないという点です。
上の項目での説明した通り、売却価格は、最終的には売り手と買い手が合意するところで決まるもので、M&A仲介会社が決めるわけでありません。いくらM&A仲介会社が高い価格を提示しても、実際にその価格に買い手が納得しなければ絵に描いた餅です。
しかし、M&A仲介会社の中には、契約を取りたいばかりに、非現実的な高値を見積もるケースも存在します。
M&A仲介会社が提示する価格に合理的な根拠があり、実現可能なものなのかを知るためにも、可能であれば、複数社に見積もりを依頼することをおすすめします。
診療所・病院の譲渡価格は専門家に相談して決めることが大切
M&Aのような相対取引(市場を介さずに、売り手と買い手が直接交渉して価格を決める取引)においては、最終的には売買価格は当事者の合意によって自由に決められます。
しかし、M&Aは経済合理性に基づいて行なわれる取引であるため、売り手と買い手のどちらかが、自分にだけ有利になるように相場から大きくかけ離れた価格を希望しても、売買の実現が遠のくだけです。
だからこそ、相場価格を推定するための価値算定が重要になるのですが、医療経営者の皆様がご自身でその算定をするのは困難でしょう。
そこで、「自分の診療所、病院はいくらくらいが相場なのだろうか」と気になる方は、医療機関専門のM&A仲介会社である株式会社エムステージマネジメントソリューションズに、お気軽にご連絡ください。無料で、譲渡価格の見積もりを実施いたします。
▼エムステージの医業承継支援サービスについて
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。医療経営士1級。医業承継士。医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。これまで、病院2件、診療所30件、介護施設2件の事業承継M&Aをサポートしてきた。エムステージグループ内のM&A戦略も推進している。