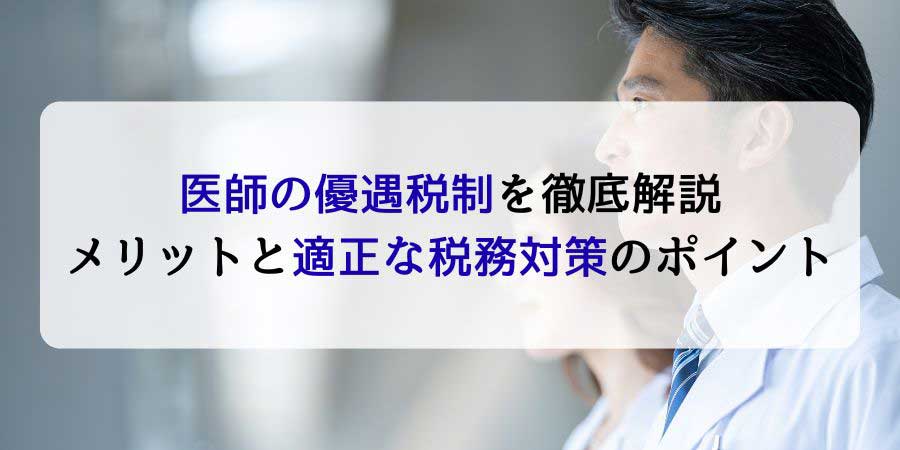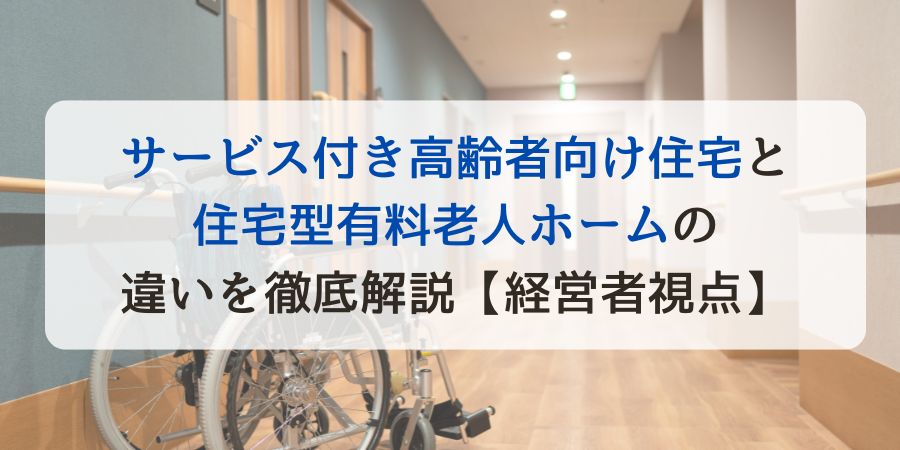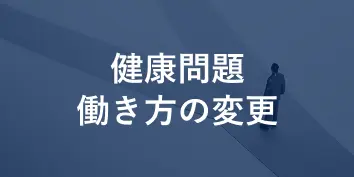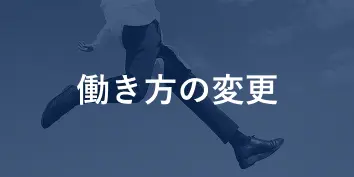クリニックにおける特定承継人とは?一般(包括)承継人との違いも解説
承継人との違いも解説-1.png)
目次
医業承継において、買い手は「特定承継人」または「一般(包括)承継人」のいずれかの立場で承継します。
個人クリニックの承継では、特定承継人として一部の資産や契約関係のみを引き継ぐケースが一般的です。一方で医療法人の承継では、一般承継人としてすべての権利義務を包括的に引き継ぐケースもあり、違いがわかりにくくなっています。
本記事では、医療業界のM&Aを専門とした「エムステージマネジメントソリューションズ」が、特別承継人と一般承継人の概要から、それぞれの違いや具体的な手続き、医療分野特有の注意点について詳しく解説します。
特定承継人とは
まずは、一般的なM&Aや相続における、特定承継人と一般承継人の概要を解説します。特定承継人とは、事業や財産の一部を選んで譲り受ける人や法人のことです。会社の事業譲渡や資産の売買などで、特定の権利だけを個別に譲り受ける側が「特定承継人」となります。
たとえば、ある会社の建物や設備など、必要な資産だけを選んで譲り受ける場合に該当します。この場合、承継する資産や権利は個別に選択が可能で、すべての債務や契約を引き継ぐ必要はありません。
一般(包括)承継人とは
一般承継人(包括承継人)とは、事業や権利・義務の「すべてを一括して引き継ぐ」人や法人のことです。会社の合併や相続など、資産だけでなく債務も含めてすべてを包括的に承継する場合に「一般承継人」となります。
最も身近な例が相続です。親から子への相続では、預貯金や不動産といった資産だけでなく、住宅ローンなどの「負の資産」も含めてすべてを包括的に承継します。
相続人は原則として、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなければなりません。ただし「相続放棄」の手続きを行えば、プラスもマイナスも含めたすべての相続を拒否することは可能です。
M&Aにおいても、株式譲渡によって会社そのものを取得する場合には、その会社が持つすべての権利義務を引き継ぐため、一般承継人としての承継となります。
特定承継人と一般(包括)承継人との違い
事業や財産を承継する側は「特定承継人」と「一般承継人(包括承継人)」の2つにわかれます。相続をする場合には基本的には一般承継人に該当し、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべてを包括的に引き継がなければなりません。
ただし遺言書などで財産が振り分けられている場合には、特定承継人となる場合もあります。一方で会社の事業承継では、承継する対象によって特定承継人か一般承継人どちらかになります。
| 相続の場合 | 会社や事業承継の場合 | |
| 一般承継人(遺言書の内容によっては特定承継人) | 合併や株式譲渡 | 資産や事業譲渡 |
| 一般承継人 | 特定承継人 | |
一般承継人と特定承継人では、引き継ぐ権利や義務の範囲に大きな違いがあります。
ここでは、それぞれの承継方法について、具体的な違いを解説していきます。
承継可能な権利の範囲
特定承継人と一般承継人では、承継できる権利の範囲が大きく異なります。特定承継人は、承継する際に権利の選択ができます。
たとえば事業用の建物や設備など、必要な資産だけを選んで引き継ぐことが可能です。つまり「この資産は引き継ぎたいが、この債務は引き継ぎたくない」といった選択もできます。
一方で一般承継人の場合、原則としてすべての権利を一括して引き継がなければなりません。相続を例にすると、プラスの財産だけを相続して借金は相続しないということはできません。
企業における経営権の譲渡でも同様に、その会社が持つすべての権利を包括的に承継することになります。
| 特定承継人 | 一般承継人(包括承継人) |
|---|---|
| 承継する資産や権利を選択可能 | すべての資産や権利を包括承継選択はできない |
承継時の義務の範囲
特定承継人と一般承継人では、引き継ぐ義務(債務や責任)の範囲も大きく異なります。特定承継人は、義務についても選択して承継ができます。
たとえば、事業用の借入金は引き継ぐが、ほかの債務は引き継がないといった選択も可能です。しかし、特定承継人が返済可能な資産や能力を持っていないと、債権者にとってはリスクが高くなります。
そのため特定承継人が債務などを引き継ぐ場合には、債権者の同意も必要です。一方で一般承継人の場合、義務もすべて包括的に引き継がなければなりません。
相続では借金なども含めて一括承継となり、会社の経営権譲渡でも、その会社が負う債務や契約上の義務をすべて引き受けることになります。
| 特定承継人 | 一般承継人(包括承継人) |
|---|---|
| 承継する債務や権利を選択可能債権者の同意が必要 | すべての義務を包括承継 |
▶特定承継人・包括承継人の違いを踏まえた親族内承継の進め方を確認する
承継人と相続人の違い
特定承継人や一般承継人をまとめて表現される「承継人」と「相続人」という2つの言葉があり、事業を譲り受けたり相続をしたりする人にとっては非常に難解だと思われます。
ここでは、それぞれの明確な定義の違いを解説しましょう。
まず「相続人」とは、被相続人(故人)の権利・義務を法定相続人として引き継ぐ立場の人のことです。民法で定められた血族関係にある人が自動的に相続人となり、意思表示がなければ当然に相続が発生します。
ただし、相続放棄という形で相続自体を拒否することは可能です。一方で「承継人」とは、会社や事業の権利・義務を引き継ぐ人のことです。たとえば、親が経営していた飲食店を「もう歳だから引退したい」という理由から、子どもに譲渡をする場合、子どもは「承継人」となります。
これが、親が亡くなって子どもが飲食店を承継する場合、子どもは「相続人」となります。つまり「相続人」は亡くなった方から相続をする人が該当し「承継人」は、相続人も含んだ広い定義として使用されている言葉です。
| 承継人 | 相続人 |
|---|---|
| 権利や義務を引き継ぐ人 | 亡くなった方から権利や義務を引き継ぐ人 |
医院継承(医業承継)における特定承継人と一般承継人のケース
医療機関のM&Aは、一般的な企業のM&Aとは大きく異なります。医療業界特有の法規制や制度によって、承継の方法や手続きが厳格に定められているためです。特に医療機関の開設者を変更する場合は、保健所への届出や保険医療機関の指定など、特有の手続きが必要となります。
このような医療業界特有の規制を踏まえた上で、医院継承における特定承継人と一般承継人のケースについて、具体的に解説します。
個人クリニックの買い手は特定承継人
個人が経営するクリニックを承継する場合、買い手は特定承継人として手続きを進めます。これは個人クリニックの場合、直接開設者の変更は行えず、一度廃院手続きをしてから新規開院の手続きを行うためです。
具体的な手続きとしては、まず売り手の医師が管轄の保健所に廃止届を提出します。そのあと買い手の医師が新規開院の届出を行い、保険医療機関の指定を受ける流れです。従業員との雇用契約も新たに結び直す必要があり、医療機器や設備なども個別に契約を結んで引き継ぎます。
個人クリニックの承継では、一度すべての契約関係をいったんリセットするため、必要な資産や契約関係を選んで引き継ぐことも可能です。
このように個別に選択して承継を行う形態であることから、個人クリニックの買い手は「特定承継人」として位置付けられます。
医療法人は譲渡内容によって異なる
医療法人のM&Aでは、譲渡する対象によって買い手が特定承継人に該当するのか一般承継人に該当するのかが変わってきます。医療法人そのものを譲渡する場合と、医療法人が持つ個別のクリニックを譲渡する場合では、承継の手続きや引き継ぐ範囲が大きく異なるためです。
それぞれのケースについて、詳しく解説していきます。
医療法人そのものの買い手となる場合は一般承継人
医療法人そのものを承継する場合、買い手は一般承継人となります。この場合、医療法人の経営権を譲渡することで、その法人が持っているすべての権利義務を包括的に引き継ぐためです。
具体的な手続きとしては、出資持分の譲渡や理事長の交代などを行います。既存の医療法人格はそのまま維持されるため、クリニックの廃院や新規開院の手続きが必要ありません。また、従業員との雇用契約や取引先との契約もそのまま継続されます。
一方で、医療法人の債務や責任もすべて引き継ぐことになるため、買い手は承継前のデューデリジェンス(資産状況や契約関係の詳細な調査)が重要です。
特に医院継承(M&A)では、許認可や保険診療の契約関係、医療法人の財務状況など、専門的な知見や重要な調査項目が多く存在します。
「エムステージマネジメントソリューションズ」では20年以上の医師紹介実績もあり、財務や法務の専門家と連携しながら、徹底的なデューデリジェンスを行っています。
思わぬ債務や契約上の責任を引き継ぐリスクを最小限に抑えるためにも、医院継承(M&A)を検討されているのであれば、ぜひ無料相談からお気軽にお問い合わせください。
医療法人が所持しているクリニックの買い手となる場合は特定承継人
医療法人が運営しているクリニックのみを承継する場合、買い手は特定承継人となります。医療法人全体ではなく、その一部のクリニックだけを切り離して承継するためです。
医療法人の持つ事業や契約関係のみを承継するため、売り手の医療法人が廃院届を提出したあと、買い手側が新規で開院する流れとなります。
医療法人が所持しているクリニックを承継する場合には、個人クリニックを承継する場合と同様に下記のような手続きや判断が必要です。
- 従業員との雇用契約は新たに契約を結び直す必要がある
- 施設などの場合は入所者とも新たに契約を結び直す必要がある
- 保険医療機関の指定も新たに取得しなければならない
- リース契約なども個別に引継ぎの判断が必要
- 債務などがある場合には債権者の同意が必要
各種許認可が降りず、開院できないといったトラブルが発生することもあるので、特定承継の場合は特に注意しなければなりません。
関連記事:医療法人内の1つの医院を譲渡する際のスキーム・注意点
医療法人が特定承継人としてクリニックを譲り受ける際によくあるトラブルや注意点
医療法人がクリニックを特定承継する際は、行政手続きの煩雑さや病床の継続使用に関する規制など、複雑な問題が発生します。
以下では、よく発生するトラブルや注意すべきポイントについて、具体的に解説します。
必要な手続きが煩雑
医療法人が特定承継人としてクリニックを譲り受ける場合、一般的な事業譲渡以上に複雑な手続きが必要です。
まず、売り手側は保健所への廃止届の提出や従業員への説明、患者への周知など、クリニックの閉院に向けた手続きを進める必要があります。
一方、買い手側は新規開設届の提出や保険医療機関の指定申請、従業員との新規雇用契約など、新規開院に向けた準備が必要です。
| 売り手側の手続き | 買い手側の手続き |
|---|---|
| 保健所へ廃止届の提出 従業員への説明患者への周知 医療機器や設備の譲渡契約書作成 取引先への通知 医療法人理事会での承認 | 保健所へ新規開設届の提出 地方厚生局への保険医療機関指定申請 各都道府県の許可従業員との新規雇用契約締結 建物・土地の賃貸借契約締結医療機器などの リース契約の新規締結 |
これらの手続きをヌケモレなく進めるためにも、医療分野に精通した専門家のサポートも受けておきましょう。
病床の引き継ぎがスムーズに行かない可能性もある
医療法人に限らず、病床のあるクリニックを承継する場合には、承継後に病床の使用が認められないケースがあるため注意しなければなりません。これは「基準病床数制度」による規制も関係しています。
基準病床数制度とは、地域で必要とされる適切な病床数(基準病床数)を都道府県が算定し、既存の病床数が基準病床数を超える地域では新規の病床設置を制限できるものです。
特に都市部の場合、すでに「病床過剰地域」になっているケースもあります。
クリニックを承継する場合、手続き上は新規開設と変わらないため、基準病床数の規制を受けます。そのため、たとえ承継前の時点で病床を持っていたとしても、承継後に病床の許可が降りない事態に陥ることもあるわけです。
病床のあるクリニックの承継では、あらかじめ地域の病床状況について、管轄の都道府県などに確認や相談も欠かせません。
場合によっては無床のクリニックへの変更も検討する必要もあり、これは収益に大きな影響を与える要因です。「エムステージマネジメントソリューションズ」では「新規開設後の病床の許可は難しい」とされていた地域でも、有床診療所をそのまま承継開業できた実績を持っております。
▶関連記事:【関東×産婦人科】行政上の許可や税務など複雑な論点を専門家チームで解決した医院継承事例
有床診療所の承継リスクについてお悩みでしたら、医療業界のM&Aに精通した私たちにご相談ください。
医院継承(医業承継)における特定承継人と一般承継人の事例
医療継承(M&A)では、承継する資産や権利の範囲によって「特定承継人」と「一般承継人」に分かれます。私たち「エムステージマネジメントソリューションズ」がサポートしてきた事例から、それぞれの特徴がよく表れた2つのケースをご紹介します。
1つ目は医療法人が所有するクリニックを特定承継人として譲り受けた事例、2つ目は医療法人の経営権を一般承継人として譲り受けた事例です。
医療法人が所有しているクリニックを譲り受けた事例
売り手の「医療法人いとう会(仮称)」は内科を中心に複数のクリニックを運営していました。その中の「おおき内科クリニック(仮称)」は管理医師のマネジメントが行き届かず、売上も減少傾向にあったため、医師の交代による立て直しを決意します。
特定承継人となったのは、関東で循環器内科の勤務をされていた40歳の院長、加藤先生(仮名)です。
結果として既存の医師との2名体制で診療を行い、医療事務や看護師は新規採用としました。新規採用の従業員に対しては、承継後のクリニックの体制が整うように、医療法人いとう会の本部で事前研修が行われ、開業までには現場でスムーズな業務が行えるスキルが身についていました。
本案件は医師の交代と職員の刷新により、マネジメント面での改善が実現できた承継です。
関連記事:【関東×内科】医業承継(医院継承)をきっかけにマネジメント面の改善を実現
医療法人の経営権を譲り受けた事例
54歳で理事長の松本先生(仮名)は、近畿地方で150床未満の一般病床がある病院を運営していました。
病院自体は無借金で利益を出していましたが、建物の老朽化や人事制度の未整備などの経営課題を抱えていました。また、子どもがいたものの医師ではなく、後継者となる医師もいない状態で、問題が多く悩んでいたとのことです。
そこで私たちは、全国的に病院経営を展開している医療法人たなべ会(仮称)を買い手(一般承継人)としてご紹介しました。
契約が成立したけっかけは、松本先生は理事長としてそのまま残り、これまでと同額の役員報酬を受け取りながら、診療の継続が可能になったためです。
買い手の医療法人たなべ会は、グループで持っている社労士や弁護士などのリソースを活用して経営課題の解決に注力する形になりました。
一方で理事長の松本先生は、退職金や病院関連会社の株式譲渡による創業者利益を確保しつつ、引き続き診療に専念できる体制が実現できたのです。
医療法人の一般承継により、後継者問題と経営課題の両方を解決できた好事例となりました。
関連記事:【近畿×内科】大手医療法人への医院継承で経営課題と後継者問題を解決
クリニックが特定承継人として事業を譲り受ける場合は専門家のサポートを受けましょう
特定承継人としてクリニックを譲り受ける場合、複雑な手続きが必要となります。保健所への廃業や開業届、保険医療機関の指定申請、従業員との雇用契約の締結など、通常の事業譲渡以上に専門的な知識が必要です。
また、基準病床数制度による規制や都道府県の許認可、医療機器のリース契約の扱いなど、医療特有の手続きも数多くあり、これらの手続きや判断を誤るとスムーズな承継ができず、最悪の場合開業できなくなることもあります。
「エムステージマネジメントソリューションズ」は20年以上の医師紹介実績を持ち、医療経営士の資格を持ったコンサルタントが在籍しているM&Aの専門家です。
医療業界特有の規制や手続きを熟知した専門家が、経営面のアドバイスから行政手続きまで、一貫したサポートをいたします。
クリニックの承継をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。