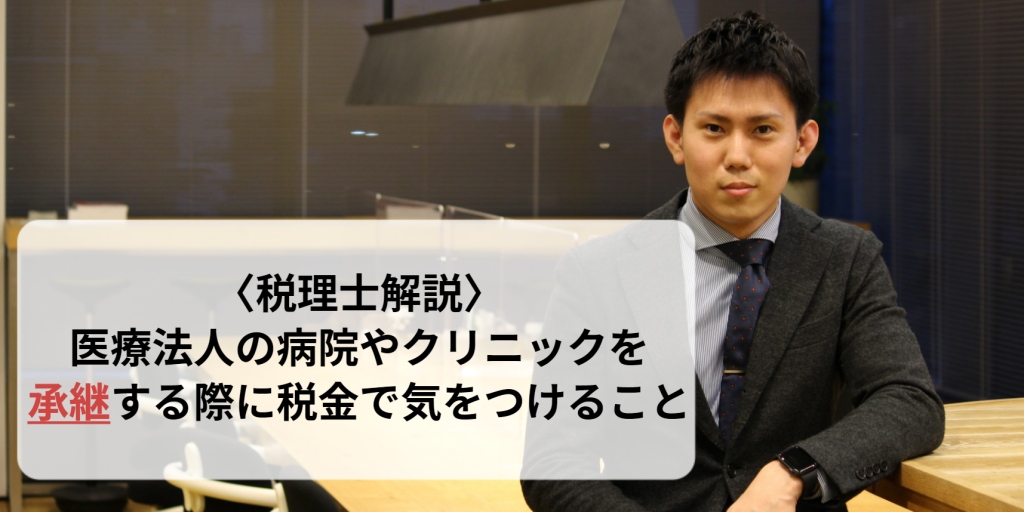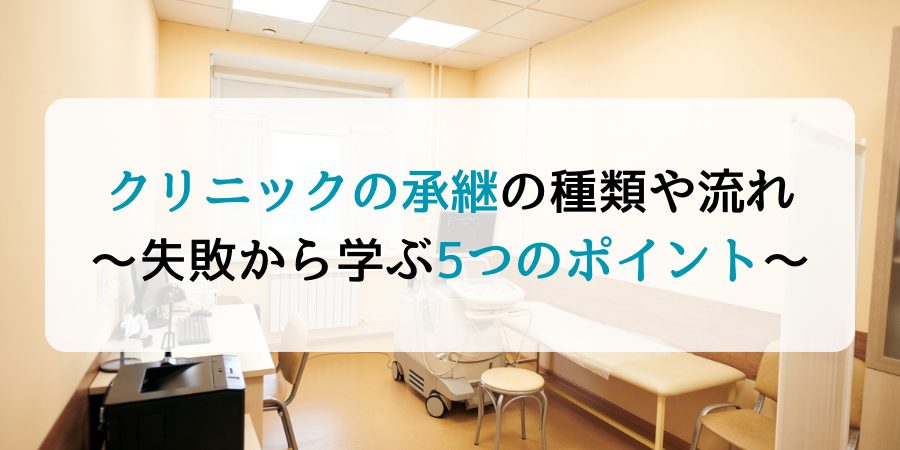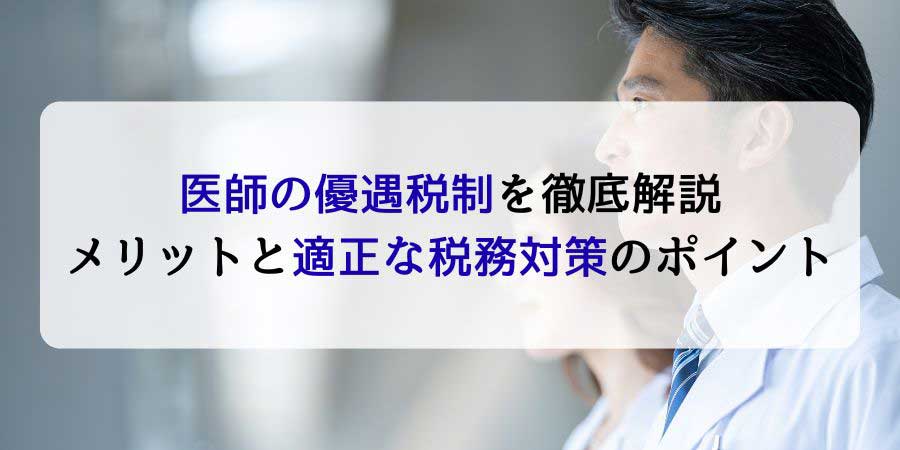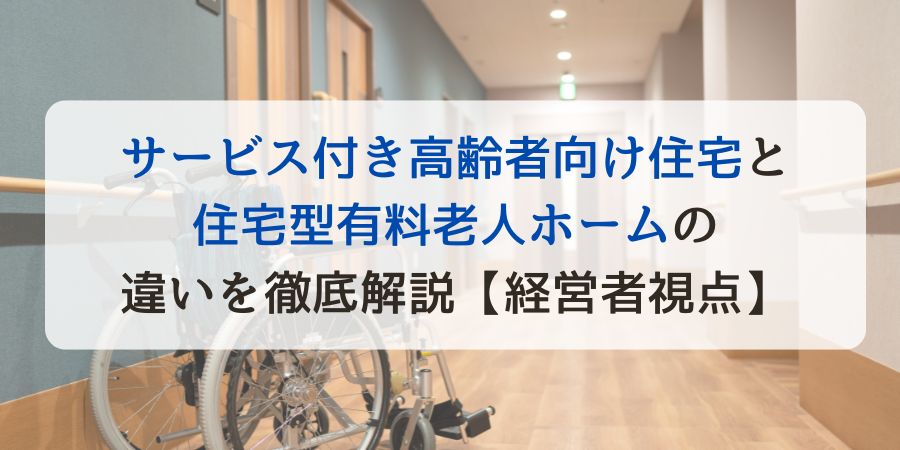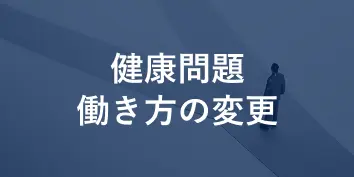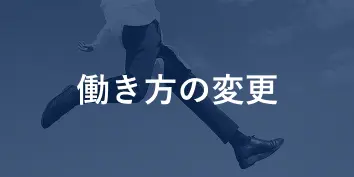出資持分払戻請求権とは?相続における医療法人と相続人の問題点を解説

医療法人の相続について考え始めた際に、必ず向き合わなければならないのが「出資持分払戻請求権」の問題です。出資持分ありの医療法人では、社員の死亡により相続が発生すると、相続人から高額な払戻請求を受ける可能性があります。
このとき、医療法人側は数千万円から数億円の資金調達が必要となり、相続人側も複雑な税務問題に直面します。本記事では、出資持分払戻請求権の基本的な仕組みから、相続が発生した際の医療法人と相続人それぞれが抱える具体的な問題から対策までわかりやすく解説いたします。
医療法人の事業承継や相続対策を検討されている先生は、ぜひ参考にしてください。
出資持分の払戻請求権とは
出資持分の払戻請求権とは、医療法人の社員が退社や死亡によってその資格を喪失した際に、その社員が保有していた出資持分に応じた金額の払い戻しを法人に対して請求できる権利のことです。
出資持分とは、医療法人に出資した金額に応じた財産に対する権利のことで、株式会社における株式に似た性質を持っています。
なお、この権利は「出資持分ありの医療法人」にのみ存在するものです。
平成19年4月以降に設立された医療法人はすべて「出資持分なしの医療法人」となるため、払戻請求権は発生しません。
しかし、平成19年3月以前に設立された医療法人の多くは出資持分ありの医療法人であり、現在でも全国に約4万の出資持分ありの医療法人が存在しています。
医療法人で出資持分払戻請求権が発生するケース
出資持分払戻請求権は、医療法人の社員が「社員の地位を失った」ときに発生します。
主なケースは、社員が退社したり死亡したりした場合です。
それぞれ詳しく解説します。
社員の退社
医療法人の社員が自己都合で退社したり法人から除名されたりなど、自らの意思や事由によって社員の資格を喪失した際に、払戻請求権が発生します。
この際に、元社員は医療法人に対して自身が保有していた出資持分の払い戻しを求めることができます。
社員の死亡(相続)
社員が死亡した場合、原則として社員の地位(資格)は相続されません。
そのため、被相続人である社員が保有していた出資持分は、相続人が「払戻請求権」という形で引き継ぐことになります。
相続人は「払戻請求権」を行使して、医療法人に対して被相続人の出資持分相当額の支払いを請求できます。
出資持分払戻請求権の権利は時効がある
出資持分払戻請求権には時効が存在するため注意しなければなりません。
民法の規定により最大10年が時効期間とされており、時効が始まるのは「権利を行使することができる時」つまり社員が退社した時点からです。
“民法第166条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。”
引用:WIKIBOOKS
特に相続が発生した場合、相続人が出資持分払戻請求権の存在を知らないまま時効が成立してしまうケースもあります。
相続人が出資持分の払戻請求権を行使した際の評価額の計算
出資持分の払戻金額は、医療法人の純資産額をベースに計算されますが、被相続人の出資時期により計算方法が異なります。
被相続人が医療法人の設立当初から出資していた場合
設立当初からの出資していた場合、評価額の計算は比較的シンプルです。
| 【基本となる計算方法】払戻金額 = 相続開始時の純資産額 × 出資持分割合 |
払戻金額は相続開始時点での医療法人の純資産額に、被相続人の出資持分の割合を乗じて算出します。
純資産額とは、医療法人が保有するすべての資産から負債を差し引いた金額のことです。
たとえば医療法人の相続開始時点での純資産額が5億円で、被相続人の出資持分が40%だった場合を考えてみましょう。
この場合の払戻金額は、5億円の40%なので2億円となります。
この2億円という払戻金額は、ほとんどのケースで被相続人が設立時に実際に出資した金額とは大きく異なります。
医療法人が長年にわたって蓄積してきた内部留保や不動産の値上がり、医療機器の増設などにより、法人の純資産額は設立時から大幅に増加していることが多いためです。
被相続人が途中から医療法人に出資していた場合
医療法人が設立されたあとに出資した場合の計算は、設立当初から出資したケースに比べて複雑になります。
この場合、出資時点での法人の純資産額と出資額によって出資持分の割合が決定し、その割合に基づいて払戻金額が計算されます。
たとえばB先生が平成20年に、既存の医療法人に対して1,000万円を出資したケースで考えてみましょう。
出資時点での医療法人の純資産額は3,000万円だったことから、B先生の出資持分は33.3%(1,000万円÷3,000万円)となりました。
その後、B先生は令和6年3月に急逝され、相続が発生しました。
相続開始時点での医療法人の純資産額は9,000万円まで成長していたと仮定します。
| 【平成20年の出資時】 B先生の出資額:1,000万円 出資時の法人純資産:3,000万円 B先生の出資持分:33.3% 【令和6年3月:B先生の逝去で相続発生】 法人純資産:9,000万円 B先生の払戻金額:9,000万円 × 33.3% = 約3,000万円 |
上記の事例では、B先生が1,000万円の出資に対して3,000万円の払戻を受けることになり、2,000万円の含み益を得られる計算です。
社員の相続後に医療法人と相続人が抱える問題
社員の死亡により相続が発生すると、医療法人側は資金繰りの問題が、相続人側は税負担の問題が出てきます。
それぞれ詳しく解説します。
医療法人は出資持分払戻に対する資金繰り問題
医療法人にとって最も深刻な問題は、高額な払戻資金の調達です。
長年の経営によって医療法人の純資産額が大きくなっている場合、払戻請求額は数千万円から数億円にのぼることも珍しくありません。
医療法人はこの支払いを原則として現金で行う必要がありますが、運転資金や設備投資などで手元の現金が不足しているケースも多く、急な高額の支払いに対応できず、資金繰りが著しく悪化するリスクがあるわけです。
最悪の場合、金融機関からの借入れを余儀なくされ、経営の維持が困難になるところも少なくありません。
相続人の3つの税務問題
相続人側も、主に税金に関する3つの大きな問題に直面します。
高額な相続税の発生
出資持分は相続財産として評価され、相続税の課税対象となります。
出資持分の評価額は高額になるケースが多く、それに伴い相続税も高額になり相続人の大きな負担となります。
たとえば出資持分の評価額が5,000万円だった場合、下記の速算表を参考にして計算してみましょう。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
出典:国税庁|相続税の税率
「5,000万円 × 20% – 700万円」という計算になり、今回のケースでは800万円もの相続税が課せられます。
相続税の支払いに対する資金ショート
相続税は、原則として相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付しなければなりません。
しかし、相続した出資持分は払戻請求権を行使したとしても、すぐに現金化できるわけではなく、法人との払戻交渉には時間がかかることもあります。
そのため、納税資金が用意できず、資金ショートに陥るリスクがあります。
相続人も最悪の場合、相続税のために金融機関から借入れなどで納税資金を確保しなければなりません。
出資持分の払い戻しに対する税金の負担
相続人が払戻請求権を行使して支払いを受けた金銭は、税務上「みなし配当」と見なされる部分と「資本の払戻し」と見なされる部分に分かれます。
この「みなし配当」に該当する部分については、配当所得として総合課税の対象となり、所得税と住民税が課されます。
【みなし配当部分】
- 払戻金額から資本等の金額を超える部分
- 総合課税(最高税率55%)
税率は最大で55%にもなり、相続税とは別に大きな税負担が発生します。
医療法人における出資持分払戻請求の対策
出資持分払戻請求権の問題を回避するために、医療法人側ができる対策をいくつか紹介します。
生前贈与を活用する
最も一般的な対策の一つが、生前に出資持分を後継者や親族へ暦年贈与していく方法です。
年間110万円以下の贈与には贈与税がかからないため、計画的に出資持分を移転できます。
ただし、贈与には時間がかかるため、早い段階で計画を立てておく必要があります。
また出資持分の贈与を受けた方も、社員でなければ払戻しを受けられない点に注意です。
後継者も社員に就任させておく必要があります。
関連記事:収入印紙が必要な譲渡契約書は?必要な金額や節税のポイントも解説
持分なし医療法人に移行する
出資持分の概念そのものが存在しない「持分なし医療法人」へ移行することも、根本的な解決策です。
持分なし医療法人に移行すれば、将来的に相続や退社に伴う払戻請求の問題は発生しなくなります。
また、医院継承時の手続きがスムーズになるなどのメリットもあります。
【持分なし医療法人に移行するメリット】
- 出資持分払戻請求権が消滅する
- 相続税の課税負担がなくなる
- 事業承継がスムーズになる
ただし移行には様々な要件を満たす必要があり、一度移行すると元に戻せないなどの注意点もあります。
関連記事:認定医療法人制度の概要|認定要件やメリット・デメリット解説
MS法人を活用する
MS法人(メディカルサービス法人)を活用して、医療法人の純資産額を減らし、出資持分の評価額を下げる方法もあります。
医療法人が保有している高額な資産をMS法人に移転することで、出資持分払戻請求時の負担を軽減できます。
MS法人とは、医療法人の関連会社として設立される営利法人で、医療法人に対してサービスの提供も可能です。
この仕組みを活用することで医療法人の資産構成を調整し、相続時の税負担や払戻負担を大幅に軽減できます。
| 【移転前】医療法人純資産:5億円出資持分評価:5億円 【MS法人設立・資産移転後】医療法人純資産:2億円MS法人純資産:3億円 |
上記のケースでは、医療法人の出資持分評価が2億円に減少したため、払戻請求を受けた際の負担も大きく抑えられます。
関連記事:MS法人とは|設立のメリット・デメリットと活用上の注意点
出資持分払戻請求権に関するよくある質問
ここでは出資持分払戻請求権に関して、よくある疑問点や質問について回答していきます。
特にクリニックの相続に関しては非常にセンシティブな話題ですし、専門的な知識も必要です。
こちらの内容も参考にしながら、必ず専門家にご相談されることをおすすめします。
持分払戻請求権は相続できますか?
はい、相続は可能です。
社員の死亡により出資持分払戻請求権が発生し、この権利は相続人に承継されます。
また、相続人が医師免許を持っていない場合でも、払戻請求権を行使できます
ただし、払戻請求権の行使には時効(10年)がある点に注意してください。
医療法人の出資持分は相続放棄できますか?
相続放棄は可能です。
ただし、出資持分(払戻請求権)だけを選んで放棄はできません。
相続放棄をする場合は、預貯金や不動産など他のプラスの財産も含め、すべての相続財産を放棄する必要があります。
【相続放棄を検討すべきケース】
- 出資持分の相続税負担が他の相続財産を上回る場合
- 医療法人に多額の債務がある場合
- 払戻請求しても実際の回収が困難な場合
【注意点】
- 相続放棄の期限は相続開始を知った時から原則3か月以内
- 一度放棄すると撤回は不可
- 他の相続財産もすべて放棄することとなる
払戻請求権と出資持分の承継はどちらが有利ですか?
どちらが有利かは、相続人の状況や医療法人の経営方針によって異なるため、一概には言えません。
一般的には、医療業界とは無縁だった方が出資持分を相続した場合には、払戻請求権を行使されるケースが多い傾向にあります。
これに関しては、やはり相続人の税負担の大きさが関係してきます。
一方で医療法人の経営に参画していきたいと思っている方の場合は、承継されるケースもあります。
専門家と相談の上、慎重に判断することが望ましいでしょう。
出資持分払戻請求権で経営破綻しないために十分な対策を
出資持分払戻請求権は、医療法人の経営の安定性と相続人の円満な資産承継の両方に関わる重要な問題です。
特に近年は医師の高齢化も進んでいることから、特にクリニックの相続に関しては早い段階の対策も必要です。
自院の出資持分の評価額がどのくらいになるのかを把握し、将来起こりうるリスクを想定した上で、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
私たちエムステージマネジメントソリューションズでも、医療分野に特化したM&A・事業承継の専門家として、様々なサポートを提供しています。
医療法人の事業承継や出資持分の問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お客様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。