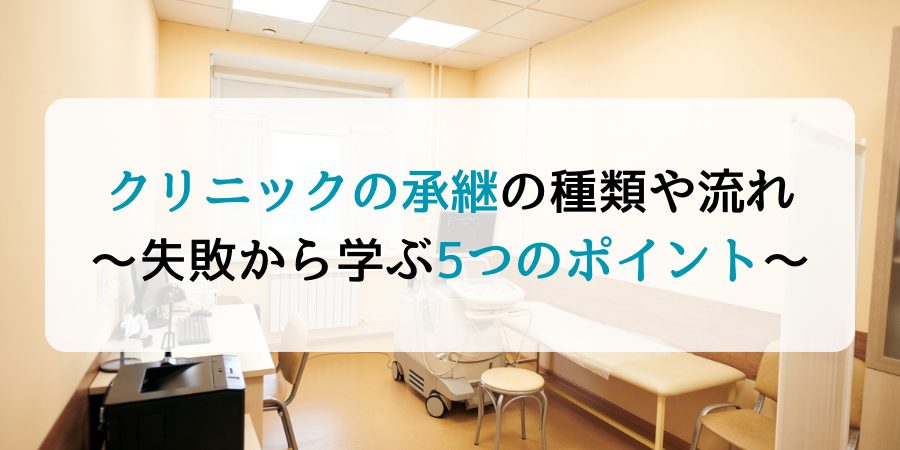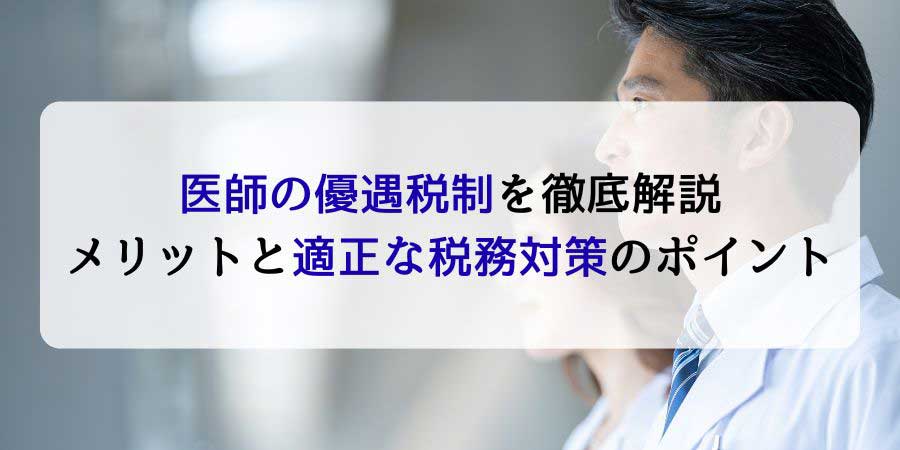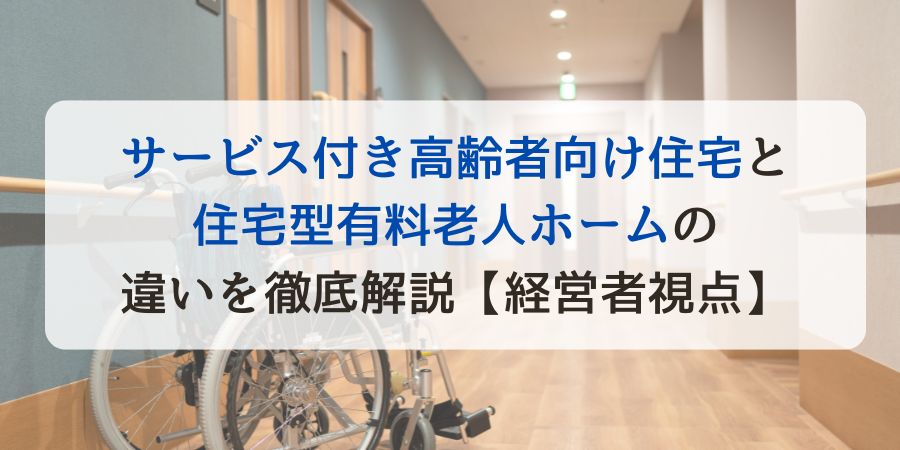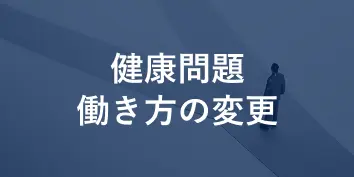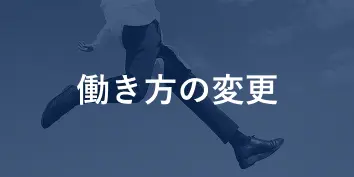クリニックの不動産賃貸に関する注意点!医院継承で注意すべき契約内容も解説

目次
クリニックの開業を成功させるためには、物件選びが極めて重要です。
しかし、一般的な住居やオフィスとは異なり、クリニックの不動産賃貸には専門的な知識が求められるため、注意点を押さえておかないと後々トラブルに発展しかねません。
そこで本記事では、クリニックの不動産賃貸を探す際の注意点について、立地選定から契約書の確認、医院継承(医業承継)のケースも含めて解説します。
本記事を読むことで、不動産賃貸におけるリスクや失敗を避け、円滑なクリニックの開業が実現します。
クリニック開業に向けて不動産賃貸を探す際の注意点
クリニックの開業に向けた不動産賃貸探しは、患者の利便性や競合状況、法的な制約など様々な視点から検討しなければなりません。
そこで、先ずはクリニックの開業で失敗しないために、重要となる8つの注意点について詳しく解説します。
- 診療圏調査を行う
- 患者のアクセスを考慮する
- 周辺の調剤薬局を把握する
- テナント料と収益性のバランスを考える
- 診察可能な時間を確認する
- 建設された年度を確認する
- 看板や広告の制限を確認する
- 同じビル内のテナントの業種を確認する
これらのポイントを考慮し、集患や安定した経営につながる物件を見つけましょう。
診療圏調査を行う
診療圏調査とは、開業しようとしている周辺地域の人口動態や年齢構成、同じ診療科の競合状況などを詳しく分析することです。
開業を検討しているエリアにおいて、見込み患者を算出するために欠かせません。
クリニックを開業する際に「好立地」と呼べる基本的な条件は、需要(医療のニーズ)が供給(医療機関数)を上回っていることです。
たとえば、高齢者が多い地域では内科や整形外科のニーズが高く、子育て世代が多いエリアでは小児科や産婦人科の需要が見込めます。
また「郊外のベッドタウン」と「都市部の駅周辺」によっても、需要の高い診療科目は異なってきます。
診療圏調査を入念に行い、開業しようとしている診療科目がその地域に適しているのか、また集患できるのかを事前に把握することが重要です。
患者のアクセスを考慮する
最寄り駅からの距離や駐車場の有無、バス停からのアクセスなど、患者の通院しやすさはクリニックの集患に直結します。
特に高齢者や子連れの患者が多いと予想される診療科目の場合は、アクセスの利便性がきわめて重要です。
たとえば高齢者の患者が多いと予想される場合、ビルの5階よりも1階のほうが通院しやすいでしょう。
患者にとってアクセスしやすい立地を選ぶことで、継続的な通院につながります。
ただし、これも一概に「高齢者の方が多いから1階が最適」というわけではありません。
美容皮膚や精神科など「利用していることが人に見られたくない」という心理が働きやすい診療科目の場合には、5階のほうが最適なケースもあります。
患者のアクセスを考慮するというのは、身体的な面だけでなく精神的な面も考える必要があります。
周辺の調剤薬局を把握する
院外処方を採用する場合、近隣の調剤薬局の確認も欠かせません。
患者の利便性を損なわないように、クリニックと薬局の連携がスムーズに行える立地を選びましょう。
院内処方を検討している場合には、特に気にするべき要素ではありません。
ただ、開業予定の地域に調剤薬局が多く点在しているのであれば、経営面のメリットデメリットを把握した上で、院外処方による開業を視野に入れるのもおすすめします。
関連記事:院内処方と院外処方、開業するならどちらを選ぶべきか
テナント料と収益性のバランスを考える
テナント料は、クリニックの経営における固定費の大部分を占めます。
立地の良さだけで判断するのではなく、診療圏調査の結果や事業計画と照らし合わせ、収益性とのバランスを慎重に検討することが大切です。
一般的にテナント料は、クリニックの収入のうち6~8%以内に抑えることが理想とされています。
好立地でも家賃が高すぎると経営を圧迫する可能性があるため、収益性とのバランスを慎重に検討しなければなりません。
診察可能な時間を確認する
商業ビルなどでは、テナントが営業できる時間や曜日が制限されている場合があります。
特に土日診療や夜間診療を予定している場合は、建物の利用規約を事前に確認し、希望の診療時間に対応できるか確認しておくことが重要です。
建設された年度を確認する
特に1981年(昭和56年)5月31日以前に建設された建物で契約する際には、注意しなければならないことがあります。
それは管轄の自治体に対して、耐震診断の報告をしなければならない点です。
1981年5月31日以前に新築工事に着手した建物は旧耐震基準で建築されているため、現在の耐震基準を満たしているかどうかの診断を行う必要があります。
看板や広告の制限を確認する
看板の設置は、クリニックの認知度向上に欠かせません。
しかしビルの規約や地域の景観条例などによって、設置できる看板のサイズやデザイン、場所が制限される場合があります。
あらかじめテナントビルの規約や周辺地域の条例などを確認して、看板の設置が可能か確認しておきましょう。
同じビル内のテナントの業種を確認する
上下もしくは同一フロアに、クリニックにとっては望ましくない業種が入っていないか確認しておきましょう。たとえば、キャバクラや消費者金融など、クリニックのイメージにそぐわない業種の店舗が入っていた場合、初めて訪れた患者にとっては大きな不安要素となるので、通院しない可能性が高いでしょう。
患者が安心して利用できる環境を提供するためにも、同じビル内のテナントの業種も考慮しなければなりません。
不動産賃貸の設備や構造をチェックする際の注意点
クリニックで使用する医療機器や診療環境には、一般的な業務で使用する機器などとは異なる要件が必要です。
特に電気容量の不足や給排水設備の不備は、開業後に大きな問題となる可能性があるので事前にしっかりと確認しておかなければなりません。
ここでは、クリニック設計時の注意点をいくつか解説します。
電気容量の確認をする
診療科目によっては、大型検査機器の導入を検討することもあるでしょう。
特にレントゲン装置やMRI、内視鏡システムなどの医療機器は高い電気容量が必要です。
たとえばCT装置は最低でも50KVAもの電気容量が求められるので、一般の建物では容量が足りないことも多いでしょう。
可能であれば電気工事業者などと一緒に、必要な電力が足りているのかどうか確認することをおすすめします。
給排水設備の確認をする
給排水設備は保健所の立ち入り検査で指摘されやすいポイントでもあるため、入念に確認しましょう。
トイレは患者と医療従事者それぞれ別にあることが望ましく、特に手洗い設備に関してはよく指摘される項目の一つです。
診察室や処置室、スタッフルームなど複数の部屋に流し台が必要となるため、設計上の問題点や改修しなければならない箇所を把握しておきましょう。
バリアフリーを考慮する
高齢者や障害者の方の移動を円滑にすることを目的とした法律「バリアフリー法」への対応は、2,000㎡未満のクリニックにおいては努力義務とされています。
しかし、診療科目によっては車椅子やベビーカーを利用する患者が多いため、エレベーターの有無や院内の段差解消は集患において重要な要素です。
また、自治体によっては独自の条例でバリアフリーの基準を定めている場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
医療機器のスペースや搬入経路の確認をする
特に大型の医療機器の導入を検討している場合には、設置スペースだけでなくエレベーターのサイズや通路の幅など、搬入経路が十分に確保できているか確認しておきましょう。
「設置場所はあるのに搬入できない」といった事態を避けるため、あらかじめ医療機器の業者と現地確認を行っておきましょう。
また、電気容量の確保も忘れないようにしてください。
有床クリニックに用途変更する場合は特に注意
有床のクリニックを開業したい場合には、その物件で用途変更が実現できるのか確認をしておきましょう。
事務所などから有床のクリニックへと用途変更する場合、特殊建築物に該当するため「建築確認申請」が必要だからです。
特殊建築物になると、消防法や建築基準法などの規制がさらに厳しくなり、工事が着工できるまでのスケジュールも長期化します。
また、自治体によっては病床数が制限されていて、そもそも有床のクリニックは新たに開業できない場合もあります。
有床クリニックの新規開業が難しい場合には、医院継承も検討してみましょう。
クリニックの設計に関係する法令を確認する
クリニックの設計や内装工事を行う際には、主に以下の法令を遵守する必要があります。
| 法令の種類 | 概要 |
| 医療法 | 患者が安心して治療を受けられるように、清潔で安全な医療環境を確保することを目的とした法令 |
| 建築基準法 | 建物の安全性を確保するために定められた法令 |
| 消防法 | 消火設備や避難経路などを確保するために定められた法令 |
これらの法規制は複雑で専門的な知識を要するため、クリニックの設計や施工実績が豊富な専門業者に相談することも検討しましょう。
関連記事:診療所の間取りを成功させるための考え方とは?法規制や広さの基準を解説
不動産賃貸の契約書に関する注意点
クリニックの賃貸借契約を結ぶ際には、医療機関特有の内装工事の制限、将来の承継を見据えた代表者変更条項、医療廃棄物の取り扱いなど、契約書の細部まで確認することが重要です。
また、契約形態によってもメリット・デメリットが大きく異なるため、長期的な事業計画に合わせて選択することも大切です。
ここでは、契約時に特に注意すべきポイントについて解説します。
不動産賃貸の契約書は2種類
事業用の賃貸借契約には、主に「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」の2種類があります。
賃貸借契約の種類は貸主側が選択するので、それぞれの特徴やメリット・デメリットを把握しておきましょう。
普通建物賃貸借契約のメリット・デメリット
普通建物賃貸借契約書とは、契約期間が満了しても自動で契約の更新もできる契約形態です。
| メリット | デメリット |
| 契約の途中でも解約(閉院)が可能大家側から一方的な契約の解除は基本的に無い契約の途中に賃料の交渉が可能 | 貸主から賃料の値上げ交渉を受ける可能性がある契約更新時に更新料が必要になる場合がある |
普通建物賃貸借契約は、地域密着型のクリニックとして長期運営を予定している場合に最適と言えます。
特に将来的な医院継承も視野に入れており、安定した経営基盤を重視する場合には、契約の継続性が重要だからです。
定期建物賃貸借契約のメリット・デメリット
定期建物賃貸借契約とは、契約期間の満了によって契約が終了し、更新がない契約形態です。
再契約は可能ですが、貸主と借主双方の合意が必要です。
| メリット | デメリット |
| 契約中は賃料が据え置き更新料が不要(更新という概念が無い) | 再契約に応じてもらえない可能性がある基本的に契約の途中に解約はできない |
定期建物賃貸借契約は、契約中に賃料の値上げ交渉が無いことが大きなメリットです。
一般的に契約期間は10〜20年程度となり、その間は貸主側と賃料に関する交渉トラブルが起きることはありません。
ただし契約期間が満了したあと、貸主側が退去を求めた場合には再契約ができないリスクがある点は理解しておく必要があります。
実際、老朽化などが理由でビルを取り壊すことになり、再契約ができず立ち退きを余儀なくされるケースも少なからずあります。
内装工事に関する記載を確認する
どこまでの内装工事が許可されているか、契約書をしっかりと確認しておきましょう。
壁の設置や撤去、配管工事、電気工事など、クリニックの機能要件を満たすために必要な工事を行った際に「許可をしていない」というトラブルになりかねないためです。
また、物件によっては、消防設備工事や電気設備工事、空調換気設備工事などの担当業者が決まっている場合がある点も注意です。
オーナー側が業者を指定するのか、テナント側が業者を指定できるのかは工事区分によっても異なります。
| A工事 | B工事 | C工事 | |
| 工事業者の選定 | オーナー | オーナー | テナント |
| 工事業者への発注 | オーナー | テナント | テナント |
| 費用の負担 | オーナー | テナント | テナント |
たとえば電気設備の工事が「B工事」に該当する場合はオーナー側が業者を選定しますが、C工事に該当する場合はテナント側が業者を選定しなければなりません。
どちらも費用の負担は「テナント側」になるため、内装工事に関する許可や工事区分などをオーナー側としっかりと確認しておく必要があります。
原状回復の範囲を確認しておく
退去時に、物件をどの状態に戻す必要があるのかという「原状回復義務」の範囲は、最もトラブルになりやすい項目です。
内装をすべて撤去して建物の骨格だけの状態に戻す「スケルトン返し」なのか、あるいはある程度の内装を残した「居抜き状態」で良いのか、具体的な範囲を話し合うことも重要です。
代表者変更に関する記載を確認する
将来的な医院継承(医業承継)を見据えている場合には「代表者を変更する際には、あらかじめ貸主の承諾を得ること」といった条項が含まれているかを確認しておくことが大切です。
この記載がある場合、承継時に貸主の承諾が得られなければ、契約が継続できなくなるリスクがあります。
「あらかじめ通知をすること」と「あらかじめ承諾を得ること」では、全く意味合いが異なるため、どのような表記になっているのかしっかりと確認しておきましょう。
医院継承で不動産賃貸の契約をする際の注意点
医療業界は医師の高齢化と後継者不足により、既存のクリニックを引き継ぐ医院継承による開業も多くなってきています。
医院継承では、承継の方法によって不動産契約の取り扱いが大きく異なります。
事業譲渡の場合は新たな契約が必要となり、出資持分譲渡の場合は一般的に既存契約を引き継ぐ方法が一般的です。
それぞれの特徴を解説します。
事業譲渡は賃貸借契約の再締結が必要
個人のクリニックや医療法人の一部のクリニックを継承する場合、多くの場合で「事業譲渡」によるスキームが行われます。
事業譲渡の場合、法的には既存のクリニックが一度廃業し、新たなクリニックが開設されるという扱いになります。
そのため行政への手続きとしても、まず売り手側が廃院届を提出し、その後買い手側が同じ場所で新たに開設届を提出するという流れになるので、賃貸借契約も再締結が必要です。
この際に契約内容が変更される場合があり、敷金や礼金なども新たに必要になる可能性もあります。
出資持分の譲渡は原則賃貸借契約を引き継ぐ
出資持分ありの医療法人を承継する場合、法人の経営権が移転するだけなので、既存の賃貸借契約は原則としてそのまま引き継がれます。
この場合、代表者の名義変更手続き程度で完了し、新たに敷金や礼金がかかることは基本的にありません。
クリニックの不動産賃貸を探す際の相談先
クリニックの開業は物件選びだけでなく、設計や行政の手続きなど様々な専門知識が必要です。
医療特有の要件や規制に対応するためには、専門家によるサポートも欠かせません。
クリニック開業に関する主な相談先と、その特徴を紹介します。
| 相談先 | 特徴 |
| 医院開業コンサルタント | クリニック開業の総合的なサポートを行う専門家。 |
| 設計・施工会社 | 内装デザインや工事に関する専門業者。特にクリニック特有の設計や施工に特化した業者選びが重要。 |
| 金融機関 | 主に融資相談や経営面のサポートを行う。地域医療の収益モデルなど具体的なデータを多数持っている。 |
| 医院継承専門の会社 | 既存のクリニックの承継支援を行っている専門会社。クリニック開業における初期費用の低減や安定した経営を実現しやすい。 |
相談先の選び方については「診療所の開業相談できる機関まとめ!後悔や失敗しないコツも紹介」の記事をご参照ください。
関連記事:診療所の開業相談できる機関まとめ!後悔や失敗しないコツも紹介
まとめ|クリニックの不動産賃貸探しはプロにご相談を
クリニックの不動産賃貸では、一般的な賃貸物件とは異なる多くの注意点があります。
診療圏調査から始まり法規制への対応、医療機器の設置要件、患者の利便性とプライバシーへの配慮など、医療業界特有の専門知識や経営的な視点が必要です。
これらの複雑なプロセスを円滑に進め、将来的なトラブルを回避するためには、クリニックの開業や承継に精通した専門家のサポートが不可欠です。
医院継承の専門家である「エムステージマネジメントソリューションズ」では、「物件選びで失敗したくない」「初期費用を抑えて安定した経営をしたい」「開業後に本当に患者が来るか不安」といった医師の皆様のお悩みを解決しています。クリニックの不動産賃貸選びでお悩みがありましたら、ぜひお気軽に無料ご相談ください。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。
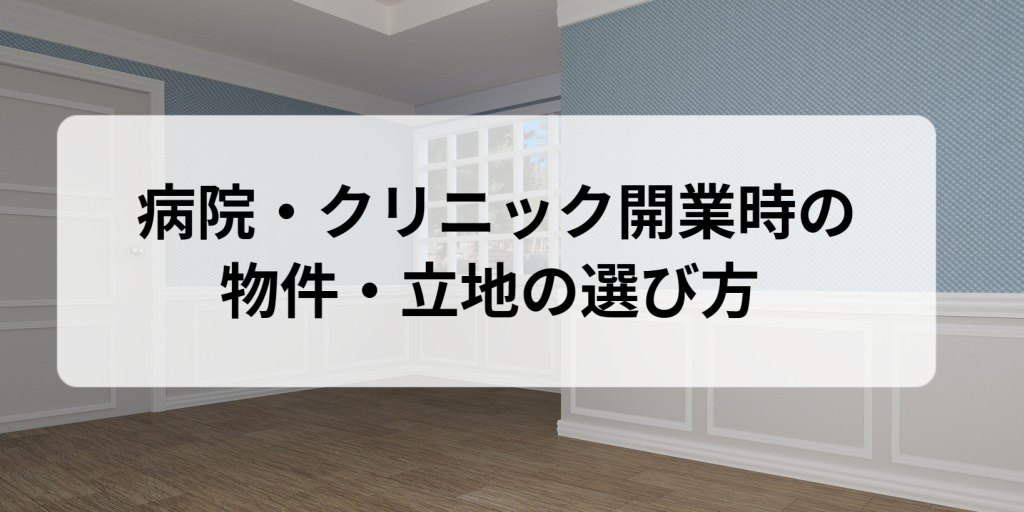
。必要な手続きやよくあるトラブルとは?-1024x512.jpg)