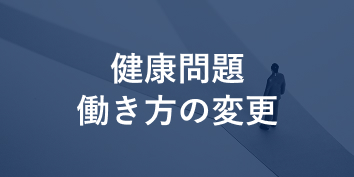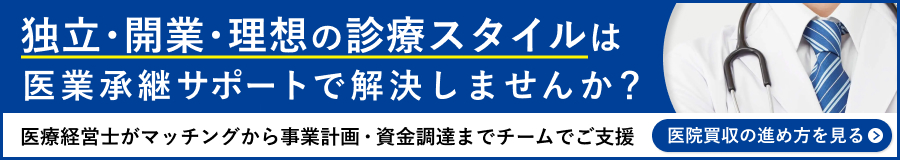【2025年最新】Web問診の普及率は約5%!費用や無料で導入する方法も紹介

目次
医療現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)化が進む中で、「Web問診」が注目を集めています。そのような中「Web問診はどれくらい普及しているのだろうか」「そろそろ導入が必要だろうか」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
そこで、本記事ではWeb問診の普及率から導入費用、導入を成功させるためのポイントをまとめました。本記事を読むことでWeb問診の必要性を理解し、クリニック運営の効率化や患者満足度向上に役立てられます。
Web問診とは患者が問診票の入力をするシステムのこと
Web問診とは、これまで紙媒体で行われていた問診票への記入を、スマートフォンやタブレットなどのデバイスを使ってWeb上で行えるようにしたシステムのことです。
患者は自宅や移動中、または院内に設置されたタブレット端末などを使って、問診に回答できるため、受付業務の効率化や院内での待ち時間短縮などが期待できます。
紙の問診票で起こりがちな記入漏れや読み間違いなどの問題を減らし、よりスムーズな医療提供をサポートするツールとして、Web問診を導入されるクリニックは増加傾向にあります。
AI問診との違い
Web問診は、基本的に従来の紙の問診票をデジタル化したものです。
一方でAI問診は、患者が問診に入力した情報をもとにAI(人工知能)が関連性の高い質問を追加で行ったり、疑われる病名を推測したりする機能を持っています。
つまりAI問診はWeb問診の機能に加えて、AIによる分析や提案機能が備わった、より高機能なシステムです。ただしAI問診はWeb問診に比べて、導入費用や月額費用は高くなる傾向にあります。
どちらのシステムが自院に適しているかは、クリニックの規模や診療科、求める機能などを考慮して検討しましょう。
| Web問診 | AI問診 | |
| 特徴 | 紙の問診をデジタル化したもの | Web問診の機能に加えてAIによる分析や追加の質問が搭載されている |
| 導入費用 | 安価 | 高価 |
2024年度におけるWeb問診の普及率は5.2%
Web問診システムの導入は徐々に進んでいますが、2024年度時点での普及率はまだ5.2%にとどまっています。
出典:PRTIMES|ミーカンパニー株式会社「診療支援ICTサービスレポート2024」
電子カルテの普及率(一般診療所で約57%)に比べると、まだまだ低い水準といえるでしょう。
Web問診の普及が遅い背景には、導入コストに対する費用対効果がわかりにくく、導入の必要性をあまり感じられないといったこともあるでしょう。
しかし、業務効率化や患者満足度向上といったメリットが大きいことから、今後Web問診の導入はさらに加速していくと予想されます。
特に新規開業当初から導入するクリニックも増えており、将来的には一般的なシステムとなっていくでしょう。
Web問診の導入費用の目安
Web問診システムの導入時には、一般的に初期費用と月額費用がかかります。
導入費用の目安としては、初期費用が10万円から30万円程度、月額費用が1万円から2万円程度と考えておくと良いでしょう。
ただし、多くのサービスでは具体的な料金を公開しておらず、ほとんどが「要問い合わせ」となっています。特に導入後のサポートや補償に関して、費用に含まれているのか必ずチェックしておきましょう。
導入を検討する際には、複数の会社から見積もりを取り、機能と費用のバランスを比較検討することが重要です。
導入時にはIT導入補助金の活用が可能
Web問診の導入費用は決して安いものではありませんが、「IT導入補助金」を活用することで、導入コストを抑えることは可能です。
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に、その経費の一部を国が補助してくれる制度のことです。
Web問診システムも、業務効率化や生産性向上に貢献するITツールとして、補助金の対象となる場合があります。
補助金の申請には、対象となるITツールの要件や申請期間、手続きなど、いくつかの条件があります。
また、申請には毎年締切日が設けられているので、IT導入補助金の公式HPからチェックしておきましょう。
関連記事:IT導入補助金とは?医療機関向けに活用術をわかりやすく開設!
Web問診を無料で導入する方法
Web問診のシステムは「Googleフォーム」を使えば、無料で自作することも可能です。
Googleフォームとは、アンケートなどの回答式のフォームを簡単に作成できるツールのことです。
患者はURLやQRコードを使ってGoogleフォームにアクセスし、問診フォームに回答します。
回答の内容は、自動的にGoogleのスプレッドシートへと記載されるシステムです。
しかしGoogleフォームを利用する場合、下記の懸念点やデメリットがあります。
- 患者の個人情報や病歴といった機密性の高い情報をスプレッドシートで管理するためセキュリティ面で非常に脆弱
- 個人情報保護の観点から医療機関での利用は推奨できない
- 電子カルテとの連携ができずデータの管理が煩雑になる
無料でWeb問診を導入できるのは魅力的ではありますが、セキュリティや機能、サポート体制などを考慮すると、有料の専用サービスを利用するのがおすすめです。
Web問診導入のメリット
Web問診システムの導入は、医療機関と患者の双方に多くのメリットをもたらします。
ここでは、主なメリットをいくつかご紹介します。
医療機関側の業務効率化につながる
Web問診導入のメリットは、医療機関側の業務効率が大幅に向上することです。
患者が事前に問診の入力をしてくれるため、受付での問診票の受け渡しや内容確認、電子カルテへの転記といった作業が不要になるためです。
受付スタッフの負担が軽減され、他の業務にも集中できます。
また、診察前に患者の情報を把握できるため、よりスムーズにカルテの準備ができたり質の高い診察を提供できたりします。
医療機関側の転記ミスがなくなる
Web問診は電子カルテへの転記作業が不要になるので、スタッフの転記ミスが防げます。
紙の問診票の場合、スタッフが問診票の内容を電子カルテに入力する際に、読み間違いや入力ミス(転記ミス)が発生するリスクがありました。
特に癖のある文字や専門用語などは、誤って解釈してしまったり読み間違えてしまうこともあるでしょう。転記ミスは重大な医療事故につながる可能性もあるため、決して軽視はできません。
Web問診システムを導入すれば、患者が入力した情報がそのままデータとして取り込まれるため、ヒューマンエラーによる転記ミスを根本的に防げます。
患者のプライバシー保護につながる
問診票には病歴やアレルギー、服用中の薬など、非常にデリケートな個人情報が含まれます。
待合室など、ほかの患者がいる場所で紙の問診票に記入することに抵抗を感じる方も多いでしょう。
Web問診であれば、患者は自宅などプライベートな空間で、落ち着いて問診に回答できます。
また紙の問診票のように、院内での紛失や盗難のリスクも低減できます。
患者のプライバシーに配慮した環境を提供することは、信頼関係の構築にもつながり、安心して受診してもらえるクリニックづくりにも貢献するでしょう。
患者の待ち時間が減少する
患者が来院前にWeb問診を済ませておくことで、受付での手続き時間を短縮できます。
問診票の記入や内容確認にかかる時間がなくなるため、来院から診察までの流れがスムーズになり、結果的に院内での待ち時間短縮につながります。
紙の問診票による記載の場合、患者は受付を済ませてから問診票に手書きで記入し、受付に問診票を渡すだけでも20〜30分程度はかかるでしょう。
Web問診なら来院前に回答をできるので、院内での待ち時間が減少します。
待ち時間の長さは、患者の満足度に大きく影響する要素の一つです。待ち時間が短縮されれば患者のストレスが軽減され、クリニックに対する印象も向上するでしょう。
患者の利便性向上につながる
Web問診システムの中には単に問診を入力するだけでなく、患者の利便性を高める機能を備えているものもあります。たとえば過去の問診履歴を患者自身が確認できたり、次回の予約日時を通知してくれたりする機能などです。
また、スマホアプリと連携できるシステムであれば、予約の変更やキャンセルなどもアプリ上で行える場合があります。
こうした機能は、患者が自身の健康情報を管理しやすくなるだけでなく、通院の手間を軽減することにもつながります。
患者にとって「使いやすい」「便利だ」と感じてもらえるシステムを導入することは、継続的な通院を促し、クリニックの集患にも貢献するでしょう。
患者は落ち着いて入力ができる
クリニックの待合室では周りの目が気になったり「早く書かないといけない」と思ったりと、落ち着いて問診票に記入できないと感じる患者もいます。
特に症状や既往歴などを詳しく伝えたい場合でも、焦ってしまって書き忘れたり、うまく表現できなかったりすることもあるでしょう。
Web問診であれば、患者は自宅などリラックスできる環境で、時間にも余裕を持って入力できます。
Web問診のデメリット
多くのメリットがあるWeb問診ですが、導入にあたってはいくつかのデメリットも考慮する必要があります。
スタッフの教育が必要
Web問診システムを導入すると業務内容や手順が変わるため、スタッフへの教育が不可欠です。
Web問診の操作方法はもちろんのこと、患者への案内方法やトラブル発生時の対応、個人情報の取り扱いに関するルールなどを習得してもらう必要があります。
スムーズな導入と運用のためには、事前にマニュアルを作成したり、研修を実施したりするなど、十分な準備期間を設けることが重要です。特に導入初期はスタッフが新しいシステムに慣れるまで、一時的に業務負担が増える可能性も考慮しておきましょう。
ランニングコストの増加
Web問診システムの導入には、初期費用に加えて月額または年額の利用料(ランニングコスト)が発生します。料金体系はサービスによって異なりますが、一般的には月額1万円から数万円程度の費用がかかることが一般的です。
クリニックの運営経費が継続的に発生するため、導入前に費用対効果を十分に検討する必要があります。業務効率化による人件費削減の効果や、患者満足度向上による増患効果などを考慮し、長期的な視点で効果を見極めることも重要です。
操作できない患者には対応が必要
Web問診は便利なシステムですが、特に高齢の方やスマホなどの操作に不慣れな方など、すべての患者がスムーズに利用できるとは限りません。
そのため、Web問診を利用できない患者への対応策を準備しておく必要があります。
具体的には従来通りの紙の問診票を用意しておく、院内に設置したタブレット端末の操作をスタッフがサポートする、といった方法が考えられます。
ただしスタッフがつきっきりで操作をサポートする場合、かえって業務負担が増えてしまうこともあるでしょう。
どのような対応策が自院にとって最適か、患者の層やスタッフの状況などを考慮して検討しなければなりません。
Web問診を導入する際のポイント
Web問診は導入するだけでも、業務効率化や待ち時間の減少などのメリットが多くあります。
しかし、一部の患者にとってはWeb問診になったことで「面倒くさくなった」とマイナスな要素になることも考えられます。
Web問診の導入で失敗しないためにも、これから紹介するポイントを押さえておくことが重要です。
患者の操作性
Web問診のシステムを選ぶ上で、患者にとっての「使いやすさ」は非常に重要なポイントです。
どんなに高機能なシステムでも入力画面がわかりにくかったり、操作が複雑だったりすると患者の手間が増加し、ストレスの原因になってしまいます。
特にスマートフォンでの入力が主になることを考えると、文字の大きさやボタンの配置など、モバイル端末での操作性に配慮されているかを確認しましょう。
可能であればデモ版などを試してみて、実際に患者の立場で操作感を確かめてみるのがおすすめです。
紙の問診票も準備
Web問診を導入した後も、引き続き紙の問診票は準備しておくことを強くおすすめします。
前述の通り、すべての患者がWeb問診を利用できるとは限りません。
デジタルデバイスの操作が苦手な方やスマートフォンを持っていない方、あるいは急な来院で事前にWeb問診を入力できなかった方などもいらっしゃるでしょう。
そのような場面でも、紙の問診票を用意しておくことでスムーズな受付が可能です。
またシステム障害などの万が一の事態に備えるという意味でも、紙の問診票は有効なバックアップ手段です。
利用している電子カルテとの連携
Web問診を導入する大きなメリットの一つが、電子カルテとの連携による業務効率化です。
Web問診で入力された情報が、自動的に電子カルテに反映される仕組みがあれば、転記の手間やミスをなくし、大幅な時間短縮につながります。
そのため導入を検討しているWeb問診のシステムが、現在利用している電子カルテと連携可能かどうかは、必ず確認しましょう。
導入後のカスタマイズ性やサポート体制
Web問診を導入したあと、クリニックの運用に合わせて設定の変更や新しい機能の追加をしたい場合もあるでしょう。そのため、導入後のカスタマイズ性もWeb問診を選ぶポイントです。
問診項目の追加や変更が容易にできるか、診療科に合わせたテンプレートが用意されているかなどを確認しましょう。またシステムにトラブルが発生した場合に、迅速に対応してくれるサポート体制が整っているかも重要です。
特に電話による対応時間や問い合わせ方法を確認し、安心して利用できる会社を選びましょう。
Web問診は開業から浅いほうが導入しやすく普及率も高い
Web問診は、開業から5年未満のクリニックでは導入が進んでいる一方で、開業から11年以上経過しているクリニックでは導入率が低い傾向にあります。
クリニックの経営が長いほど導入率が低い背景としては、すでに確立されている業務フローや院内ルールの変更への抵抗感、既存のシステムとの連携の問題などが障壁になっていると考えられるでしょう。
DX化が進む医療業界において、Web問診の導入は患者満足度の向上や業務効率化だけでなく、将来的な医院経営の安定化にもつながります。
特にクリニックの新規開業や医院承継を検討されている方は、開業計画の初期段階からWeb問診などのデジタルツールの導入を視野に入れておくことをおすすめします。
医院開業や承継をお考えでしたら、私たち「エムステージマネジメントソリューションズ」にご相談ください。Web問診などのデジタルツール導入のサポートはもちろんのこと、医院の立地選定から事業計画の策定まで、医療経営士が対応いたします。長期的に安定した医院運営を実現するため、開業後のサポートも可能です。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。

。必要な手続きやよくあるトラブルとは?-1024x512.jpg)