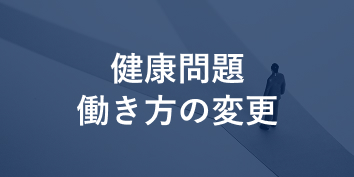保険診療で前金の請求は禁止?未払いのリスク低減や回収方法を解説

目次
医療機関にとって、入院や手術などの高額医療費における未払いのリスクは深刻な問題です。そのため「保険診療では前金を請求できないのか」「確実に未払いの診療費を回収するにはどうすればよいのか」こうした悩みを持っている方は多くいらっしゃいます。
本記事では、保険診療における前金の考え方と、未払いリスクを減らすための実践的な方法、そして未払いが発生した際の効果的な回収方法を解説します。
保険診療における前金の請求は禁止事項に該当する可能性がある
法律などの公的な資料では「保険診療において前金の徴収は禁止」という記載は見当たりません。しかし、日本の医療制度の基本理念を見てみると、事実上前金の徴収は禁止されていると判断ができます。
まず「医療機関は非営利性が求められている」という点で、前金は行うべきではないと考えられます。
| 1 医療機関の開設者に関する確認事項 (1) 医療法第7条に定める開設者とは、医療機関の開設・経営の責任主体であり、原則として営利を目的としない法人又は医師(歯科医業にあっては歯科医師。以下同じ。)である個人であること。 引用:厚生労働省|医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について |
医療サービスを提供する前に支払いを求めることは、医療行為よりも収益確保を優先させる姿勢と見なされ、非営利の原則に反する可能性があるためです。
また、日本の医療制度は「必要なときに平等に医療を受けられる」という点が、国際的に見ても高く評価されています。
| 我が国の医療制度は、すべての国民が健康保険や国民健康保険といった公的な医療保険制度に加入し、いつでも必要な医療を受けることができる国民皆保険制度を採用している。 引用:厚生労働省|厚生労働白書 |
保険診療で前金を徴収した場合「前金を支払わないと患者は診療が受けられない」という事態が発生してしまうため、上記の理念に反すると考えられるでしょう。
保険診療において前金を受け取る行為は、この2点の基本理念に反すると判断できるため、事実上禁止されていると考えられます。前金制度を考えている場合には、医師会などに相談することをおすすめします。
入院費用に関しては保証金(前金)制度が許容されている
保険診療において前金の徴収は避けておくべき行為ですが、入院費用に関しては事実上の前金といえる「保証金制度」が認められています。
厚生労働省の通知「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」では、以下のように明記されています。
| 入院時や松葉杖等の貸与の際に事前に患者から預託される金銭(いわゆる「預り金」)については、その取扱いが明確になっていなかったところであるが、将来的に発生することが予想される債権を適正に管理する観点から、保険医療機関が患者から「預り金」を求める場合にあっては、当該保険医療機関は、患者側への十分な情報提供、同意の確認や内容、金額、精算方法等の明示などの適正な手続を確保すること。 出典:厚生労働省|「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について |
このように、入院費用については適切な手続きを行った上で保証金の徴収が可能です。
入院は通常の外来診療と比べて費用が高額になりやすく、また長期間にわたる場合もあるため、医療機関側の未収リスクを軽減する措置として認められていると考えられます。
ただし、事前に入院費用の保証金を請求する際には、以下のポイントを考慮しましょう。
- 患者に対して保証金の内容や金額を明示すること
- 患者の同意を得ること
- 精算の方法を明確にすること
患者とのトラブルを防ぐためにも、保証金の内容についてしっかりとした説明や情報提供が必要です。
保険診療で禁止されていること
保険診療を行う医療機関には、さまざまな禁止事項が定められています。これらは「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に規定されており、主な禁止事項は以下のとおりです。
経済上の利益の提供による誘引の禁止(第2条の4の2)
患者を自分の医療機関に誘導するための、金銭や物品などの経済的利益の提供が禁止されています。たとえば来院した患者に商品券を配ったり、無料の物品を提供したりなどが禁止です。
特定の保険薬局への誘導の禁止(第2条の5、第19条の3)
処方箋を発行する際「うちの近くの〇〇薬局に行ってください」など、特定の保険薬局で調剤を受けるように患者に指示したり誘導したりすることが禁止されています。
無診察診療の禁止(第12条)
患者を直接診察せずに診断や処方を行うことは禁止されています。医師が患者の状態を適切に把握し、正確な診断と治療を行うためには直接の診察が不可欠だからです。
たとえ以前診察した患者の定期健診だったとしても、薬を処方するには改めて診察が必要です。ただし「リフィル処方箋」であれば、再診の手間がなく必要な薬のみ処方ができます。
関連記事:リフィル処方箋とは?制度概要とクリニックや診療所への影響
特殊療法等の禁止(第18条)
医学的に認められていない特殊な療法や、保険診療として認められていない治療法を保険診療として提供することは禁止されています。
研究的検査の禁止(第20条1のへ)
医学的な研究目的で行われる検査を、保険診療として行う行為は禁止されています。研究目的の検査は患者の治療に直接関係しない場合があるため、保険診療とは区別しなければなりません。ただし治験に関しては例外です。
健康診断の禁止(第20条1のハ)
保険診療の枠内で健康診断を行うことは禁止されています。健康診断は疾病の治療を目的とするものではなく、予防や早期発見を目的とするためなので、保険外診療として扱われます。
濃厚(過剰)診療の禁止(第20条)
必要以上の診察や検査、投薬などを行う過剰診療は禁止されています。たとえば、必要のない高額検査を繰り返し行うなどの行為が該当します。
▶収益管理や法令対応を踏まえて医業承継(M&A)の選択肢を整理する
前金以外で保険診療未払いのリスクを減らすためにできること
保険診療において前金の請求は原則として避けるべきですが、医療機関としては未払いのリスクへの対策は行いたいところでしょう。
ここでは、前金以外の方法で保険診療の未払いリスクを低減できる方法を、6つ紹介します。
入院の際には保証金を設ける
患者の入院が必要な場合には、保証金の制度を導入することで未払いのリスクを低減できます。入院治療は通常の外来診療に比べて費用も高額になりがちなため、医療機関としても未払いのリスクが心配です。
入院で必要な費用に関しては保証金の制度が認められているため、適切に運用して未払のリスクを低減しましょう。ただし、保証金制度を導入する際は、患者への十分な説明と同意が不可欠です。
口座振替を導入する
患者の銀行口座から診療費を自動的に引き落とせる「口座振替」を導入することで、患者の支払い忘れも防ぎ、確実な医療費の徴収にもつながります。
特に定期的に通院する慢性疾患の患者や、リハビリテーションなど継続的な治療が必要な患者に最適です。毎回の支払い手続きが不要になり、患者にとってもメリットがあります。
導入にあたっては、金融機関との契約や患者からの口座振替依頼書の取得などの準備は必要ですが、一度システムを整えれば事務作業の効率化にもつながります。
クレジットカード払いに対応する
クレジットカード決済の導入は、保険診療の未払いリスクを大幅に軽減できる対策のひとつです。
患者の手元に現金がなくても即時に支払いが完了するため、未収金の発生を防止できます。高額な治療費の場合に特に有効で、患者側も分割払いやポイント還元などのメリットを受けられます。
導入にはカード会社への加盟店手数料が発生しますが、未収金対策のコストと比較すれば十分に見合う投資といえるでしょう。
連帯保証人の提示を求める
特に高額な医療費が予想される手術や入院では、連帯保証人の設定が未払いリスクを減らす効果的な方法です。
総務省が行った調査によると、連帯保証人の提示を求めていた25の病院のうち、18の病院で過去3年間に「連帯保証人に請求したことがある」と回答しています。
【過去3年間で連帯保証人に対して請求したことがあるか】
| 請求したことがある | 18 |
| 請求したことがない | 7 |
出典:総務省|入院費用等の担保についての連帯保証人以外の設定
上記の結果からも、特に入院などの高額な医療費は患者本人の未払いの可能性が高いことがわかります。
しかし「連帯保証人が意味を理解せずにサインをしていた」「そもそも支払い能力のない連帯保証人だった」などのことから、連帯保証人に請求をしても実際には回収できていない状況に陥っているところも少なくありません。
そのため、あらかじめ連帯保証人の制度に関する説明を患者にするのはもちろんのこと、連帯保証人に対しても支払い義務の範囲を明確に伝えて、正式な書面で契約を結ぶ必要があります。
また、保証金を預かっておくなど、ほかの方法と組み合わせて対策をすることも重要です。
医療費後払いサービスを導入する
医療機関の未収金リスクを軽減する方法として、医療費後払いサービスも注目されています。「医療費後払いサービス」とは、患者の診療費を後払い決済サービス会社が立て替えるシステムです。
患者はクレジットカードやコンビニ支払い、口座振替などさまざまな支払い方法を選べる点がメリットで、医療機関は未払いのリスクを回避できて、事務作業の負担も軽減できるメリットがあります。ただし、医療費後払いサービスを導入する際には「未払い保証」の有無をチェックしましょう。
未払い保証のない後払いサービスの場合、患者の支払いが滞ると医療機関への支払いも止まってしまいます。
誓約書にサインをもらう
医療費が支払えない患者に対して誓約書にサインをもらうことは、未収金を回収するために必須ともいえる手続きです。
誓約書は患者が将来的に医療費を支払う意思を文書化したものなので、法的にも有効な証明となります。誓約書には未払いの総額や支払い期限、分割払いの場合は各回の支払い額や日程を明記します。
また、支払いが滞った場合の対応(遅延損害金の発生など)についても記載しておきましょう。ただし、患者に誓約書へのサインを求める際は、強圧的な態度にならないよう十分な配慮が必要です。
保険診療の未払いが発生した際の主な回収方法
保険診療の未払いが発生した際に、電話などで請求をしてすぐに支払ってもらえるのであれば悩まされることはありません。しかし初期の請求段階では、回収できない場合がほとんどです。
ここでは、未払いを回収するために必要な手順を、4つの段階にわけて解説します。
1.メールや電話などで請求する
未払いが発生した場合には、まずメールや電話で請求を行います。この時点では患者が単に支払いを忘れている場合も多いため、丁寧かつ冷静な対応を心がけましょう。
電話では相手の状況を確認しながら柔軟に対応しつつ、「いつ支払えるのか」という点を確認することが重要です。メールの場合は支払期限が過ぎている点を記載しつつ、支払い方法や振込先の情報も記載しておきましょう。
また、対応した記録を残しておくことで、その後の対応がスムーズになります。
2.医療費未払いに関する督促状を送付する
電話やメールでの連絡に反応がない場合は、次は督促状の送付を検討しましょう。督促状には未払い金額や診療日、支払期限などを明記し、公式な文書として発送します。配達証明付き郵便を利用して、確実に督促状が届いた証拠を残しておくことも重要です。
督促状を送る際も威圧的な表現は避け、支払い方法や分割払いの相談にも応じる旨を伝えるとよいでしょう。督促状の送付記録は、万が一法的手続きに移行する際の重要な証拠となります。
3.強制徴収制度を活用する
督促状を送っても反応がなく、医療費の未払いが長期化した場合には「強制徴収制度」の活用も検討しましょう。
強制徴収制度とは、患者の未払いの医療費を医療機関に代わって保険者(健康保険組合や市区町村など)が徴収する仕組みです。
| 保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び組合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。 引用:国民健康保険法|第42条の2項 |
医療機関に代わって徴収するだけなので、制度を活用してすぐに未払金を回収できるわけではありませんが、回収業務の手間や時間からは解放されます。
また、強制徴収制度を活用するには「医療機関が一定の回収努力を行わなければならない」という条件があるので、あらかじめ保険者側に確認をしておくと良いでしょう。
4.弁護士に依頼する
医療費未払いの回収が難航する場合、弁護士に依頼することも検討しましょう。弁護士に依頼すると、まず内容証明郵便による正式な督促から始まります。弁護士からの督促状は心理的な効果も高く、この段階で支払いにつながるケースも多いでしょう。
電話や対面での交渉も代行してくれるため、医療機関側の心理的負担や業務負担も軽減されます。特に最終手段として訴訟を行う可能性がある場合には、債権回収の専門知識を持った弁護士に依頼することをおすすめします。
保険診療の未払いに備えて対応マニュアルを作成しておく
保険診療の未払いは医療機関にとって大きな負担となるため、事前に対応マニュアルを作成しておくことも重要です。窓口での対応方法として、患者の状況別に応答例を用意しておくと実務に役立ちます。
たとえば「支払う意思はあるが今日は手元にない」「支払う意思がない」などのケース別の対応フローを図式化しておくと良いでしょう。
また、電話での督促の際の会話例や、督促状の文例も準備しておくと効率的です。未収金管理表で患者ごとの状況を記録し、定期的に確認する体制も重要です。
ただしお金に関することは、患者とトラブルになりやすい要因ということも把握しておきましょう。患者への接遇対応も含めて、定期的に研修の機会を設けて周知徹底を行うことが重要です。
関連記事:医療の接遇マナー5原則とは?言葉遣いのポイントやマニュアル作成方法を解説
保険診療の未払い対策は前金以外の方法を用意しておきましょう
保険診療において前金徴収は原則として避けるべき対応ですが、医療機関としては未払いリスクへの備えは必要です。特に入院などの高額な医療費が見込まれる場合には保証金制度の導入や連帯保証人の設定、医療費後払いサービスの活用を検討しましょう。
未払いが発生した際に備えて、電話やメールでの請求から始め、段階的に督促状の送付や法的手段へと移行する手順を準備しておく必要があります。
これらの対策をマニュアル化し、定期的な研修を通じてスタッフ全員に周知徹底することで、窓口での対応も円滑にできます。
患者との信頼関係を損なわないよう配慮をしながら、医療機関として安定した経営を守るためにも適切な未払い対策を準備しておきましょう。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。