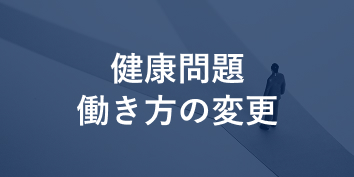クリニックの内装のポイントとは?工程や費用、注意点を解説

目次
内装の設計には、清潔感・バリアフリー・動線・プライバシーなど、患者の満足度に直結する多くのポイントが関わってきます。しかし、設計ミスや施工トラブル、法令の見落としがあると、開業に大きな支障が生じやすいです。
そこで本記事では、クリニック内装の基本から工程、費用相場、設計の注意点まで解説します。補助金・助成金を活用してコストを抑える方法や、医業承継時に内装費用を節約するポイントも紹介しているので、ぜひご覧ください。
クリニックの内装の重要性とは?
クリニックの内装は、患者が最初に目にするため、第一印象を大きく左右します。清潔感があり落ち着いた空間は、緊張や不安を和らげ、安心感を与えるでしょう。
また、視認性の高い案内表示や動線のわかりやすさなど、使いやすさへの配慮も求められます。高齢者や身体障害のある方でも快適に利用できるよう、バリアフリー設計を取り入れることも重要です。段差の解消、手すりの設置、広めの通路など、誰にとっても過ごしやすい環境を整えると、患者満足度の向上につながります。
クリニックの内装で考えること
クリニックの内装で考えることは3つあります。
- 患者層に合わせたデザインになっているか
- 利用しやすい導線設計になっているか
- プライバシーに配慮した設計になっているか
詳しく解説します。
患者層に合わせたデザインになっているか
クリニックの内装は、患者層に合わせたデザインが大切です。診療科や立地によって来院者の年齢層や目的が異なるため、ターゲットに応じた空間づくりが必要です。たとえば、小児科では子供が楽しめるようなカラフルな壁紙やキャラクターの装飾が親しまれています。待合スペースに絵本や遊べる空間を配置すると、子供の不安を和らげる効果もあります。
一方、成人や高齢者が中心の内科では、落ち着いたトーンの内装が安心感を与えます。競合と似たような設備であっても、デザインによって差別化することもできるでしょう。
利用しやすい導線設計になっているか
導線設計は、患者が迷わずに安全に利用できることが大切です。特に高齢者や身体障害がある方への配慮が欠かせません。廊下や入口の幅を広めに取り、段差の解消や手すりの設置を行いましょう。
視覚的な誘導サインや、床素材の色分けによるエリア区分も有効です。スタッフと患者の導線を分けると、バックヤードの効率化とプライバシー保護にもつながります。診療科によっては、処置室や検査室の距離も考慮し、無駄のない移動が可能な配置にしましょう。競合との差をつけるためにも、使いやすさに加えて安心感を与える空間設計が大切です。
関連記事:診療所の間取りを成功させるための考え方とは?法規制や広さの基準を解説
プライバシーに配慮した設計になっているか
プライバシーに配慮した内装は、患者の安心感に直結します。特に心療内科や美容クリニックなど、デリケートな相談が多い診療科では配慮が欠かせません。
診察室やカウンセリングルームは、待合スペースから見えない場所に設けましょう。扉や仕切りの位置にも注意が必要です。加えて、患者同士の会話や診察内容が漏れ聞こえないように、防音材や音を吸収する素材を使用して患者のプライバシーを守る配慮が大切です。
クリニックの内装工事の工程
クリニックの内装工事では、主に6つの工程があります。
- 業者選定
- 現場調査
- 内装設計
- 施工
- 完成検査
- 引き渡し
それぞれ解説します。
業者選定
内装工事を成功させるためには、どの業者に依頼するかが重要です。複数の業者から相見積もりを取り、費用の内訳だけでなく対応の丁寧さも比較検討しましょう。医療機関の内装に精通した業者であれば、動線設計や法令対応、衛生管理に配慮した内装を実現できます。
業者選定には設計完了前のタイミングが望ましく、工事開始の6か月以上前には依頼先を決めておきましょう。経験不足の業者に依頼すると、医療機器との干渉や施工ミスが起こりやすく、トラブルの元になります。
現場調査
現場調査では、建物の実際の構造や設備状況を確認します。法律に適合しているか、耐震性や構造強度に問題がないかをチェックする工程です。特に、水回りや電気設備が適切に設置されているかを調査し、回収・改修が必要かを判断します。これらの設備は、医療機器の安定した導入・使用にも大きく影響します。
現場調査の所要時間は1日〜数日程度が一般的です。事前の設計と現場の実情が異なる場合、図面の修正や工事計画の変更が必要になります。失敗例では、コンセントの位置が診療機器と合わなかったり、水回りの排水勾配が不十分だったりで改修が必要になる場合もあります。
内装設計
内装設計では、まずクリニックのコンセプトとターゲット層を明確にします。小児科であれば明るく親しみやすい色合い、皮膚科や美容系であれば清潔感と高級感を重視した設計がおすすめです。業者と話し合いながら、受付や診察室、待合室の配置や色彩、素材を決めていきます。
設計にはバリアフリー基準、非常口の配置、換気量の確保など法的な制約が伴います。設計期間は約1~2か月が目安です。照明は色温度にも配慮が必要で、過度に青白い光は冷たく感じられ、温かすぎると診察に支障をきたす場合があります。配線計画やコンセントの数、スタッフの動線も早期に決定しないと、後の修正が困難になります。内装設計は見た目だけでなく機能性との両立が求められるため、初期段階で十分な時間を取りましょう。
施工
クリニックの内装工事は設計完了後、実際の施工フェーズに移行します。一般的な工期は約3か月前後です。初期段階では床や壁の下地処理、配管や配線の敷設を行います。続いて、壁や天井の骨組みを組み、ボードを貼り、塗装やクロス貼りで仕上げていく手順です。
この工程で、設備機器や照明器具も設置します。あらかじめクリニックの雰囲気に合う照明や内装材を選定しておくことが重要です。照明の色温度が冷たすぎて待合室の印象が硬くなったという失敗例もあるので注意しましょう。ゾーニングによっては、診療スペースと休憩スペースの内装のトーンを分ける配慮も必要です。
完成検査
完成検査では、設計図と一致しているか、法令を遵守しているかなどを確認します。壁や床の状態、照明の動作確認、配線や配管の適正な設置、空調や換気設備の機能確認などが主なチェック項目です。所要時間は半日から1日程度です。
検査時に不備が発覚した場合は、修正対応に数日を要する場合があります。照明の色温度が診療行為に適していない、換気設備の音が大きすぎるなど、設計段階では見えにくい問題も発覚しやすい工程です。
保健所による開設前検査にも影響するため、細部まで丁寧に確認する必要があります。完成検査での指摘が多いと、開業時期に遅れが生じるリスクもあるため、各工程での中間チェックが重要です。
引き渡し
内装工事が完了した後、最終の完成検査を経て問題がなければクリニックの引き渡しが行われます。引き渡しは内装工事全体の最後のステップで、通常、工事開始から約3か月後が目安です。
現地で設計内容や設備仕様が反映されているか確認し、施工ミスや不具合があればその場で対応可否を確認します。速やかに補修・調整が行われるかどうかを事前に業者と取り決めておくと安心です。よくある失敗例として、医療機器と電源位置がずれていたなどがあるため、引き渡し時には、家具・設備配置を想定した動線確認も必要です。
クリニックの内装工事にかかる費用
クリニックの内装工事にかかる費用は、坪単価で30万円〜50万円程度が目安です。ただし、物件の構造や立地条件、診療科目、デザイン性によって金額は変動します。たとえば、美容皮膚科や歯科のようにデザイン性を重視する場合は、費用が高くなる傾向です。内科・外科・整形外科では、X線室や処置室などの特別な設備が必要になるため、標準よりも費用が上がりやすいです。
新築物件やスケルトン物件では配管や電気工事を含むためコストがかさみますが、内装が残された居抜き物件を利用すれば、大幅に費用を抑えられます。設計段階から目的に合った設備や動線を検討すると、無駄なコストの発生を防げるでしょう。コスト管理と集患を両立させるには、診療スタイルに合った内装設計が重要です。
関連記事:診察室の広さの基準は?クリニックの売上目標から考慮すべき広さも解説
クリニックの内装費用を抑えるポイント
クリニックの内装費用を抑えるポイントは3つあります。
- 居抜き物件を選ぶ
- 相見積もりを取る
- 補助金や助成金を利用する
詳しく解説します。
居抜き物件を選ぶ
居抜き物件を選ぶと、内装費用を大きく抑えられます。前テナントが使用していた設備や内装をそのまま活用できるため、新たな工事がほとんど必要ないです。診療科目が一致していれば、診察室や待合スペースのレイアウト変更も不要な場合があります。上記の通り、内装や設備をそのまま利用できるため、内装工事にかかる費用を抑えられます。
ただし、設備の状態に応じてメンテナンスが必要です。老朽化や動作不良があると、修理費が別途発生します。物件契約前に必ず動作確認を行い、必要に応じて見積もりを取っておくと安心です。
相見積もりを取る
内装費用を抑えるためには、相見積もりの取得が欠かせません。最低でも3社程度から見積もりを取り、価格だけでなく提案内容や業者の対応も比較しましょう。複数の業者から相見積もりを取って信頼できる業者を選びましょう。安くても質が低い業者もあるため、実績などの考慮が必要です。
また、見積もりの内訳がはっきりしているか、追加料金はかかるのかも確認しましょう。見積もり内容が明確でない場合は、後から予想外の費用が発生するリスクがあります。事前に詳細を説明してもらい、不明点は必ず質問しましょう。丁寧な対応と透明性のある業者ほど、安心して任せられます。
補助金や助成金を利用する
内装費用を抑える有効な手段の一つが補助金や助成金の活用です。医業承継時にはさまざまな支援制度が利用できる可能性があります。それぞれ紹介します。
| 内容 | |
| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が自社の経営を見直し、持続的な経営に向けた経営計画を策定した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する補助金制度です。 患者の利便性向上や新規顧客獲得を目的とした待合室や受付の改装バリアフリー化(例:スロープ設置、トイレの改修)新しいサービス提供のための診療室の増設や改装業務効率化を目的としたスタッフ動線の改善 などの目的で活用できます。 |
| 医療施設等施設整備費補助金 | へき地医療の確保や臨床研修医の研修環境の充実を目的とした補助金です。医療施設の新築や改修、医療機器の導入など、地域医療体制の強化に資する施設整備に対して給付されます。 |
| IT導入補助金 | 中小企業や小規模事業者が業務効率化やデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するために、ITツール(ソフトウェアやクラウドサービスなど)を導入する際の費用の一部を国が補助する制度です。 電子カルテや予約システムの導入に伴う電源工事、レイアウト変更で活用できます。 |
上記のような補助金を活用して内装費用を抑えましょう。
クリニックの内装を決める際の注意点
クリニックの内装を決める際は、2つの注意点があります。
- 法律を守った設計になっているか
- 水道や電気などの設備との兼ね合い
詳しく解説します。
法律を守った設計になっているか
クリニックの内装設計では、法的基準を満たしているかどうかの確認が必要です。医療施設としての機能を果たすには、以下の法律に対応した構造でなければなりません。それぞれ解説します。
| 内容 | |
| 建築基準法 | 建築基準法は建物の構造や設備、用途に関する基準を定めた法律です。防火・耐火構造の義務、避難経路・非常口の確保、バリアフリーなど気を付ける点がいくつかあります。一般的な建物より厳しいため注意しましょう。 |
| 医療法 | 医療法では、構造設備基準、床面積と動線、患者のプライバシー確保などの点に注意が必要です。たとえば、診察室と待合室は分けられており十分な広さが確保できているか、十分な広さの通路幅を確保できているかなどです。 |
| 消防法 | 消防法では、避難経路の確保、防火区画の設置、不燃材・準不燃材の使用、非常用照明と誘導灯の設置などがあります。 |
| バリアフリー法 | 高齢者や障害者が施設を円滑に利用できるようにするための法律です。出入り口や通路の幅、段差の解消、手すりの設置などで基準が定められています。 |
これらの法律は、患者と職員の安全、快適な医療環境を守るために定められています。設計前に行政や設計事務所と連携し、事前の法令チェックを行うと、トラブルを回避できるでしょう。
水道や電気などの設備との兼ね合い
クリニックでは、水道や電気の設置位置、新設・増設を検討する必要があります。診療科によって必要な設備は異なり、たとえば歯科ではユニットごとの給排水、皮膚科や内科では処置室・洗面・手洗い場の確保が重要です。
また、機器の性能に応じた電力も必要です。必要な電力が確保できていない場合、ブレーカーや分電盤の新設・増設が必要になります。それにより内装にも影響します。
これらの設備条件は、内装レイアウトや天井・壁・床の構造に直接関係するため、初期段階での詳細な調整が不可欠です。建物の既存インフラとの整合性も確認し、トラブルや余計な費用を防ぐためにも、専門業者と連携した事前調査と設計が重要になります。
よくある質問
クリニックの内装に関してよくある質問を紹介します。
- クリニックの内装はいつから検討し始めべき?
- 内装業者と設計士は別にした方が良い?
それぞれ解説します。
クリニックの内装はいつから検討し始めるべき?
クリニックの内装は、およそ1年〜半年前から検討し始めましょう。物件の選定、レイアウトの構想、設計事務所や施工会社との打ち合わせには時間がかかります。とくに医療機器や動線の配置は診療内容と密接に関係するため、慎重な計画が必要です。
開業スケジュールを逆算し、余裕を持った準備が重要です。直前に決めると、設計変更や施工の遅れにより開業時期がずれる恐れがあります。複数の業者との連携が必要となるため、段階ごとに確認や調整を行う時間を確保しましょう。
内装業者と設計士は別にした方が良い?
内装業者と設計士を別々に依頼すると、役割が明確になる一方で、情報共有や調整が複雑になる可能性があります。設計士は空間デザインに特化しており、細部にこだわった設計を提案できるというメリットがあります。
しかし、現場での対応が必要になる場面では、設計士と内装業者が別々だと、工事の進行に支障が出やすいです。スケジュールの遅延やコストの増加につながる可能性もあるため注意が必要です。同じ業者に設計から施工まで一括で依頼すれば、社内での情報共有が円滑になり、トラブルが起きにくくなります。結果として、全体の進行がスムーズになりやすいです。
内装設計で理想のクリニックを実現しましょう
クリニックの内装は、患者の第一印象やリピート率に直結する重要な要素です。内装設計では清潔感・バリアフリー・導線・プライバシーなど、患者視点の配慮が求められます。診療科やターゲット層に応じたデザインや、快適で迷いにくい動線設計、防音や視線対策によるプライバシー確保が重要です。
内装工事は業者選定から始まり、設計・施工・検査・引き渡しと段階を追って進行し、法令遵守も不可欠です。費用は坪単価30~50万円が目安で、居抜き物件活用や相見積もり、補助金(小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金など)の活用でコスト削減も可能です。
法律や設備との整合性にも注意し、信頼できる業者との連携で、安心・快適な医療空間を実現しましょう。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。