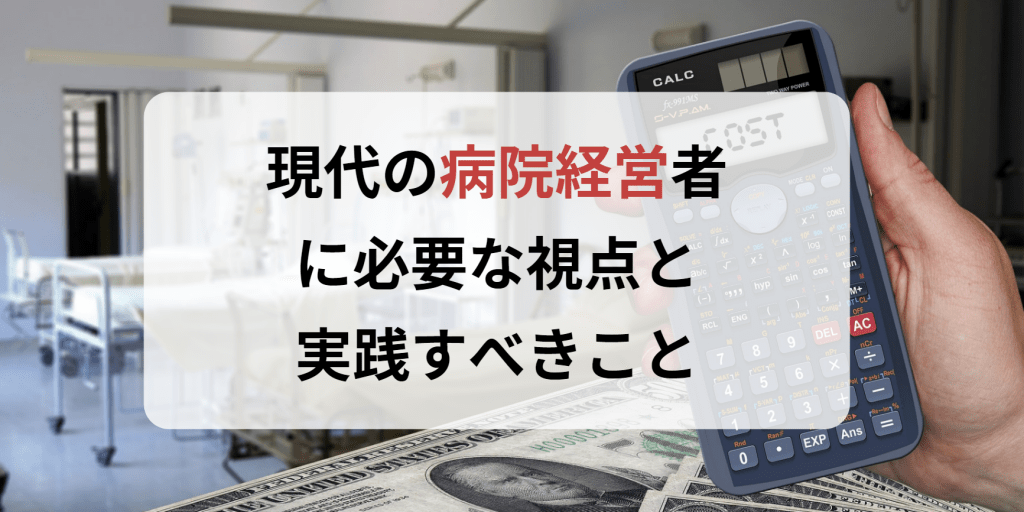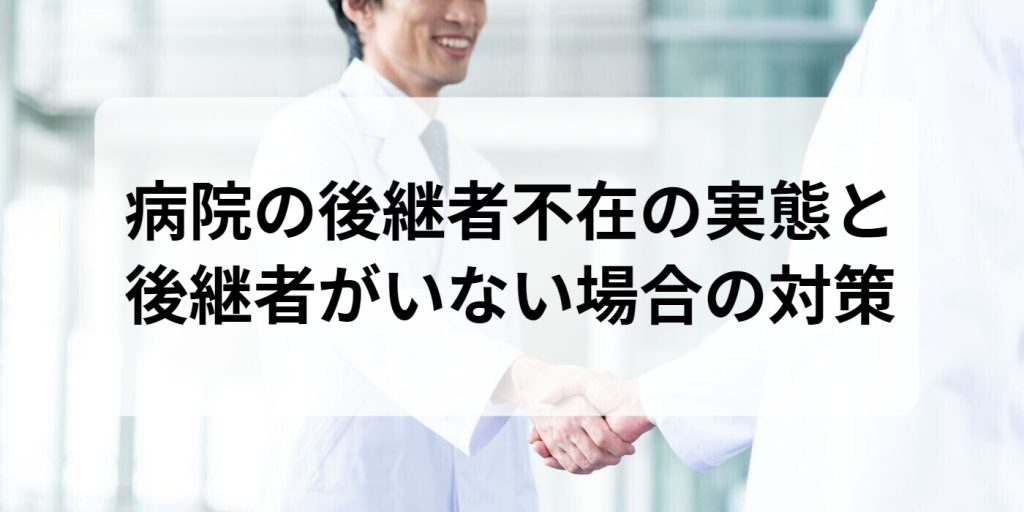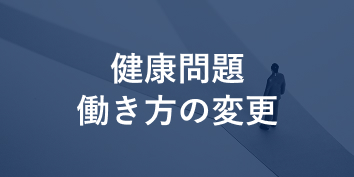クリニック無償譲渡のメリット・デメリットとは?税金や成功のポイントも解説

目次
「クリニックの後継者が見つからない」「経営状況が厳しくて買い手が見つからない」「院長の急病ですぐに承継先を探さなければならない」
このような状況から「無償譲渡」を検討される方は多くいらっしゃいます。承継開業を検討されている先生にとっては「無償譲渡のクリニックって大丈夫なのか?」と不安になることでしょう。
そこで本記事では、クリニックが無償譲渡を検討する背景から無償譲渡のメリット・デメリット、税務上の注意点を解説いたします。
この記事を読むことで、無償譲渡で譲ろうと思っている方は「無償譲渡以外の選択肢」が増え、譲り受けようと思っている方は、リスクを理解した上での適切な承継開業が実現します。
無償譲渡とは対価を受け取らずに財産を譲ること
無償譲渡とは、文字通り「無償」で財産を他者に譲り渡すことをいいます。クリニックの場合は医療機器や内装、患者情報、営業権などの資産を、金銭の授受なしに承継することを指します。
通常の医院継承では、クリニックの資産価値や将来性を評価して譲渡価格を設定しますが、無償譲渡では金銭的な対価は発生しません。
ただし、借入金などの負債については「買い手側が引き継ぐ」「売り手側が処理する」「一部のみ引き継ぐ」など、契約によって取り扱いが異なります。
無償譲渡と贈与の違い
無償譲渡と贈与では、言葉の意味に違いはありません。法律上は「贈与」という言葉で統一されており、税務上も贈与として扱われます。
ただしM&Aなどでは「無償譲渡」という表現が使われることも多く、本記事でも「無償譲渡」として解説を続けます。重要なのは、法律上は贈与として取り扱われるため、贈与税の課税対象となる可能性があることです。
クリニックが無償譲渡を検討する背景
クリニックのM&Aでは「無償で譲渡します」という案件もあります。
承継開業を検討されている先生の中には「経営上問題があるから無償譲渡するのでは?」という不安を抱く方もいらっしゃるでしょう。確かに無償譲渡にはさまざまな背景がありますが、必ずしも経営状況が悪いからとは限りません。
ここでは「なぜ有償ではなく無償譲渡を検討するのか」その主な背景を紹介します。
院長が急に倒れた
最も緊急性の高いケースが、現院長の急病や急逝です。クリニックの経営は院長の診療に依存しているケースも多く、院長が倒れてしまうと経営が困難になります。後継者の目星が付いていたなら問題はありませんが、近年は後継者不在が深刻な問題にもなっています。
後継者がいない場合には承継先をじっくり探している余裕もないため、無償譲渡によって迅速に承継する必要性が出てくるわけです。クリニックを存続させて患者や地域住民への影響を最小限に抑えるためにも、無償譲渡を選択されるケースがあります。
関連記事:院長が急逝したら閉院?手続きの流れやよくあるトラブルと解決法を紹介
買い手が見つからなかった
M&Aによる医院継承では条件とタイミングが非常に重要で、有償での買い手が見つからないケースもあります。たとえば以下のような状況では、買い手候補が限定されたり難色を示されたりすることもあります。
- 人口減少が進んでいる地域のクリニック
- 専門性が高く、対応できる医師が限られる診療科
- 競合の多い激戦区
- 追加で設備投資が必要な古い施設
特にクリニックの状況に対して譲渡価格が高額な場合は、買い手候補が出てこなかったりマッチングをしても「価格交渉」が発生したりすることも多いです。
売り手側の先生としても、長年築き上げてきたクリニックを手放すわけですから「これ以上は条件を下げられない」という方もいらっしゃいます。そのような場合は、やはり成約まで行かないことも多く、また次の買い手候補者が現れるまで時間がかかるものです。
そうこうしているうちに、院長の体調が悪くなったり急病で倒れてしまったりと、買い手候補者を探している時間が無くなることもあります。
時間をかけて後継者を探すつもりだったものの条件とタイミングが合わず、最終的に無償譲渡で承継先を探されるケースもあります。
赤字経営が続いている
中には単純に経営状況が悪いことが理由で、無償譲渡にしているクリニックもあります。
借入金が多額で売上に対して返済負担が重い状況や、慢性的な患者数の減少によって資産価値がマイナスになっている場合では、有償での譲渡は現実的ではありません。
ただし、赤字の原因はさまざまにあり、必ずしも「黒字転換しない」とは限りません。
たとえば、以下のような要因で一時的に赤字になっている場合もあります。
- 院長の体調不良による診療日数の減少
- 競合クリニックの開設による一時的な患者数の減少
- 設備投資による償却負担の増加
- スタッフ不足による診療体制の縮小
このような場合、医療業界に精通した仲介会社に相談することで、経営状況の改善方法や将来性について専門的な分析を受けられます。
結果として、無償譲渡ではなく有償での譲渡が可能になるケースもあります。また買い手側も、特に無償譲渡のクリニックの案件は経営状況を入念に把握したいでしょう。
信頼できる仲介会社を通じて入念なデューデリジェンス(詳細調査)を行えば、無償譲渡になっている背景がわかり、そのクリニックの将来性も見えてくるので安心です。
▶無償譲渡も含めたクリニック売却・譲渡(M&A)の進め方を確認する
無償譲渡のメリット
無償譲渡にはさまざまな背景や理由がありますが、売り手と買い手双方にとってメリットもあります。特に通常のM&Aでは時間やコストがかかる部分を簡素化できるため、状況によっては有償譲渡よりも効率的に医院継承を実現できる場合もあるのです。
ここでは無償譲渡の主なメリットを、譲渡側と譲受側それぞれの視点から詳しく解説します。
【譲渡側】後継者が見つかりやすい
無償譲渡の最大のメリットは、後継者が見つかりやすくなることです。
通常のM&Aでは、買い手側は数千万円から億単位の資金調達が必要になります。
特に初めてクリニックを開業される先生にとって「数千万から億単位の出費が発生する」というのは非常にインパクトが強く「契約しても大丈夫だろうか」「失敗して多額の借金が残ったらどうしようか」と不安になり、契約にまでなかなか進めない方もいらっしゃいます。
特に以下のような医師にとって、無償譲渡は魅力的な選択肢です。
- 開業資金に限りがある若手医師
- 勤務医から開業医への転身を考える医師
- 地域医療への貢献を重視する医師
- リスクを抑えて開業したい医師
候補者が増えることで、より適切な後継者を見つけられる可能性が高まります。
【譲渡側】マッチングから契約までがスムーズ
有償によるM&Aの場合は、最終的に金額面で折り合いが付かずに破談となるケースも多々あります。
資産価値の評価や将来性の見込み、リスクの評価などで、売り手と買い手の認識にギャップが生じることは、クリニックに限らずM&Aにおいてよくある話です。無償譲渡の場合は金額面のやりとりがない分、契約までスムーズに行きやすくなります。
ただし負債がある場合は、後々トラブルにならないためにも、取り扱いや引き継ぎ条件についてしっかりと話し合っておく必要があります。
【譲受側】開業コストを大幅に抑えられる
承継開業を検討している先生にとって最大のメリットは、開業コストを大幅に抑えられることです。
通常の新規開業の場合、以下のような費用が必要になります。
- 物件取得費用(敷金・礼金・保証金など)
- 内装工事費用
- 医療機器購入費用
- 電子カルテシステム導入費用
- 広告宣伝費用
関連記事:クリニックの開業資金はいくら必要?診療科目別でわかる費用や調達方法を紹介
診療科目や規模によっても異なりますが、一般的に新規開業の費用は5,000万円から1億円程度が必要です。無償譲渡による承継開業では、これらの多くを引き継げるので、開業資金を大幅に節約できます。初期投資の負担が軽減される分、より安定したクリニック経営にもつながります。
無償譲渡のデメリット
無償譲渡には注意すべきデメリットも存在します。特に金銭の授受がないからこそ見落としがちなリスクや、契約後に発覚する問題もあるため、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
ここでは譲渡側と譲受側、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
【譲渡側】クリニックの経営方針が変わる可能性がある
無償譲渡に限ったことではありませんが、譲受側によってクリニックの経営方針が変わったり、従業員の待遇が変わったりする可能性があります。
たとえば、承継後に以下のようにクリニックの環境が変化することもあります。
- 診療方針の大幅な変更
- スタッフの入れ替え
- 診療時間や休診日の変更
- 医療サービスの内容変更
一刻を争うため無償譲渡を検討している場合でも、残っている従業員や患者が満足できるように、譲受側の意向などを確認しておくことが重要です。
【譲受側】負債を引き継ぐ可能性がある
無償譲渡では、資産だけでなく負債も引き継ぐ可能性があります。
主な負債として、以下のようなものがあります。
- 医療機器のリース残債
- 銀行借入金
- 買掛金(薬品代、材料費など)
- 未払い給与や社会保険料
- 税金の滞納
特に経営状況が悪化しているクリニックでは、隠れた負債が存在する可能性もあります。無償譲渡だからといって安易に引き受けるのではなく、財務状況をしっかりと調査(デューデリジェンス)することが不可欠です。
また、負債の引き継ぎ方法についても、あらかじめ明確にしておく必要があります。
すべての負債を引き継ぐのか一部のみなのか、または負債は譲渡側が処理するのかを、契約書に明記することが欠かせません。たとえ親族内で無償譲渡(親族内承継)を行う場合でも、個人間で手続きを行うと負債の見落としや契約上のトラブルが発生するリスクがあるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
クリニックの無償譲渡で発生する税金
クリニックの無償譲渡は金銭の授受はありませんが、税務上は「贈与」として扱われるため、税金が発生する可能性があります。譲渡側と譲り受ける側、それぞれの税金について解説します。
譲渡側に発生する税金
クリニックを無償譲渡した場合、譲渡側(現院長)には「みなし譲渡所得税」が発生する可能性があります。税法上では無償譲渡を「適正な時価で売却し、その代金を贈与した」と解釈するためです。
そのため、実際には金銭の授受がなくても、税務上は「時価での売却」として扱われます。みなし譲渡所得税が発生する可能性があるのは、開業時の投資額よりもクリニックの時価評価額が高い場合です。
たとえば立地が良く不動産価値が開業時に比べて上昇している場合や、医療機器や設備の簿価よりも時価評価額が高い場合などが該当します。特に「みなし譲渡所得税」は申告漏れが起きやすく、専門家による判断が必要な内容です。
無償譲渡を行う場合は、税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
譲り受ける側に発生する税金
クリニックを無償で譲り受けた側(後継者)には、贈与税が発生する可能性があります。無償で取得したクリニックは、税務上「贈与を受けた財産」として扱われるため、贈与税の課税対象となります。
課税対象となるのは、クリニックの時価評価額が贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超える場合です。贈与税には累進税率が採用されており、贈与財産の価額が高くなるほど税率も高くなります。(最大55%)クリニックの場合は譲渡(贈与)の規模が大きいため、譲り受けた側の贈与税の負担も大きくなりがちです。
また院長が亡くなり、遺族がクリニックを引き継いだなどのケースでは、贈与税ではなく「相続税」の課税対象となります。相続税も累進税率になっていて、相続した資産に対して最大55%の税率が課せられます。
クリニックの無償譲渡を成功させるためのポイント
特に第三者への無償譲渡は、急いで承継先を見つける必要がある場合に検討される承継方法です。
しかし、慌てて承継先を見つけようとすると、契約で不備が出てしまったり思わぬ税金が発生したりと、さまざまなトラブルが発生する可能性もあります。円滑にクリニックの無償譲渡を行うためにも、譲渡側と譲り受ける側それぞれが押さえておくべきポイントを解説します。
信頼できる専門家を見つける
無償譲渡を成功させるためには、医療業界のM&Aに精通している専門家(仲介会社)のサポートは欠かせません。医院継承は複雑な税務処理や医療法に基づいた手続きが必要になり、負債の詳細調査や医療業界特有の法規制への対応も必要だからです。
仲介会社を選ぶ際には、担当者との相性や信頼関係も重要です。残念ながら仲介会社の中には自社の利益が出る案件を優先し、さらに半ば強引に成約へと結びつけようとするところもあります。
こちらの意向を理解し、適切なアドバイスをしてくれる担当者かどうかを見極めましょう。また1社だけに依頼するのではなく、複数の仲介会社を活用することで、より適切な後継者を見つけられる可能性が高まります。
譲渡の計画は早めにしておく
無償譲渡を検討する状況になってからでは選択肢が限られてくるため、可能な限り早めに譲渡計画を立てておきましょう。医師の多くは日々の診療に追われ、承継について具体的に考え始めるのが体調に不安を感じてからという方も多くいらっしゃいます。
しかし、この段階で承継先を探すとなると時間的な制約も出てくるため、結果として無償譲渡を選択せざるを得ない状況に陥りがちです。
早めに承継について計画をしておけば、まずは有償での医院継承から十分に検討ができます。時間をかけて適切な後継者を探すことで、クリニックの価値を正当に評価してくれる先生と出会える可能性も高まります。
また担当者と定期的にコミュニケーションを取っておくことで、万が一院長が急逝してしまったときでも安心です。担当者は院長の意向やクリニックの状況をしっかりと把握できているため、タイムリミットが短い中でも迅速に最適な後継者を見つけられるためです。
余裕を持った医院継承の計画によって、一刻を争う事態になった場合でも有償による譲渡先が見つかる可能性もあります。
赤字や院長の急逝でもまずは有償譲渡から検討する
クリニックの赤字経営が続いていたり、院長の急逝などで急いで後継者を見つけなければならなかったりすると「無償でいいから、とにかく後継者を見つけたい」と考えるのも普通のことだと思います。
しかしこのような状況下でも、まずは有償譲渡の可能性を探りましょう。赤字経営だったとしても、状況によっては買い手候補者が見つかるためです。
たとえば以下のような状況の場合、有償譲渡も十分可能です。
- 立地が良好で将来性がある
- 専門性が高く競合が少ない
- 患者基盤がしっかりしている
- 設備が新しく追加投資が不要
特に院長が亡くなって遺族が相続した場合には、クリニックを有償譲渡する際の「譲渡所得税」を軽減できる可能性があります。
「取得費加算の特例」により、支払った相続税の一部を譲渡所得の計算上、取得費に加算できるため、譲渡所得税の負担を軽減できるのです。
つまり、相続税を支払った後にクリニックを有償譲渡する場合、譲渡益に対して「譲渡所得税」が課税されるのですが、この特例を使うことで譲渡所得税を大幅に軽減できるのです。
ただし、取得費加算の特例制度を利用するには期限や条件などもあるため、詳しくは税理士などの専門家に相談しましょう。
無償譲渡は「承継先がどうしても見つからない」「とにかく急いで後継者を見つけなければならない」という状況下において効果的な承継方法ではありますが、これまで築き上げてきたクリニックの価値に対して、適切な報酬を受け取れるように検討することも重要です。
まとめ:クリニックの無償譲渡は医院継承の専門家に相談を
クリニックの無償譲渡は、後継者を見つけやすく契約がスムーズに進む一方で、税務上の問題や負債の引き継ぎなど、注意すべき点も多くあります。
特に「みなし譲渡所得税」や贈与税といった複雑な税務処理、医療法に基づいた手続きなどを専門知識なしに進めるのは現実的ではありません。
余裕の無い状況であるほど、医療業界のM&Aに精通した専門家に相談をおすすめします。医院継承は患者や地域住民、従業員など多くの関係者に影響を与える決断ですので、慎重に進めなければなりません。
無償譲渡のクリニックで開業を検討されている先生も、思わぬ負債などで失敗しないために、担当者と相談をしながら入念にデューデリジェンスを行うことをおすすめします。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。
について-1024x512.png)