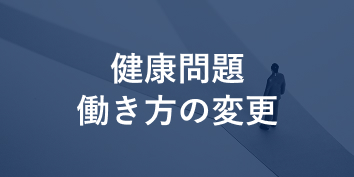医療機関のデジタルサイネージ活用事例は?導入ポイントや自作の方法も解説

目次
デジタルサイネージとは、ディスプレイなどを使ってサービス内容の発信や、電光掲示板などの役割ができるシステムのことです。医療機関では待合室での診察順の表示や健康情報の発信、院内マップの案内などに活用されています。
紙のポスターとは異なり、簡単に内容を更新できて動画も流せるため、患者の注目を集めやすいというメリットがある一方で「広告規制」に注意しなければなりません。
そこで本記事ではデジタルサイネージの種類から活用事例、注意すべきポイントを詳しく解説します。
低コストで導入できる「デジタルサイネージの自作方法」も紹介しているので、最後までぜひご覧ください。
医療機関に最適なデジタルサイネージの種類
「デジタルサイネージ」には数多くの種類があります。
中でも、特に医療機関が導入しやすい種類のデジタルサイネージは、下記の3つです。
| ネットワークタイプ | インターネット経由で配信するコンテンツを一括管理、配信できるタイプ。医療機関内での複数のデジタルサイネージの管理や、待合室での診察状況のリアルタイム表示などに適しています。 |
| スタンドアロンタイプ | ネットワークには接続せず、USBメモリなどで単独で動作するタイプ。初期費用が安く、院内の基本情報や診療案内の表示に適しています。インターネット環境が不要なため、セキュリティリスクも低減できます。 |
| インタラクティブ | タッチパネル式で患者が操作もできるタイプ。院内マップの検索などができて、AIの技術によって目の前の患者のニーズに合わせたコンテンツ配信などもできます。 |
デジタルサイネージを導入する際には、それぞれの医療機関の目的に合わせて最適なタイプを選びましょう。
医療機関がデジタルサイネージで配信している事例
医療機関では患者への情報提供や医療サービスの紹介、施設案内などでデジタルサイネージが多く活用されています。
従来の紙のポスターやパンフレットと比べて、動画などのコンテンツは患者の関心を惹きやすく、また情報の更新も簡単なためです。
ここでは、医療機関で実際に行われている、デジタルサイネージの活用事例をご紹介します。
診療サービスの紹介
医療機関の存在や診療サービスの認知を広げるために、クリニックで提供している診療サービスなどを配信しているケースは多くあります。
たとえば屋外の入口にデジタルサイネージを設置し、クリニックの特徴から診療内容などを配信することで、行き交う人に対してクリニックの存在を認知してもらえるでしょう。
また歯科クリニックなら、待合室などでセラミック治療やインプラントなどの料金、ビフォーアフターの写真などをわかりやすく配信することで、特に女性の患者に対して診療サービスの認知ができます。
院内設備やフロアの案内
大規模な総合病院などでは、患者が迷わないためにデジタルサイネージを院内各所に設置しているケースも増えています。
たとえばエレベーターホールにデジタルサイネージを設置し、フロアマップなどを表示することで、エレベーターから降りた患者は迷わずに目的の場所にたどり着けるでしょう。
また病院の入口付近に、タッチパネル式のデジタルサイネージが設置されているケースも多いです。院内の施設や病室を簡単に検索できるため、初めて病院を訪れる患者やお見舞いに来られた方も安心できます。
待ち時間や診療対応時間などの案内
多くの患者が不満に感じる「待ち時間」の問題解決として、デジタルサイネージを導入する医療機関も増えています。
たとえば待合室の壁にデジタルサイネージを設置し、患者の番号が表示されるシステムを導入するケースです。
デジタルサイネージで表示されている内容はスマホと連動もできるため、患者は自身のスマホでも現在呼ばれている番号や、診療までの待ち時間が把握できます。
このシステムによって、患者は「常に待合室で待たないといけない」というストレスから開放され、待ち時間を活用して買い物なども可能です。
医療機関がデジタルサイネージを導入するメリット
医療機関にデジタルサイネージを導入することで、患者サービスの向上や業務効率化など多くのメリットが生まれます。
ここでは、医療機関がデジタルサイネージを導入する主なメリットを4つ解説します。
認知や集患につながる
医療機関の外壁や入口付近にデジタルサイネージを設置することで、通行人や来院者の目を惹き、クリニックの認知度向上に効果を発揮します。
特に新規開業のクリニックは認知度が低いため、診療内容や専門性をデジタルサイネージで配信することも、重要な施策といえるでしょう。また従来の看板と違い、時間帯や曜日によって表示内容を変更できる点も大きな特徴です。
たとえば午前中は「健診のご案内」を表示し、仕事帰りの人が多くなる夕方には「インフルエンザ予防接種の受付中」など、時間帯によって興味を惹きやすい内容に変更することも効果的な認知方法です。
設置場所によっては24時間表示させることも可能なため、休診日や診療時間外でもクリニックの特色が配信できて、新規患者の獲得にもつながります。
紙媒体による作成の手間が減る
紙ポスターやパンフレットでは、デザイン制作から印刷、掲示という工程に加え、情報が古くなれば張り替えが必要で、そのたびに時間と費用がかかります。
デジタルサイネージなら一度コンテンツを作成すれば、あとはシステム上で簡単に更新できるため、長期的に見れば印刷コストや作業時間の大幅な削減につながります。
特に医療機関では、季節性の疾患情報や予防接種のお知らせなど、定期的に内容を更新する必要があるケースも多く、デジタル化によるメリットは大きいといえるでしょう。
またクリニックなどでは、スタッフが紙媒体のポスターやパンフレットなどを作成しているところも多いでしょう。
デジタルサイネージを導入することで、スタッフは本来の医療に関する業務に集中できます。
患者のプライバシーの配慮につながる
医療機関の中には、患者の呼び出し方法として「〇〇さん、診察室へどうぞ」といったアナウンスを行っているところも多いでしょう。
特に心療内科や婦人科など、受診していることが周囲に知られたくない診療科では、このアナウンス方法が患者にとってストレスとなる傾向があります。
デジタルサイネージを活用した番号呼び出しシステムを導入すれば、患者は名前を呼ばれることなく自分の順番を確認できます。
これにより、待合室にいるほかの患者に診療科や名前を知られることがないので、患者は安心して診察が受けられるわけです。デジタルサイネージを導入することは、患者が安心して来院できる環境づくりにつながります。
患者の待ち時間のストレス軽減につながる
「医療機関に対する不満ランキング」で常にトップに出てくるほど、医療機関の待ち時間の長さは患者にとってストレスの大きな要因です。
デジタルサイネージを導入して待ち状況をリアルタイムに表示したり、診察が始まるまでの目安の時間を提示したりして、患者の待ち時間に関するストレスを軽減できます。
また、待ち時間中に健康情報や医療コラム、季節の話題など有益なコンテンツを配信することで、患者は単に「待つ」だけでなく「知る」時間として有効活用も可能です。
特に小児科では、子ども向けのアニメーションを流すことで、子どもの退屈を紛らわせるとともに、親も待ち時間を落ち着いて過ごせるでしょう。
さらに、現在の待ち人数をスマートフォンで確認できるシステムにすれば、患者は近隣のカフェなどで待つこともでき、待合室の混雑状況を緩和できて患者満足度の向上も同時に実現ができます。
医療機関がデジタルサイネージを導入するデメリット
デジタルサイネージは多くのメリットをもたらす一方で、医療機関特有の課題もあります。
導入を検討する際にはあらかじめデメリットを理解し、対策を行うことも重要です。
ここでは医療機関がデジタルサイネージを導入する際のデメリットを2つ紹介します。
広告規制などで配信内容が制限される
医療機関が配信する広告には、医療法による厳しい規制が設けられているので注意しましょう。配信内容によっては「広告」に該当し、医療機関が表示できる内容には多くの制約が生じるものもあります。
たとえば「最高の技術」「安全な治療」といった表現や、治療の効果に関する患者の体験談、症例写真のビフォーアフターを掲載する場合も規制を守らなければなりません。
万が一、配信している内容が「医療広告ガイドライン」に反していた場合には、行政から是正の指導が入ります。
是正に従わなかった場合には、懲役や罰金などの罰則に加えて、クリニックの開設許可取り消しなど、非常に重たい行政処分を受ける場合もあるので十分に注意しなければなりません。
これは、たとえ待合室内の表示であっても、医療広告ガイドラインに則った内容にする必要があります。
操作方法の周知や配信内容の管理が大変
デジタルサイネージを導入する際には、更新方法や操作手順をスタッフに周知する必要もありますが、多忙な医療現場でマニュアルや操作方法の共有は容易ではないでしょう。
また、誰がどのようなタイミングで情報を更新するのか、その責任者や手順を明確にしておかないと、古い情報が表示されたままになったり、複数の担当者による操作で内容が上書きされたりするトラブルも発生します。
システムトラブルが発生した際にもすぐ対応できるように、ある程度知識を持ったスタッフの教育やシフト調整も必要なケースもあるでしょう。
デジタルサイネージの導入によって、スタッフの教育や管理などの手間が増える点はデメリットといえます。
デジタルサイネージ導入の料金相場
医療機関でデジタルサイネージを導入する際の費用は、機器の種類や性能、設置方法などによって大きく変動します。
【導入で必要なものと費用の目安】
| 必要なもの | 費用の目安 | 内容 |
| ディスプレイ | 10万〜100万円 | 一般的なサイズ43〜55インチ程度屋外に設置する場合には防水機能なども必要になるため費用は高くなる傾向 |
| 設置機材 | 無料〜20万円 | 壁掛けや天吊り、スタンド式など設置方法や依頼した業者によっても料金が変動 |
| セットトップボックス(コンテンツ再生用の機器) | 無料〜30万円 | USBを差し込むタイプの「スタンドアロン型」は比較的安価な傾向にあり、インターネット上で配信を管理する「ネットワーク配信型」は高額な傾向にある |
| コンテンツ制作費用 | 無料〜15万円 | 自作する場合は不要制作会社に依頼する場合は2〜3分程度の動画で10万円程度の費用が目安 |
| その他 | 数万円程度 | 業者によっては保守点検費用や管理費などが必要また、ランニングコストとして電気代が数千円程度 |
デジタルサイネージを導入する場合、初期費用としてトータル30万〜100万円程度は必要です。
デジタルサイネージを導入する際に使える補助金
医療機関がデジタルサイネージを導入する際には、政府や自治体の補助金制度を活用できる場合があります。
特に利用しやすいのは「IT導入補助金」で、デジタル化による業務効率化や生産性向上を目的とした制度です。IT導入補助金では、最大450万円まで補助が受けられます。
「小規模事業者持続化補助金」も、デジタルサイネージの導入時に使える補助金で、最大200万円まで補助が受けられます。
補助金は返済が不要ですので、要件を満たしているのであれば利用しないと損ともいえます。
デジタルサイネージの導入を検討している場合は、補助金を活用できるかチェックしておきましょう。
関連記事:IT導入補助金とは?医療機関向けに活用術をわかりやすく開設!
医療機関がデジタルサイネージを導入する際のポイント
医療機関がデジタルサイネージを導入する際には、一般企業とは異なる特有の注意点があります。
広告規制への対応や静かな診療環境への配慮など、医療現場ならではの要素も考慮しなければなりません。
ここでは、デジタルサイネージ導入時のポイントを3つ開設します。
医療の規制に精通している業者を選ぶ
医療機関でデジタルサイネージを導入する際に最も重要なのは、医療広告に関する規制を理解している業者を選ぶことです。
医療広告ガイドラインに違反した内容を配信すると、行政指導や罰則の対象となる可能性があるためです。
一般的なデジタルサイネージの業者に依頼した場合、医療機関特有の規制を把握しないままコンテンツを作ってしまい、罰則や行政処分などにつながるリスクが発生してしまいます。
また、医療機関の特性上配信するコンテンツの「音量」についても考慮しなければなりません。基本的に大きな音量は出せないため、字幕や映像のみで内容が伝わるコンテンツづくりも大切です。
行政から指導を受けないためにも、医療業界でのコンテンツ作成を専門とした業者を選びましょう。
アフターフォローの内容を確認する
トラブルや故障などの万が一に備えて、アフターフォローの内容を確認しておきましょう。
特にデジタルサイネージを使って患者の呼び出しを行っている場合には、システムエラーによって使えなくなった場合でも、すぐに対処してもらえるかどうかが重要です。
主に、以下のような内容を確認しておけば、いざというときも安心です。
- トラブル発生時の対応時間(24時間対応してもらえるか)
- 代替機器の貸出サービスの有無
- 保守契約の内容や費用
- 定期メンテナンスの有無
コンテンツを更新する際に必要な費用を確認する
デジタルサイネージを導入する際には、初期費用だけでなく「コンテンツの内容を更新する際の費用」についても確認しておきましょう。
初期費用は明確に提示されていても、コンテンツの更新にかかる費用は見積もりに含まれていないケースもあるためです。
特に医療機関では季節特有の健康情報の配信など、定期的なコンテンツ更新が必要なことも多いので、更新費用の確認が重要です。
自院でコンテンツを更新できるシステムなのか、更新を委託する必要がある場合には1回あたりの更新費用を確認しておきましょう。導入後に思わぬ追加の費用が発生しないためにも、更新費用の確認は重要です。
医療機関がデジタルサイネージを自作する方法
デジタルサイネージの導入は、専門業者に依頼したほうが高品質なコンテンツを作れるのは当然のことです。
しかし、初期費用やランニングコストを見てみると、手軽に導入できる金額ともいえません。
可能な限り費用を抑えてデジタルサイネージを導入したい場合「自作」という方法もあります。自作なら、数万円程度でデジタルサイネージの導入も可能です。
ここでは、自作でデジタルサイネージを導入する手順を紹介します。
1.必要な機材を購入する
まずはデジタルサイネージの導入に必要な機材を購入しましょう。
最低限必要な機材は、以下の3点です。
- ディスプレイ
- 映像の再生機器(USBメディアプレイヤーなど)
- 設置器具
USBメモリやSDカードを再生できるタイプのディスプレイを選んだり、ディスプレイに直接パソコンを接続したりする場合、再生機器は不要です。
ディスプレイはサイズが小さいと視認性が悪くなるため、一般的には40〜55インチ程度が良いとされていますが、実際に設置する場所を考慮しながら選びましょう。
2.配信する内容を自作する
機材が用意できたら、実際に配信する内容(コンテンツ)をパソコンで制作します。
「PowerPoint」や「Canva」なら、無料版でも充分なコンテンツが作れるのでおすすめです。
繰り返しになりますが、医療機関が「広告」を配信する際には、下記の表現が禁止されています。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の
写真等の広告
出典:厚生労働省|医療広告ガイドライン
特に医療サービスに関する内容は「広告」として認識される可能性が高いため、表現には注意しなければなりません。
3.ディスプレイで配信をする
コンテンツが完成したら、下記いずれかの方法で実際に配信を行います。
【コンテンツの配信方法】
- パソコンを接続して配信する
- USBメモリーやSDカードを差し込んで配信する
コンテンツをチェックして、問題がなければ自作のデジタルサイネージが完成です。
ただ自作のデジタルサイネージは屋外には不向きなので、あくまで院内などで使用することをおすすめします。
一般的に売られているディスプレイは屋内使用が前提なので、雨や砂埃などに弱く故障しやすいためです。
デジタルサイネージを自作するメリット・デメリット
医療機関がデジタルサイネージを自作する際の、メリットとデメリットは下記のとおりです。
| メリット | デメリット |
| 導入費用が安く抑えられるコンテンツの自由度が高いコンテンツを更新しやすい | コンテンツづくりに時間がかかる医療広告ガイドラインを理解する必要があるプロに比べてコンテンツの品質が見劣りする |
デジタルサイネージを自作した場合、最大のメリットは「安さ」といえるでしょう。
コンテンツ制作に必要なソフトは無料のものも多いため、極端な話「ディスプレイ」とパソコンさえあればデジタルサイネージは導入できます。
しかし動画編集ソフトなどの使い方を知らない人の場合、たった数分の内容を作るだけでも何時間もの作業が必要です。
さらに、広告規制や高品質なコンテンツを作成するための知識も必要です。
ITやデザインに詳しいスタッフがいる場合は、自作の「安く抑えられる」というメリットを活かせる可能性は高いでしょう。
あまり知識が無い場合はデメリットのほうが大きいため、業者に依頼することをおすすめします。
医療業界の規制に注意しながらデジタルサイネージの導入をしましょう
デジタルサイネージは医療サービスの認知や患者のストレス軽減、プライバシーの配慮など、さまざまな効果が期待できます。
特に新規開業の場合、屋外にデジタルサイネージを設置することで、認知拡大に貢献できるでしょう。ただし、医療機関は「医療広告ガイドライン」を守らなければなりません。
行政処分などのリスクを負わないためにも、業者に依頼する場合は医療業界の規制に精通しているか、必ずチェックしましょう。
また、すでに地域で認知されているクリニックを承継する「医院継承」なら、開業後に多くの先生が悩まされる「集患問題」も軽減されます。
クリニックの開業などをお考えでしたら、医院継承も視野に入れてみることをおすすめします。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。
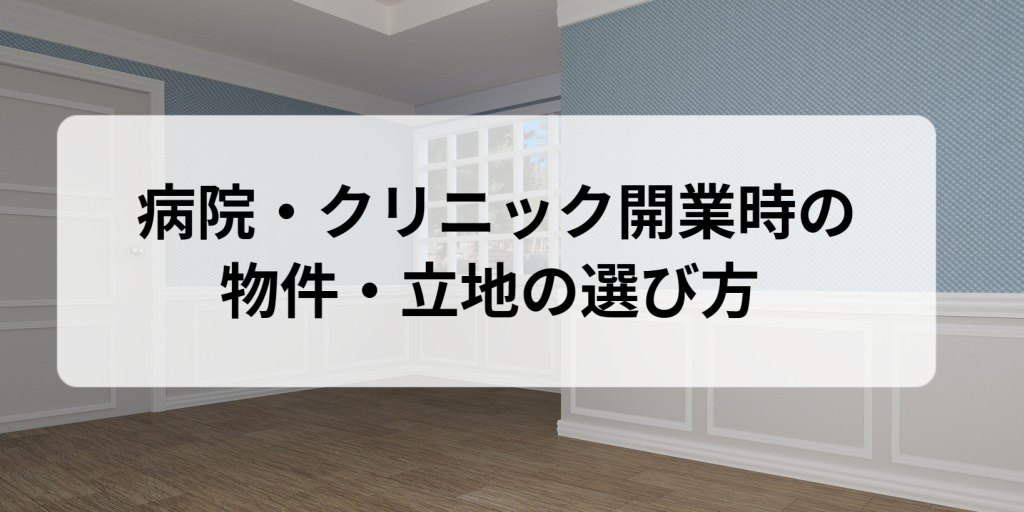
。必要な手続きやよくあるトラブルとは?-1024x512.jpg)