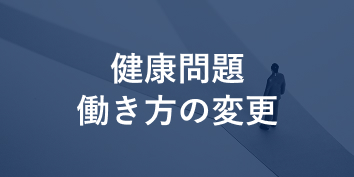みなし配当とは?クリニックで発生するケースや税務処理の方法を解説

目次
「みなし配当というワードを耳にするけれど、実際にはどのように発生するのだろう?」
「単に株式を譲渡しただけなのに、どうして配当として課税されるのだろう?」
税務処理において「みなし配当」は極めて複雑な概念であるため、組織再編や株式取引を実施する際に悩むケースが多いでしょう。
この記事では、みなし配当の根本的な考え方から事例、適正な税務手続きの進め方まで詳しく解説します。
医療法人における「みなし配当」が起こる場面も含まれていますので、特にクリニックの譲渡や後継者による開業を考えている方は最後までお読みください。
みなし配当とは利益分配と捉えられて税金がかかるもの
みなし配当とは実質的には配当として支給されていなくても、法律上「収益の配分があった」と判断されて課税の対象になるものを指します。
たとえば医療法人なら出資者が持分を譲り渡したり、企業が自社株式を購入したりする場合において、その対価が出資金額を上回るとき、その超過した部分が「みなし配当」に該当します。
医療法人は経営の移転や組織の再構築などの状況で「みなし配当」が生じることもあり、あらかじめ把握しておかないと予期せぬ税負担が発生する恐れがあります。
みなし配当の基本的な計算式
みなし配当は基本的には「受領した金銭から最初の出資額(取得原価)を控除した金額」で計算します。
【みなし配当額 = 交付金額 – 資本金等の額に対応する部分】
例えば出資持分を有する医療法人が持分の払戻しを行う場合「受け取った払戻し金額」から「元々投資した出資金」を差し引いた額が「みなし配当」です。
上記の計算式は非常に単純化したもので、実際は取引の内容によって計算は少し異なるため、具体的に「みなし配当」を正確に把握したい場合は、税務の専門家に相談することをおすすめします。
みなし配当が発生した場合の主な税務処理の方法
みなし配当が発生した場合、支払う側や受け取る側の立場によって税務処理の仕方が変わります。
ここでは「配当を支払う立場の法人」「受け取る立場の法人」「受け取る立場の個人」それぞれの主な手続きや注意点を解説します。
みなし配当を支払った法人
みなし配当を支払う側の法人が実施すべき税務処理は、主に3つあります。
まず、みなし配当に該当する額に対して源泉徴収を実施する必要があります。個人の株主に支払う際は約20%の税率で源泉徴収を行います。
次に、源泉徴収した税額は「みなし配当を支払った月」の翌月10日までに税務署へ納めなければなりません。
また「配当等とみなす金額に関する支払調書」を作成し、支払いを行った月の翌月末日までに税務署へ提出する必要があります。株主に対しても「みなし配当」の生じた理由や金額などを伝達する必要があります。
みなし配当を受け取った法人
みなし配当を受け取った側の法人は、主に2つの税務処理を実行します。
「みなし配当」の部分については「受取配当金」として、みなし配当に該当しない部分(資本の払い戻し)については「株式の譲渡対価」として処理しなければなりません。
この計算結果がプラスであれば益金(収益)として、マイナスであれば損金(経費)として処理します。
また「受取配当金」は益金不算入制度の適用範囲となり、課税の対象から除くことができるケースもあるため「法人は「みなし配当」を益金不算入できる場合もある」の項目で詳しく説明しています。
みなし配当を受け取った個人
みなし配当を受け取った個人は、一般的な配当金と同様に「配当所得」として所得税や住民税の対象です。
税務処理の方式は、受け取った配当金が「上場会社からの配当」か「非上場会社からの配当」かにより異なります。
上場会社からの「みなし配当」は申告分離課税を選ぶことができ、税率は20.315%です。一方で非上場会社からの「みなし配当」は必ず総合課税となり、他の所得と合わせて最高45%の税率が適用されます。
また「みなし配当」に該当しない部分についても株式の譲渡損益として算出し、確定申告する必要があります。
法人は「みなし配当」を益金不算入できるケースもある
法人がみなし配当を受領した場合「益金不算入制度」を利用できるケースがあります。
益金不算入とは二重課税を回避するための制度で、受け取った配当金の全体または一部を課税対象から外せる仕組みです。
配当金は支給する側の法人で、すでに法人税が課税されているため、受け取る側でも全額課税すると、二重に課税されてしまいます。二重課税を防ぐため、みなし配当については株式の保有率に応じて20%から100%の不算入率が適用されるわけです。
特に100%子会社からの「みなし配当」や、株式保有率が3分の1を超える関連法人からの「みなし配当」は、全額が益金不算入になるケースがあります。
ただし、益金不算入が適用されないケースもあるため注意が必要です。
“益金不算入の規定が適用されないこととなる「自己株式等の取得が予定されている株式等」とは、法人が取得する株式等のうち、その株式等の取得時において、発行法人が自己株式等として取得することが具体的に予定されているものをいう。”
引用:国税庁|第1 法人税基本通達関係
益金不算入制度の適用条件は複雑であるため、みなし配当が発生する取引を検討する際は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
▶みなし配当など税務論点も含めたクリニック売却・譲渡(M&A)の進め方を確認する
一般企業で「みなし配当」が発生するケース
みなし配当は、さまざまな取引や組織再編の場面で発生します。
【みなし配当が発生するケース】
- 法人による自社株式の取得
- 資本剰余金を財源とする配当
- 解散後の残余財産の分配
- 企業の合併や分割
上記の取引を行った際に「みなし配当」が発生するケースがあるため、税務処理を行う際に注意しなければなりません。
それぞれ詳しく解説していきます。
法人による自己株式の取得
企業が株主から自社の株式を購入する「自己株式の取得」では、株主に支払う価格が株式の帳簿価額を超過する部分について「みなし配当」が生じます。
例えば、1株あたりの純資産額が5万円の企業が、株主から1株10万円で自社株式を買い取る場合、差額の5万円が「みなし配当」に該当します。
この取引は株主にとっては株式の譲渡のように見えますが、税務上は「会社の利益を株主へ分配した」と解釈されるのです。特に中小企業のオーナーが自社の株式を会社に売却する時に、注意しなければならないポイントです。
資本剰余金を原資とした配当
企業が株主へ配当を行う際、通常は利益剰余金から支出しますが、資本剰余金(資本準備金や資本金の減少によって生まれた剰余金など)から配当を行うケースがあります。
このように資本剰余金から配当が支給された場合でも、その一部は「みなし配当」として処理されます。これは実質的に、企業に蓄積された利益の分配と同等だと考えられるためです。
株主からすると単なる配当金の受け取りに見えますが、その原資が資本剰余金である場合、税務上の扱いが変化する可能性があるため注意が必要です。
解散による残余財産の分配
会社が解散して清算する際、株主に分配される残余財産が帳簿価額(取得原価)を超える部分については、みなし配当として処理されます。
例えば、1株10万円で取得した株式を持つ株主が、会社解散時に1株あたり30万円の残余財産を受領した場合、差額の20万円がみなし配当となります。
このケースも株主が株式と引き換えに現金を受け取る取引ですが、税務上は「企業に蓄積された利益の分配」とみなされるわけです。
特に収益性が高い事業を長期間運営してきた会社の解散では、多額の「みなし配当」が発生する可能性があるため、事前に税務上の影響を検討することが重要です。
会社の合併や分割
企業が合併や分割(会社分割)を実施する際にも、株主にみなし配当が発生することがあります。
合併では消滅する会社の株主が合併法人から対価を受け取る場合、その金額が元々の株式の帳簿価額を超える部分が「みなし配当」として扱われます。
たとえばA社とB社が合併してC社になる際に、B社の株主が合併の対価として株式の代わりに現金を受領したとして、この現金が株式の取得価額を上回る場合、その超過分が「みなし配当」に該当する計算です。会社分割でも同様に、分割法人の株主が分割承継法人から金銭等を受領し、その金額が株式の帳簿価額を超える場合は「みなし配当」として扱われます。
組織再編は単純な株式の売買とは異なり、法人の資産や負債が移転する取引になるため、株主が受け取る経済的利益についても特別な税務処理が必要になります。
クリニックでは出資持分がある場合に「みなし配当」が発生
出資持分のあるクリニックでは、医療法人の解散や社員の退社で「みなし配当」が生じます。
医療法人が解散する時に、社員(出資者)が受領した残余財産が初期の出資額を上回ると、その差額は「みなし配当」として課税対象になります。たとえば医療法人の設立時に100万円を出資した社員が、解散時に500万円の残余財産を受け取った場合、差額の400万円が「みなし配当」です。
また社員が医療法人から退社する際に、出資持分の払い戻しを受ける場合も同じです。
払い戻し額が出資額を超過する部分は「みなし配当」として扱われます。
これは医療法人が長期間にわたって積み上げてきた利益が、出資持分の払い戻しという形で出資者に配分されたと考えられるためです。
特に医療法人の事業継承や譲渡を検討する際には、この「みなし配当」による税負担に注意する必要があります。
出資持分のない医療法人に移行する場合
出資持分のある医療法人から「出資持分なし」へと移行する場合でも、移行方法によっては「みなし配当」が生じるケースがあります。
出資持分のない医療法人に、移行する際の状況別に説明します。
【全員が出資持分を放棄して移行する場合】
出資者は対価となる資金を受け取らないため、みなし配当も発生しません。
【出資持分の払い戻しを受けて移行する場合】
出資額を超える部分(利益剰余金部分)について、みなし配当として出資者側は所得税が課税されます。
【基金拠出型法人へ移行する場合】
出資額部分のみを基金とする場合:みなし配当は発生しません。
利益剰余金部分も含めて基金とする場合:超過分が「みなし配当」として出資者側が課税されます。
出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行において、みなし配当が生じるかどうかは「払い戻しを受けるか」「放棄するか」という選択と、移行先の法人形態によって決まります。
出資持分のないクリニックは「みなし配当」は発生しない
出資持分のない医療法人では、譲渡時でも退職時でも利益分配という概念が存在しないため基本的に「みなし配当」は発生しません。
持分がないということは、医療法人の財産に対する個人の権利が認められていないということであり、財産を払い戻す際の「利益の分配」という事態が起こらないためです。
ただし出資持分のないクリニックでも「みなし配当」以外の部分で税金の負担が増えるケースはあります。
たとえば一般的な水準よりも高額な退職金を支給した場合には、法人税法第34条2項に基づいて損金算入が認められない恐れがあります
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
出典:法人税 e-Gov法令検索|第34条2項
関連記事:病院・診療所を売却した際の退職金について
特にクリニックの事業継承では、スキームによって売り手側や買い手側の税負担などが大幅に変化します。
クリニックの医院継承を検討される際は、医療業界独自の法規制や税制にも詳しいM&A仲介業者に依頼することをおすすめします。
みなし配当に関する注意点
みなし配当は、特殊な税務処理が必要になるため、手続きが複雑だったり気付きにくかったりなど、いくつか注意点があります。
ここでは「みなし配当」に関する注意点を3つ解説していきます。
財務処理が複雑
みなし配当が生じると「みなし配当を行った法人」「みなし配当を受領した法人」「みなし配当を受けた個人」の3つの立場それぞれで異なる手続きが必要です。
| 立場 | 主な税務処理 |
| みなし配当を渡した法人 | みなし配当額に対する源泉徴収「配当等とみなす金額に関する支払調書」の作成・提出翌月10日までの納付手続き |
| みなし配当を受けた法人 | 受取配当金としての計上益金不算入制度の適用可否判断みなし譲渡損益の計算 |
| みなし配当を受けた個人 | 配当所得として確定申告課税方式の選択(総合課税か申告分離課税か)株式譲渡損益の計算 |
また、みなし配当に該当する金額と該当しない金額を適切に区別するためには、資本金等の額と利益積立金などの計算も必要です。
このような税務処理を、経営者自身が行うのは非常に難しいと言えるでしょう。
誤った処理は税務調査時の指摘や追加課税にもつながるため、税理士などの専門家に相談するほうが賢明です。
特に個人の税金負担が増加する
みなし配当が発生した場合、特に個人株主にとって税金の負担が重くなる傾向があります。
個人が「みなし配当」を受け取る場合は配当所得として扱われ、課税対象となるためです。
非上場企業からの「みなし配当」は必ず総合課税が適用され、他の所得と合算して累進税率が課されます。所得税(最高45%)と住民税(一律10%)を合計すると、最大で55%もの税率が適用される可能性もあるのです。
上場企業の通常の配当金であれば、申告分離課税を選択することで一律20.315%の税率に抑えることが可能です。これは医療法人の出資持分の払い戻しや譲渡、クリニックのM&Aに関わる取引においても、個人の税負担に大きく影響するため事前の確認が不可欠です。
発生していることに気付きにくい
みなし配当は、実際に配当金として支給されるわけではないため、発生したことに気づきにくいという特徴があります。
特に医療法人の出資持分の払い戻しや譲渡のような取引では「株式の売買」や「持分の譲渡」と認識していることが多く、みなし配当が発生することを見落としがちです。
たとえばクリニックの院長が出資持分を譲渡した際に、受領した対価が単なる「持分の売却代金」ではなく、一部は「みなし配当」として異なる税務処理が必要になることを認識していないケースも見られます。
みなし配当が発生していることに気づかないと源泉徴収漏れや申告漏れにつながり、後で税務調査で指摘された際に、追加課税やペナルティの対象となる可能性があります。
本記事で紹介したような「みなし配当」が発生する可能性のある取引を行う際には、専門家への相談が重要です。
みなし配当が発生する取引では専門家のサポートを受けましょう
みなし配当は配当として支給していなくても「利益の分配があった」とみなされ課税対象となる複雑な仕組みです。医療法人の出資持分の払い戻しや譲渡、自社株式の取得、組織再編など様々な場面で生じる可能性があります。
計算方法や税務処理は非常に複雑で、誤った手続きを行うと予期せぬ追加課税を招きかねません。特に個人の場合は最大55%もの高い税率が適用されるケースもあり、想定以上に税負担が大きくなることもあります。
クリニックの承継においても、スキーム(承継方法)によって売り手と買い手双方の税負担が大きく変わります。
医院承継について検討されているのなら、医療業界の法規制や税制に精通した「エムステージマネジメントソリューションズ」にお任せください。みなし配当の問題を含めた税務面のアドバイスから、理想的な承継先の選定まで、トータルでサポートいたします。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。