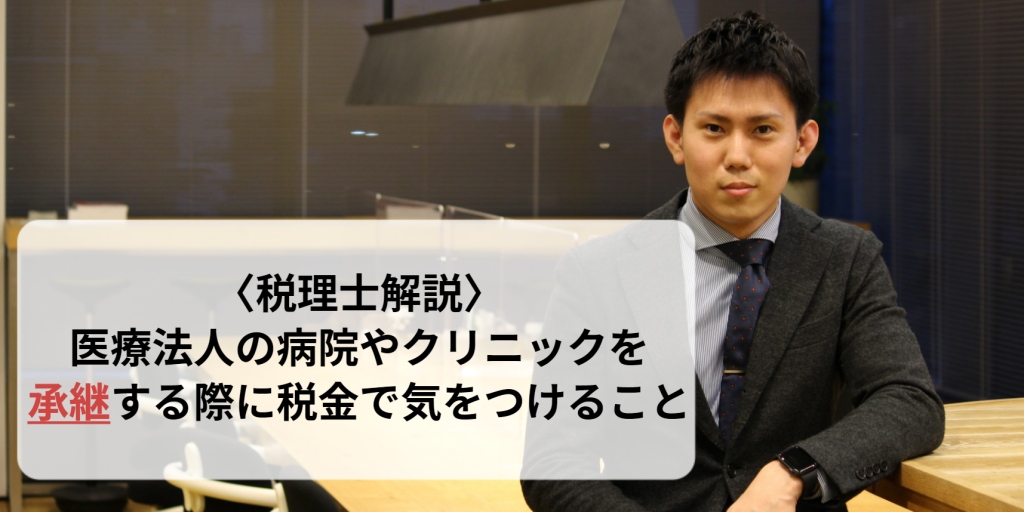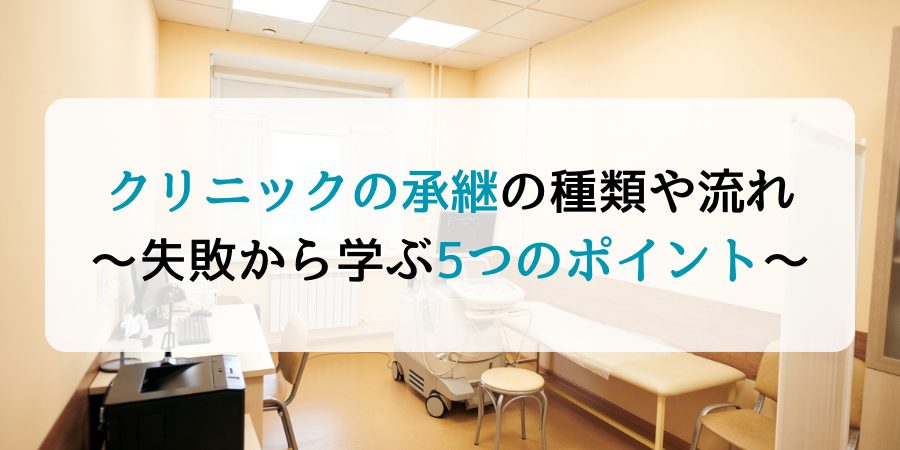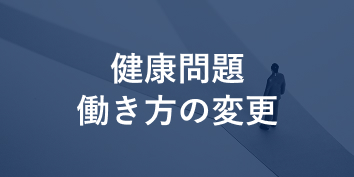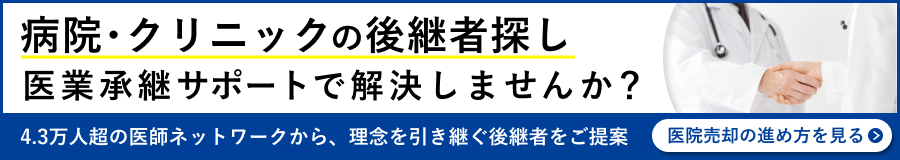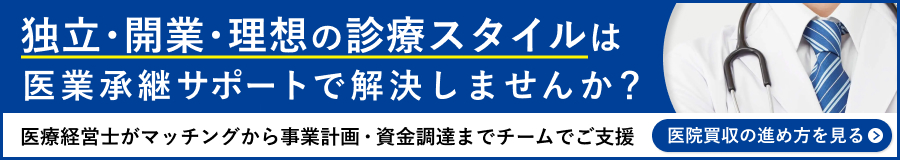ノンネームシートとは?役割・記載内容・企業概要書との違い

目次
「ノンネームシート」は、譲渡企業の情報を匿名で提供し、譲受企業の関心を引き出すための資料です。企業名を伏せたうえで、事業内容や財務状況、譲渡希望条件などの概要を伝えることで、秘密保持契約前でも情報提供が可能となります。
本記事では、ノンネームシートの基本的な役割や記載内容、作成時の注意点、IM(Information Memorandum:企業概要書)との違いまでを詳しく解説します。
ノンネームシートとは
ノンネームシートは、M&Aの初期段階で譲受企業に提示される、譲渡企業の概要を匿名でまとめた資料です。企業名や所在地など、特定に繋がる情報を伏せつつ、事業内容や財務状況、譲渡理由といった主要な情報を簡潔に記載します。
取引先や従業員に情報が漏れるリスクを最小限に抑えながら、譲受企業の関心を高める役割を果たします。
ノンネームシートが必要な理由
M&Aの場面において、ノンネームシートが必要とされる理由は、情報開示における慎重さとスピード感の両立にあります。
企業の売却を検討しているという情報は、それ自体が非常にセンシティブなものであり、ひとたび社外に漏れれば、従業員の不安や取引先の信用低下といった予期せぬ波紋を広げる可能性があります。
こうした事態を未然に防ぐため、売り手企業は実名を伏せた形で、自社の魅力を適切に伝える手段が求められます。
そこで活躍するのがノンネームシートです。企業名や所在地などの特定情報を開示せずに、事業内容や市場ポジション、財務状況、譲渡理由などを簡潔に整理し、買い手に「検討するに値する案件かどうか」を見極めてもらうためのものです。
名前を明かさずとも、企業の価値や将来性をしっかりと伝えることができれば、相手からの関心を引き出し、次の段階へと交渉を進める糸口となります。
つまり、ノンネームシートはM&Aという繊細なプロセスの入口に立つ、第一の橋渡し役といえます。
ノンネームシートが必要となるフェーズ
ノンネームシートが活用されるのは、M&Aプロセスの中でも最も初期段階、すなわち「打診」と「接触」のフェーズです。譲渡企業が売却の意向を固め、専門のM&A仲介会社と共に事前準備を進めていく中で、この資料は重要な役割を果たします。
正式な交渉や契約には至っておらず、買い手候補に対して広くアプローチを開始する時期では、ノンネームシートによって匿名性を担保しつつ、買い手に「検討に値する案件か」を判断してもらいます。
この時点では、秘密保持契約(NDA)は未締結であるため、提供される情報は企業の特定につながらないレベルに留められますが、それでも買い手は事業内容や財務の概要、譲渡の背景などから、案件の魅力をおおまかに把握できます。
そして、より深い情報を得て具体的な検討に進みたいと感じた場合には、ネームクリアを行います。ネームクリアとは、NDAを締結した上で譲渡企業名を開示することです。これによって、詳細な企業概要書(IM)の提供へと進展します。
関連記事:医業承継における「ネームクリア」について
ノンネームシートの記載内容
M&Aにおいて初期の情報提供手段として活用されるノンネームシートは、譲渡企業の概要を匿名のまま伝える重要な資料です。買い手が初期段階で「この企業に興味があるかどうか」を判断する材料となるため、簡潔かつ的確な情報整理が求められます。
以下では、ノンネームシートに一般的に記載される内容を解説します。
企業概要
ノンネームシートには、譲渡企業の基本的な事業内容や所在地域、従業員数などを記載します。ただし、企業が特定されないように配慮し、「東京都内に複数拠点を持つ中小製造業」といったように、一定の抽象度でまとめます。企業の特徴や強み、提供している製品やサービスの概要も、買い手の興味を引く要素として簡潔に触れます。
財務状況
財務に関する情報は、買い手にとって重要な判断材料であるため、売上高や営業利益などの数値を掲載します。ただし、ここでも匿名性を維持するため、「売上高は約5億円、営業利益は直近で4,000万円」など、大まかなレンジで記載することが一般的です。
過去数年分の業績推移が簡潔に示されることで、事業の安定性や成長性についておおよそのイメージを持つことができます。
譲渡理由
譲渡企業がなぜ会社を手放すのか、その背景は買い手にとって気になる情報の1つです。ノンネームシートには、「後継者不在による事業承継のため」や「新たな成長フェーズに向けた資本提携のため」など、端的かつ一般的な表現で譲渡理由を記載します。あくまで企業名が特定されない範囲で、納得感のある理由を簡潔に伝えることが大切です。
譲渡希望額・条件
売却を希望する金額や譲渡のスキーム(株式譲渡・事業譲渡など)、譲渡の時期といった条件も、ノンネームシートに記載します。「半年以内の譲渡を希望」「希望価格は1億円程度」など、交渉の出発点となる情報を示すことで、買い手が次のステップへ進むかどうかの判断材料となります。
また、譲渡後の経営体制や従業員の処遇について希望がある場合には、その点にも簡単に触れましょう。
▶ノンネームシートから始めるクリニック売却・譲渡(M&A)の進め方を確認する
クリニックM&A向けノンネームシートの記載内容
M&Aの初期段階で使用されるノンネームシートは、買い手が関心を持つかどうかを判断するための重要な資料です。ここでは、クリニックにおけるノンネームシートの記載項目と、その書き方を紹介します。
基本情報
診療科目や所在地(エリア)は、企業の特定につながらない範囲で簡潔に記載します。たとえば「○○県○○市」程度であれば人口が多い地域では問題ありませんが、地方の小規模エリアの場合には「○○県西部」など、さらにぼかす配慮が必要です。
- 診療科目:内科、小児科(今後の追加も可能)
- 所在地:関東地方、○○県○○市(詳細非公開)
- 開業形態:テナント/自社所有(いずれか記載)
- 創業年数:開業から15年目
- 譲渡スキーム:事業譲渡/株式譲渡(応相談)
- 譲渡希望時期:2025年10月以降
所在地については特定されない事が重要なため、エリアによって公開される情報の深度が異なります。たとえば、名古屋市など人口が多い市であれば、診療所も多いので公開できますが、人口の少ない市だと診療所も少なく、特定の恐れがあるため公開しない場合も多いです。
経営状況
買い手が最も注目するのが経営数値です。特に年間売上や修正後利益(実質利益)は、開示範囲に注意しながらも、投資判断の材料となるため明記する必要があります。
- 年間売上:4,800万円(直近3年平均)
- 修正後利益:800万円(診療報酬増減調整済み)
- 診療報酬内訳:保険診療90%/自由診療10%
- 1日平均外来数:35人
- 年間患者数:約9,000人
- スタッフ構成:医師1名(院長)、看護師2名、医療事務2名、受付1名
設備・環境
診療設備については、導入している機器の種類を簡潔に記載し、システム環境や診療時間も明記します。
- 主な設備:電子カルテ(富士通)、X線、超音波エコー、心電図
- 診療時間:平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00(休診:水・日・祝)
- 競合クリニック数:3軒(診療圏調査あり)
- 患者層:30~60代中心(家族層が多い)
立地・物件情報
アクセス性や地域特性は、買い手の集患戦略にも影響するため重要です。賃貸物件の場合は契約継続の可否、家賃なども記載します。
- 最寄駅:○○駅より徒歩7分
- 駐車場:患者用5台分あり
- 賃貸契約:継続可能(家賃月25万円/契約残2年)
- 立地環境:住宅街に隣接した地域密着型の立地
譲渡条件
譲渡希望価格だけでなく、譲渡スキームや引継ぎの可否、スタッフの継続雇用の可否を含めて整理します。
- 譲渡価格:2,000万円(応相談)
- 譲渡スキーム:事業譲渡を想定(株式譲渡も可)
- 引継ぎ期間:最大3か月程度、院長による支援あり
- スタッフの引継ぎ:全員継続雇用可
セールスポイント・その他特徴
クリニックの強みや将来性など、買い手にとって魅力となる要素を記載します。事実を簡潔にまとめ、「買いたい」と思わせる内容にするのがポイントです。
- 地域で15年以上にわたる信頼と実績
- 自由診療の拡大による成長余地あり
- 電子カルテ・医療機器も比較的新しく、運用しやすい
- 診療圏内に競合が少なく、患者数も安定
- 駅近・駐車場完備でアクセス良好
ノンネームシート作成時の注意点
ノンネームシートは、譲渡企業の情報を匿名のまま譲受企業に伝える資料である以上、情報の記載内容とその扱いには細心の注意が必要です。作成時のミスや認識のずれが、後の交渉や信頼関係に影響を及ぼすことも少なくありません。ここでは、譲渡企業・譲受企業それぞれの立場で意識しておきたい注意点を解説します。
正確な情報を仲介会社に伝える(譲渡企業)
譲渡企業が最初に行うべきは、自社の実情を正しく把握し、その内容を仲介会社に正確かつ誠実に伝えることです。
たとえば、直近3年間の売上や営業利益、従業員構成、固定資産の保有状況など、数値や事実に基づいた情報が求められます。
仮に売上を実態より多く見せようとしたり、不採算部門の存在を伏せた状態で資料が作成された場合、交渉段階での齟齬が生じ、買い手からの信頼を失いかねません。
ノンネームシートの内容確認を徹底する(譲渡企業)
仲介会社によってノンネームシートが作成された後には、譲渡企業自らがその内容を丁寧に確認する必要があります。特に注意したいのは、情報の表現方法や抽象度です。
たとえば、「全国展開の医療法人」と記載されていても、実態は地方に2拠点のみ、というケースもあります。このような表現のズレがあると、買い手が過大な期待を抱き、後の交渉で齟齬が生まれる原因となります。
また、開示を希望しない情報やセンシティブな内容が含まれていないかどうかも、事前に確認しておくべき重要なポイントです。
ノンネームシートの提出先を慎重に選定する(譲渡企業)
ノンネームシートは、不特定多数にばらまく資料ではありません。提出先をどこにするかによって、情報流出リスクや交渉機会の質が大きく変わります。
たとえば、同業他社に資料が渡った場合、事業戦略や財務の一端が競合に知られることになりかねません。地域密着型のサービス業などでは、限られたエリア内での競合関係に配慮し、地理的な絞り込みを行うこともあります。
譲渡企業の希望や懸念は、事前に仲介会社と綿密にすり合わせ、提出先の選定方針に反映させておくべきです。
ノンネームシートの情報開示範囲を理解する(譲受企業)
譲受企業にとって、ノンネームシートはあくまでも「概要確認用」の資料であることを理解することが大切です。企業名はもちろん、細かな資産情報や契約内容などは伏せられており、これだけで正確な価値判断を下すことはできません。
たとえば、売上5億円と記載があっても、それが保険収入中心の安定型か、自費診療主体の変動型かによって、リスク評価はまったく異なります。
こうした前提を踏まえ、ノンネームシートの情報はあくまで初期判断の参考に留めるべきです。
ノンネームシートをもとに適切な情報開示手続きを進める(譲受企業)
ノンネームシートを見て関心を持った譲受企業は、次のステップとして秘密保持契約(NDA)を締結し、より詳細な資料の開示を受ける段階に入ります。
重要なのは、正式な手続きを経ずにメールや電話で企業名や詳細な財務内容を探ろうとしないことです。たとえば、特定の診療科や診療圏の記述から企業を推測し、関係者に接触するような行為は、相手側に不信感を与え、交渉が破談になるリスクがあります。
秘密保持契約(NDA)締結前の情報管理に注意する
ノンネームシートは匿名性を保った資料であるものの、内容には財務や診療実績など、競合に知られると不利になる情報が含まれることがあります。そのため、情報を慎重に取り扱う必要があります。
たとえば、紙資料を複数部数コピーして自由に回覧するといった運用は避け、閲覧権限を限定し、メール添付の際にはパスワード保護を徹底するなど、基本的なセキュリティ対策を講じましょう。
M&A仲介会社との連携を強化し、適切な情報共有を行う
譲渡企業が安心してノンネームシートの作成を任せられるかどうかは、仲介会社との信頼関係と情報共有の質にかかっています。たとえば、譲渡企業が「自由診療の成長余地がある」と考えている場合でも、具体的にどの診療分野で、どのような設備投資やスタッフ配置を想定しているのかまで説明しなければ、仲介会社はその魅力を的確に資料に落とし込めません。
仲介会社を単なる外注先ではなく、自社の戦略パートナーとして捉え、細かな情報や想いまで共有する姿勢が大切です。
ノンネームシートの誤解や認識のズレを防ぐための対策
読み手である譲受企業が誤った解釈をしないよう、ノンネームシートの文章や表現には一貫性とわかりやすさが求められます。たとえば、「地域で長年の実績あり」と記載する場合には、具体的に「開業15年」「地域住民からの紹介が全体の◯割」といった事実に基づいた裏付けを添えることで、理解しやすくなります。
情報漏洩リスクを防ぐための管理体制を整備する
ノンネームシートに記載された情報が外部に流出した場合、譲渡企業にとって信用失墜や競争上の不利益といった重大な影響が生じるおそれがあります。
そのリスクを回避するためには、資料の管理体制を社内外ともに整備しておくことが不可欠です。社内では、閲覧できる部署や担当者を限定し、管理責任者を明確にしておきましょう。
また、仲介会社に対しては、どのような情報管理ポリシーを持ち、誰がどの段階で資料にアクセスできるのかを事前に確認することで、より安心して連携できるでしょう。
関連記事:医業承継(医院継承)における譲渡が成立するまでの期間
ノンネームシートとIM(企業概要書)の違い
M&Aでは、段階に応じて異なる資料を使用します。その中でも特に混同されやすいのが「ノンネームシート」と「IM(Information Memorandum/企業概要書)」です。どちらも譲受企業に情報を提供する資料ですが、開示タイミングや内容の詳細度、取り扱いの注意点などに違いがあります。
ここでは、それぞれの特徴を比較しながら違いを解説します。
情報の開示タイミング
ノンネームシートは、M&Aの初期段階で使用する資料です。この時点ではまだ秘密保持契約(NDA)を締結しておらず、譲渡企業の実名などは明かされていません。あくまでも「このような企業が売却を検討している」といった、匿名のまま概要を伝えることが目的です。
一方、IMは秘密保持契約を締結したあとに提供される詳細資料であり、企業名や代表者名、正確な所在地といった特定可能な情報も含まれます。買い手が本格的な検討に進むタイミングで渡されるため、情報の深度も一気に高まります。
記載される情報の詳細度
ノンネームシートは通常、A4用紙1枚に収まる程度の情報量で構成します。事業のジャンル、所在地のエリア、従業員数、売上規模、譲渡希望金額など、投資判断の入口として必要最小限の情報を記載します。
これに対してIMは、事業の沿革から各事業の収益性、財務諸表の推移、保有資産、契約関係、法的リスク、今後の成長戦略までを網羅した、数十ページに及ぶ資料です。
企業名の開示有無
ノンネームシートでは、企業名や固有名詞は明かされません。たとえば、「東京都内に2拠点を展開する年商5億円規模の老舗製造業」といった抽象的な表現が用いられ、読み手が特定企業を推測することは極めて困難な内容になっています。
一方、IMは「ネームクリア」と呼ばれる手続きを経て初めて開示される資料であり、企業名や所在地はもちろん、代表者や顧客層、競合他社の情報までもが含まれます。従って、扱う側にはより高度な情報管理意識が求められます。
情報開示のリスクと取り扱い
仮にノンネームシートの内容が外部に漏れたとしても、匿名性が維持されているため影響は限定的です。第三者が見ても企業を特定できるレベルではなく、風評リスクや信用棄損に直結するおそれは比較的少ないといえます。
一方、IMは社名を含めた機密情報が盛り込まれているため、万が一の流出時には取引先との関係悪化や株価下落、訴訟リスクなど深刻な事態を招く可能性があります。そのため、IMの管理にあたってはアクセス制限、電子ロック、閲覧記録の保存など、万全のセキュリティ体制が必須です。
提供の目的
ノンネームシートの目的は、「この案件に興味を持ってもらえるかどうか」を判断してもらうことです。譲受企業にとっては、初期接触の段階でその後の情報取得や交渉に進むべきかどうかの“フィルター”のような役割を果たします。
それに対し、IMはM&Aの実行を前提に詳細な分析を行うための資料です。買い手が本気でその企業を買収する価値があるか、事業リスクは許容できるかなど、最終判断を下すための裏付けとして機能します。
つまり、ノンネームシートは“興味を持たせる”ための入り口であり、IMは“意思決定を支える”ための出口に位置付けられます。
ノンネームシートはM&Aの成功の鍵
ノンネームシートは、M&Aの第一歩として、譲渡企業の魅力を匿名のまま正確かつ魅力的に伝えるための重要な資料です。譲受企業の関心を引き、次の交渉ステージへと進むかどうかを左右します。
エムステージは、医療・ヘルスケア分野に特化したM&A支援に強みを持ち、これまでに数多くのクリニック・医療法人の譲渡・承継を成功に導いてきました。単なる資料作成にとどまらず、ノンネームシートの設計段階から、IM(企業概要書)の作成、譲受先の選定、交渉支援、最終契約の締結に至るまで、ワンストップでサポートを提供しています。
「自院を誰かに託したいが、何から始めればいいかわからない」「できるだけ信頼できる相手に譲りたい」といったお悩みをお持ちの方は、どうぞ安心してエムステージにご相談ください。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。