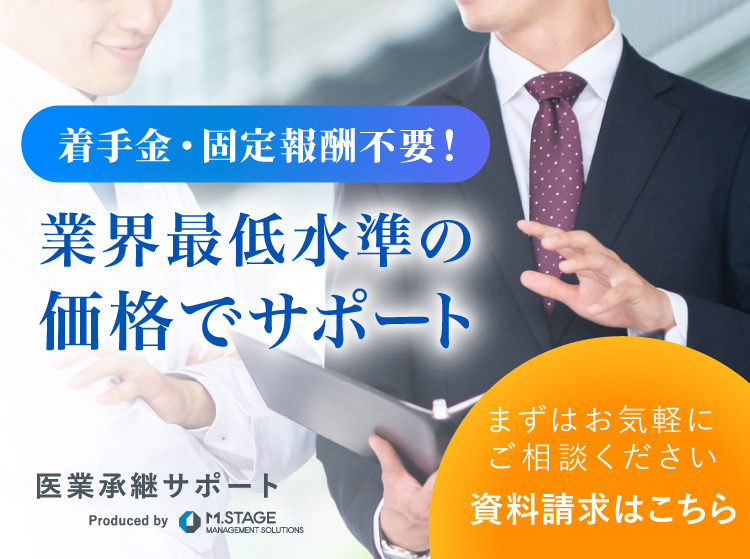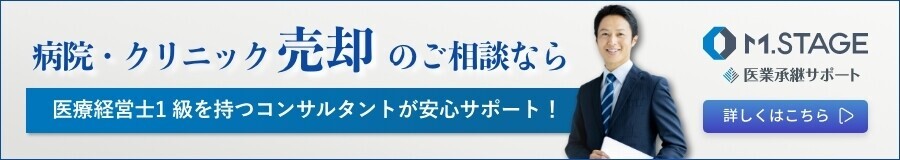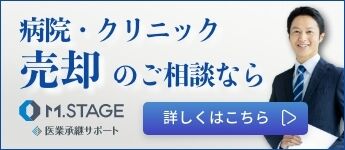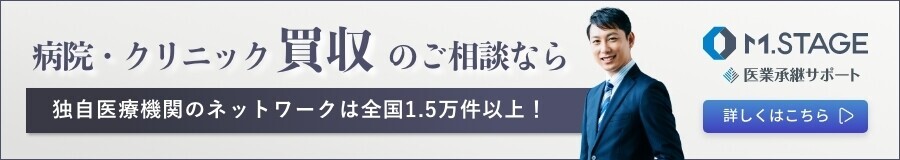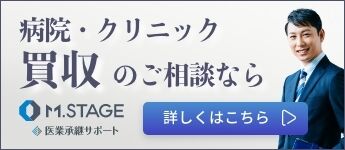医業承継(医院継承)におけるクロージングの工程を徹底解説!
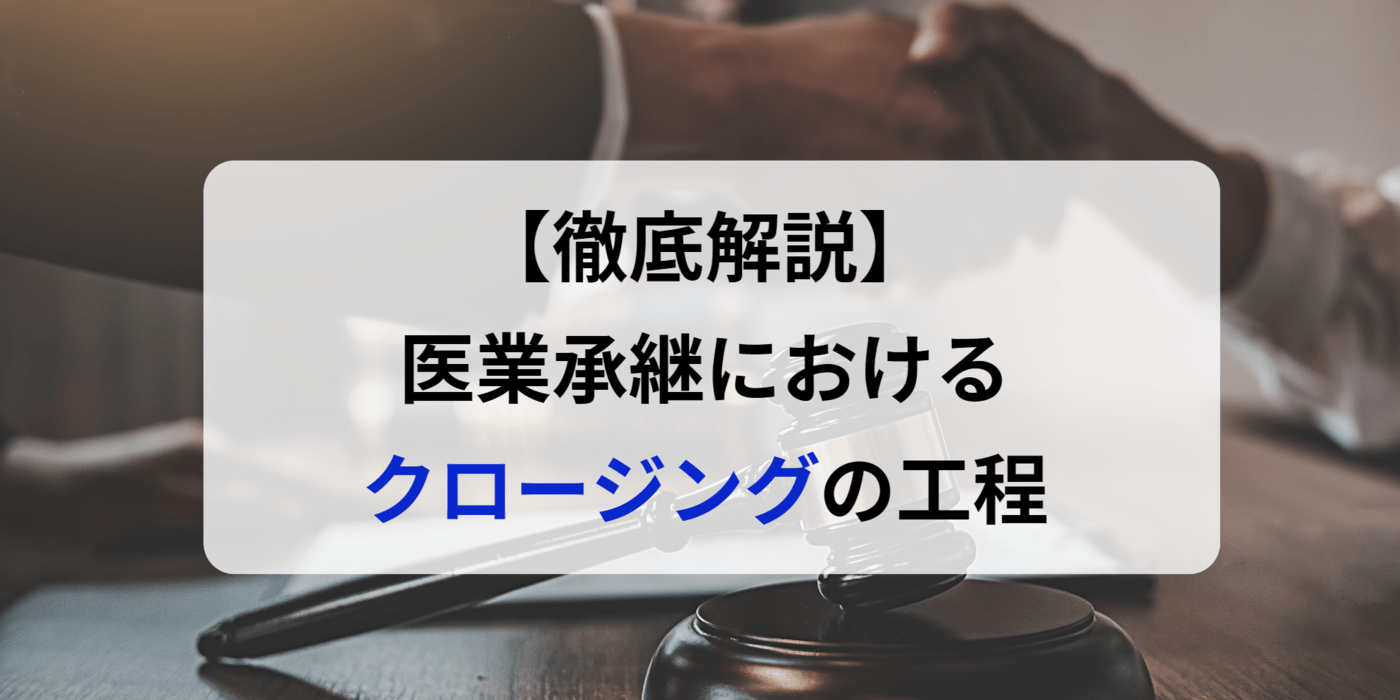
目次
医業承継(医院継承)における「クロージング」とは、第三者承継(M&A)の最終工程である経営権の移転と対価の支払いを実行・完了する工程のことです。クロージングまでにはいくつかの準備手続きを済ませておく必要があり、場合によってはクロージング後にも手続きが必要になります。
本記事では、M&Aの最終契約締結からクロージング前後までの工程について、医業承継ならではのポイントに留意しながら解説します。
医業承継(医院継承)におけるクロージングとは
M&Aの全体プロセスは、大きく分けると、「準備・検討段階(相手探しやマッチング)」、「条件交渉・契約締結段階」「実行段階」の3段階で進行します。
一連の流れのうち、最後の「実行段階」の中心となる部分が、一般的に「クロージング」と呼ばれる段階です。具体的には、最終契約に基づいて「経営権の移転」および「対価の支払い」を行います。
最終契約までのプロセスがうまくいっても、このクロージングで失敗すると契約そのものが破談となってしまうため、最も重要な工程といえます。なお医業承継のクロージングでは、医療法人の社員総会や行政手続きなどの手続きが含まれるため、一定の期間が必要となります。
病院・クリニックの承継をご検討中の方は医業承継専門の
株式会社エムステージマネジメントソリューションズに無料相談してみませんか?
エムステージグループの医業承継支援サービスについての詳細はこちら▼
M&Aにおける譲渡と合併
「M&A」は、英語の「Mergers and Acquisitions」の頭文字です。Mergersは「合併」、Acquisitionsは「買収」なので、日本語でいえば「買収と合併」です。「買収」は買い手視点の言葉で、売り手視点では「売却」または「譲渡」となります。
M&Aの本質は対価を伴う経営権の売買であるため、譲渡(買収)は常に行れますが、合併は必ずしも行われるわけではありません。合併とは、2つ以上の法人を1つの法人とすることです。
たとえば、A法人がB法人をM&Aで買収した場合は、B法人の法人格を消滅させてA法人に吸収し、1つの法人にまとめることになります(吸収合併)。一方、A法人がB法人を買収した後、売り手のB法人の法人格をそのまま残しておき、A法人のグループ法人として運営することも可能です。
法人の合併をするためには、法律上の複雑な手続きが必要となるため、実際のM&Aでは被買収法人をそのまま残して運営する方が一般的です。
個人開設(個人事業経営)の医院や、医療法人が運営する医院の一部を譲渡する場合は、法人譲渡とは別の「事業譲渡」という枠組みで実行されます。また、医療法人が運営する医院の一部を譲渡する場合には、吸収分割という方法もあります。
以上を医業承継に当てはめると、医療機関譲渡の代表的なスキームは下記のような種類に分けられます。また、スキームによってクロージングにおける経営権の移行方法や、対価の支払い方法などが異なります。
- 医療法人を譲渡する(譲渡法人は存続)
- 医療法人を吸収合併する(譲渡法人は消滅)
- 個人開設の医療機関を譲渡する(事業譲渡)
- 医療法人の分院を譲渡する(事業譲渡、または吸収分割)
なお、第三者承継によって合併が行れる場合は、経営権の譲渡も同時に行れますが、簡便化のために「合併する」と表記します。
医療法人譲渡のクロージング(経営権移行手続き)
医療法人譲渡とは、医療法人の法人格そのものを譲渡することを指します。なお、医療法人は大きく社団医療法人と財団医療法人に分かれるので、それぞれについて説明します。
社団医療法人の経営権移行プロセス
社団医療法人の最高意思決定機関は社員総会であり、総社員の過半数が出席した社員総会において出席者の過半数が承認することにより議題が可決されます。したがって、社員の入れ替えにより社員の過半数を買い手側の人物・法人が占めれば、経営権が買い手に移転します。
なお、ここでの「社員」とは、医療法上で規定される法人の構成員たる社員のことであり、法人が雇用する従業員のことではありません。通常、社団医療法人の経営権の譲渡は、以下の流れで行われます。
- 売り手側の社員総会を開催し、買い手側の人物・法人(営利企業以外)が社員として入社することを承認する決議を行う。
- 売り手側の社員が退社し、社員の過半数を買い手側が占めるようにする。
- 新たな社員体制による社員総会で旧役員(理事・監事)の解任と新役員の選任を決議する。
- 新たな理事による理事会を開催し、新理事長を選任する。
- 社員名簿を更新し、行政(保健所、厚生局)には役員と管理者の変更届出を提出。法務局での理事長変更登記を行う。また、税務署や労基署等には代表者変更の届出を行う。
- 出資持分の定めのある医療法人の場合、上記と並行して、持分譲渡の手続きも行い、出資者名簿を更新する。
経営権移行時の理事・理事長の変更について
M&Aにより経営権を譲渡する場合、社員と合わせて理事・理事長も買い手側の人物に変更するのが通例です。
しかし、医療法人の最終的な経営権の所在はあくまで社員総会(社員の過半数)にあり、理事会も理事長も法人の最終的な経営意思決定者ではありません。そのため、経営権の移行に際しては、理事や理事長の変更は必須ではないということです。
実際に、M&A前に社員兼理事長だった代表者が、M&A後に社員としては退社した上で、いわゆる「雇われ理事長」として理事長職を継続するケースもあります。
医療法において、医療法人の理事長は医師または歯科医師であることが要件とされています。そのため、買い手が医療法人以外の営利企業(医療関連分野の株式会社やファンドなど)や、非医師の個人であるような場合によく見られる手法です。
財団医療法人の経営権移行プロセス
財団医療法人の場合の最高意思決定機関は、評議員により構成される評議員会です。役員の解任・選任は、評議員会決議により行われます(決議の条件は社団法人と同じ)。
また、評議員は一定の要件に該当する人物(医療従事者など)の中から、理事会により選任されるのが通例です。したがって、財団医療法人の経営権譲渡では、売り手法人の理事会で評議員の入れ替えを決議し、新たな評議員会で役員の解任・選任を行い、必要な届出・登記を行います。
医療法人吸収合併のクロージング(経営権移行手続き)
吸収合併は、医療法に基づき以下の流れで行われます。①~⑤の手続きは、売り手・買い手の双方が協力して行います。
- 吸収合併契約を締結する。
- 社団医療法人の場合、社員総会において全社員の賛成による吸収合併契約承認決議を行う。財団医療法人の場合は、理事の3分の2以上の賛成による承認決議を行う。
- 都道府県知事へ、合併認可申請を行う。
- 合併の認可が下りたら、財産目録・貸借対照表を主たる事務所に備え置き、債権者へ開示する。
- 債権者に対し、合併に異議を述べるための期間を設ける。債権者から異議が述べられた場合は、債務の弁済や担保提供などの対応を取る(債権者保護手続き)
- 契約書に記された効力発生日に、合併が成立する。売り手法人のすべての権利義務が買い手法人へ一括して承継され、売り手法人は消滅する。
- 合併後の法人が合併登記を行う。
医療法人譲渡の対価の支払い
医療法人の第三者承継の場合は、法人の合併という形を取るか否かに関わらず、何らかの対価の授受が行われます。対価の授受には医療法の規定などがなく、私的取引として自由に行れるものであるため、多様な方法が考えられます。
どのように対価を支払うのかという点も、クロージングに関わる重要な要素になります。なお社団医療法人には、定款において「出資持分の定めのある医療法人」と、基金拠出型医療法人などの「出資持分の定めのない医療法人」とがあります。
両者の一般的な対価授受方法は異なるため、それぞれを解説します。
出資持分の定めがある医療法人の場合
定款に出資持分の定めのある社団医療法人を譲渡する際には、その持分が譲渡の対象となります。上述の経営権移行の手続きと並行して、持分譲渡の手続きが行われるのが通例です。
医療法人の社員の地位と出資持分とは結合していないので、社員の交替がそのまま出資者の交替になるわけではありません。つまり、理論上はM&Aで退社する旧社員が、そのまま出資をし続けていてもいいということになります。
しかし、出資者であるだけでは社員総会での決議権がないため、出資をしている意味がほぼありません。そのため、退社して社員を交替する際に、旧社員が保有していた出資持分を買い手に譲渡し、対価として現金などを受け取ることが通常の流れとなっています。
また、多くの医療法人では出資者が理事や理事長に就いていますが、その場合は、主に「出資持分の譲渡対価のみで支払う」ケースと、「出資持分の譲渡対価+役員退職金で支払う」ケースに分かれて行われています。さらに、医療法人が保有する、または出資者が保有していて医療法人に貸し付けている不動産を絡めるケースなどもあります。
このようにさまざまな対価の支払い方法がある理由は、売り手にとっての出資持分の譲渡対価は譲渡所得として課税されるのに対して、退職金として受け取れる場合は退職所得として課税され、一般的には課税上有利になるためです。
ただし、医療法人の財務状況や売り手の所得状況、その他の条件によって課税上の有利・不利は変化するため、個別の状況により検討されます。なお、出資持分の対価の支払いや退職金の支払いは、最終契約で定めた譲渡日に銀行振込で行うケースが大半です。
出資持分の定めがない医療法人の場合
出資持分の定めがない医療法人を譲渡する場合や、持分譲渡を行わない場合は、M&Aを機に退職する人物に対しては退職金の調整を行い、M&A後も法人(売り手法人や合併後の法人)に残る人物に対しては役員または従業員としての報酬や賞与の金額調整などにより対価の受け渡しを行います。
なお、基金拠出型医療法人の場合は、資金の拠出者はM&Aに際して拠出した基金と同額の返還を受けることが一般的です。
■■関連記事■■
個人開設医院のクロージング(経営権移行手続き)
医療法人を譲渡する場合の譲渡を実施する主体は、その法人の経営権を持つ社員となり、医療法人が譲渡の対象となります。
一方、個人開設医院の譲渡の場合、実施する主体は医院の院長ですが、個人が開設して経営している医院そのものを譲渡することはできません。医院の行政から与えられる開設許可は、あくまでその個人(院長)に与えられた許可であり、その許可を他人に譲渡することは認められていないのです。
そこで譲渡の対象になるものは、その医院で営まれている事業を構成する権利義務(資産・負債・契約など)です。これらを個別に移転するスキームは、「事業譲渡」と呼ばれます。
たとえば、院長が所有する不動産で医院を開設しているのなら、その不動産や所有する医療機器、薬品、患者の情報(カルテ)などが有形資産として譲渡の対象になります。また、無形資産としては診療ノウハウや集患ノウハウ、地域における知名度などが譲渡対象に含まれると考えられます。
個人開設医院の事業譲渡のクロージング
事業譲渡では、権利義務の1点1点について、個別に買い手の法人・個人に移転する手続きが必要です。
債権(売掛金など)や債務(買掛金など)、従業員の雇用契約、医薬品卸などとの取引契約、不動産賃貸借契約をはじめとする第三者が絡む権利義務を移転するには、第三者当人の同意が求められます。また、院長自身が所有する不動産を移転する場合には、所有権移転登記が必要です。
上記のような権利義務の移転手続きに加え、行政手続きも必要です。先に述べたとおり、医院の開設許可自体は譲渡できないため、行政上は売り手の医院については廃院し、買い手のもとで同じ場所に新たに診療所を開設するという扱いになります。
事業譲渡日から10日以内に、行政に対して医院の廃止および開設の届出をする必要があります。保険診療を行う場合には、厚生局に対して保険医療機関指定申請も行います。買い手が医療法人の場合は、開設する診療所が増えるため、定款の変更が必要です。
定款変更には、社員総会決議(財団医療法人の場合は評議員会の意見を聴いた上での理事会決議)と都道府県知事による認可が求められます。定款変更の認可が下りるまでには、通常1~3か月程度かかるため、定款変更認可申請は最終契約の締結後速やかに行う必要があります。
個人開設医院譲渡の対価の支払い
事業譲渡の対価の支払いは、最終契約で定めた事業譲渡日に銀行振込で行われるのが通例です。
しかし、権利義務の移転や行政上の手続きのすべてをその日までに完了できるとは限りません。もし事業譲渡日までに完了しない手続きがある場合には、事業譲渡日後遅滞なく完遂できるような措置を取ることが、売り手側の義務として求められます。
なお、売り手が受け取る所得の種類としては、有形資産・無形資産をあわせて、総合課税の譲渡所得となります。ただし、医院で利用している不動産を譲渡した場合は分離課税となります。
医療法人の分院(一部の医院)譲渡のクロージング
医療法人の分院(一部の医院)を譲渡する場合、「事業譲渡」による方法と、権利義務を一括して買い手法人に移転する「吸収分割」のスキームが利用できます。ただし、持分の定めのある医療法人は吸収分割を行うことができないため、事業譲渡となります。
分院を事業譲渡する場合
売り手法人において、分院譲渡は「重要な資産の処分」に該当します。
そのため、社員総会での承認決議が必要です。また、定款変更(開設する病院・診療所の変更)のためには、社員総会決議(評議員会の意見を聴いた上での理事会決議)と都道府県知事の認可が求められます。なお買い手が法人の場合、買い手側でも定款変更手続きを行う必要があります。
その他の手続き(権利義務の移転、対価受け渡し、売り手における分院廃止届出、買い手における診療所開設届出、保険医療機関指定申請)は個人開設医院の譲渡の場合と同様です。
■■関連記事■■
分院を吸収分割する場合
吸収分割は、医療法に基づき以下の流れで行われます。①~⑤の手続きは、売り手・買い手の双方で協力して行います。
- 吸収分割契約を締結する。
- 社団医療法人の場合、社員総会において全社員の賛成による吸収分割承認決議(財団医療法人の場合、理事の3分の2以上の賛成による承認決議)を行う。
- 都道府県知事へ、分割認可申請を行う。
- 分割の認可が下りたら、財産目録・貸借対照表を主たる事務所に備え置き、債権者へ開示する。
- 債権者保護手続きを行う。
- 売り手法人において、2~5の手続きと並行して労働契約の承継に関する手続き(後述)を行う。
- 契約書に記された効力発生日に分割が成立し、分割される事業に属する権利義務が買い手法人に一括して承継される。
- 買い手法人が分割の登記を行う。
吸収分割の場合の、労働契約の扱い
売り手法人が雇用している従業員は、吸収分割契約に基づき労働契約が買い手法人に承継される人と、承継されずに売り手法人に残留する人とに分かれますが、以下に該当する従業員は分割の前後で業務内容や労働条件が大きく変わる可能性があります。
(A)吸収分割契約締結時点で分割対象事業に主として従事していたにも関わらず、吸収分割契約において労働契約承継の対象となっていない従業員
(B)吸収分割契約締結時点で分割対象事業とは別の事業に主として従事していたにも関わらず、吸収分割契約において労働契約承継の対象となっている従業員
売り手法人は、これらに該当する従業員が異議を述べるための期間を設ける必要があります。期間内に異議が述べられた場合、(A)の従業員であれば買い手法人へ労働契約が承継され、(B)の従業員であれば売り手法人へ残留することになります。
まとめ:クロージングは十分に検討し、丁寧に行おう
M&Aのクロージングでは、最終契約締結からクロージング日前後に掛けて、法令や契約に従いさまざまな手続きを遂行する必要があります。医業承継では、行政上の手続きも必要になるケースが多いことが特色です。
どのような手続きが必要になるかは、医療法人の類型やM&Aスキームによって異なります。クロージングの工程については、スケジュール面も含めて条件交渉の段階で十分に検討し、最終契約に反映することが必要です。
医業のM&Aは、一般の事業会社のM&Aとは異なる専門的な知見が必要となるため、専門の仲介会社に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。
医業承継のご相談なら、ぜひ医業承継専門の仲介会社エムステージマネジメントソリューションズにお問い合わせください。専門のコンサルタントが、徹底サポートいたします。
承継も視野に入れているという先生は、まずは資料をチェックされてみてはいかがでしょうか。
▼エムステージの医業承継支援サービスについて
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。医療経営士1級。医業承継士。医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。これまで、病院2件、診療所30件、介護施設2件の事業承継M&Aをサポートしてきた。エムステージグループ内のM&A戦略も推進している。