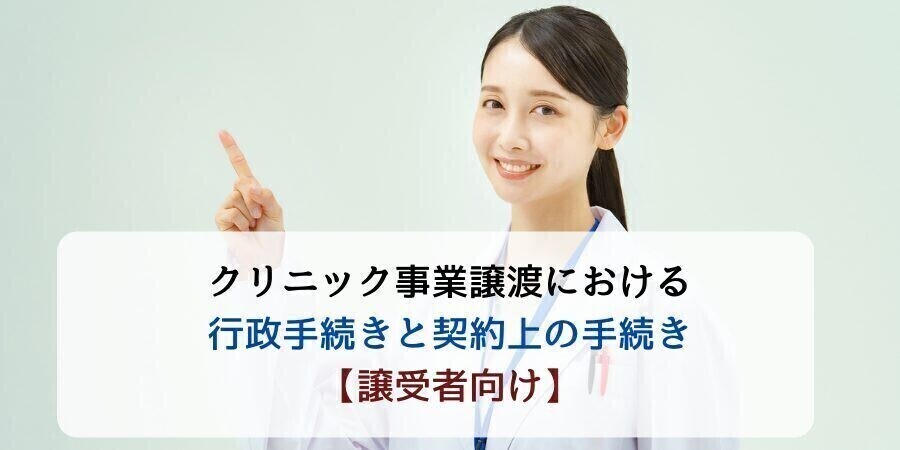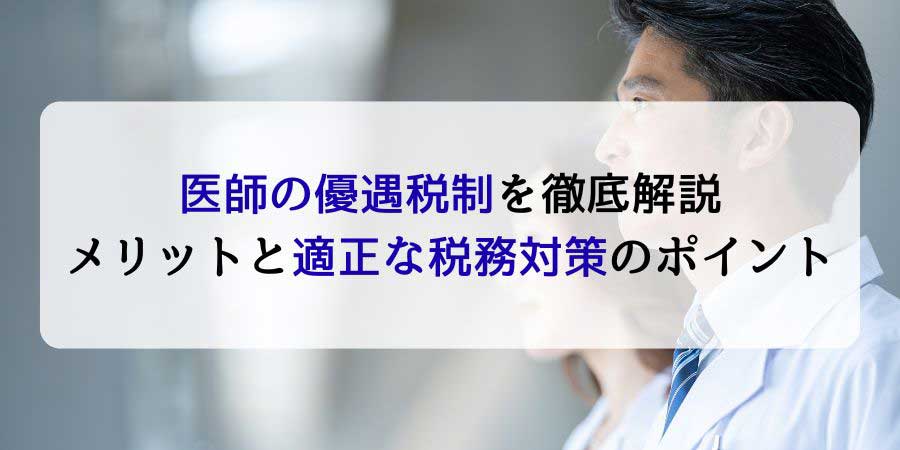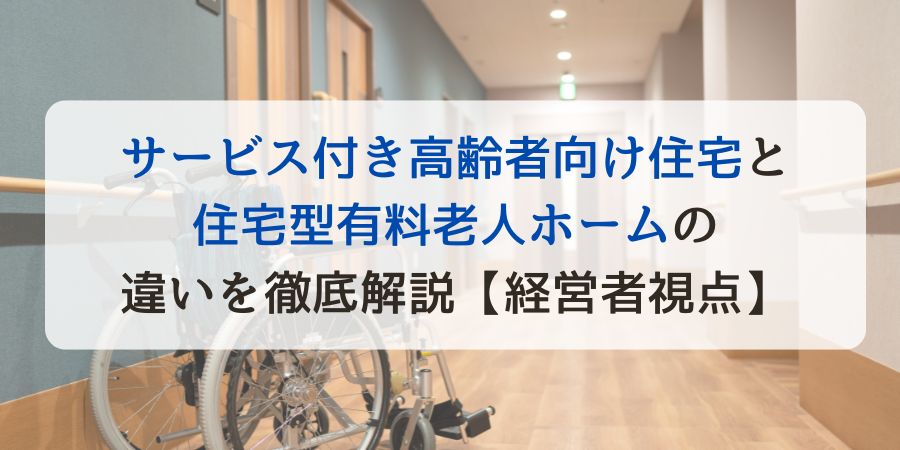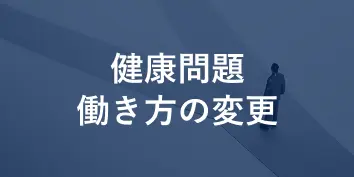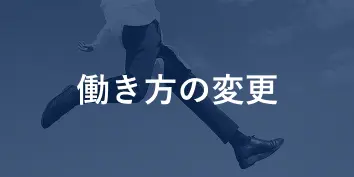クリニック開設における管理者とは?経営者や開設者との違いも解説

目次
クリニックの開設において「開設者」「管理者」「経営者」の概念や役割は必ず理解しておかなければなりません。これらの役割は医療法によって厳格に定められており、特に医療法人においては複雑な規定があります。
特に管理者に関して適切な選任が行われていない場合には、行政処分や医療機関の運営に重大な影響を与えるリスクがあるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
本記事では、クリニック開設における管理者の役割と責任、さらに開設者や経営者との違いについて解説します。
医療法人における「開設者・管理者・経営者」の違い
クリニックや病院の運営には、法的に定められた3つの重要な役割があります。
【医療法によって定められている3つの役割】
- 開設者
- 管理者
- 経営者
医療機関を経営する上で、それぞれの責任と権限を正しく理解しておかなければなりません。
開設者とは
開設者とはクリニックや病院を所有している医療法人、または個人でクリニックを開業した人そのものを指します。
法的な責任を負い、クリニックの設立や運営に関する最終的な意思決定を行う立場です。
開設者の主な責任や権限は以下のとおりです。
| 開設者の責任 | 開設者の権限 |
| 医療機関の設立と運営に対する最終的な責任医療法に基づく各種手続きの実施管理者の選任と監督 | 医療機関の運営方針の決定管理者の任命・解任重要な設備投資や契約の決定 |
管理者とは
管理者とは、医療行為が適切に行われるように管理する人のことです。
医療法第10条で定められており、病院または診療所が医業を行うものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業を行うものである場合は臨床研修等修了歯科医師に管理させなければならないとされています。
出典:e-Gov法令検索|医療法 第10条
医療法人においては、主に理事長が管理者を務めるケースが多く見られます。
| 管理者の主な責任 | 管理者の資格要件 |
| 医療行為が適切に行われるための管理と監督医療従事者の指導と監督医療安全の確保医療法をはじめとする関連法令の遵守 | 医師免許または歯科医師免許の保有が必須臨床研修の修了が必要 |
なお一般的に使われている「雇われ院長(管理医師)」とは、法律的な立場で言うと「管理者」と同意語です。
関連記事:管理医師とは?雇われ院長と開業医の違い
経営者とは
経営者とは「ヒト・モノ・カネ」といった経営資源の管理を行う人のことです。
医療業界では「管理者」と同じ意味合いで使われることも多く、法的な定義は明確に定められていません。
医療機関における経営者の役割としては以下が挙げられます。
| 医療機関における経営者の主な役割 |
| より良い医療の提供と患者の満足度向上スタッフの労働環境整備と働き方の改善診療報酬に基づく経営管理と財務運営医療機器や設備に関する判断地域医療への貢献や他の医療機関との連携 |
個人クリニックは一人ですべての役割と責任を持つ
個人経営のクリニックの場合、必然的に「開設者・管理者・経営者」のすべてを院長である医師または歯科医師が兼任します。これは、意思決定が迅速に行えるというメリットがある一方で、すべての責任を一人で負うことになります。
| 個人経営のメリット | 個人経営のデメリット |
| 迅速な意思決定が可能運営方針の統一を図りやすい利益の配分を自由に決められる | すべての責任が院長に集中する事業承継の手続きが複雑になる資金調達の選択肢が限られる |
もし医療法人化を検討する場合は、これらの役割分担が大きく変わることも理解しておかなければなりません。
医療法人は「管理者」の選任が必須
医療法では、医療法人が開設するすべての病院・診療所・介護老人保健施設には、その管理者を「理事として選任しなければならない」と定められています。
“6 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。”
出典:e-Gov法令検索|医療法 第46条の5第6項
この規定により、医療法人における管理者は単なる現場責任者ではなく、法人の経営に参画する理事としての権限と責任を持つことになります。
【医療法人における管理者の重要なポイント】
- 必ず医療法人の「理事」でなければならない
- 管理者の職を退いたときは「理事の職」を失う(医療法第46条の5第7項)
- 理事として法人運営に参画する義務がある
医療法人における管理者の選任要件
医療法人が管理者を選任する際には、以下の要件を満たさなければなりません。
【基本的な管理者の選任要件】
- 医師免許または歯科医師免許を有すること
- 医療法人の理事であること
- 実際に法人運営に参画できること
一般的には理事の中から一人が管理者として選任されますが、必ずしも理事長である必要はありません。
都道府県知事の認可があれば、理事ではない人でも管理者に選任が可能です。
しかし、いずれの場合においても、管理者は「医師免許または歯科医師免許」を保有していなければなりません。
医療法人が開設者を変更する場合の手続き
医療法人が開設者を変更する(運営している医療法人名を変える)場合には、非常に数多くの手続きが必要です。
これは、医療機関の「オーナー」が変わることを意味するため、行政機関への多岐にわたる届出や認可が必要になります。
開設者の変更手続きは、主に下記5つの手順です。
- 都道府県知事に認可を受ける
- 法務局に登記手続きを行う
- 保健所に届出をする
- 厚生局へ届出をする
- その他の各種機関に変更手続きや届出をする
ここでは、それぞれ主な手順を解説しますが、実際の手続きに関しては司法書士などの専門家のサポートを受けるようにしましょう。
1.都道府県知事に認可を受ける
医療法人の定款変更には、まず都道府県知事の認可が必要です。(医療法第50条)
開設者の変更は定款の根本的な変更にあたるため、必ず事前に認可を受けなければなりません。
【認可申請の流れ】
- 事前相談(必要に応じて)
- 仮申請の提出
- 本申請の提出
- 審査のあと認可が下りる
認可の申請は1〜2か月程度時間を要するため、十分に余裕を持って手続きを進める必要があります。
2.法務局に登記手続きを行う
都道府県知事から認可を受けたら「2週間以内に」法務局で変更登記の申請を行う必要があります。
【登記申請時の注意点】
- 変更年月日は「認可書が到達した日」となります
- 必要書類をすべて揃えて申請する
- 登記完了後は登記事項証明書を取得する
【登記手続きで必要な書類】
- 変更登記申請書
- 定款変更認可書の原本
- 社員総会議事録の原本
- 委任状(司法書士に依頼した場合は必要)
3.保健所に届出をする
クリニックの開設者が変更になるため、管轄の保健所に対して「診療所開設者の名称変更届」を提出します。
手続きの期限に関して厳密には設けられていませんが、法務局に変更登記を行ったあと「速やかに行うことが望ましい」とされています。
「クリニックの所在地を管轄している保健所」に届出しなければなりませんので、複数の地域に医療機関がある場合には「それぞれの診療所を管轄している保健所」に対して届出をしなければなりません。
【主な提出書類】
- 診療所開設者の名称変更届(所定様式)
- 登記事項証明書
- 定款または寄附行為
4.厚生局へ届出をする
保険医療機関として指定を受けている場合は「保健所に届出を行ったあと」厚生局への届出も必要です。
【厚生局への主な届出】
- 保険医療機関届出事項変更届
- 開設者変更に関する各種手続き
5.その他の各種機関に変更手続きや届出をする
これまでの手続きで、開設者変更に伴う「クリニックの経営における必要最低限の届出」は完了しました。
ほかにも、以下の機関で変更手続きや届出が必要となる場合があります。
- 医師会への届出
- 社会保険に関する届出
- 金融機関への届出
- 税務署への届出
- 賃貸借契約やリース契約などの各種契約先へ変更手続きや通知
契約書類や届出が前の開設者のままになっていると、最悪の場合契約の効力が無効となってしまう可能性もあります。
ヌケモレが無いように、しっかりと変更手続きや届出を行わなければなりません。
医療法人の管理者を変更する場合の手続き
医療法人の「管理者」を変更する際には、主に3つの行政機関に対して届出や変更手続きが必要です。
【都道府県知事:役員変更届】
医療法人の管理者は、医療法により必ず理事でなければなりません。つまり管理者の変更は、医療法人の役員(理事)の変更に該当するので、都道府県知事に対して「役員変更届」を提出する必要があります。
【保健所:診療所開設届出事項変更届】
クリニックの開設届にも管理者の記載事項が含まれているため、管理者が変更になった場合は、管轄の保健所に対して「診療所開設届出事項変更届」を提出します。
【厚生局:保険医療機関届出事項変更届】
保険医療機関として運営している場合は管理者情報の変更が必要なので、厚生局に「保険医療機関届出事項変更届」を提出します。
なお上記の手続きは、すべて同時進行が可能です。
医療法人は管理者を含む理事の「名義貸し」に注意
厚生労働省の「医療法人運営管理指導要綱」には、理事について「実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当でない」という記載があります。
出典:厚生労働省|医療法人運営管理指導要綱
これは、医療法人の理事(管理者も含む)が、単に名前を貸すだけで実質的な業務に関与しない「名義貸し」を厳しく戒めているものです。
【名義貸しのリスク】
| 法的リスク | 保険医取消の処分行政上の措置として戒告や注意 |
| 経営上のリスク | 経営が悪化した場合に債権者から支払いを求められる |
たとえば急に管理者が退職することになって、新たな管理者が見つかるまで知人の医師に管理者となってもらったとしても、運営に携わっていないと「名義貸し」とみなされてしまいます。
特に管理者となった方の、今後の医師人生を大きく左右するペナルティが課せられてしまいます。
管理者を含む理事は「法人運営にしっかりと携われる先生」を選任しなければなりません。
急逝や退職などで管理者が不在となった場合の対策方法
管理者が急逝したり、突然退職したりするなどして不在となった場合、クリニックの運営に大きな支障が生じます。
医療法では「医療機関には必ず管理者を置かなければならない」と定められているため、速やかな対応が必要です。
そのようなケースになった場合の、具体的な対策方法を3つ紹介します。
他のクリニックの院長(管理者)に兼任してもらう
原則として、一人の医師が複数の病院や診療所の管理者となることはできません。
“病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、次の各号のいずれかに該当するものとしてその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。”
出典:e-Gov法令検索|医療法「第12条2」
しかし以下の例外的なケースに該当し、都道府県知事の許可を受けた場合には、他のクリニックの院長が兼務することも可能です。
【兼任が認められる例】
医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所を管理しようとする場合(例:へき地医療など)
ただし、この場合でも兼任には厳格な条件が伴い、その許可も容易ではありません。
他の医療機関で働いている勤務医の先生に依頼する
一時的な対応として、他の医療機関で働いている「勤務医の先生」に管理者を依頼することも考えられます。
ただし、この場合も以下の点に注意が必要です。
【勤務先の許諾】
勤務先のクリニックや病院が兼業を許可している必要があります。
【診療所の休診日や休診時間に対応してもらう】
原則として「その診療所の休診日や休診時間についてのみ勤務してもらう」ということを条件に認められるケースが多いです。
【管理者の責任】
短期間であっても、管理者は医療法上の責任を負うことになります。
このケースは認められるかどうか判断が難しいので、詳しくは管轄の保健所などに相談することをおすすめします。
医院継承も視野に入れる
管理者が急逝した場合や後任が見つからない場合は、医院継承も選択肢の一つとして検討する必要があります。
たとえば院長の急逝により管理者不在となった場合、一時的な管理者の確保は応急処置に過ぎず、根本的な解決にはなりません。
医院継承なら新たな医師が管理者として就任することで、地域医療を途切れることなく提供できます。
特に院長の体調の変化によって、クリニックの経営が難しくなり閉院を余儀なくされるケースは非常に多いです。
あらかじめ医院継承の専門家と関係を築いておけば、そのような緊急性の高い場合でも「その院長が一番大事にしている診療方針や経営方法」などを良く理解できているので、適切な承継先とのマッチングとスピーディーな承継が実現します。
関連記事:院長が急逝したら閉院?手続きの流れやよくあるトラブルと解決法を紹介
開設者や管理者に関するよくある質問
ここでは医療機関の経営で悩まされる「開設者」や「管理者」に関する質問にお答えします。
医療法人の開設者と管理者は同一でないとダメなのでしょうか?
いいえ、医療法人の開設者と管理者は同一である必要はありません。
医療法人における開設者は「法人」であり、管理者は「医師または歯科医師である個人」となるため、本質的に異なる存在です。
ただし、医療法人の管理者は必ず「その医療法人の理事でなければならない」と定められています。
そのため、管理者は医療法人という組織の一員として、法人運営に参画することになります。
また「管理者は必ず理事長」という必要もないため、理事長以外の理事が管理者を務めることも可能です。
管理者が不在になった場合の変更手続きの期限は?
医療機関の管理者が不在になった場合の変更手続きについて、医療法には「◯日以内に手続きをしなければならない」という明確な期限は定められていません。
しかし医療法では「病院や診療所には必ず管理者を置かなければならない」と規定されているので、管理者が不在となることはこの規定に違反する状態となります。
そのため速やかに管理者を選任し、変更手続きをしなければなりません。
一般的に「管理者の変更届出」については、管理者の変更が生じてから「10日以内」に提出を求める自治体が多いですが、これはあくまで目安です。
提出先の自治体によって異なる場合があるため、管理者が不在になった場合は、速やかに管轄の保健所や都道府県の医療担当部署に問い合わせて、具体的な手続きと期限を確認するようにしましょう。
まとめ:クリニック開設には管理者や開設者の役割の理解が必須
医療法人では法人そのものが「開設者」となり、その代表である「理事長」が「経営者」としての役割を強く果たします。
そして「管理者」は医療現場の責任者として医療の質と安全を守る、という明確な役割分担があります。
管理者は医師もしくは歯科医師免許が必須であり、医療法人の場合は理事の中から選任する必要があるなど、法的要件を満たさなければなりません。
医療法人の運営に参画できない医師を理事(管理者)に選任すると「名義貸し」となり法的リスクを伴います。
そのため、管理者不在などの緊急事態に備えた対策をしっかりと検討しておくべきです。
特に院長の高齢化や体調変化により医院継承を検討される場合は、適切なタイミングでの準備が重要です。
医院継承の専門家である私たち「エムステージマネジメントソリューションズ」では、クリニックの先生が大事にしている医療方針や「クリニックの雰囲気」をしっかりと汲み取り、最適なマッチング先をご提案させていただいております。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。