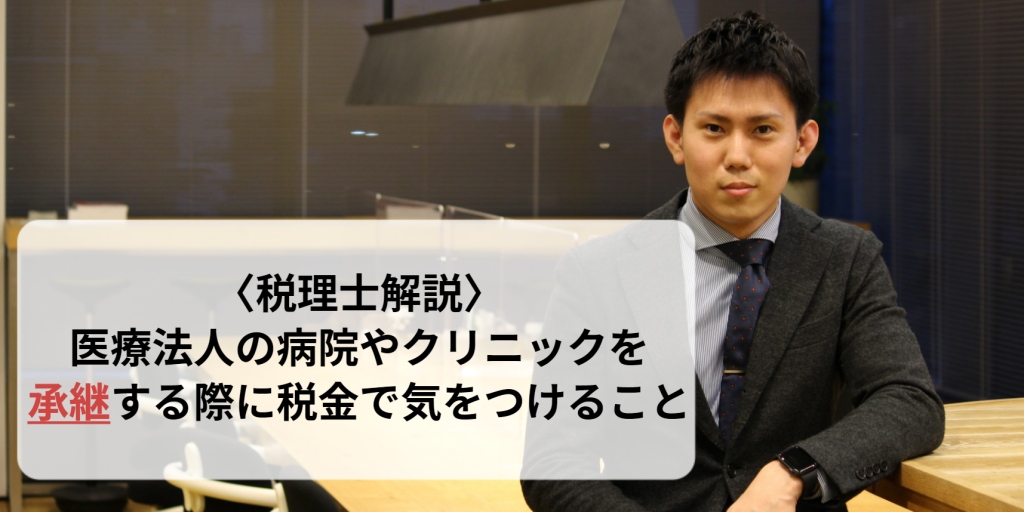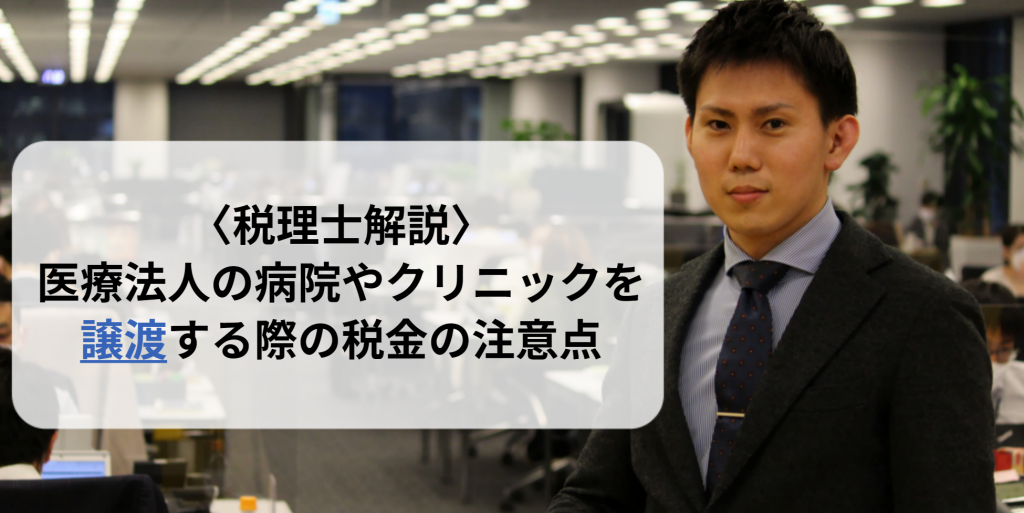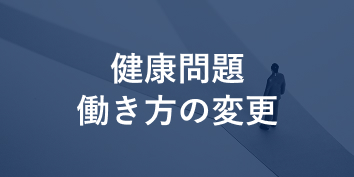医療法人格とは?取得するメリットやデメリット、取得方法を解説!

目次
「後継者が見つからない」「節税対策や事業拡大をしたい」そんな悩みを抱える開業医の方に注目されているのが医療法人格の取得です。個人経営のままでは、税負担が増加したり事業を拡大しにくかったりなど限界があります。
医療法人格を取得すれば、法人単位で財産や契約を管理でき、社会的信用や資金調達力が向上します。さらに、法人税による節税効果や、事業の継続性を確保できるなどの具体的な恩恵が得られます。とはいえ、設立には複雑な手続きや運営管理が伴い、不安を感じる方も少なくないです。
本記事では、医療法人格の基本から取得手順、メリット・デメリット、設立後の注意点まで解説します。医療法人化を検討する開業医にとって必要な医療法人格の知識を提供します。
医療法人格とは
医療法人格とは、医療法に基づいて設立される法人を指します。主な目的は、病院、診療所、介護老人保健施設などの運営により医療サービスの提供です。個人開業と異なり、法人格を持つと医療機関の財産が法人に帰属し、事業の継続性や信用力が高まります。
設立には都道府県知事の認可が必要であり、運営には厳格な規定が設けられています。近年では、後継者問題や経営の安定化を理由に、個人から法人化を検討する医療機関も増加しています。法人になること社会保険や税務上の取り扱いも変わるため、事前に専門家と相談することが重要です。
医療法人格の取得は、安定した医療提供体制を築く上で有効な選択肢となります。
医療法人格と医療法人の違い
医療法人格とは、医療法人が持つ法的な地位です。医療法人として活動するためには、法人格を取得する必要があります。法人格を持つと、財産の所有や契約の締結、債務の負担などが法人単位で可能です。個人ではなく、独立した法人として権利や義務を持つ点が特徴です。
一方、医療法人とは、医療サービスを提供するために設立された法人そのものを意味します。医療法人は病院や診療所、介護施設などを運営し、営利を目的とせず地域医療の発展に貢献する存在です。医療法人格を取得すると、正式に医療法人として認められ、活動を行えます。
医療法人格はあくまでも「資格」であり、医療法人は「組織」そのものを指します。医療法人格と医療法人の違いを理解するのは、医療法人の設立や運営を検討するうえで重要です。
医療法人格を取得するメリット
医療法人格を取得するメリットは3つあります。
- スムーズな医院継承ができる
- 社会的信用が向上する
- 節税効果が得られる
それぞれ解説します。
スムーズな医院継承ができる
医療法人格を取得していると、医院継承がスムーズに行えます。法人に帰属する財産や契約関係はそのまま引き継がれるため、個人開業医と異なり、大がかりな名義変更や契約のやり直しが不要です。特に、理事長の交代が容易であるため、医院継承に伴う複雑な手続きを省略できます。患者やスタッフへの影響も抑えられ、診療体制を維持できます。
また、法人名義での継続的な雇用契約や取引先との関係も変わらないため、承継後のトラブルも軽減されます。これにより、承継者は速やかに新たな経営体制を構築でき、スムーズな事業継続を実現可能です。
社会的信用が向上する
医療法人格を取得すると、社会的信用が大きく向上します。個人事業主に比べて組織運営の透明性が高く、対外的な信頼感が増します。そのため、法人化すると社会的信用が向上し、金融機関からの融資も受けやすいです。資金調達が容易になれば、新しい医療機器の導入やクリニックの増設なども現実的な選択肢になります。
患者に対しても、法人組織としての安心感を与えられ、診療所のイメージアップにつながります。また、採用に関しても優秀な人材が集まりやすくなる可能性が高まるでしょう。上記のように法人格の取得は、経営基盤の強化と成長戦略の実現につながります。
節税効果が得られる
医療法人格を取得すると、個人開業時よりも大きな節税効果を得られます。これは、法人化により、課税対象が所得税から法人税に変わるためです。所得税は最低5%、最高45%と幅広く、所得が増えるほど負担が重くなります。
一方、法人税は最低19%、最大23.2%と低く抑えられており、所得が多いほど節税効果が顕著です。さらに、生命保険料や役員退職金を経費として計上できるため、課税所得を圧縮しやすくなります。
節税だけでなく、資金計画や事業承継にも有利な環境を整えられるため、医療法人化は経営していくうえで重要です。
関連記事:医療法人化をマルっと解説!メリット・デメリットから手続きの流れまで
医療法人格を取得するデメリット
医療法人格を取得するデメリットは2つあります。
- 運営管理が複雑になる
- 社会保険・雇用保険への加入義務がある
詳しく解説します。
運営管理が複雑になる
医療法人格を取得すると、運営管理が個人開業に比べて格段に複雑になります。年に2回の社員総会や理事会の開催が法律で義務付けられており、その都度議事録の作成と管理が必要です。また、毎年の事業報告書や決算書を作成し、行政機関への提出が求められます。役員や社員の変更があった場合も、定款変更や届け出が必要です。
これらの事務作業は、専門知識がなければ対応が難しく、外部の税理士や行政書士のサポートが必要になる場面も増えます。煩雑な事務手続きに追われると、院長が医療に集中しにくくなるリスクもあります。法人運営には、あらかじめ十分な管理体制と人員配置を整えておくことが大切です。
社会保険・雇用保険への加入義務がある
医療法人格を取得すると、全職員に対して社会保険と雇用保険への加入が義務付けられます。そのため、給与支払額に対して法人負担の保険料が発生し、人件費が増加するため経営の負担が大きいです。個人開業医のように一部職員のみを対象にするのは不可能です。
これらの手続きに対応するために、事務員の雇用や社会保険労務士との契約が必要になる場合もあります。社会保険制度に対応するための知識も不可欠です。法人化によって社会的信用は高まるものの、経営コストと管理負担が大きくなる点に注意が必要です。
医療法人格の取得方法
医療法人格を取得するためには、主に7つの手順が必要です。
- 設立事前登録
- 医療法人設立説明会へ参加
- 定款の作成
- 設立総会の開催
- 設立認可申請書の作成と提出
- 設立認可の審査
- 設立登記の申請
それぞれ解説します。
設立事前登録
医療法人を設立する際には、都道府県で設立事前登録を行います。これは本申請の前段階にあたる重要な手続きです。
事前登録では、法人設立の意向や概要について提出書類にまとめ、審査を受けます。設立事前登録の受付は年に2回しかありません。通常、春と秋に設定される場合が多いため、スケジュールを確認して準備しましょう。手続きに遅れると、次回の受付まで待たなければなりません。
医療法人設立説明会へ参加
医療法人格の取得を目指す場合、医療法人設立説明会への参加が必要です。この説明会は年に2回ほど開催され、参加しないと認可申請に進めません。
説明会では、法人設立に必要な手続きや書類作成の注意点について詳しく案内されます。申し込みは事前に必要で、定員制の場合もあるため早めの手続きがおすすめです。
定款の作成
医療法人の設立には、まず定款を作成します。定款には、法人の目的、名称、所在地、業務内容、役員に関する規定などを記載します。
医療法人では、医療法の規定に従った内容が求められ、営利を目的としないと明確な記載が必要です。作成後は、設立時の社員全員の記名押印が必要で、都道府県知事の認可申請時に添付書類として提出します。
設立総会の開催
医療法人を設立するためには、設立総会の開催が必要です。設立総会では以下の項目を決定します。総会の開催日時、出席者の氏名、議長の氏名、議事案とその結果、議事録を作成した人の氏名です。
これらの事項は、議事録に記載しなければなりません。設立総会の議事録は、医療法人設立申請において必要な重要書類です。総会は、3人以上の設立者が開催し、適切に進行される必要があります。
設立認可申請書の作成と提出
設立認可申請書の作成では、組織の設立趣意、定款、事業計画、予算書、役員名簿、設立総会議事録などを正確に記載します。設立認可申請書を作成したら、必要な添付書類とともに提出します。
添付書類には、定款案、設立趣意書、役員名簿、資産目録、事業計画書などが必要です。内容に不備があると審査が遅れるため、記載漏れや誤記に注意しましょう。
設立認可の審査
設立認可の審査は、提出された書類の内容を基に各都道府県の医療審議会で行われます。審査では、設立目的や事業内容が医療法に適合しているか、法人運営の安定性、設立後の医療提供体制が適切かどうかが重視されやすいです。
問題なしと判断されれば、設立認可書が交付されます。不備や疑義があった場合に追加資料の提出を求められる場合もあります。審査には数か月かかる場合があり、早めの対応が必要です。
設立登記の申請
医療法人の設立認可書を受け取った後、2週間以内に設立登記を行います。登記には、法人の名称、所在地、役員に関する情報などが必要です。登記申請書と併せて、定款や設立認可書の写し、役員の就任承諾書、印鑑証明書などを提出します。
登記は本店所在地を管轄する法務局で行います。不備があると受理されないため、事前に書類を整えておくことが重要です。設立登記が完了すると、法人としての権利を取得し、医療行為や契約行為を法人名義で行えるようになります。
医院継承(医業承継)時に医療法人格がないことのデメリット
医院継承で医療法人格がないと2つのデメリットがあります。
- 承継時の手続きが複雑になる
- 税負担が増加する
詳しく解説します。
承継時の手続きが複雑になる
医院継承を検討する際、医療法人格がないと多くの手続きが発生します。個人開業医の場合、建物・医療機器・リース契約・従業員との雇用契約などがすべて「個人名義」となっているため、承継時にはそれぞれの名義を一つひとつ変更する必要があります。一方で医療法人格があれば、法人単位で契約や資産、雇用関係を一括して承継でき、事務的負担を軽減できます。
また、法人化によって社会保険への加入など、法人としての事務手続きや継続的な費用負担が生じる点も見逃せないです。医療法人格がないままの承継は、円滑な引き継ぎの妨げとなり、患者や従業員への影響も大きくなります。スムーズな事業継続のためには、事前の法人化が重要です。
税負担が増加する
個人開業医のまま医院を承継する場合、税務面で不利になる場合が多いです。たとえば、建物や医療機器などの資産を後継者に譲渡すると、その評価額に応じて贈与税または譲渡所得税が発生します。評価額が高額であればあるほど税負担も増加し、承継が困難になります。
これに対し、医療法人として運営していれば、法人が資産を所有しているため、承継時に個人間で資産の移転が発生せず、大きな税負担を回避可能です。さらに、法人税率は個人の最高所得税率よりも低く、節税効果も期待できます。医療法人格を取得していないと、納税額が膨らみ、後継者にとって大きな金銭的負担となる恐れがあります。医院経営の引き継ぎにおいて、税制面の不利益は無視できません。
関連記事:医療法人にしない理由は3つ!メリット・デメリットを含めて解説
よくある質問
医療法人に関してよくある質問を紹介します。
- 開業医は法人化した方が良い?
- 設立にかかる費用と時間は?
- 法人化後は診療科目などは変えられる?
それぞれ解説します。
開業医は法人化した方が良い?
開業医は、収入が増えて税負担が大きくなっている場合、法人化を検討する価値があります。個人事業主のままだと高額な所得税が課されるため、法人化により税率を抑えましょう。ただし、法人化により社会保険への加入義務が生じるため負担が増加する部分もあります。
事業を拡大していきたい場合にも法人化は有効です。法人組織であれば、資金調達や人材採用の面でも有利に働きます。さらに、後継者がいない場合にも法人化はおすすめです。法人化しておけば、第三者への事業承継や売却がスムーズに進められるからです。
設立にかかる費用と時間は?
医療法人の設立には、準備から認可取得まで半年から1年程かかります。各都道府県で受付期間が異なり、申請タイミングによっても期間が前後します。短縮を目指しても、申請書類の整備や行政とのやり取りに時間がかかるため、余裕を持った計画が必要です。
費用は総額で100万円程かかります。内訳には、定款作成、公証人手数料、登録免許税、専門家への依頼料などが含まれます。都道府県によって必要書類や審査基準が異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。
法人化後は診療科目などは変えられる?
法人化後でも診療科目の変更は可能です。ただし、変更に伴う手続きが必要になります。診療科目を変更した場合、変更後10日以内に保健所へ「診療所開設許可事項一部変更届」を提出しなければなりません。
診療科目以外にも、施設の名称、構造設備、所在地に変更が生じた場合も同様に届け出が必要です。スムーズに変更手続きを進めるためには、事前に必要書類や提出方法を確認しておくことが重要です。
医療法人格を取得して医療法人設立の恩恵を受けましょう
医療法人格の取得は、医院継承や経営の安定化、節税対策を実現したい開業医にとって重要です。法人格を持つと、財産や契約が法人に帰属し、社会的信用や資金調達力が向上します。また、法人税の適用により節税が可能となり、長期的な経営基盤の強化にもつながります。
一方で、法人運営には社員総会や決算報告など複雑な手続きが必要で、社会保険の義務付けなど負担も増加します。設立には事前登録や説明会参加、定款作成、設立総会、認可申請、審査、登記といった段階を経る必要があり、半年〜1年程度の期間と100万円前後の費用がかかります。
法人化は経営と承継の両面で有効な手段であり、将来を見据えた準備が欠かせません。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。