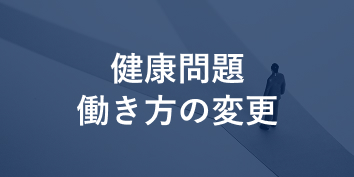医療法人の定款変更完全ガイド|手続きの流れから費用・失敗しないポイントまで解説

目次
クリニックの分院を開設する場合や、承継に伴って役員構成を変更する場合など、医療法人の運営において「定款」の変更が必要になる場面があります。
しかし、株式会社の定款変更とは手続きが異なり「何から手をつければ良いのか分からない」「手続きが複雑で面倒だ」と感じている先生も多いのではないでしょうか。
医療法人の定款変更は都道府県知事の認可が必要であり、手続きには専門的な知識と時間を要します。
準備不足のまま進めてしまうと、事業計画に遅れが生じる可能性もあるでしょう。
そこで本記事では、医療法人における定款変更の手続きの流れや費用、期間の目安、そして失敗しないための注意点まで詳しく解説します。
医療法人の定款変更に関する医療法の定め
そもそも定款(ていかん)とは法人の組織や運営、活動に関する根本的な規則を定めたもので「法人の憲法」とも呼ばれるほど重要な文書です。
定款には法人の目的や名称、主たる事務所の所在地、役員に関する規定などが記載されており、法人はこの定款に基づいて運営します。
一般的な株式会社が定款の内容を変更しようとする場合、基本的に「株主総会」で決議されたあとは変更の手続きを行うのみです。
しかし、医療法人が定款を変更しようとする場合は「都道府県知事の認可」も必要です。
これは医療法第54条の9によって規定されています。
“第五十四条の九
社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。
2 財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条第一項に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
5 医療法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。
6 第四十四条第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。”
出典:e-Gov法令検索|医療法
社団医療法人が定款を変更しようとする際には、まず「社員総会の決議」を行ったあと都道府県知事の認可を受けて初めて、定款の変更が効力を発揮します。
医療法人財団の場合は定款ではなく「寄附行為」と呼ぶ
社団医療法人の根本規則を「定款」と呼ぶのに対して、財団医療法人の場合は「寄附行為」と呼びます。
これは法人の設立根拠が異なるためです。
社団は社員が出資して設立されるのに対し、財団は個人や法人が財産を寄附することによって設立されます。
本記事では便宜上、主に「定款変更」という言葉を用いて解説しますが、財団医療法人の場合は「寄附行為の変更」と読み替えてください。
手続きの基本的な流れや考え方は共通しています。
医療法人で定款変更が必要となるケース
以下に該当するケースでは、定款の変更が必要です。
- 新たに分院を開設する場合
- 施設を閉鎖(閉院)する場合
- 施設の場所を移転する場合
- 既存の施設を増築したり拡張したりする場合
- 有料老人ホームや訪問看護ステーションといった附帯業務を開始、または廃止する場合
- 施設の名称を変更する場合
- 事業拡大などで定款で定めた役員の上限を超える場合
- 定款で定めた会計年度(決算期)を変更する場合
上記のほかに医療法の改正など、各種法律に対応するために定款変更が必要となる場合もあります。
定款変更は都道府県知事の認可が必要
医療法第54条の9第3項に明記されているとおり、医療法人が定款を変更する際には「都道府県知事の認可」が必要です。
これは医療法人が「医療の提供」という公益性の高い事業を行っているためです。
ただし、全ての変更に対して認可が必要なわけではありません。
「事務所の所在地のみの変更(都道府県内での移転)」や「公告の方法の変更」など、厚生労働省令で定める軽微な事項については、認可は不要で「届出」のみで手続きが完了します。
医療法人における定款変更の流れ
医療法人の定款変更は、以下の流れに沿って手続きを行います。
- 理事会の決議・社員総会での承認を得る
- 登記事項に伴う定款変更など必要な添付書類を用意する
- 仮審査のあと本申請の提出を行う
- 登記事項に関する定款変更の場合は法務局の手続きも必要
それぞれの手順を解説します。
1.理事会の決議・社員総会での承認を得る
まず、理事会で定款変更案を決議し、そのあと社員総会を開催して定款変更の承認を得る必要があります。
社団医療法人の場合は社員総会の決議、財団医療法人の場合は評議員会での意見聴取が必要です。
定款変更の必要書類となる「議事録の作成」も忘れずに行いましょう。
2.登記事項に伴う定款変更など必要な添付書類を用意する
意思決定が完了したら、次は都道府県に提出する書類の準備です。
定款変更は、その内容によって必要となる書類が大きく異なります。
【基本的に必要となる書類例】
- 定款変更認可申請書
- 定款変更理由書
- 新旧条文対照表
- 変更後定款案
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 法人登記事項証明書
- 医療法人の概要書
【変更内容によって追加で必要となる書類例】
- 新規開設の場合:施設概要書や平面図、賃貸借契約書など
- 附帯業務追加の場合:事業計画書や収支予算書など
- 役員変更の場合:就任承諾書や履歴書など
都道府県によって必要となる書類は異なる場合があるため、あらかじめ所管部署に確認しておきましょう。
3.仮審査のあと本申請の提出を行う
必要書類が用意できたら、保健所に郵送で提出します。
多くの都道府県では、本申請時の書類不備を防ぐことを目的として、まずは「仮審査」や「事前チェック」が実施されています。
仮審査では提出予定の書類一式が確認され、記載不備などがあれば修正などの対応が必要です。
指摘された点を修正した後、正式な本申請を行います。
本申請では「正本」と「副本」をそれぞれ提出しなければなりません。
必要部数は都道府県によって異なるので確認しておきましょう。
4.登記事項に関する定款変更の場合は法務局の手続きも必要
本審査が完了し、都道府県知事から無事に「定款変更認可証」が交付されたら定款の変更は効力が発揮します。
ただし定款変更の内容が下記の「登記事項」に関わる場合は、法務局で変更登記を行う必要もあります。
【登記事項に関する定款変更】
- 法人名称の変更
- 所在地の変更
- 医療法人の目的の変更
- 役員に関する変更
変更登記は定款変更が認可された日から2週間以内に申請する必要があり、期限を過ぎると過料の対象となるため注意してください。
医療法人の定款変更に必要な期間は約3か月
定款変更の手続きは仮申請で1〜2か月程度、そのあとの本申請から認可書が交付されるまで2週間程度と、実際の手続きだけで約3か月は必要です。
手続きの前に必要となる理事会や社員総会の決議、書類作成なども含めるとトータルで5〜6か月程度はかかると見越してスケジュールを組むことが重要です。
定款変更の効力発生日は「認可証の受取日」
定款変更の効力は、都道府県知事から認可証を受け取った日から発生します。
認可証を受け取る前は、変更内容に基づいた事業が開始できませんので注意してください。
たとえば新規診療所の開設を行う場合、定款変更の認可を受けてから(認可書を受け取ってから)保健所に開設許可申請を行い、許可を得た後に診療を開始する流れになります。
医療法人の定款変更にかかる費用
一般的な株式会社の定款変更では、登記事項の変更があり法務局に手続きを行う際に「登録免許税」が必要です。
医療法人の場合「登録免許税」は非課税、つまり費用はかかりません。
理由としては、登録免許税が課せられる範囲に「医療法人」が含まれていないためです。
“(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。”
出典:e-Gov法令検索|登録免許税法
上記の「別表第一」には医療法人の項目が無いため、医療法人は登録免許税の課税対象とはなりません。
都道府県知事の認可手続きも基本的に費用は発生しませんので、医療法人は定款変更の手続きで大きな費用は必要ありません。
定款変更の認可や登記後に忘れがちな変更手続き
定款変更と登記の手続きが無事に完了しても、これで終わりではありません。
医療法人の名称や所在地、代表者などが変更された場合、関係各所への届出も必要です。
変更手続きを忘れていると診療報酬の入金が遅れたり、行政からの重要な通知が届かなかったりといったトラブルにつながる可能性もあります。
最低限、以下の機関の変更手続きや表記の変更を忘れないようにしましょう。
・保健所
・厚生局(地方厚生局)
・税務署・都道府県税事務所
・銀行・取引先への連絡
・その他(パンフレットや名刺、公式サイトなど)
▶医院承継・クリニックM&Aの最新情報はトップページからご覧ください
医療法人の定款変更を専門家に依頼する場合のポイント
医療法人の定款変更は複雑な手続きであるため、専門家に依頼される先生も多いでしょう。
ここでは、専門家の選び方と活用方法について解説します。
都道府県知事の認可までのサポートを受けるなら「行政書士」
定款変更認可申請の書類作成や手続きに関してサポートしてもらいたい場合は、行政書士に依頼するのが良いでしょう。
【行政書士に依頼できる主な業務】
- 定款変更認可申請書類の作成
- 都道府県との事前相談の同行
- 保健所での各種申請手続き
特に医療法人の定款変更は一般的な株式会社の手続きとは異なるため、下記のポイントを抑えて行政書士を選びましょう。
【行政書士の選び方のポイント】
- 医療法人業務の実績が豊富であること
- 医療法について詳しい知識を持っていること
- 所在する都道府県の手続きに精通していること
- レスポンスが早くて丁寧な説明をしてくれること
法務局に登記申請を行う際のサポートを受けるなら「司法書士」
法務局での登記申請に関する業務は、司法書士の独占業務となります。
そのため特記事項の変更が伴う場合のサポートは、司法書士にしかできません。
【司法書士に依頼できる業務例】
- 医療法人の変更登記申請
- 登記事項証明書の取得代行
- 登記内容のアドバイス
【司法書士の選び方のポイント】
- 医療法人の登記実績があること
- 迅速な対応ができること(認可後2週間以内の登記が必要)
- 行政書士との連携体制があること
医院継承による定款変更なら仲介会社に相談
医院継承では、承継者の専門分野に合わせた診療科目の変更や新たな附帯業務の追加、出資持分の処理、役員構成の変更など、複数の定款変更が同時に発生します。
また、これらの事務的な変更手続きだけでなく、譲る側の適切な税負担の軽減、譲り受ける側の資金調達や承継後の経営状況など、医院継承時には様々な課題を解決しなければなりません。
円滑な医院継承を実現するためにも、医療業界に特化した仲介会社に相談をしましょう。
私たちエムステージマネジメントソリューションズでは、医院継承に関する豊富な実績を持ち、定款変更を含む各種手続きに関しても専門家との連携も視野にいれながら、円滑な承継を実現いたします。
単なる譲る側と譲り受ける側のマッチングだけでなく、承継が実現したあとのフォローアップもしっかりと行います。
医院継承をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
医療法人が定款変更を行う際の注意点
最後に、定款変更で思わぬ失敗を避けるための重要な注意点を6つ紹介します。
必要な書類や手続きに要する期間は都道府県によって異なる
都道府県によって定款変更に必要な書類や部数、審査期間が異なります。
【都道府県ごとで異なる点】
- 必要書類の種類や様式
- 事前審査の有無や方法
- 審査期間の長さ
あらかじめ都道府県の担当部署に確認し、手続きで必要な書類や全体のスケジュールを確認しておきましょう。
「出資持分あり」から「出資持分なし」への移行は社員全員の同意が必要
医院継承や相続税対策として、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を検討されるケースも増えています。
この移行に関しても定款変更を行わなければなりませんが、その前提として「社員全員の同意」を得なければなりません。
社員一人ひとりが持つ法人への財産権(出資持分)を、全員が完全に放棄することになるためです。
出資持分は、退社時や法人解散時に払い戻し請求ができる、社員個人の重要な資産です。
多数決によって一部の社員の財産権を強制的に放棄させることは、個人の財産権を著しく侵害することになります。
そのため、重大な権利の変更にあたるこの移行には、社員全員の明確な同意が必要です。
税務上の問題も複雑に絡むため、必ず専門家と相談しながら慎重に進めましょう。
法務局に登記申請が遅れると100万円以下の罰金が発生
定款変更に伴う登記事項の変更は、認可日から2週間以内に法務局に申請する必要があります。
この期限を過ぎると、裁判所から100万円以下の過料が科せられる可能性があるため注意しなければなりません。
原始定款の内容は直接改変しない
医療法人設立時に作成した「原始定款」は、設立の根拠となる重要な文書であるため、定款変更時に改変してはいけません。
定款変更は、原始定款とは別の「定款変更書」として作成し、変更箇所がわかるように「新旧条文対照表」も作成する必要があります。
公証人の認証は不要
医療法人を設立し、定款を初めて定めた際には、公証人の認証を受ける必要があります。
しかし定款の変更を行う際には、再度認証を受ける必要はありません。
都道府県の認可と、特記事項の変更の場合は法務局への届出のみで手続きは完了します。
医療法人財団の合併はあらかじめ寄附行為に記載が必要
医療法人財団で、将来的に他の医療法人との合併も視野に入れている場合は、特に「寄附行為(定款)」の内容に注意しましょう。
医療法人財団が合併を行うためには、寄附行為に「合併が可能」と定められている必要があるためです。
“第五十八条の二 社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。”
出典:e-Gov法令検索|医療法
将来の選択肢を狭めないためにも、設立時や変更の機会に、合併に関する条項を寄附行為に盛り込んでおくことをおすすめします。
まとめ:ミスや漏れの無い定款変更を実現するためにも専門家に相談を
医療法人の定款変更は、一般企業の定款変更と比べて複雑で特殊な手続きが多く、失敗時の影響も大きいため、十分な準備と専門知識が必要です。
手続きの複雑さや要求される膨大な書類の数、認可までに数か月を要するという時間的な制約もあります。
これらの負担をご自身で抱え込むことは、本来注力すべき診療業務や経営改善への時間を奪い、結果として法人全体の機会損失にもつながりかねません。
特に医院継承に伴う定款変更をお考えの際は、ぜひ私たちエムステージマネジメントソリューションズにご相談ください。
医院継承では定款変更をはじめとする複雑な手続きが必要となるため、適切な専門家との連携が不可欠です。
私たちは医療業界での豊富な経験を活かし、必要に応じて各種方面の専門家と協力しながら、円滑な医院継承の実現をお手伝いいたします。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。