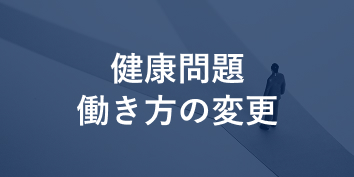医療機関が労働基準監督署に通報されたらどうなる?違反の事例や対策方法を解説

目次
「スタッフとの労務トラブルは未然に防ぎたい」「残業代や労働時間、うちのクリニックは大丈夫だろうか…」こうした労務に関する不安をお持ちの先生は、多くいらっしゃるでしょう。
本記事では万が一、労働基準監督署(労働基準監督署)に従業員から通報された場合、どのような流れで調査が進むのか、医療機関でよくある違反事例、そして事前に取るべき対策について、わかりやすく解説します。
本記事を読むことで労務リスクを理解した上で職場環境が改善でき、医療スタッフも経営者も安心して医療提供に専念できる体制づくりができます。
労働基準監督署に通報されたらどうなる?
「法令違反がある」と労働基準監督署に対して、従業員などから通報(申告)があった場合でも、すぐに調査が開始されるわけではありません。
通報の内容は事実性があるのか、労働基準監督署が対応すべき内容なのかなど、まずは通報内容の精査が行われます。
通報内容に違法性があり、労働基準監督署が対応すべきと判断された場合、実際に調査が行われます。
調査の結果、法令違反などが認められた場合には労働基準監督署から指導が行われ、悪質な場合には罰金が科されることもあるため、適切な対応や改善が必要です。
労働基準監督署が調査を行うきっかけ
労働基準監督署の調査は、従業員からの通報(これを「申告監督」と言います)だけがきっかけではなく、以下の4種類があります。
- 定期監督
- 申告監督
- 災害時監督
- 再監督
それぞれ詳しく解説します。
定期監督
「定期監督」は労働基準監督署が毎年策定する監督計画に基づき、無作為に選ばれた事業所に対して行われる調査です。
特定の業種や社会的に関心の高いテーマ(たとえば長時間労働の是正など)に焦点を当てて、対象の事業所が選定されることもあります。
基本的に定期監督は拒否ができないため、いつ対象になっても問題がないように、日頃から適切な労務管理が重要です。
申告監督
「申告監督」は本記事のテーマでもある、クリニックで働いているスタッフや過去に働いていたスタッフ(あるいはその関係者)から、申告があった場合に行われる調査です。
「給料が支払われない」「違法な時間外労働がある」など、労働基準法の違反内容に関して、事情聴取が行われたり必要な帳簿の確認などが行われたりします。
違反が認められた場合には是正の指導が入り、それでも改善されなかった場合には、労働基準法の定めによって罰金が科されたり、企業名が公表されたりします。
災害時監督
「災害時監督」はクリニック内で労働災害(労災)が発生した場合に、その原因究明や再発防止策の確認のために行われる調査です。
事故の状況や安全管理体制、安全教育の実施状況などが詳しく調べられます。
医療機関では感染者の血液が付着した器具による外傷、いわゆる「針刺し事故」や転倒、腰痛なども労災に該当する可能性があります。
クリニックはアクシデントが発生した際の対応手順を明確にし、スタッフに周知しておく必要があるのはもちろんのこと「そもそもアクシデントや労災が発生しないための工夫や仕組み」も行わなければなりません。
再監督
「再監督」は過去に労働基準監督署から指導や是正勧告を受けた事業所やクリニックに対し、その後の改善状況を確認するために行われる調査です。
改善が不十分であったり報告を怠ったりした場合には、送検や罰金などの、より厳しい措置が取られる可能性もあるため、誠実に対応する必要があります。
▶労務リスクも含めた医業承継(M&A)の全体像と経営判断を確認する
労働基準監督署に通報されたあとの流れ
労働基準監督署に通報されたあと、下記の手順に沿って調査や指導などが行われます。
- 通報内容の精査が行われる
- 事業所に対して精査が行われる
- 【違法性があった場合】行政処分が下される
- 【より悪質だった場合】送検や罰則が科される
それぞれ詳しく解説していきます。
通報内容の精査が行われる
まずは労働基準監督署に通報された情報に基づいて、法令違反の可能性や信憑性が検討されます。
匿名による通報の場合、具体的な情報が少ないと調査には至らない場合もあります。
また「労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法」以外の通報も、労働基準監督署の対応外になり、ほとんどが調査されません。
たとえばセクハラやパワハラなどは、基本的に労働基準監督署の管轄外の問題となるためです。
事業所に対して調査が行われる
法令違反の疑いがあると判断した場合には、事業の代表者を呼び出したり、労働基準監督官が事業所やクリニックを訪問したりして調査を行います。
呼び出し調査が行われる場合には、労働基準監督署から「出頭要求通知書」が送付されます。
指定された日時に、事実確認のための指定された書類を用意して、労働基準監督署に出頭しなければなりません。
その後、監督官による立入調査が行われます。
立入調査は事前の告知があるケースと、特に悪質な違反だと予測される場合には抜き打ちで行われるケースもあります。事前に連絡をすると書類を改ざんされたり破棄されたりすることが考えられるため、抜き打ち調査が行われるわけです。
【立ち入り調査の主な内容】
- 労働関係の帳簿の確認
- 勤務の実態調査
- 従業員に対する聞き取り調査
【違法性があった場合】行政処分が下される
調査の結果、法令違反が確認された場合には、その内容に応じて以下の措置が取られます。
【助言指導】
法令違反とまでは言えないものの、改善が望ましい点がある場合に「指導票」が交付されます。法的な強制力はありませんが、改善報告が求められることが多いです。
【是正勧告】
明確な法令違反がある場合には「是正勧告書」が交付されます。違反事項と是正期日が記載されており、期日までに改善をして報告をしなければなりません。
是正勧告は法令違反が認められているため、改善をしない、報告もしなかった場合には送検や罰則などが行われます。
【より悪質だった場合】送検や罰則が科される
是正勧告に従わない、違反内容が悪質である、繰り返し違反を続けるといった場合には、書類送検され、罰金や懲役刑などの刑事罰が科される可能性があります。
令和4年のデータによると783件の送検が行われ、そのうち264件が裁判にまで発展して罰金の支払いを命じられています。
※出典:厚生労働省労働基準局|令和4年労働基準監督年報(送検結果の推移)
社会福祉施設を含む医療機関も、6件の送検が行われていました。
特に医療法人が送検された場合、個人のクリニック以上にリスクが高い点に注意しなければなりません。
医療法人が経営している1つのクリニックで送検や行政処分を受けた場合、医療法人そのものの労働環境や医療体制に不信感を抱かれ、患者からの信用を失う可能性が高いためです。
労働基準監督署から通知が届いた場合には迅速に是正の対処を行い、体制の見直しが必要です。
労働基準監督署が動くまでの期間
労働基準監督署へ通報されてから実際に動くまでの期間は、一般的に約1〜2週間程度です。
ただし、労働基準監督署の繁忙状況や通報内容の緊急性によっても、動くまでの期間は変動します。
たとえば匿名による相談で信用性の高い証拠も無い通報内容の場合には、優先度が低いと判断され、すぐには動きません。
一方で明らかな法令違反の証拠があり、事件性の高い(送検の可能性が高い)通報内容の場合には、すぐに調査が行われるケースもあります。
よくある労働基準法の違反事例
ここでは医療機関で起きやすい労働基準法の違反事例を紹介します。
自院の状況と照らし合わせ、該当していないか確認をしておきましょう。
法定労働時間を超えた労働
法定労働時間は基本的に1日8時間、1週間あたり40時間が上限となっていて、超過する場合には従業員と36協定を締結しなければなりません。
しかし、実際には医師以外の職種(看護師・事務・技師・助手など)に対して36協定を締結していなかったり、協定の範囲を超えた長時間労働を行わせたりするケースも違反として指摘されています。
特に医師の労働時間に関しては、2024年4月から上限規制が適用されている点に注意しなければなりません。
A水準(年間960時間以内)、B水準(年間1,860時間以内)など、適用される水準に応じた労働時間管理が必要です。
これまで医師の労働時間に関して、特別な条件下においては長期の労働時間が認められていましたが、働き方改革によって現在は上限が定められています。
関連記事:2024年4月から改正医療法が施行!医師の働き方改革にどう対応する?
残業代や割増賃金の未払い
残業代や割増賃金など、給与に関する違反は医療機関でも起こりがちです。
事実、令和4年に医療機関が送検された16件のうち、12件は「賃金の支払い」に関する違反内容です。
※出典:厚生労働省労働基準局|令和4年労働基準監督年報(送検結果の推移)
医療機関でありがちな残業代未払いの事例には、以下のようなものがあります。
- 固定残業代として支払ってはいるが、実際には固定残業時間を超過した残業があり、その部分の未払いがあった
- 診察時間終了後の残務処理時間(カルテ入力、片付け、翌日の準備など)を労働時間として管理していなかった
- 診療報酬請求の締め切りに間に合わせるためのサービス残業が常態化していた
- 看護師・受付スタッフの休日振替や時間外労働の管理不備があった
- シフト制のスタッフの勤務間インターバルが確保されていなかった
- 複数の医療機関で勤務しているスタッフの勤務時間が正しく管理されていなかった
これらは医療機関の業務内容上「やむを得ない」といった状況があったとしても、労働基準法上は違反となるため労働時間の管理は徹底して行わなければなりません。
機械や設備が安全基準を満たしていない
医療機関特有の安全衛生に関する違反としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 医療機器や設備が安全基準を満たしていない
- 感染防止対策が不十分である
- 有害物質(消毒液など)の取り扱いに関する安全教育が行われていない
- 針刺し事故などの労働災害防止対策が不十分である
上記に関して、マニュアルや安全防止策を行っているか確認をしておきましょう。
健康診断が行われていない
健康診断に関する違反は、以下のようなケースで指摘されることがあります。
- 定期健康診断を実施していない、または一部のスタッフが受診していない
- 深夜業務に従事する職員に対して6か月ごとの健康診断を実施していない
- 長時間労働者に対する医師の面接指導を実施していない
- ストレスチェックを実施していない(50人以上が勤務している大規模な病院などでは必須)
日々過酷な環境の中で働く医療従事者にとって、健康管理は特に重要です。
通報されないために環境を整備するのではなく「そもそも従業員が心身ともに健康で安心して働けるために」環境を整備しなければなりません。
令和5年度の労働基準監督署による監督指導の結果
厚生労働省の発表によると、長時間労働が疑われる事業場に対して行われた監督指導では、26,117の事業所のうち11,610の事業場(44.5%)で違法な時間外労働が確認されています。
こうした違反は、業種を問わず多くの事業場で発生しており、中でも「労働時間」に関する違反が最も多く指摘されています。
主な違反内容は36協定の未締結、締結していたとしても上限時間を超えた労働の実態です。
労働基準監督署による監督指導は、長時間労働の是正や過重労働による健康障害防止のため、今後も強化されることが考えられます。
労働基準監督署に通報されないための対策7選
労働基準監督署からの調査や指導を未然に防ぐためには、日頃の適切な労働環境や管理体制づくりが重要です。
ここでは具体的な対策方法を7つ紹介します。
労働条件通知書と雇用契約書の交付をする
スタッフを採用する際、労働条件通知書を交付し、雇用契約書を締結することは法令上の義務です。
特に以下の点に注意して交付を行いましょう。
- 労働時間、休日、給与、残業代の計算方法などを明確に記載する
- 固定残業代制度を採用する場合は、その旨と超過分の計算方法を明記する
- 非常勤スタッフや短時間勤務者にも必ず交付する
残業や休日出勤では必ず36協定の締結を行う
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や、法定休日(週1日または4週4日)に労働させる場合は、36協定の締結と届出が必要です。
特に医療機関では、急患対応などで予定外の時間外労働が発生することが多いため、36協定は必須と言えます。
医師の場合は2024年4月から適用されている、時間外労働の上限規制に適合した36協定を行わなければなりません。
タイムカード以外で出退勤の記録が残る仕組みを導入する
労働時間に対して適切に賃金を支払うためには、正しい出退勤の記録を残さなければなりません。
「タイムカードを切ったあとも実際は労働が行われていた」「タイムカードの打刻を忘れていた」などを防ぐためにも、タイムカード以外の記録が残る仕組みも導入しておきましょう。
- ICカードや生体認証など、客観的な記録が残る勤怠管理システムを導入する
- パソコンの使用時間のログや電子カルテへのアクセス記録を残す
労働基準法で定められた帳簿の作成・保存をする
労働基準法では以下の帳簿を作成し、一定期間保存することが義務付けられています。
- 労働者名簿(退職後3年間保存)
- 賃金台帳(3年間保存)
- 出勤簿やタイムカードなどの労働時間の記録(3年間保存)
- 雇入れ時の労働条件通知書の写し
特に賃金台帳には労働日数や労働時間数、残業時間数、休日労働時間数などを漏れなく記載することが重要です。
従業員の健康診断を行う
常時雇用する従業員に対しては、雇い入れ時および原則として1年に1回は定期健康診断を実施する義務があります。
以下のポイントに沿って、従業員の健康診断を行いましょう。
- 年1回の定期健康診断を全スタッフに実施する(パート・アルバイトも対象)
- 深夜業務に従事するスタッフには6か月ごとの健康診断を実施する
- 健診結果に基づく保健指導を行う
- 長時間労働者には医師による面接指導を実施する
社労士などの専門家によるサポートを受ける
労働関連の法律は複雑で、頻繁に法改正も行われます。
院長や理事長が診療や経営を行いながら最新の法規を常に把握し、適切な労務管理を行うのは困難なことも多いでしょう。
そこで、専門家である社会保険労務士などのサポートを受けることを強くおすすめします。
【社会保険労務士が対応できる主な内容】
- 労務管理システムの導入や運用のサポート
- 就業規則や各種規程の見直しや整備
- 新たな法改正への対応方法のアドバイス
労働基準監督署に通報されないためにも実態の把握と改善を行いましょう
院長や理事長は、日々の診療や経営状況の改善で多忙な環境と言えます。
そのような中、知らず知らずのうちに一緒に働いている従業員の労働環境も悪化し、労働基準監督署への通報のリスクが進行しているケースも多くあります。
医療機関は人命を預かる立場であり、スタッフの健康管理や適正な労働環境の確保は、質の高い医療サービスを提供する上で非常に重要です。労務問題を放置すると、スタッフの離職や患者サービスの低下につながる恐れもあります。
職員との信頼関係を保つためにも、日々の記録管理や就業ルールの見直しを行い、第三者の専門家にチェックしてもらうことがおすすめです。人材確保の観点からも、医療機関の労働環境の改善は重要な経営課題です。
法令遵守はもちろんのこと、働きやすい職場づくりを通じて、従業員や患者が安心できる環境を整えていきましょう。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。