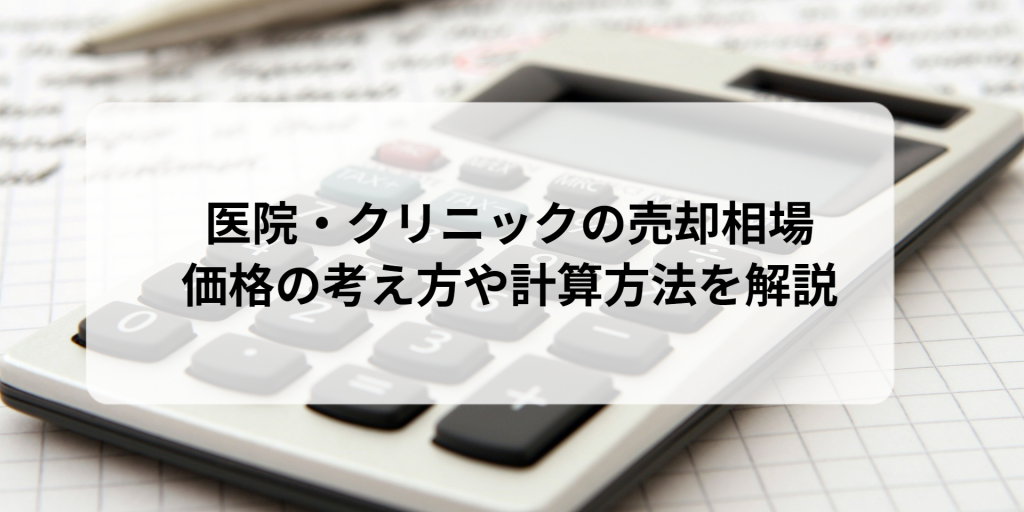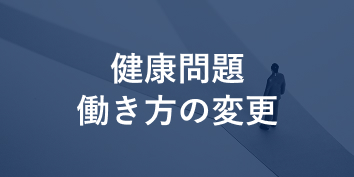保険返戻金の計算方法は?税金や活用方法をクリニック経営者向けに解説

目次
クリニック経営において、将来的な資金確保は重要な課題の一つです。
中でも生命保険の解約返戻金は、院長自身の退職金としての資金や医院継承時の資金として活用できる貴重な資産となります。
しかし解約返戻金の仕組みや税金の取り扱い、効果的な活用方法について詳しく理解されている経営者の方は少ないでしょう。
そこで本記事では、保険返戻金の基本的な仕組みから計算方法、税金の取り扱い、そしてクリニック経営における具体的な活用方法を解説します。
保険の解約返戻金を活用して円滑な医院継承を実現した事例も紹介しているので、クリニックの承継を検討されている先生は、ぜひチェックしてください。
保険返戻金とは積立資金の払い戻しを受けること
保険返戻金とは、生命保険契約を途中で解約した際に、保険会社から契約者に払い戻されるお金のことです。正式には「解約返戻金」と呼ばれ、これまでに支払った保険料の一部が積み立てられており、その積立金が返還される仕組みです。
クリニック経営者の多くが加入している「法人向け生命保険」の中には、この積立機能を持った「積立型保険」が多く存在します。
積立型保険は万が一の保障を確保しつつ、将来的な資金形成も行える仕組みになっているため、経営戦略としても効果的な保険とされています。
掛け捨て型保険は解約返戻金がない
解約返戻金がない保険に「掛け捨て型保険」が挙げられます。「掛け捨て」の名の通り、毎月支払う保険料は万が一の保障時にのみ使われ、解約時に返戻金は受け取れません。
積立機能がない分、積立型保険と同じ補償内容だった場合に掛け捨て型のほうが安く、保険料の負担が抑えられます。
ただし保険料を支払い続けても、解約時に資金が戻ってくることがないため、将来的な資金形成も視野に入れたい場合には、必ずしも最適な選択とは言えないでしょう。
クリニック経営においては、保険の選択時に「保障機能」と「資金形成機能」のどちらを重視するかを明確にし、経営戦略に合った商品を選択することも重要です。
解約返戻金は3つのタイプがある
生命保険における解約返戻金は、主に3つのタイプに分類されます。
それぞれ特徴が異なるため、経営戦略や資金計画に合ったタイプを選択することが大切です。
従来型
従来型は最も一般的な解約返戻金の仕組みで、契約年数が経過するにつれて解約返戻金額も増加していくタイプです。従来型の特徴は、比較的早い時期でも解約返戻金を受け取れる点です。
ただし、契約初期の解約返戻金額は支払った保険料総額を下回ることがほとんどですので、元本を回収するためには一定期間の継続が必要です。
保険料は3つのタイプの中で最も高く設定されることが多いため、月々の負担を考慮する必要があります。
低解約返戻金型
低解約返戻金型は、保険料を支払っている期間は解約返戻金が低く抑えられている分、従来型に比べて保険料の安い保険です。保険料払込期間中は、従来型の約70%程度の解約返戻金となるのが一般的です。
払込期間が終了した後は、従来型と同等またはそれ以上の解約返戻金を受け取れます。
低解約返戻金型の最大の特徴は、保険料の負担を抑えながら将来的な資金形成も計画できる点です。
現在の資金繰りを重視しつつも、将来的な万が一の運営資金の確保や退職金の準備を行いたい場合にも適しています。
無解約返戻金型
無解約返戻金型は解約返戻金が一切設定されていない、または設定されていても非常に少ないタイプです。いわゆる「掛け捨て型保険」が、このタイプに該当します。
保険料は3つのタイプの中で最も安いため、保険料負担は最小限に抑えつつ、将来に向けた積み立ては違う方法で行いたい場合に最適です。
関連記事:開業医が行うべき資産形成は?資産1億の割合や運用方法を解説
生命保険の解約返戻金で受け取れるお金の計算方法
解約返戻金の金額は、保険会社が契約ごとに設定している「解約返戻金表」に基づいて決定されます。
解約返戻金表は、契約時に提示される「保険設計書」や各保険会社のホームページなどに記載されており、契約年数と経過月数によって具体的な金額の確認が可能です。
基本的な解約返戻金の計算式は、下記のとおりです。
| 解約返戻金額 = 払込保険料 × 解約返戻率 |
たとえば払込保険料が800万円で解約返戻率が105%だった場合、受け取れる解約返戻金は840万円です。
なお「解約返戻率」は、契約年数や商品の種類によっても変動します。
契約から5年経過時点で80%、10年経過時点で95%、15年経過時点で105%といった具合で設定されているので、契約されている保険会社で確認をしましょう。
▶税金や活用方法を踏まえてリニック売却・譲渡(M&A)の進め方を確認する
保険の解約返戻金が振り込まれるタイミング
解約返戻金が振り込まれるタイミングは、保険会社や手続きの状況によって多少異なりますが、一般的には解約手続き完了から約1週間から10日程度で指定した口座に振り込まれます。
解約手続きの基本的な手順は以下のとおりです。
- 解約の申請をする:保険会社に解約の意思を伝えて必要書類の請求をします。
- 書類を提出する:解約請求書や印鑑証明書、身分証明書などの必要書類を提出します。
- 書類の確認が行われる:保険会社が書類の内容を確認し、実際の解約返戻金額が算出されます。
- 振り込みが実行される:確認が完了したあと、指定口座に解約返戻金が振り込まれます。
解約手続きは原則、契約者本人(法人契約の場合は代表者)のみ手続きが可能で、代理人に手続きを行ってもらう場合には契約者本人の委任状が必要です。
また、保険証券の紛失や印鑑相違などがあると手続きが遅れる可能性もあるため、あらかじめ必要書類の確認をしておくことが大切です。
保険の解約返戻金にかかる税金
解約返戻金を受け取る際には、契約の形態や受取人によって異なる税金が課せられます。
「契約者本人が受け取る場合」と「契約者以外が受け取る場合」で課税内容が異なるため、正しい税務処理を行うために理解しておきましょう。
契約者が受け取る場合:所得税と住民税
個人契約で契約者本人が解約返戻金を受け取る場合、所得税と住民税の課税対象となります。
この場合の税務上の取り扱いは「一時所得」として分類されます。
一時所得の計算式は以下のとおりです。
| 一時所得 =(解約返戻金 - 支払保険料総額 - 特別控除50万円)× 1/2 |
この計算式からわかるように、解約返戻金が支払った保険料総額を上回った場合のみ、その差額から50万円を差し引いた金額の半分が課税対象となります。
具体例として、支払保険料総額が1,000万円、解約返戻金が1,200万円の場合を見てみましょう。
| 解約返戻金(1,200万円)- 支払保険料総額(1,000万円) = 200万円一時所得:(200万円 - 特別控除50万円)× 1/2 = 75万円 |
この75万円が他の所得と合算され、所得税(5%〜45%)と住民税(10%)の課税対象となります。
法人契約の場合は、解約返戻金は法人の収入として計上され、法人税(23.2%)の課税対象となります。
ただし、これまでに損金算入した保険料がある場合は、その分を考慮した税務処理が必要です。
契約者以外の人が受け取る場合:贈与税
契約者以外の人が解約返戻金を受け取る場合は、贈与税の課税対象となります。これは、契約者から受取人への財産移転とみなされるためです。
贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられており、解約返戻金が110万円を超える場合に超過分に対して贈与税が課せられます。
贈与税の計算式は下記のとおりです。
| 贈与税=解約返戻金 ー 110万円 × 贈与税率 ー 贈与税率に基づく控除額 |
贈与税率は累進課税となっており、贈与額が大きくなるほど税率も高くなります。
出典:国税庁|贈与税の計算と税率
たとえば解約返戻金が1,200万円だった場合の贈与税は、下記のとおりです。
| 課税対象額:1,200万円 - 110万円 = 1,090万円贈与税額:1,090万円 × 贈与税率45% - 175万円 = 315.5万円 |
仮に契約者本人となる院長自身が解約返戻金を受け取り、そのあと後継者に資金を渡した場合でも「贈与税」は発生します。解約返戻金を活用して後継者の資金負担を軽減したい場合には、適切な金利を設定して貸付を行えば、贈与とはならないため税負担も軽減されます。
ただし、貸付条件が緩い場合には「みなし贈与」と判断される可能性があるため、承継時に解約返戻金の活用を検討する際には、税理士や仲介会社に相談するようにしてください。
クリニックにおける保険返戻金の活用方法
解約返戻金は、クリニックの経営で活用できる重要な資金源です。主な活用方法として「退職金の準備」「事業資金や設備投資」「医院継承時の資金」の3つが挙げられます。
ここでは、それぞれの活用方法の具体的な内容と効果について詳しく解説します。
院長自身や従業員の退職金
クリニック経営者にとって、自身や従業員の退職金の準備は重要な経営課題の一つです。
解約返戻金は、このような退職金問題の原資として活用できます。
院長自身の退職金として活用する場合、勤務医時代から保険に加入し、開業後も継続することで、退職時に大きな資金を確保することができます。たとえば30代で保険に加入し、65歳の引退時まで継続した場合、支払った保険料を上回る解約返戻金を受け取れる可能性が大きいでしょう。
従業員の退職金制度として活用する場合は、クリニックが契約者となり、従業員を被保険者とする養老保険などを活用することが一般的です。この場合、従業員の退職時に解約返戻金を退職金として支給することで、従業員の定着率向上や求人力の強化にもつながります。
また、解約返戻金を退職金として活用することで、クリニックの資金繰りも大きな負担になることはありません。
クリニックの事業資金や設備投資の資金源
医療技術の進歩に伴って、クリニックの定期的な設備投資やメンテナンス費用も必要です。
CT装置やMRI、内視鏡などの高額な医療機器の導入や院内のリニューアル工事など、まとまった資金が必要な場面でも解約返戻金を活用できます。
解約返戻金を設備投資の資金として活用するメリットは、銀行融資と異なり金利負担がないことです。
また、融資審査や担保設定などの手続きも不要で、すぐに資金の調達が可能です。
たとえば、内科クリニックが皮膚科を併設する際の設備投資や人件費の資金源として解約返戻金を活用することで、リスクを抑えながら事業拡大を図れます。
ただし解約のタイミングによっては返戻率が100%未満だったり、保障がなくなったりするリスクは考慮しなければなりません。
円滑な医院継承の実現
医院継承は、多くのクリニック経営者が直面する重要な課題です。解約返戻金は、親族承継と第三者承継の両方において、円滑な医院継承を実現するための重要な資金源となります。
それぞれ解約返戻金の活用方法を紹介します。
親族に承継する場合
親族承継では、解約返戻金を活用して「後継者の負担軽減」と「相続対策」が行えます。後継者の負担軽減として最も効果的な方法は、現院長が解約返戻金を活用して医院の財務状況を改善することです。
たとえば、解約返戻金で医院の借入金を返済すれば、後継者が引き継ぐ債務を軽減できます。
老朽化した設備の更新に活用することで、後継者の初期投資負担を削減することも可能です。
解約返戻金を原資として、適正な金利設定で後継者に貸付を行えば贈与税が発生することなく資金の移動もできます。
院長が急逝した場合には、解約返戻金がより重要な役割を果たします。
突発的な相続では遺族に高額な相続税の支払い負担が発生し、同時にクリニックの経営も不安定になりがちです。
このときでも解約返戻金を相続税の納税資金として活用できるほか、遺族(後継者)がクリニックの経営を安定させるまでの運転資金としても重要な資金源となります。
計画的な承継ができなかった場合でも、保険による資金確保があることで、円滑な医院継承を実現できます。
第三者に継承する場合
第三者承継における解約返戻金の活用は、主に「クリニックの評価額向上」と「買い手の資金調達支援」の2つの効果があります。評価額向上の観点では、解約返戻金はクリニックの資産として評価されるため、医院継承における譲渡価格の算定でプラス要因です。
買い手にとっても、承継後に活用できる資金があることは大きな安心材料となり、より良い条件での承継が期待できます。
買い手の資金調達支援では、解約返戻金でクリニックの財務状況が改善されることで、買い手が銀行融資を受ける際の条件が有利になる可能性があります。
保険返戻金を活用することで、医院継承時のさまざまな「資金」に関する問題を解決できます。
保険の解約返戻金に関する注意点
解約返戻金を活用する際には、いくつか重要な注意点があります。
- 元本割れの可能性がある
- 再度契約時にはデメリットがある
これらを理解せずに解約を行うと、予想以上の損失や不利益を被る可能性があるため注意しましょう。
元本割れの可能性がある
解約返戻金で最も注意すべき点は、元本割れのリスクです。特に契約から短期間での解約では、支払った保険料総額を下回る金額しか受け取れない場合がほとんどです。
元本割れを避けるためには、契約時に提供される「保険設計書」に記載されている解約返戻金額を確認し、元本を回収できる時期を把握しておきましょう。
また、緊急時の資金確保に備えて、解約返戻金以外の資金調達手段の検討もおすすめします。
たとえばスタッフの退職金に備えて資金の積み立てを検討しているなら「中小企業退職金共済制度(中退共)」を活用する方法もあります。中退共は国が運営している「従業員の退職金を積み立てるための制度」で、従業員ごとに掛け金の設定が可能です。
スタッフの保険は費用負担の一番小さい「掛け捨て型」を契約し、中退共で退職金を備えておけば「元本割れ」のリスクはありません。
再度契約時にはデメリットがある
一度解約した保険に再度加入する場合、さまざまなデメリットが生じることもあります。
再度加入時の健康状態や年齢によっては加入を断られたり、保険料が高くなったりします。
当然ですが保険を解約すると積立期間がリセットされるため、再契約後は再び元本が回収できるまで何年もの期間が必要です。「資金形成」という面で考えた場合、再契約は大幅に効率が悪くなると言えます。
保険の商品によっては、一定期間再契約ができないものもあるため、特に資金繰りのために解約返戻金を活用しようと思っている場合には、その後のことも含めて慎重な判断が必要です。
まとめ:保険の解約返戻金を上手く活用して円滑なクリニック経営を実現しましょう
保険の解約返戻金はクリニック経営における退職金準備や設備投資、そして医院継承時に活用できる重要な資金源です。特に医院継承では、親族承継と第三者承継のどちらにおいても、後継者の負担軽減やクリニックの価値向上に大きく貢献します。
ただし解約返戻金は元本割れや複雑な税務処理が伴い、その後の再契約にはデメリットも発生するため、計画的に活用しなければなりません。また、医院継承における最適な活用方法は、承継の方法やクリニックの状況によっても大きく異なります。
私たちエムステージマネジメントソリューションズは、医院継承の専門知識を持ったコンサルタントが、解約返戻金を含めた資金計画から円滑な承継までトータルサポートいたします。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。