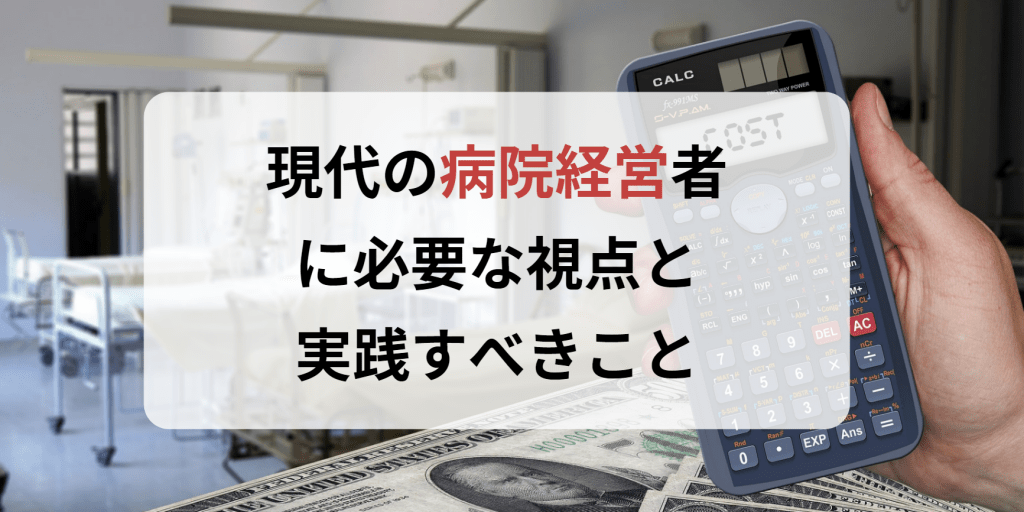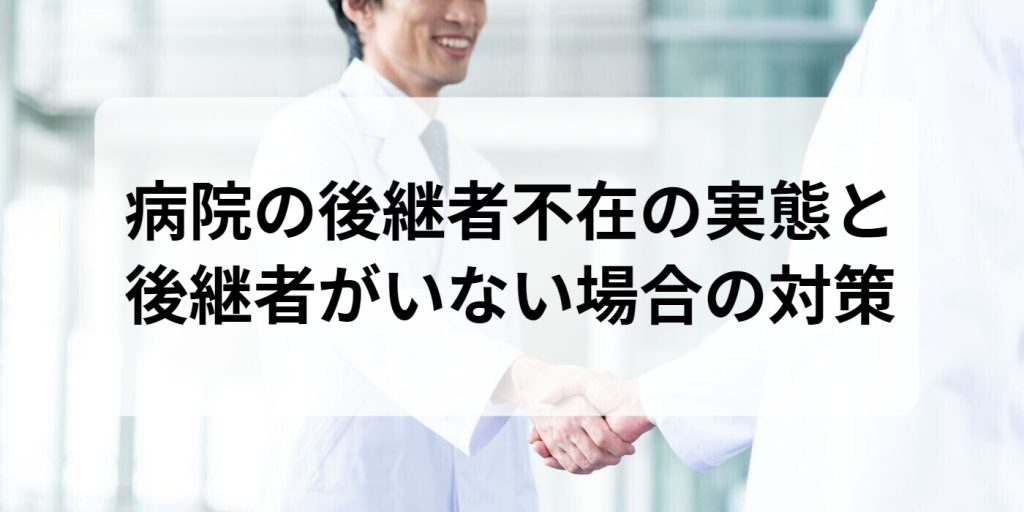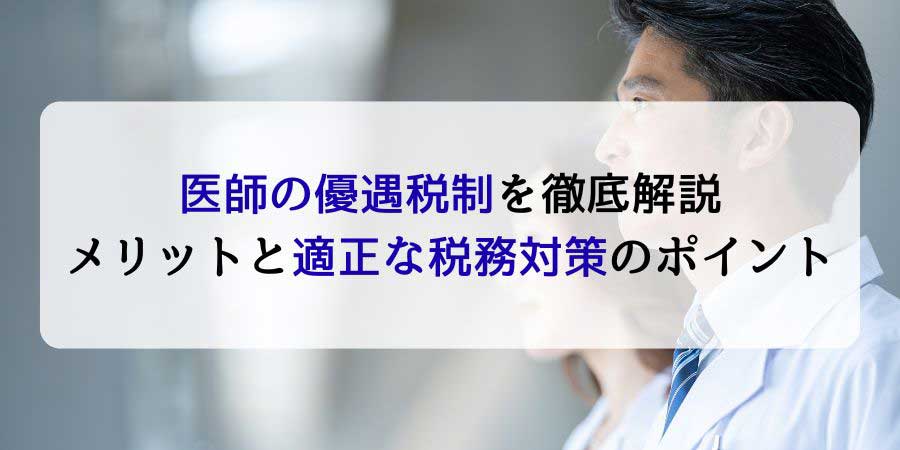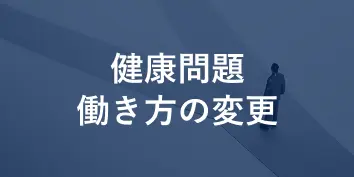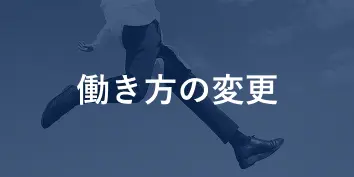クリニックにおける役員退職金の計算方法は?税金や医院継承時のポイントも解説

目次
医療法人を運営するクリニックの理事長や役員にとって、役員退職金は将来の重要な資金源と言えるでしょう。しかし役員退職金の計算方法や税務上の取り扱い、さらには医院継承時の最適な活用方法について理解されている先生は少ない傾向にあります。
そこで本記事では、役員退職金の仕組みから受け取れる金額の計算方法、税負担や医院継承時のポイントまで解説します。
役員退職金とは法人の役員が退職時に受け取れる慰労金のこと
役員退職金とは、医療法人の理事長や理事などの役員が、退職する際に支給される金銭のことです。
一般的には「役員退職慰労金」とも呼ばれており、個人で開業している医師の場合、事業主である自分自身に退職金を支払うという概念はありません。そのため個人でクリニック経営している院長が「退職金」を受け取りたい場合には、あらかじめ小規模企業共済などの制度を利用しておく必要があります。
一方、医療法人であれば、法人と役員は法的に別人格とみなされるため、法人から役員に対して退職金の支給が可能です。役員退職金は法律で支給が義務付けられているものではありませんが、適正な範囲内であれば医療法人にとっても大きな節税効果のある制度です。
医療法人における役員退職金の計算方法
役員退職金の適正な金額は、一般的に「功績倍率法」という計算方法を用いて算出します。
【功績倍率法による役員退職金の計算方法】
役員退職金=最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
| 最終報酬月額 | 役員が退職した際の報酬月額。 |
| 役員在任年数 | 役員として在任した期間。あくまで役員になってからの期間がカウントされます。(個人事業主から法人成りした場合も同様) |
| 功績倍率 | 役員(役職別)が会社に貢献した実績を反映するための倍率。 |
役員退職金の計算で用いられる功績倍率とは
会社の貢献度を倍率として反映する「功績倍率」は、基本的には自由に設定が可能です。
しかし、あまりにも高い倍率を設定すると、税務調査時に経費として認められない可能性があるため注意しなければなりません。
役職別の功績倍率の目安は、下記のとおりです。
| 理事長 | 2.5〜3.0 |
| 理事 | 2.0〜2.5 |
| 監事 | 1.2〜2.0 |
【シミュレーション】勤続30年の理事長が受け取れる役員退職金の計算
ここでは、実際に受け取れる役員退職金をシミュレーションしてみましょう。
山田理事長(仮名)が、下記の条件で退職した場合を想定します。
- 年齢:70歳
- 役職:理事長
- 勤続年数:30年
- 最終報酬月額:150万円
- 功績倍率:3.0
役員退職金の計算式「最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率」に当てはめると「150万円 × 30年 × 3.0 = 1億3,500万円」となり、山田理事長は1億3,500万円の役員退職金を受け取れることがわかります。ただし役員退職金には、退職所得控除を差し引いた金額に対して課税される点も把握しておきましょう。
役員退職金の受け取り時にかかる税金の計算方法
役員退職金を受け取る際には「退職所得」として所得税と住民税が課税されます。退職所得には優遇措置が設けられており、税負担が軽減されます。
さきほどの山田理事長の役員退職金(1億3,500万円)の事例から、具体的な税金の計算方法を見ていきましょう。
以下の手順で計算していきます。
- 退職所得控除額の計算
- 課税退職所得金額の計算
- 所得税額の計算
- 住民税額の計算
1.退職所得控除額の計算
まずは退職所得控除額の計算を行います。勤続年数に応じて以下のように計算します。
【退職所得控除額の計算式】
| 勤続年数20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 勤続年数20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年) |
山田理事長は勤続年数30年でしたので「勤続年数20年超」の計算式を使います。
| 800万円 + 70万円 ×(30年 – 20年)= 800万円 + 700万円= 1,500万円 |
山田理事長(勤続30年)の場合、退職所得控除額は1,500万円です。
2.課税退職所得金額の計算
続いて課税対象となる金額「課税退職所得金額」の計算をします。
退職所得は、退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の「2分の1」が課税対象※となります。
※勤続年数が5年以下の場合は適用されません。
課税退職所得金額は下記の計算式を用います。
| 課税退職所得金額 =(退職金額 – 退職所得控除額)× 1/2 |
退職金が1億3,500万円、退職所得控除が1,500万円の山田理事長の場合は、下記の計算を行います。
| (1億3,500万円 – 1,500万円) × 1/2= 1億2,000万円 × 1/2= 6,000万円 |
山田理事長は1億3,500万円の役員退職金に対して、6,000万円の部分が課税対象になることがわかりました。
3.所得税額の計算
課税退職所得は、金額に応じた累進課税が課せられます。
国税庁が公開している「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を使えば、所得税額を簡単に計算できます。
出典:国税庁ホームページ
課税退職所得金額が6,000万円の山田理事長の場合、所得税率は45%、控除額は479万6,000円で計算をします。
| (6,000万円 × 45% – 479万6,000円) × 1.021= (2,700万円 – 479万6,000円) × 1.021= 2,220万4,000円 × 1.021= 2,267万円(概算) |
山田理事長の場合、約2,267万円の所得税(復興特別所得税込み)が課税される計算です。
4.住民税額の計算
住民税は課税退職所得金額に対して、一律10%の税率で計算します。
山田理事長の場合、6,000万円の課税退職所得に対する10%で、600万円の住民税が発生します。
所得税が約2,267万円、住民税が600万円となり、最終的に山田理事長が受け取れる役員退職金は1億633万円です。
| 役員退職金1億3,500万円 – 所得税2,267万円 – 住民税600万円 = 手取り額1億633万円 |
▶役員退職金や税務設計も含めたクリニック売却・譲渡(M&A)の進め方を確認する
役員が亡くなった場合の役員退職金と弔慰金について
役員が在任中に亡くなった場合は遺族が役員退職金を相続し、弔慰金を支給されるところもあります。
弔慰金とは、遺族を慰めるために支払われる制度のことです。
遺族が役員退職金や弔慰金を受け取った場合「相続税」が発生しますが、それぞれ非課税枠が設けられています。
役員退職金を相続した場合「500万円 × 法定相続人の数」が非課税枠です。
たとえば妻と子ども1人が役員退職金を相続した場合「500万円 × 2人 =1,000万円」までは、相続税がかかりません。
一方で弔慰金は、亡くなられたのが「業務中もしくは業務外」によって非課税枠が異なります。
【弔慰金の非課税枠】
- 業務上の死亡の場合:最終報酬月額 × 36ヶ月
- 業務外の死亡の場合:最終報酬月額 × 6ヶ月
たとえば、最終報酬月額150万円の理事長が業務外で亡くなった場合「150万円 × 6ヶ月 = 900万円」まで、弔慰金の相続税が非課税です。
役員退職金を支払う医療法人の税務処理
医療法人が役員退職金を支払う場合、適正な金額であれば全額を損金算入できます。
ただし下記の要件を確認しておきましょう。
- 功績倍率法などは適正に計算された金額であること
- 役員退職金の規程が整備されていること
- 社員総会で決議されていること
- 同業種や同規模の医療法人に比べても不相当に高額でないこと
特に功績倍率を一般的な数値よりも高く設定すると「役員退職金が不当に高額だ」と判断され、損金として認められない可能性が出てきます。
「役員退職金の計算で用いられる功績倍率とは」の項目で紹介した功績倍率を超過しすぎないように注意しなければなりません。
損金算入は支給確定日に計上
役員退職金の損金算入時期は、原則として社員総会の決議などで「支払額が確定した日の事業年度」です。
たとえば事業年度を、4月1日から翌年3月31日に設定している会社を想定しましょう。
2025年3月に社員総会で退職金5,000万円の支給が決議され、実際に支給されたのが2025年8月(2026年度)だったとしても、損金算入は社員総会で決議された「2025年度」で計上します。
役員退職金がもらえないケース
役員退職金の支給は義務ではありません。
そのため下記に該当する場合には役員退職金が支給されない、もしくは支給されない可能性が高いです。
【個人の開業医】
退職金は基本的に法人の制度ですので、個人事業主は退職金をもらえません。
【規程が整備されていない】
役員退職金の規程が定款に定められていない場合にはもらえません。
【社員総会の決議が得られない場合】
役員退職金の支給には、原則として社員総会の決議が必要です。
【帰責事由などで解任されている】
横領や汚職などの理由で解任された場合、一般的に退職金はもらえません。
役員退職金に関する規程を定めておく
役員退職金を確実に受け取るためには、役員退職金に関する規程を整備しておくことが重要です。
これは「会社法第361条」にも定められています。
“取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。”
出典:Wikibooks|会社法第361条
最低限、下記の内容は盛り込んでおきましょう。
- 支給対象者について(理事長、理事、監事)
- 計算方法について(功績倍率法など)
- 功績倍率の設定について
- 支給時期と方法について
- 弔慰金について
- 減額や支給しない事由について
規程がない状態で役員退職金を支給した場合、税務調査で「退職金の支給根拠が不明確」として損金算入が否認される可能性があります。
また明確な支給基準があれば社員総会での承認も得やすくなるため、規定の整備は必須です。
医院継承時における役員退職金の影響とポイント
役員退職金は、医院継承時においても売り手側や買い手側に大きく影響のある要素です。
出資持分の有無によっても取り扱いが異なるため、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
出資持分ありの医療法人の場合
出資持分の定めのある医療法人では、売り手側の報酬の受け取り方法は主に2つのパターンがあります。
【①出資持分の譲渡対価のみ】
全額を出資持分の譲渡に対する譲渡対価として受け取る方法です。この場合、買い手側が売り手側に対して直接支払います。
【②出資持分の譲渡対価 + 役員退職金】
出資持分の譲渡対価と役員退職金を組み合わせて受け取る方法です。出資持分の譲渡対価は買い手側が支払い、役員退職金は医療法人が支払います。
どちらのパターンも売り手側の報酬額は変わりません。
しかし一部を役員退職金として受け取る②のパターンのほうが、売り手側にとって節税効果があります。
それは、報酬の受け取り方によって課税内容も異なるためです。
- 出資持分の譲渡対価:譲渡所得として課税(20.315%)
- 役員退職金:退職所得として課税(退職所得控除 + 2分の1課税)
たとえば、譲渡対価として1億円を受け取る場合を比較しましょう。
【パターン1(全額出資持分で譲渡)】
| 税額 = 1億円 × 20.315% = 約2,032万円手取り = 約7,968万円 |
【パターン2(退職金5,000万円 + 出資持分の譲渡対価5,000万円)】
| 【退職金(勤続30年の場合)】退職所得控除 = 1,500万円課税退職所得 =(5,000万円 – 1,500万円)× 1/2 = 1,750万円退職金の税額 = 約544万円 【譲渡対価】譲渡所得税額 = 5,000万円 × 20.315% = 約1,016万円合計税額 = 544万円 + 1,016万円 = 1,560万円手取り = 8,440万円 |
この例では、パターン2の方が売り手側にとって約472万円の節税効果があります。
買い手側にとっても、役員退職金が組み合わさることで初期投資額は抑えられます。
役員退職金の支払いによって医療法人の純資産が減少し、出資持分の評価額も下がるためです。
出資持分なしの医療法人の場合
出資持分の定めのない医療法人(基金拠出型医療法人など)には、出資持分という概念がありません。
【基金拠出型医療法人の特徴】
- 基金は拠出であり、持分ではない
- 拠出者に残余財産分配請求権はない
- 基金の返還請求権のみ有する
出資持分がないことから、医業承継時の対価は一般的に「役員退職金と功労金」を組み合わせて受け取ります。
役員退職金に関する注意点
役員退職金を活用する際には、以下の点に注意しておきましょう。
役員就任から5年以下の受け取りは税負担が高くなる
「特定役員退職手当等」に該当する場合、税制上の優遇措置を受けられない点に注意しましょう。
特定役員退職手当等とは、役員になってから5年以下の人が退職し、退職金を受け取る場合のことです。通常なら役員退職金の課税対象は、退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の「2分の1」です。
しかし、役員から5年以下の「特定役員」に該当する場合「2分の1課税」の優遇措置がありません。たとえば役員になってから勤続3年で退職し、3,000万円の退職金を受け取った場合を想定してみましょう。
勤続年数20年以下ですので、退職所得控除の計算式は「40万円 × 勤続年数(最低80万円)」です。
【退職所得控除額】
| 40万円 × 3年 = 120万円 |
【課税退職所得金額】
| 3,000万円 – 120万円 = 2,880万円(2分の1課税なし) |
このように、5年以内に役員退職金を受け取ると税負担が大幅に増加します。
特に個人事業主から法人成りをしたあと、医院継承を検討される先生は「役員(法人成り)になってからの期間」も把握しておくことが重要です。
役員退職金で医療法人の資金を圧迫しないように対策しておく
役員退職金は数千万円から数億円にのぼることもあり、医療法人の運転資金に大きな影響を与える可能性があります。
高額な役員退職金の支払いで医療法人の資金繰りが悪化することを防ぐため、あらかじめ現金の貯蓄をしておきましょう。
また、退職金に対する準備として、医療法人契約による生命保険の活用もおすすめです。保険料は全額損金算入できて、解約返戻金を退職金の財源として活用できます。また、中小企業退職金共済制度や特定退職金共済制度などの公的制度も検討しましょう。
これらの制度を組み合わせることで、高額な役員退職金を支給した際でも資金ショートを防ぎ、安定したクリニック経営ができます。
まとめ:役員退職金で税負担を増やさないためにも専門家へ相談がおすすめ
役員退職金は、医療法人にとって節税効果が高く、役員にとっても税制上の優遇措置を受けられる制度です。しかし、その計算方法や税務上の取り扱い、医院継承時の活用方法は複雑なため、知識なしに進めると税負担が増加してしまうでしょう。
もっとも節税効果があり、適切な方法で役員退職金を受け取るためにも、医療法人の事情に精通している税理士や医院継承の専門家に相談されることをおすすめします。
特に医院継承に関するご相談でしたら、ぜひ弊社までお気軽にご連絡ください。
医療業界専門のコンサルタントが、あなたのクリニックの状況に応じた最適な継承方法をご提案いたします。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。
について-1024x512.png)