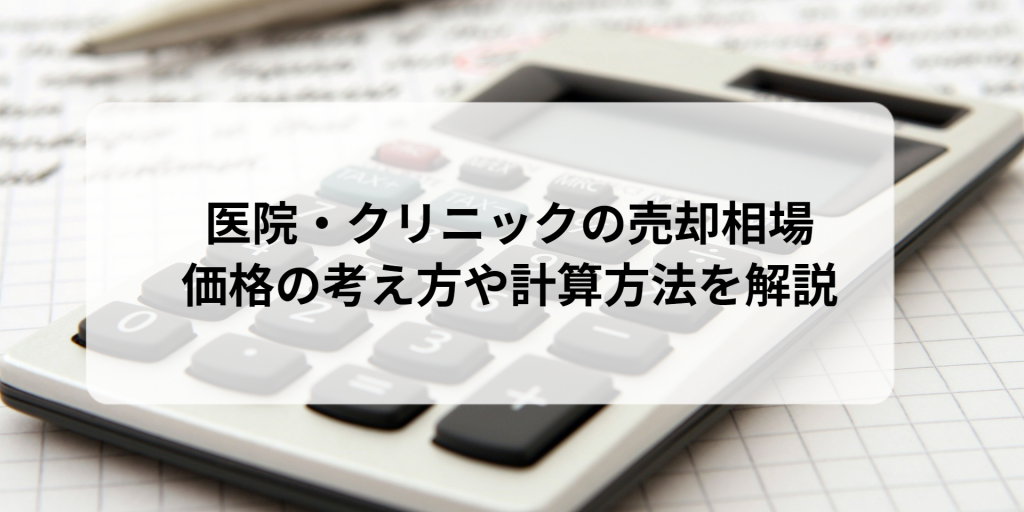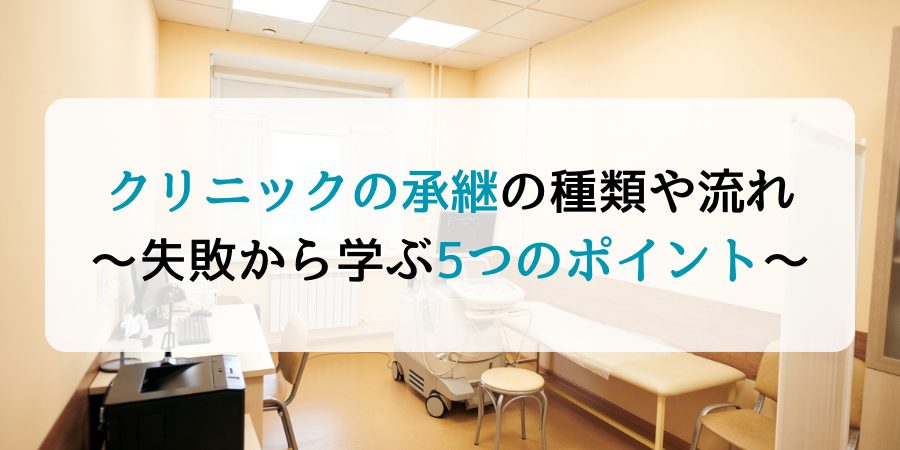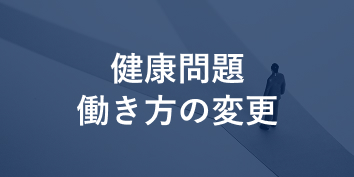新患率を上げるには?医院継承(医業承継)後に新患率が低下する3つの理由も解説
後に新患率が低下する3つの理由も解説-1.png)
目次
「医院を継承したのに、新患が増えない。」そんな悩みを抱えていませんか?院長が交代すると、患者が減少し、新患の獲得が難しくなるケースは少なくありません。
地域の患者にとっても新しい院長に対する不安があり、受診をためらう可能性があります。また、医院のブランディングや認知度が低下すると、これまでの集患力を維持できず、新規の患者が定着しにくくなります。
本記事では、承継後の医院で新患が減少する3つの原因を解説し、それを解決するための具体的な施策をご紹介します。「新患を増やし、医院経営を安定させたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
新患率とは
新患率とは、総患者数のうち新規患者が占める割合を示す指標です。新患率は「新患率=新患患者数÷総患者数」 の計算式で求められます。たとえば、1カ月の総患者数が500人で、新規患者が50人であれば、新患率は10%となります。この数値は、医療機関の集客力を測る重要な指標の一つです。
医院継承を検討する際には、新患率の確認が大切です。新患率が高い場合、その医院は新しい患者を継続的に獲得できており、将来的な成長が見込めます。一方で、新患率が極端に低いと、既存患者の比率が高く、新規患者の流入が少ないため、成長性が低い可能性があります。
譲渡先の医院が、地域に根付いた安定した経営をしているのか、それとも新規患者の獲得に課題があるのかを確認しておきましょう。
医療機関の新患率はどれぐらい?
医療機関の新患率とは、全外来患者数に占める新規患者の割合です。独立行政法人福祉医療機構(WAM)の報告によれば、2023年度の新患率は9.3%でした。 他の年度を考慮しても新患率はおおむね9%前後で推移しています。
新患率が低い場合、既存の患者に依存している可能性があり、将来的な患者減少のリスクが高まります。一方で、新患率が高い病院は、新たな患者層を獲得できているため、経営の発展が期待できます。
そのため、事業承継後の経営目標の設定にも、この数値を活用することが重要です。新患率を維持・向上させるためには、診療科の充実やオンライン診療の導入、地域との連携強化などの施策が必要です。過去数年間の新患率の推移を分析し、経営戦略に活かしましょう。
出典:令和5年度 病院の経営分析参考指標(ダイジェスト版)|独立行政法人 福祉医療機構(WAM)
新患率に影響を与える要因
新患率に影響を与える要因は以下の3つです。
- 医院の立地条件
- 診療科目の特性
- 医院の差別化戦略
詳しく解説します。
医院の立地条件
新患率に大きく影響を与える要因の一つは、立地条件です。特に交通アクセスが良く利便性の高い場所にある医院は、新規の患者が来院しやすく、新患率が高まる傾向にあります。駅やバス停から徒歩圏内であれば、通院の負担が軽減されるため、患者が通いやすくなります。
医院継承する際には、立地条件を事前に確認することが重要です。同じ診療科目であっても、駅前や商業エリアの医院と住宅地にある医院では、ターゲットとする患者層が異なります。そのため、既存の患者の動向を把握し、地域の特性を理解した上で診療科目を設定しましょう。
診療科目の特性
新患率は、診療科目の特性によって大きく左右されます。皮膚科や耳鼻咽喉科、整形外科など、急な症状で受診する場合も多く、新患率が高い傾向です。
反対に、精神科や内科のように継続的な治療が求められる診療科は、一度通院が定着すると患者の定着率が高くなるため再診率が高くなる可能性があります。診療科目と患者層の相性を見極めると、スムーズな運営と新患獲得の戦略を立てられます。
医院の差別化戦略
クリニックが新患を増やすためには、他院との差別化が重要です。競争が激化する医療業界では、患者にとって「この医院を選ぶ理由」を明確にする必要があります。診療時間の柔軟性を持たせる、オンライン診療を導入する、専門的な診療分野に特化するなど、他院にはない強みを打ち出すと、新患の関心を引きやすくなります。
また、患者に質の高いサービスを提供することも重要です。たとえば、待ち時間の短縮、院内の設備や清潔感、スタッフの接遇レベルの向上などは、患者の満足度を高め、紹介や口コミの増加につながります。さらに、独自の医療機器の導入や最新治療法の提供など、自院でしか受けられないサービスの提供が他院との差別化につながります。
医院継承(医業承継)後に新患率が低下する3つの理由
医院継承後に新患率が低下する理由として以下の3つが挙げられます。
- 経営者交代による患者の不安
- 承継後のマーケティング不足
- 診療方針やサービスの変化が影響
詳しく解説します。
経営者交代による患者の不安
医院の承継後、新患率が低下する要因の一つに、経営者交代による患者の不安が挙げられます。患者にとって、慣れ親しんだ院長の交代は大きな変化です。「診療の質は変わらないか」「新しい院長の人柄はどうか」といった不安から、来院を控える人が増える可能性があります。
このような状況を防ぐためには、医院の理念や院長の診療方針を明確に伝えることが重要です。たとえば、公式サイトやSNSを活用し、新院長の経歴や医療への思いを発信すると、患者の安心感を高められます。また、院長が積極的に地域の健康イベントに参加することも効果的です。
経営者交代後の患者の不安を払拭し、継続的な来院を促すためには、情報発信と積極的なコミュニケーションが不可欠です。
承継後のマーケティング不足
医院継承すると、院長の交代に伴いマーケティング戦略の修正が必要になります。前院長が行っていたマーケティング施策を縮小したり、WebサイトやSNSの更新が滞ったりすると、地域の患者に対する露出度が低下し、新患の流入が減少する可能性があります。
そのため、医院継承後は積極的なマーケティングが必要です。具体的には、WebサイトのリニューアルやSEO対策、SNSを活用した情報発信、広告などが効果的です。前院長の患者層を維持しつつ、新しい診療方針や特徴を伝えると、安心感を与えながら新患を増やせます。
診療方針やサービスの変化が影響
医院継承後、新患の獲得が思うように進まない理由の一つに、診療方針やサービスの変化が挙げられます。承継前の医院は、地域住民にとって馴染みのある診療スタイルや治療方針を提供しており、患者の期待に応えていたと考えられます。
しかし、承継後に診療内容や対応方針を変更すると、既存患者が離れるだけでなく、新患の来院も鈍る可能性があるでしょう。特に、従来の診療科目を削減や追加を行うと、地域のニーズと合致せず集患が難しくなる場合もあります。
そのため、医院継承時に診療科目やサービス内容を変更する場合は、事前のニーズ調査が不可欠です。地域の人口動態や競合医院の状況を分析し、どの診療科目が求められているのかを把握すると、適切な戦略を立てられます。また、既存の患者に対して事前に周知し、スムーズな移行で離脱を防ぐことも重要です。
承継後の経営に関する不安など医院継承に関するお悩みはエムステージにご相談ください。
▶医業承継後の集患課題を踏まえた承継開業(買収)の進め方を確認する
新患率を上げるための施策
新患率を上げるための施策は、大きく3つあります。
- 承継前後で共同診療期間を設ける
- 地域特性に応じた診療科目の見直し
- マーケティングの強化
各施策を実施して新患率を上げましょう。
承継前後で共同診療期間を設ける
承継したクリニックで新患率を上げるためには、一定期間、前院長と新院長が共同で診療を行うことが有効です。この期間を設けると、患者は新院長の診療スタイルを直接体験でき、診療の質に対する安心感を得られます。特に、高齢の患者や長年通院している人にとって、担当医の変更は不安要素となるため、共同診療は心理的な負担を軽減するのに効果的です。
既存患者の離脱を防ぎつつ、口コミを通じて「新しい院長先生も丁寧に診察してくれる」など良い評判が広がるでしょう。その結果、地域住民の間で信頼性が高まり、新規患者の獲得につながります。
地域特性に応じた診療科目の見直し
新患率を向上させるには、地域の医療ニーズに合った診療科目を提供することが重要です。たとえば、高齢者が多い地域では生活習慣病の管理や整形外科、在宅医療への需要が高く、一方で子育て世代が多い地域では小児科や産婦人科のニーズが高いと考えられます。地域に適した診療科目を設定して、患者の関心を集めることが安定した集患につながります。
医院継承では、地域の人口構成や競合医院の診療内容を詳細に調査することが大切です。近隣に同じ診療科の医院が多い場合は、診療内容を差別化するか、他の不足している科目を追加することも選択肢の一つです。
上記のような地域特性を考慮した診療科目の見直しは、長期的なクリニック経営の安定に影響します。
マーケティングの強化
新患率を向上させるためには、まず認知度を高めることが重要です。そのために、ホームページの最適化、MEO対策、SNSの活用など、多様なマーケティング施策によるマーケティングの強化が必要です。
ホームページは、SEO対策を施し検索結果で上位表示されるようにし、予約のしやすさや治療内容の分かりやすさを意識して集患効果を高めます。また、MEO対策により地域での検索結果に表示されやすくなると、来院率の向上が期待できます。さらに、SNSを用いたターゲット層に適した情報の発信も大切です。
ターゲットに合わせたマーケティングを強化し、継続的に情報発信を行うと、新患率の向上につながります。
再新患率を増やすための施策
再新患率を増やすためには、以下の3つの施策がおすすめです。
- クリニックに対する関心を維持する
- 休眠患者にリマインドする
- 診察後にその場で予約を取る仕組みを作る
詳しく解説します。
クリニックに対する関心を維持する
再新患率を高めるには、既存患者がクリニックに対して興味を持ち続けるような取り組みが欠かせません。診察後に患者がクリニックを意識する機会が減ると、再来院の機会も失われがちです。そのため、定期的な情報発信を通じて患者との接点を維持することが重要です。
具体的には、LINEやメールマガジンを活用し、健康管理に役立つ情報、季節ごとの注意点、新しい治療法や予防接種の案内などを提供すると良いでしょう。また、SNSを活用して診療時間の変更やキャンペーン情報を発信すると、患者の関心を維持できます。
診察後にその場で予約を取る仕組みを作る
患者の再来院を促すためには、診察後のタイミングで次回の予約を取る仕組みを作ることが効果的です。診察が終わった直後は、患者の健康意識が高まっているため、その場で次回の予約を確定しやすくなります。
たとえば、受付で次回の診療日を提案し、患者に都合の良い日時を選んでもらうことがおすすめです。スマホやタブレットを活用したオンライン予約システムを導入すれば、患者が待ち時間なくスムーズに予約を完了できるため、利便性が向上します。
この仕組みを整えると、患者が定期的に通院する習慣を身につけやすくなり、再新患率の向上につながるでしょう。
休眠患者にリマインドする
一度来院したものの、その後通院が途絶えてしまった休眠患者に対して、積極的なアプローチを行うことも再新患率の向上に効果的です。
休眠患者の主な理由として、「忙しくて受診を後回しにしている」「症状が軽減して放置している」「来院のきっかけがない」などが考えられます。このような患者に、定期健診の案内や、健康診断の割引キャンペーンなどを用意し、患者にとって魅力的なきっかけを提供することがおすすめです。
また、一定期間来院のない患者に対して、SMSやメールを活用したリマインド通知を送ることも受診の意識を高めるのにつながります。特に、季節の変わり目やインフルエンザ予防接種の時期など、患者の健康意識が高いタイミングを狙ってアプローチすると、より再来院を促せるでしょう。
よくある質問
新患率に関してよくある疑問を紹介します。
- 新患と初診の違い
- 承継前と新患率が変わらないようにするには?
疑問を解消して新患率の向上につなげましょう
新患と初診の違い
新患とは、その医療機関を初めて受診する患者で「過去に一度も来院したことがない人」を指します。一方、初診は、その医療機関で初めて診療を受けた患者(=新患)に加えて、過去に受診歴がある患者が1か月以上経過して再び受診する場合(=再新患)も含まれます。このように初診は新患と再新患が含まれる用語です。
承継前と新患率が変わらないようにするためには?
医療機関の承継後も新患率を維持するには、スムーズな引き継ぎが重要です。診療方針の共有を徹底し、前院長の治療スタイルや患者対応の特徴を把握して患者の離脱を防ぎます。また、引き継ぎ期間を設けて前院長と新院長が並行して診療を行い、患者が徐々に新体制へ慣れるよう調整しましょう。患者に対しては、承継の背景や今後の診療方針を適切に説明し、不安を払拭すると信頼関係を維持できます。
医院継承(医業承継)後に新患率が下がらないように対策しましょう
新患率は、クリニックや医院の承継を検討する際に重要な指標の一つです。新患率が高い場合、その医院は継続的に新しい患者を獲得できていると考えられ、安定した経営が期待できます。逆に新患率が低下していると、集患力に課題がある可能性があり、承継後の経営リスクが高まります。
そのため、医院継承する際には、現在の新患率を維持し、さらに集客の増加を目指す施策を取り入れることが長期的に経営する上で重要です。具体的には、オンライン予約システムの導入、地域のニーズに合わせた診療メニューの追加、SEO対策を施したウェブサイトの運用などがあります。
承継後に新患率を高める取り組みを続けて安定した経営を実現しましょう。医院継承に関するお悩みはエムステージにご相談ください。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。