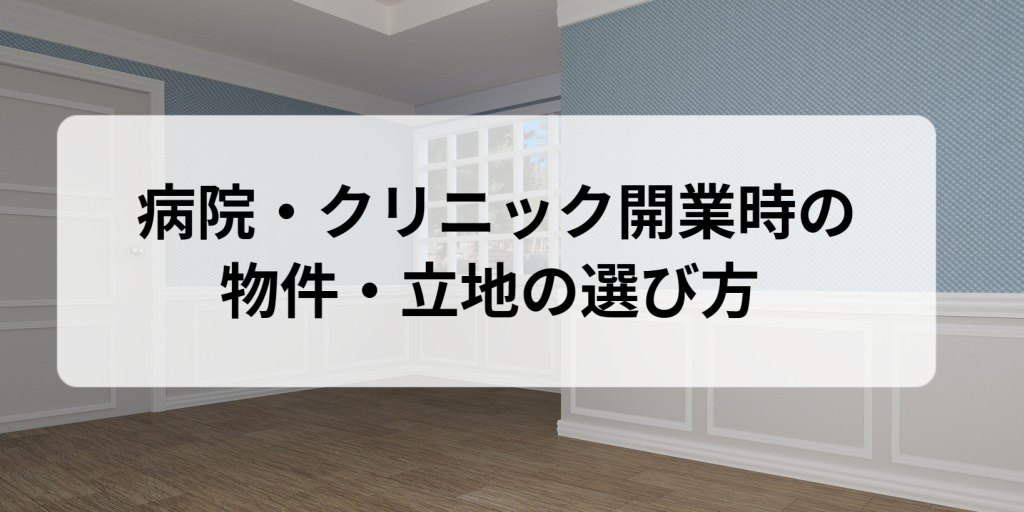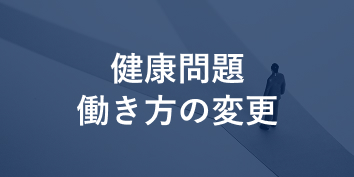クリニックの運転資金の調達方法とは?資金の内訳や運転資金不足を防ぐ対策も解説

目次
「クリニックの運営に必要な資金が不足している」「医院承継後の運転資金が心配」とお悩みはありませんか。クリニックを経営する中で、スタッフの給与、設備の維持費など、資金繰りに悩む経営者の方は少なくありません。
運転資金の準備を怠ると承継後に経営が停滞したり、患者さんやスタッフの信頼を損ねるリスクがあるため、運転資金の計画をしっかり立てることは、医療承継成功のカギといえるでしょう。
本記事では、運転資金の調達方法、運転資金の内訳や資金不足を防ぐための対策を解説します。医院承継後の資金繰りが不安な方はぜひご覧ください。
クリニックの開業資金
クリニックの開業資金の内訳は、主に「開業資金」と「運営資金」に分けることができます。以下でそれぞれ解説します。
開業資金
クリニックの開業資金は、規模や開業するエリアによって異なりますが、5,000万〜1億円程度が必要です。内訳として、物件費用、内装工事、医療機器、設備費用などがあります。医療機器の費用はリースを導入すると初期費用を抑えることが可能です。
医院承継では、買収費用、医療機器の更新費なども必要になりますが、建物代や広告、採用、医療機器購入費などを抑えられるため、全体として新規開業より安くなる傾向です。
運転資金
クリニックを開業する際には、診療報酬が安定して入金されるまでの間、運転資金を確保しておくことが重要です。運転資金は固定費と変動費の2種類に分けられます。
| 内容 | |
| 固定費 | 家賃、人件費、福利厚生費、リース代、水道光熱費など |
| 変動費 | 薬剤費、検査代、消耗品費、運賃、広告費など |
保険診療の場合、診療報酬が入金されるまで2カ月ほど遅れ、開業直後は収益が発生しにくい状況が続きます。そのため、運転資金が不足すると「黒字倒産」のリスクが高まります。
医院承継では、運転資金を確保することが重要です。
クリニックの運転資金の内訳
クリニックの運転資金で主要なものは以下の4つです。
- 人件費
- 医薬品や備品
- 家賃や光熱費
- 税金や保険料の支払い
詳しく解説します。
人件費
人件費はクリニックの運転資金の中で大きな割合を占める場合が多い費用です。人件費には、スタッフの給与、賞与、退職金、社会保険料、福利厚生費などが含まれます。医療法人では人件費率は49%の割合、個人診療所では24.6%となっており、出費のうち多くの割合を占めています。
診療科目や規模によって異なりますが、整形外科やリハビリを伴う診療科ではスタッフ数が多くなるため、人件費率が高くなる傾向です。パートタイムやアルバイトスタッフを活用し、コストを抑えることも大切です。
医薬品や備品
医薬品にかかる費用は診療科によって異なりますが、年間で500万円〜2,000万円ほど必要です。令和元年の調査では、個人診療所の中で精神科が最も高く2,160万9,000円、耳鼻咽喉科で517万4,000円と低くなっています。
医薬品費を抑えるために過剰な在庫を防ぎ使用頻度の低い医薬品は必要に応じて発注することが大切です。また、医薬品や備品の仕入れ先を複数比較し、コストパフォーマンスの良い業者を選定しましょう。
家賃や光熱費
クリニックの運営では、家賃や光熱費が毎月必要です。家賃は立地条件や物件の規模によって大きく異なりますが、月間売上の10%以内に抑えるとよいでしょう。テナント開業では、保証金(敷金)は家賃の6〜12ヵ月分の場合が多く、200〜600万円程度必要です。
クリニックは、医療機器や空調設備の使用頻度が高いため、光熱費が高くなる傾向です。医療法人のクリニックは、年間経費総額が1.5億円に対して200万円(1.6%)ほどになっています。割合としては小さいものの積み重なると大きな金額になってしまいます。
税金や保険料の支払い
クリニックを運営する中で税金や保険料の支払いも必要です。事業規模や従業員数、運営形態によっても金額は変わります。詳しい内訳を以下で解説します。
| 内容 | |
| 所得税 | 個人経営の場合に支払う税金で、必要経費を差し引いた後の所得に課税されます。所得に応じて5%〜45%(累進課税制度)の税金が課されます。 |
| 法人税 | 医療法人としてクリニックを運営している場合に必要な税金です。個人事業主の所得税に比べて税率が低く、節税効果が期待できます。 所得金額が800万円以下の場合:15%(資本金1億円以下の場合)所得金額が800万円を超える場合:23.2% |
| 住民税 | 個人事業主・医療法人のいずれにも課される税金です。 個人事業主の場合:所得に関係なく一律10%医療法人の場合:法人税額に応じて課税 |
| 個人事業税 | 個人事業主としてクリニックを運営している場合に課される税金です。個人事業税=(事業所得−各種控除−事業主控除290万円)×税率の計算式で求められます。税率の箇所は医業で5%です。 |
| 社会保険料(健康保険介護保険厚生年金保険) | 医療法人や常勤職員が5人以上の場合、社会保険への加入が義務付けられます。保険料は従業員の給与に基づいて計算し、事業主と従業員で折半します。 例)月収30万円の場合、事業主負担が44,820円、従業員負担が44,820円(健康保険料:14,970円、厚生年金保険料:27,450円、介護保険料:2,400円) |
| 医師国民健康保険 | 個人事業主や従業員5人未満のクリニックに対して課されます。所得に関係なく一定額の保険料であり、高所得者にとっては負担が軽減されます。 例)東京都医師国保の場合、医師の月額保険料は約34,500円、従業員は約13,500円 |
税金の種類は幅広く金額も大きく異なるため、必要に応じて運転資金を確保しておきましょう。
運転資金の調達方法
運転資金の調達方法は、主に5種類あります。
- 福祉医療機構の融資
- 日本政策金融公庫の融資
- 医師会の融資
- 補助金や助成金
- リースやファクタリング
詳しく解説します。
福祉医療機構の融資
福祉医療機構は、福祉・医療施設向けに低金利で長期返済可能な融資を提供しています。
運転資金の融資は、人件費、光熱費、医薬品などが対象です。
金利は年0.7%〜1.7%と低金利で、返済期間は最大10年以内です。融資率は必要資金の70〜80%が一般的ですが、条件によっては優遇措置が適用される可能性があります。優遇措置が適用される場面はさまざまなため、医院承継に関連する内容を抜粋して紹介します。
| 内容 | |
| 病院の耐震化に関わる整備 | 未耐震の病院・介護医療院の建物を耐震化する整備に優遇融資を実施(貸与利率の引下げ、融資率の引上げ) 例)老朽化した建物の耐震性を向上させるための補強工事や、新耐震基準を満たすための建替え。 |
| 地域医療構想の推進に向けた支援 | 地域医療構想の達成に向けた取組を行う病院に対して、施設整備及び運転資金の優遇融資を実施(貸与利率の引下げ、融資率の引上げ) 例)高齢者の医療と介護を一体的に提供する施設を整備 |
| GX実現に向けた整備事業に関わる支援 | GX実現を促進する観点から、建築物省エネ法に基づく誘導基準に適合する施設整備に対し、優遇融資を実施(融資率の引上げ、貸与利率の優遇) 例)高効率な空調設備の導入 |
| 感染症対策を伴う整備事業に関わる支援 | 福祉施設、医療施設で今後想定される感染症発生に向けた、感染症対策を伴う施設整備に優遇融資を実施(融資率の引上げ、貸与利率の優遇) 例)陰圧室の設置や空調システムの改修 |
上記のような優遇措置があるので、医院承継の計画段階から参考にしてみてください。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫は、政府が運営する金融機関で、クリニック開業時や運営資金の調達によく利用される融資です。融資限度額は運転資金で最大4,800万円です。返済期間は最長10年以内、金利は1.0%台〜3.0%台と低くなっています。
条件によっては、無担保・無保証人での融資が可能で、低金利、審査期間が短く迅速な資金調達が可能です。承継する医院の経営実績や収益性が審査の重要なポイントになります。
医師会の融資
医師会では、会員向けに低金利で利用できる融資制度を提供しています。医師会への加入が必須条件です。運転資金に加えて、建築費、医療機器購入費なども融資対象になります。新規開業に対する融資と医院承継に対する融資があるため、表で解説します。
| 新規開業ローン | 診療所継承ローン | |
| 対象 | 診療所建築、用地購入、初期運転資金、医療機器購入、医師会入会金など | 新築・増改築・リフォーム、医療機器購入など |
| 融資限度額 | 2億円 | 3億円 |
| 金利 | 変動金利 | 変動金利 |
| 返済期間 | 35年以内 | 35年以内 |
(出典:新規開業時のローン|大阪府医師信用組合・診療所承継ローン|大阪府医師信用組合)
上記は大阪府の一例であり、必ずしも融資限度額の上限まで融資してもらえるわけではないため注意しましょう。地方自治体や信用保証協会と連携している場合は、さらに金利優遇や信用保証料の補助を受けられる場合があります。
補助金や助成金
補助金や助成金を上手に活用すると、クリニックの開業や運営を効率的に進められます。医院承継に利用できる融資では「事業承継・引継ぎ補助金」があります。事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継をきっかけに新たな取り組みを行う場合や、経営資源を引き継ぐ際に必要な経費を補助する制度です。具体的な内容を表で解説します。
| 内容 | |
| 補助額 | 最大800万円補助率は1/2または2/3 |
| 補助対象 | 設備費、原材料費、委託費、広報費など |
創業者向け補助金には「創業助成金」もありますが、こちらは新規事業の立ち上げが対象になります。ただし、以下の条件を満たす場合は医院承継でも活用可能です。
- 承継後に新たな診療科を追加する
- 新たなサービスを開始する(健康診断や訪問診療)
- 医院を法人化する
- 医療過疎地で医院承継する
注意点として、創業助成金の条件は自治体によっても異なるため、事前に確認しておきましょう。
リースやファクタリング
リースは、医療機器や設備を購入する代わりに、リース会社から借りて使用する仕組みです。月々のリース料を支払うと、初期費用を抑えながら必要な機器を導入できるため、資金繰りがスムーズになります。ただし、契約期間中の中途解約が難しく、違約金が発生する可能性があるため注意が必要です。
ファクタリングは、診療報酬や介護報酬などの売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する資金調達方法です。入金に2か月〜3か月程度かかる診療報酬債権を前倒しで受け取れるメリットがあります。早期に資金を確保できるため、キャッシュフロー改善につながります。また、審査に通りやすく、資金用途が自由なのも特徴です。
関連記事:医院・クリニック承継開業の資金調達【コンサルタント解説】
運転資金不足を防ぐための対策
運転資金不足を防ぐためには、以下の3点を実施しましょう。
- コストを削減する
- キャッシュフローを安定させる
- 支出のタイミングを調整する
それぞれ解説します。
コストを削減する
運転資金不足を防ぐには、固定費や変動費の見直しなどコスト削減が大切です。固定費と変動費は、以下のような項目があります。
| 固定費(売上に関係なく毎月一定額発生する費用) | 例)人件費、家賃、保険料、リース料 |
| 変動費(売上に応じて増減する費用) | 例)医薬品、消耗品、水道光熱費、広告費 |
固定費を削減するには、業務のIT化や自動化によりスタッフの負担を軽減し、必要な人員を最適化します。また、契約内容を見直し不要な費用を削ることが大切です。
一方、変動費では医薬品や消耗品を大量購入して割引を活用する、電力・ガス会社との契約内容を見直しましょう。広告費では、低コストで効果的に集患できるSNSやホームページを利用します。
キャッシュフローを安定させる
医院承継では、キャッシュフローは経営の安定性を左右する重要な要素です。特に開業初期や診療報酬の入金タイムラグがある場合、資金繰りが悪化しやすくなります。
診療報酬の請求業務を効率化し、請求漏れや遅延を防ぐと、入金サイクルを短縮できます。また、電子カルテやレセプト請求システムを導入すると、業務効率を向上させることが可能です。
さらに、キャッシュフローを安定させるには、毎月の収支を把握して資金の流れを可視化するキャッシュフロー計画書を作成するのも大切です。主に以下の3項目を整理しましょう。
| 営業活動 | 診療収益や人件費、医療材料費など、日常業務に関連する収支 |
| 投資活動 | 医療機器の購入や施設改修など、将来の利益を生むための投資に関する収支 |
| 財務活動 | 融資の借入や返済、出資金など、資金調達に関連する収支 |
上記の項目を可視化してキャッシュフローを安定させましょう。
支出のタイミングを調整する
資金不足を防ぐために、支出のタイミングを調整しましょう。支払い条件の交渉により、支出タイミングを調整すると資金繰り改善につながります。
診療報酬の入金時期を早める方法も可能です。診療報酬は、診療月の翌月10日までにレセプト(診療報酬明細書)を提出し、審査を経て翌々月20日頃に支払われることが一般的です。例えば、1月の診療分は3月20日頃に入金されます。それに対して、電子レセプトを利用すると審査が早くなり、入金時期が早まる可能性があります。
高額な設備費、内装費に関しては分割払いやリース契約を利用して大きな支出を避けることも大切です。このように、支出タイミングを調整すると資金繰りの柔軟性を高められます。
よくある質問
運転資金に関してよくある質問に答えます。
- 運転資金の融資を受けるために大切なことは何?
- 運転資金不足は患者満足度に影響する?
詳しく解説します。
運転資金の融資を受けるために大切なことは何?
融資を申し込む際、「なぜ資金が必要なのか」と「いくら必要なのか」を事業計画書に盛り込むことが大切です。また、財務状況が健全であるか、自己資金は十分にあるかなども判断材料になります。
運転資金不足は患者満足度に影響する?
医療機器や設備の更新やメンテナンスが滞る、必要な薬剤や医療消耗品の仕入れが遅れるなどは、サービスの質が低下し患者満足度に影響します。また、運転資金不足で設備への投資を怠れば、清潔さや快適さが失われ患者満足度が低下します。
運転資金を賢く調達して安定した経営を目指しましょう
クリニック経営では、運転資金の計画が成功の鍵です。運転資金不足は、サービスの質低下や業務効率の低下を通じて患者満足度に影響します。また、黒字倒産の可能性もゼロではありません。
運転資金不足を防ぐためには、融資を利用しつつ経営改善に努めることが大切です。一方で、不採算の部門や非コア事業を切り離して、経営を効率化させるのも有効です。
エムステージは、独自に有する1.7万件以上の医療機関ネットワークを活用し、全国エリアで病院・クリニックの医院継承案件に対応可能です。運転資金の資金繰りで困っている方は、ぜひご相談ください。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。