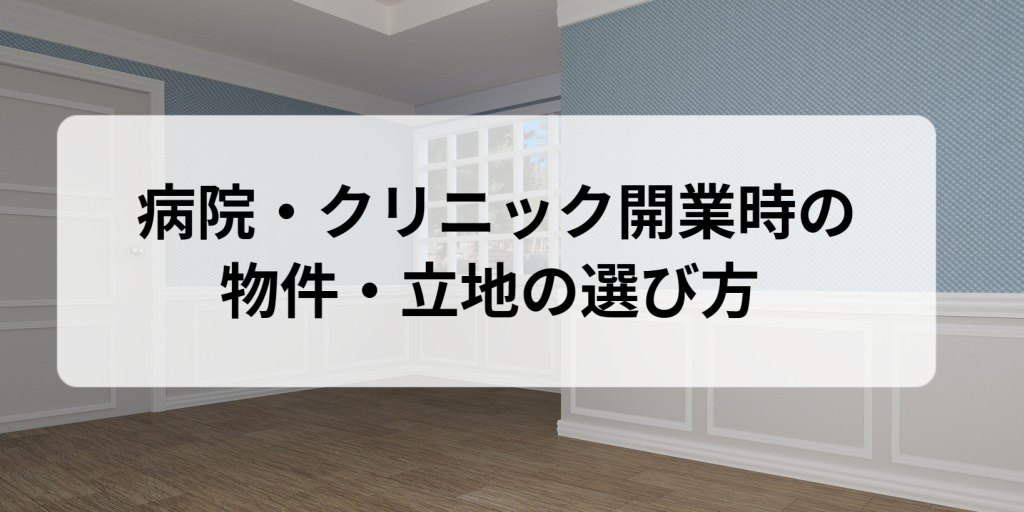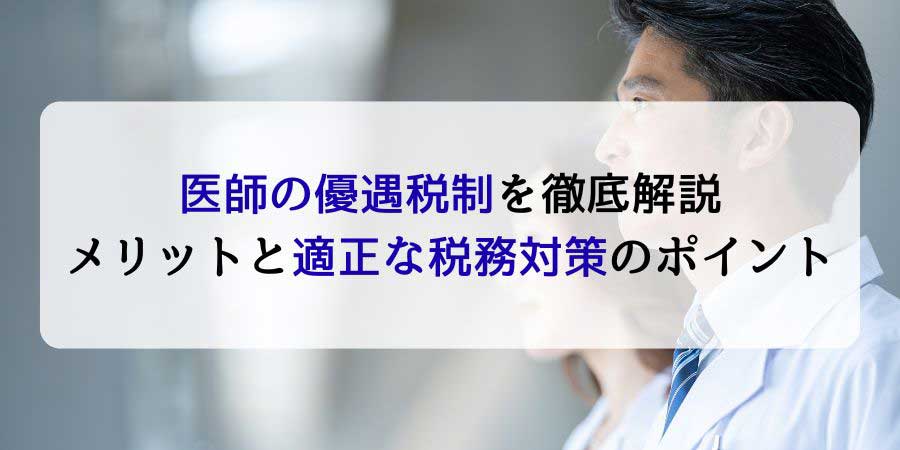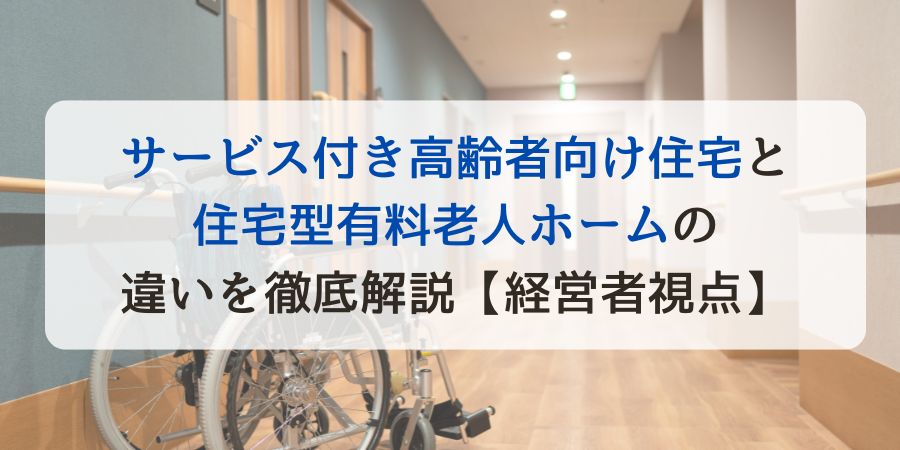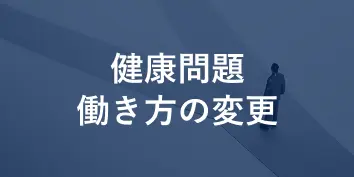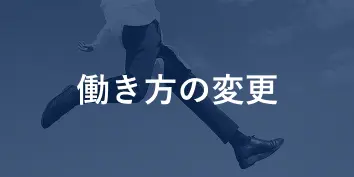開業医が行うべき資産形成は?資産1億の割合や運用方法を解説

目次
日々の診療に追われて、自身の資産形成については後回しになってしまいがちな開業医の方もいらっしゃるでしょう。将来の教育資金や老後資金をどう準備すべきか、効率的な節税方法は何か、どのような投資が自分に合っているのか、多くの開業医の方がこのような悩みを抱えていると思います。
本記事では、開業医の方に最適な資産形成の方法をご紹介します。医師の資産形成の実情からおすすめの投資方法まで、忙しい開業医の方の将来設計に役立つ情報をまとめました。
資産形成が1億円を超えている医師の割合は約13%
医師の方の中では「資産1億」を一つの目標としている方も多くいらっしゃいます。そこで、リクルートドクターズキャリアが行った調査によると、資産1億円を超えている医師の割合は、医師全体の約13%程度※という結果が出ています。
このデータは世帯としての資産額となっているため、医師1人の資産とは言い切れません。ただ、日本の年収ランキングで常にトップ3にはランクインしている職業の医師ですら、1億の資産形成をできているのは少ないということがわかります。
約62%が貯蓄のみによる資産形成
同じくリクルートドクターズキャリアが行った調査では、約62%もの医師が「貯蓄のみ」で資産を築いていることがわかっています。株式や投資信託などの金融商品を持っている医師は全体の約38%、不動産投資をしている医師はさらに少なく約13%程度です。
※出典:医師の「お金」大アンケート|リクルートドクターズキャリア
高収入と言われる医師ですが、お金の増やし方については堅実な選択をされる人が多く、預金などの安全な方法を選ぶ傾向にあります。
開業医が資産形成をする際にはライフプランの設計が重要
開業医の資産形成は、ただ漠然と貯蓄したり投資したりするよりも、まずはライフプランの設計が重要です。一般的に富裕層と呼ばれる資産1億円以上を目指されるケースも多いですが、闇雲にその金額を目標にすると現在の生活水準を下げたり、リスクの高い投資に手を出したりする可能性があるためです。
リスクをできるかぎり減らし、安定した資産形成を行うためには「将来必要な資金」を明確にすることが重要です。まずは老後の生活費や子どもの教育資金など、実際にどれくらいのお金が必要なのか把握をしましょう。
老後に必要な生活費を把握する
老後の生活を安心して送るためには、まず必要となる生活費を把握しておきましょう。総務省の家計調査によると、2024年の平均的な消費支出は単身世帯で月額約17万円、2人世帯では約27万円となっています。
【世帯別の1か月の平均消費支出】
単身:169,547円
2人世帯:268,755円
出典:家計調査 家計収支編 単身世帯|政府統計の総合窓口
出典:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯|政府統計の総合窓口
しかし、ゆとりある老後生活を望む場合は、一般的な平均値よりも多めの資金が必要です。生命保険文化センターの調査によると、夫婦でゆとりある老後生活を送るために必要としている1か月の生活費は、約37.9万円※という結果が出ています。
医師の場合、生活水準が高いことも考えられるため、より多くの老後資金が必要になるケースもあるでしょう。自分自身のライフスタイルや希望の生活水準を考慮して、具体的な生活費を算出することが大切です。
老後に受け取れる公的年金を把握する
老後の資産形成を考える上で、公的年金の給付内容の把握は非常に重要です。厚生労働省が行った調査によると、厚生年金保険(第1号)の平均年金月額は約14.4万円、国民年金は約5.6万円となっています。
出典:令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局
開業医の場合、国民年金に加えて国民年金基金や勤務医時代の厚生年金などの上乗せ部分があるかどうかで受給額が大きく変わってきます。また医療法人化している場合には、厚生年金の加入期間などによっても受け取れる年金受給額は異なります。
自分がどの年金制度に加入しているのかを確認し「ねんきんネット」などのサービスを活用して、将来の年金受給見込額を具体的に把握しておきましょう。
▶将来の引退や承継を見据えた医業承継(M&A)の考え方を見る
開業医が資産形成を行う前に知っておきたい節税方法
資産形成を行う前に、まずは支出の削減から始めましょう。資産形成よりも効果が早く、減らした分をそのまま資産形成に回せるためです。
特に医療業界は動く金額が大きいため、支出を減らす上で節税は非常に効果的です。個人クリニックから医療法人化まで、規模に応じたさまざまな節税方法があります。
【開業医が活用できる節税方法】
- 青色申告控除の申請
- 償却資産の活用
- 小規模企業共済の加入
- 所得を家族に分散
- 医療法人化
- MS法人の設立
- 特別支出控除の申請
- 資産管理会社の設立
これらの節税方法を活用することで、税金の負担を減らし、より多くの資金を資産形成に回せます。それぞれの節税方法について、具体的に解説していきます。
青色申告控除の申請
青色申告控除の申請は、もっとも基本的かつ効果の高い節税対策です。青色申告を行うことで最大65万円もの控除が受けられるためです。
また、青色申告を行っておくと赤字が繰り越せたり、家族への給与支払いを経費にできたりなど、税務上のさまざまなメリットがあります。
ただし、青色申告の控除を最大限活用するには、複式簿記による記帳と電子申告(e-Tax)の利用が条件です。できる限り税負担を抑えるためにも、医療機関を専門とした税理士などのサポートを受けることをおすすめします。
償却資産の活用
償却資産とは事業用の建物や機械、器具などの資産のことを指し、時間の経過とともに価値が減少していくものです。
クリニックにおいても、医療機器や備品などの設備投資が「償却資産」として計上ができて、大きな節税効果を生みます。
法定耐用年数に基づいて減価償却という経費の計上方法を行うことで、購入時に一括で経費計上するのではなく、複数年に分けて経費計上ができます。税負担を複数年に分けて軽減できるため、無駄のない資金計画が可能です。
小規模企業共済の加入
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度として活用できる共済制度です。開業医も小規模企業共済に加入が可能で、大きな節税メリットがあります。
最大のメリットは、掛け金が全額所得控除の対象となる点です。月額1,000円から70,000円までの範囲で自由に設定が可能で、上限の7万円を掛け金とした場合は、年間最大84万円もの所得控除が受けられます。
医師のような高所得者にとって、この控除額は非常に大きな節税と言えるでしょう。
また、将来受け取る共済金は「一括」と「分割」が選べます。一括で受け取れば「退職所得扱い」分割で受け取れば「雑所得扱い」となり、いずれにしても貯蓄で資産を増やすよりも税制上で有利です。
納付した掛け金は将来的に確実に受け取れるため、資産形成と節税を同時に実現できる優れた制度と言えるでしょう。
所得を家族に分散
開業医が活用できる有効な節税方法の一つに「所得の分散」があります。配偶者や子どもなどにクリニックの業務を手伝ってもらい、給与を支払うことで所得の分散ができます。
身内に医師がいなかったとしても、たとえば配偶者には受付や会計業務の担当を、子どもにはクリニックの清掃や書類整理などを行ってもらうことは可能でしょう。
高い税率区分となる医師から家族に所得を移すことで、世帯全体としての節税効果が生まれます。
ただし、実態を伴わない「名義だけの雇用」は税務調査で否認されるリスクがあるため、業務内容や勤務時間の記録をしっかりと残しておきましょう。
医療法人化
クリニックの経営形態を個人から医療法人に変えることで、税金面で大きなメリットが得られます。個人で医院を経営していると、収入が増えるほど税率が高くなり、最高で45%もの所得税がかかります。
一方で医療法人の場合は所得税が「法人税」へと変わり、税率は一律で23.2%です。つまり収入の多い医師なら、法人化によって税負担が大きく抑えられるわけです。
また、退職金制度を作れたり、将来的にクリニックを引き継ぐときにもスムーズにできたりと、長期的に見てもメリットが多くあります。
個人事業主としての年間所得が1,800万円を超えてきた場合には、医療法人化したほうが税負担は少なくなります。
MS法人の設立
MS法人とは「メディカルサービス法人」の略で、医療法人とは別で設立する法人です。医療法人は医療行為以外の業務ができないという制限がありますが、MS法人はその制限を受けません。
たとえば医療設備や建物をMS法人が所有し、それを医療法人に賃貸する形にすることで、医療法人からMS法人へと利益を移転させ、税負担を軽減できます。
不動産の購入や管理、医薬品などの仕入れから販売など、医療周辺業務をMS法人で行うことで節税効果を高められます。
さらに、将来の相続対策としても活用できる点がメリットです。MS法人なら親族を役員や株主にして給与や配当の形で資産を移転できるため、相続財産を圧縮し相続税負担を減らせます。
また、医療法人の場合は基本的に後継者は医師である必要がありますが、MS法人は医師でなくても経営できるため、子どもが医者ではなかったとしても相続が可能です。
関連記事:MS法人とは|設立のメリット・デメリットと活用上の注意点
特別支出控除の申請
特別支出控除とは、会社員(給与所得者)が利用できる経費控除の制度です。開業医が医療法人化して役員報酬を受け取る場合は給与所得者として扱われるので、特別支出控除を活用できます。
医師の場合は、学会参加のための旅費や宿泊費、専門書の購入費、資格取得のための費用などを「特定支出控除」として申請が可能です。
ただし、特別支出控除として申請できるのは、給与所得に対して定められた「給与所得控除額」の半分を超えた場合のみです。
資産管理会社の設立
資産管理会社とは、個人の資産管理を目的として設立する会社のことで、プライベートカンパニーとも呼ばれます。
最大の特徴は節税効果の高さです。開業医は課税所得に対して、最大で55%もの税率が適用されます。そこで資産管理会社を設立して家族を役員にすれば、役員報酬として所得を分散でき、全体の税負担を減らせます。
さらに、不動産所有による黒字と他の事業の赤字を相殺できる「損益通算」も可能になります。また、個人の繰越控除が最長3年なのに対し、資産管理会社では最長10年まで延長できる点もメリットです。
MS法人との違いは、MS法人が医療関連サービスの提供を目的とするのに対して、資産管理会社は純粋に資産の保有や運用に特化している点です。
はじめて資産形成を行う開業医におすすめの投資や制度
資金形成の方法は非常に数多くありますが、ここでは初めて資産形成を行う開業医の方におすすめの投資方法や制度を5つ紹介します。
- 株式投資
- 不動産投資
- 投資信託
- 純金積立
- iDeCo
ご自身の資金状況やリスク許容度に合わせて、これらの方法を組み合わせることで効果的な資産形成が可能です。
それぞれの投資方法について詳しく解説します。
株式投資
株式投資は、企業の株を購入して利益を得る投資方法です。株の価格が上がったときに売って得る「値上がり益」と、企業から定期的に支払われる「配当金」という2種類の利益が期待できます。
特に開業医のような高所得者には、税金面で優遇される「NISA」や「つみたてNISA」などの制度がおすすめです。毎月決まった金額を投資する方法を使えば、相場の上下に振り回されず、長期的な資産形成が可能になります。
ただし、株式市場は短期的には大きく変動することもあるため、最初から大きな金額を投資するのではなく、少額から始めて徐々に慣れていくことをおすすめします。
不動産投資
不動産投資は、アパートやマンションなどの物件を所有して家賃収入を得る方法です。魅力は毎月安定した収入が見込める点と、高い節税効果です。減価償却費や諸経費の計上ができて、高所得者となる開業医の税負担が軽減できます。
さらに、資産管理会社やMS法人を設立して不動産を所有すれば、節税効果も高められます。法人税率が適用されるので、個人で所有するよりも税負担が減るだけでなく、法人で得た収益を将来の退職金として受け取ることも可能です。また融資の面でも、個人より法人のほうが有利な条件で借り入れできるケースもあります。
ただし、空室のリスクや修繕費用の負担などのデメリットはあります。
投資信託
投資信託とは、多くの投資家から資金を集めて専門家(ファンドマネージャー)が運用する商品のことです。特に資産形成が初めての方に、おすすめの投資方法の一つです。
投資信託の最大の特徴は「分散投資」が簡単にできることが挙げられます。一つの投資信託で、数十から数百の企業や国の債券に分散投資が可能です。
株式投資のように個別の株式や債券に投資するよりも、リスクを抑えられる点がメリットです。また数千円程度の少額から始められ、銘柄選びもプロに任せられるので、忙しい開業医でも手間をかけずに投資できます。
特に「インデックス型」と呼ばれる投資信託は手数料が安く、長期的な資産形成に向いています。NISA(少額投資非課税制度)やiDeCoと組み合わせれば税制優遇も受けられ、効率的な資産形成が可能です。
しかし当然元本の保証はないため、市場の変動によっては損失が生じる可能性のある点は理解した上で投資をしましょう。
純金積立
純金積立は、毎月一定額の金(ゴールド)を購入して積み立てていく資産形成方法です。金は世界共通の価値を持っていて、インフレにも強いことから長期的な資産形成として人気があります。
純金積立の特徴は、5,000円程度の少額から始められる手軽さと、株式市場などと値動きが異なるため、ポートフォリオ(資産の組み合わせ)の分散効果が期待できる点です。特に世界情勢が不安定な時期やインフレ傾向にある時期には、金の価格も上昇する傾向にある点も特徴です。
デメリットとしては、購入時と売却時に手数料がかかることや、配当などの定期的な収益がない点が挙げられます。
また、純金を売却した際に得た利益は「譲渡所得」に含まれます。つまり、累進課税率(最高55%)が適用されるので、高所得の開業医にとっては税負担が大きくなる可能性がある点も、デメリットとして把握しておきましょう。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛け金を積み立てて運用し、60歳以降に受け取れる私的年金制度です。
iDeCoの魅力は、税制面でのメリットが多いことです。
| 段階 | 税制面でのメリット |
| 積立時 | 毎月の掛け金が全額所得控除になり、所得税や住民税の負担が軽減される |
| 運用時 | 運用中の利益(配当金や値上がり益)に税金がかからない |
| 受取時 | 退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、税負担を抑えられる |
個人開業医(第1号被保険者)の場合は月額最大68,000円、医療法人の理事長など企業型年金がない会社員(第2号被保険者)の場合は月額最大23,000円まで積立可能です。高所得者である医師にとっては大きな節税効果が期待できます。
ただし、原則60歳まで引き出せないことや、自分で運用商品を選ぶ必要があることを理解した上で活用しましょう。
開業医が資産形成を始めるならまずは将来設計から
資産形成は「いくら貯めるか」という数字の目標だけでなく、「何のために貯めるか」という目的を明確にすることが大切です。子どもがいる場合には将来必要になる教育資金、老後に必要となる資金をきちんと把握し、それに向けた資産形成の計画を立てましょう。
まずは節税対策で支出を減らし、その浮いた資金を投資などの運用にまわすことが基本です。投資方法や制度はそれぞれ特徴が異なるため、自分の状況や目標に合わせて選択しましょう。
複数の方法に分散し、リスクを抑えながら資産形成を進めていくことをおすすめします。
エムステージマネジメントソリューションズのコンサルタントは医療経営士の資格を保持しているため、経営に関するアドバイスなどのサポートも行います。クリニックや医院の医業承継に興味をお持ちの方は、ぜひ一度エムステージマネジメントソリューションズに無料でご相談ください。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。