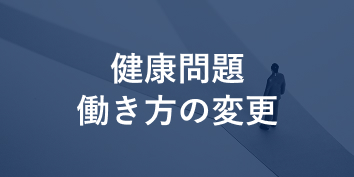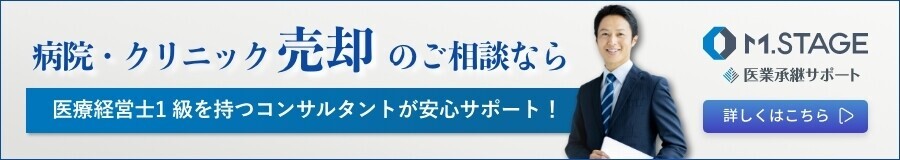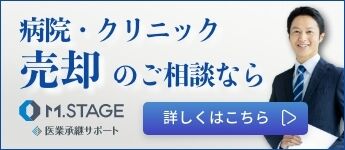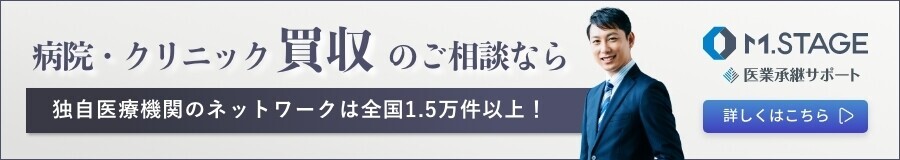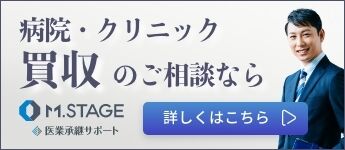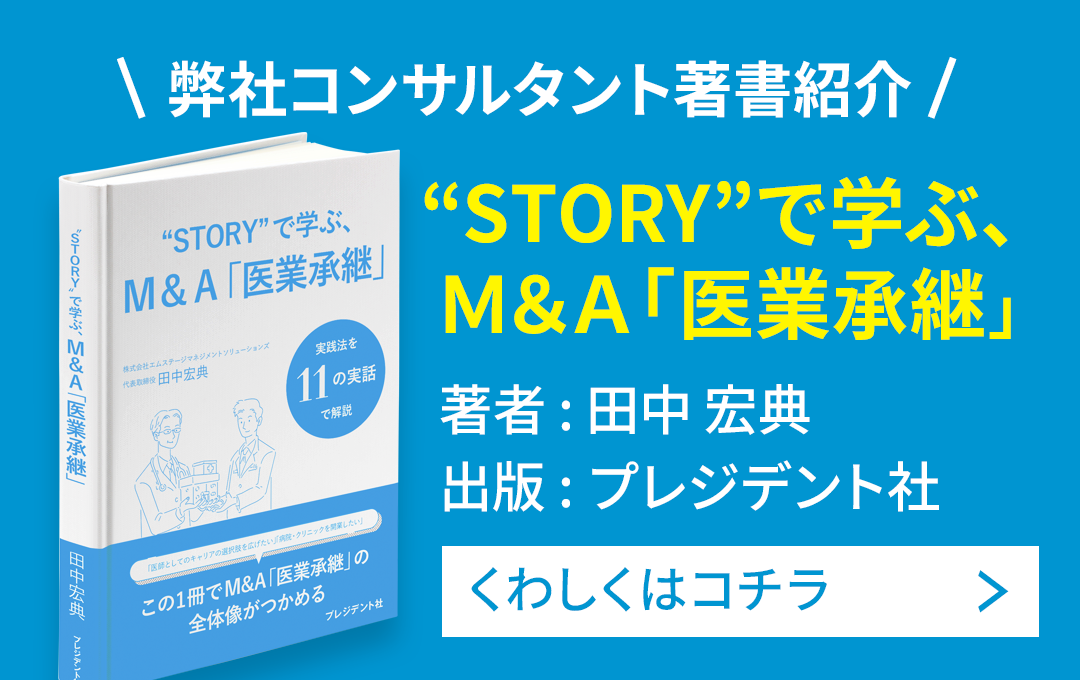新規開業と承継開業のメリット・デメリット【徹底比較】
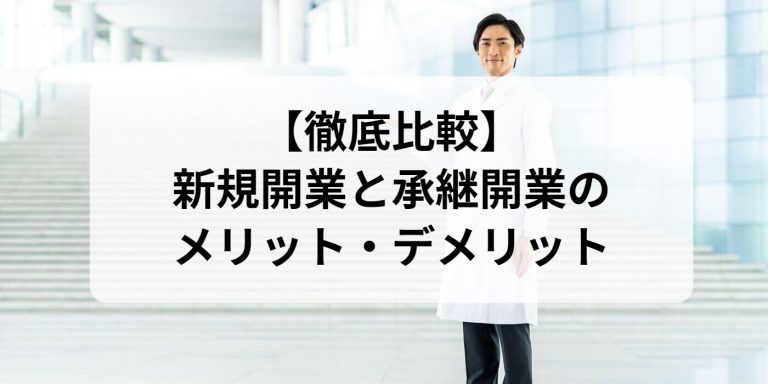
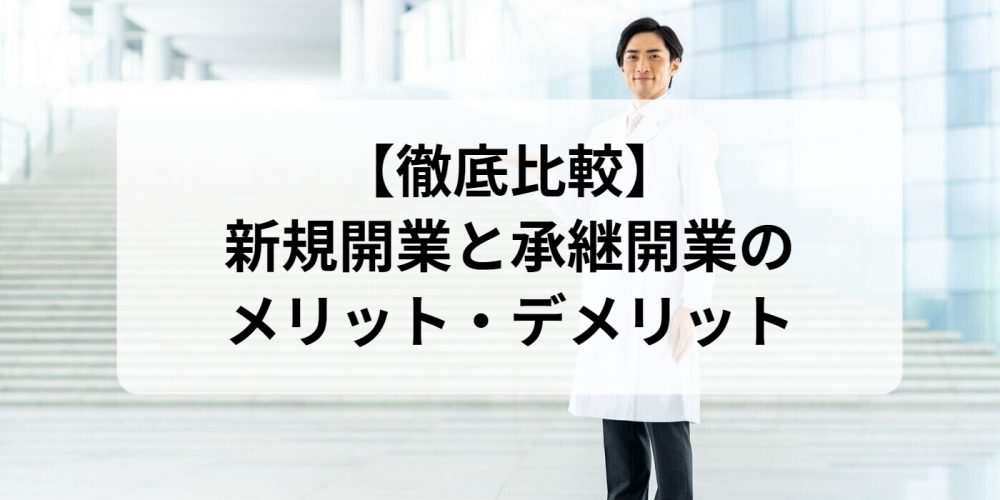
目次
クリニックや医院の開業には新規開業と承継開業があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。新規開業は理想の立地や設備を選べる自由度が高い反面、初期費用が高く、経営の軌道に乗るまで時間がかかります。一方で、承継開業は初期費用を抑えて既存の患者やスタッフを引き継ぐことが可能ですが、前院長の方針の影響を受けやすく、条件の合う案件が少ない場合があるため、どちらの方法でも専門家と相談しながら慎重に選択することが大切です。
本記事では、「新規開業」と「承継開業」、それぞれのメリットやデメリットだけでなく、開業までの流れや注意点を挙げて比較しているので、開業する際にご参考ください。
病院・クリニックの承継をご検討中の方はプロに無料相談してみませんか?
エムステージグループの医業承継支援サービスについての詳細はこちら▼
新規開業と承継開業のメリット・デメリット比較
| 新規開業 | 承継開業 | |
| メリット | ・自分が思い描く、理想の立地で開業ができる ・建物の内装や間取り、設備も自分の思い通りにできる ・スタッフや取引業者を1から選定できる | ・開業にかかる初期費用を削減できる ・患者を引き継げるため、事業の見通しを立てやすい ・雇用されているスタッフを引き継げる ・開業にかかる時間や労力を削減できる ・承継元の前院長が築いてきた信頼関係を引き継げる |
| デメリット | ・開業にかかる初期費用が大きい ・経営が軌道に乗るまで時間がかかる ・開業までに時間と労力がかかる ・新規の患者を集めなければならないため、事業の見通しが立てづらい | ・承継元の前院長の診療方針を考慮する必要も ・建て直しやリフォームなどが必要となることも ・売却案件の中から選ぶので、全てが希望条件に当てはまるとは限らない |
端的に表せば「新規開業は自由度が高いがコストが高い」「承継開業は自由度が低いがコストも低い」ということになりますが、ケースバイケースです。それぞれのデメリットを上回るメリットがあるケース、メリットを上回るデメリットがあるケースもあります。両方視野に入れておきながら慎重に検討していきましょう。
それでは、以下でそれぞれについて解説していきます。
クリニックや医院を新規開業するメリット
クリニックや医院を新規開業するメリットは、主に以下の3つです。
- 自分が思い描く、理想の立地・物件で開業ができる
- 建物の内装や間取り、設備も自分の思い通りにできる
- スタッフ採用や取引業者を1から選定できる
順番に解説します。
1. 自分が思い描く、理想の立地・物件で開業ができる
新規開業の場合は立地を自由に選んだり、多くの敷地・物件の中から選択したりすることができます。絶対にこのエリアの物件が良い・生まれ育った地元で開業したいなど特別な思い入れがある場合は新規開業することで自由に選択ができます。
2. 建物の内装や間取り、設備も自分の思い通りにできる
新築の場合には自分の希望を設計に反映できますし、賃貸の場合でも建物の躯体だけという、いわゆる「スケルトン物件」であることがほとんどなので、内装工事で配置やインテリアなどを決めることができます。
また、医療機器やシステムなどの設備も、自分の好みのものを導入することができます。こだわりを反映させやすく、医師としてやりたい医療を提供しやすい環境をつくれる点がメリットです。
3. スタッフ採用や取引業者を1から選定できる
スタッフはいちから採用に関われますし、取引業者は複数の業者の中から比較検討して選ぶことができます。時間も手間もかかり、失敗するリスクもありますが、クリニックの立上げをしているなかで生まれる仲間意識も得られるメリットかもしれません。
▼開業しやすい診療科について知りたい方は、こちらの関連記事をチェック!
クリニックや医院を承継開業するメリット
クリニックや医院を承継開業するメリットは、主に以下の3つです。
- 開業にかかる初期費用を削減できる
- 患者を引き継げるため、事業の見通しを立てやすい
- 雇用されているスタッフを引き継げる
- 開業にかかる時間や労力を削減できる
- 承継元の前院長が築いてきた信頼関係を引き継げる
1. 開業にかかる初期費用を削減できる
承継開業の場合、基本的には既存の建物を引き継ぐので、建設費がかかりません。医療機器やインテリアなども一緒に引き継げば、かなり初期費用を削減できることになります。
地域においてクリニックや医院の認知度もすでにあるので、認知度の無い新規開業と比べると開業の際の広告費も少なくて済むことでしょう。
2. 患者を引き継げるため、事業の見通しを立てやすい
承継するクリニックや医院はすでに同じ科目で営業しているため、来院する患者層や患者単価、来院ニーズなどを引き継いだカルテのデータで知ることができます。
そのため、承継開業は新規開業に比べ、経営などの見通しが立てやすいと言えるでしょう。また、患者を引き継ぐことも可能なため、収益を最初から見込むことができます。
3. 雇用されているスタッフを引き継げる
承継開業の場合には、雇用スタッフをそのまま引き継ぐことがほとんどです。
とくに、医療法人の場合には、雇用契約を医療法人とスタッフの間で結んでいるため、その医療法人を引き継ぐとそのまま雇用契約も継続となります。
医師や看護師など採用難易度が高い専門スタッフを引き継げることは、開業するクリニックや医院の大きな強みとなるでしょう。
4. 開業にかかる時間や労力を削減できる
承継開業では、必要な物件探しや設計、建設、雇用スタッフの採用などにかかる時間をカットできるため、開業までの準備期間が短縮できます。
また、建物や内装の設計、依頼業者の選定、医療機器の選定などもそのまま引き継げば、開業までの検討事項を削減することが可能です。
5. 承継元の前院長が築いてきた信頼関係を引き継げる
長年運営してきた承継元の実績があれば、銀行からの融資が受けやすい場合があります。また、地域にあるほかの医療機関との連携や医師会への入会なども、スムーズに行える可能性が高まります。
■■関連記事■■
クリニックや医院を新規開業するデメリット
クリニックや医院を新規開業するメリットが多くある一方で、デメリットもあります。新規開業する際は以下の点に注意しましょう。
- 開業にかかる初期費用が大きい
- 経営が軌道に乗るまで時間がかかる
- 開業までに時間と労力がかかる
- 新規の患者を集めなければならないため、事業の見通しが立てづらい
1. 開業にかかる初期費用が大きい
開業にかかる初期費用は、新規開業の方が承継開業と比べて高い傾向にあります。新しく建物を建築する場合は物件費用に加え建設費もかかりますし、賃貸する場合でも内装工事費や家具などの費用がかかります。
また、看板を立てたりホームページを作成したりと、患者を新規で獲得するための広告費用は少なくはありません。
2. 経営が軌道に乗るまで時間がかかる
新規開業の場合は全く患者がいないところからスタートするため、最初は経営が赤字のところもあるなど、承継開業と比べて収支が安定するまでに時間がかかります。
3. 開業までに時間と労力がかかる
物件探しから取引業者の選定、新規雇用スタッフの採用・育成、労務管理の整備なども行わなければならないので、かかる時間や労力は大きくなります。
とくに、勤務医を行いながら開業準備をするとなると、時間の捻出にはかなり工夫が必要になるでしょう。
4. 新規の患者を集めなければならないため、事業の見通しが立てづらい
開業後、どのような患者がどんなニーズでどのくらい来院するのかなど、診療圏調査などである程度予測は立てますが、やはり開業してみないことには分かりません。
クリニックや医院を承継開業するデメリット
新規開業だけでなく、承継開業にもデメリットが存在します。以下の点に注意することが大切です。
- 前院長の診療方針の考慮が必要な場合がある
- 建て直しやリフォームなどが必要となることもある
- 売却案件の中から選ぶので、全てが希望条件に当てはまるとは限らない
1. 前院長の診療方針の影響を受ける場合がある
長く通院しているような患者の診療方針は前院長に聞いた方が良い場合もあります。また、従業員が前院長の縁故者であったりする場合もあります。
そのように、承継元であるクリニックや医院の運営年数が長い場合、前院長と患者や従業員とのつながりが強いため、承継後もすぐに自分のスタイルで運営することが難しいことがあります。
2. 建て直しやリフォームなどが必要となることもある
承継した建物が老朽化していたり、内装や設備の使い勝手が悪かったりする場合には、建て直しやリフォームをしなければならず、多額の修繕費がかかる場合があります。
3. 売却案件の中から選ぶので、全てが希望条件に当てはまるとは限らない
限られた売却希望の案件の中から、立地や譲渡金額等さまざまな条件を比較しつつ、自分の承継したい案件を選ぶことになります。
クリニックや医院を開業するまでの流れ
新規開業と承継開業の流れについて、比較しやすいよう大まかな項目をピックアップしてご紹介します。
新規開業するまでの流れ
- 立地、物件の検討
- 施設の施工
- スタッフ採用
- 導入設備やシステムの検討
- 備品購入
- 各種開業手続き
承継開業するまでの流れ
- 売却・譲渡案件探し
- 売り手との条件すり合わせ
- 各種手続き
このように、承継開業の方が新規開業に比べ既存の施設やスタッフなど今あるものをそのまま引き継ぐことが可能な分、開業までに必要な項目も少なくなります。
クリニックや医院を新規開業する際の注意点

クリニックや医院を新規開業する際は、計画性が重要です。以下のポイントに気をつけながら進めましょう。
- ホームページを作ってPRし、効率的に集患する
- コストをなるべく削り、借入金の負担を減らす
- スケジュール通りに進むよう、綿密な計画を立てる
1. ホームページを作ってPRし、効率的に集患する
新規開業の場合は、もちろん患者集めもゼロからのスタート。集患に苦戦してしまうと、借入金返済時期を延ばさなればならなくなることも。
最近では、医療機関を受診する際に、インターネットで情報を得る人が増えています。調査によると、外来患者の23.5%が医療機関が発信するインターネットの情報を「情報の入手先」としています*。
*厚生労働省『令和2(2020)年受療行動調査(概数)の概況』
このように、患者の多くは医療機関を選ぶ際にインターネットで情報収集を行っているため、新規開業の際はホームページの制作が欠かせません。ホームページに病院やクリニックの強みなどの情報を掲載し、ほかの医療機関と差別化を図りましょう。
2. コストをなるべく削り、借入金の負担を減らす
建物や内装、設備の建設費、医療機器の導入費など、新規開業では多額の初期費用がかかります。いくらでも予算があれば良いですが、立ち上げの不安定な時期に借入金の負担はなるべく少なくしたいもの。
そこで、事業が軌道に乗るまではスタッフの雇用を常勤ではなくパートを検討したり、リース料が高額になるCTなどの機器の導入は採算が取れるどうかを考慮し、慎重に判断するようにしましょう。
3. スケジュール通りに進むよう、綿密な計画を立てる
新規開業の場合は、開業地選びや不動産探し、雇用スタッフの採用・教育などに時間がかかり、開業が予定より遅れてしまうことがあります。
もし勤務医を辞めて開業準備を行っていた場合、無収入状態が長引いてしまうと、生活のために開業を諦めて勤務医に戻るなんてことにもなりかねません。
そのようにならないためにも、初期費用も含め入念に準備をして、スケジュール通りに開業準備を進めましょう。
クリニックや医院を承継開業する際の注意点
クリニックや医院を承継開業する際も、新規開業の場合と同じく計画性も重要ですが、ここではその他に気を付けるべきことを解説します。
- 承継前に、譲渡の理由を確認しておく
- 患者離れの対策をする
- 承継元スタッフの引継ぎは慎重に行う
1. 承継前に、譲渡の理由を確認しておく
医業承継する場合は、売却側がなぜその医療機関を譲渡したいのかを必ず確認をしておきましょう。
その理由が患者離れによる経営不振であったり、医療事故により評判が落ちてしまっていたりする場合、その医療機関を承継開業しても経営を安定させるのはなかなか難しくなります。
2. 患者離れの対策をする
承継開業では患者のカルテが承継されるので、患者をそのまま引き継ぐことが可能です。
しかし、長年地域で運営してきた医療機関ほど患者と前院長との結びつきも強いため、承継して院長が変わることで一定数の患者離れが起こる可能性は高くなります。
とは言え、患者離れは経営にも大きな影響があるので、最小限にとどめたいもの。そのためには、承継後前院長の診療方針をいきなり変えるのではなく、患者の様子を見ながら徐々に自分のスタイルを出していく方が良いでしょう。
承継する前に非常勤で勤務して前院長の診療方針を確認したり、前院長から患者に紹介してもらったりして、スムーズな形での院長の交代を患者にイメージさせるようにしてください。
3. 承継元スタッフの引継ぎは慎重に行う
承継元が医療法人の場合、スタッフの契約も医療法人に紐づいているため、そのまま雇用し続けるのが一般的です。長年勤めて地域や患者のことをよく知っているスタッフは、承継後も大きな力になってくれるでしょう。
しかし、スタッフとは相性があるのも事実です。そのまま何も言わずにスタッフを自動的に引き継ぐのではなく、承継開業前にひとり一人と面接し、開業するクリニックの理念や診療方針などをしっかりと説明して、納得した上で働いてもらうようにしましょう。
また、ベテランスタッフだと支払う給与が相場より高く設定されている場合もあるため、注意が必要です。
開業を検討中の場合は専門業者に相談しましょう
新規開業と承継開業、それぞれメリットやデメリットがあることをお分かりいただけたのではないでしょうか。自分の行いたい診療コンセプトなどを元に、どちらの開業方法が適しているかよく検討してみてください。
新規開業と承継開業のどちらも医療法など専門知識が必要になるので、とりまとめてくれるような専門家や専門の仲介会社に相談すると、スムーズに進行できるでしょう。
エムステージマネジメントソリューションズでは医業承継専門のチームが徹底サポートさせていただきます。コンサルタントは医療経営士の資格を保持しているため、経営に関するアドバイスなども可能です。また、「事業計画書の作成」や「資金調達コンサルティング及び金融機関等との融資交渉」なども開業支援の業務内なので、安心してご依頼ください。
クリニックや医院の医業承継に興味をお持ちの方は、ぜひ一度エムステージマネジメントソリューションズに無料でご相談ください。
▼エムステージの医業承継支援サービスについて
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月、プレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を上梓。
そのほか、医院承継の実務と現場知見に基づく発信を行っており、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演や寄稿も多数。医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として活動している。
>著者プロフィール詳細(wikipedia)