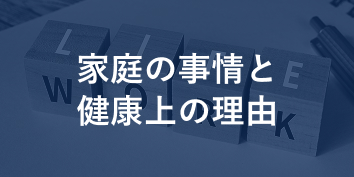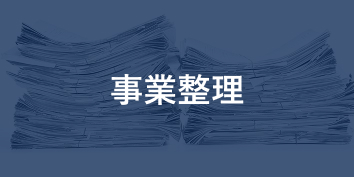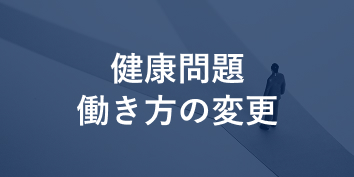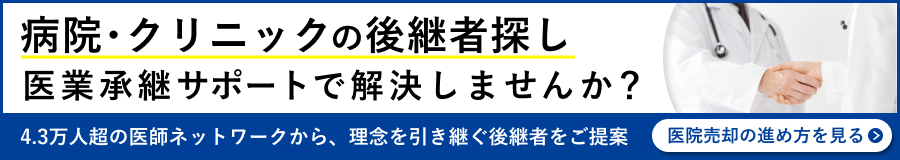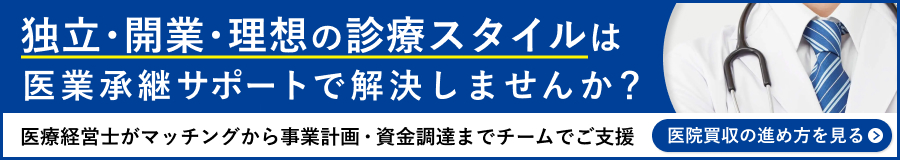【東京×循環器内科】多額の負債を抱えた状態から医院継承に成功した医療法人

クリニックを新規で開業する際は、銀行から開業資金を借り入れることが一般的です。しかし、実際に医業経営を進めると予定通りの収益が上がらなかったり、不測の事態が生じたりして、融資の返済が負担になってくるケースがよくあります。
本件は、債務超過にまで陥ってしまった医療法人が、M&Aで譲渡できた事例をご紹介します。
【売り手側】経営トラブルにより債務超過状態の医療法人石橋会、柿本理事長(70歳)
本件で売り手となったのは、東京都某市にある医療法人石橋会(仮称)の理事長、柿本先生(仮名)です。
医療法人石橋会では、19床の有床診療所である石橋クリニックを運営していました。診療科目は、柿本先生の専門である循環器内科が中心です。柿本先生はクリニック開業当初から、心臓をはじめとした循環器系の手術の執刀も担当してきました。
同地域では、心臓の手術にも対応できる循環器系のクリニックが希少であったため、広域から患者が来院し、開院からしばらくの間は石橋クリニックの収益は好調でした。
しかし、柿本先生は5年ほど前から比較的ハードな循環器系の執刀を行うことや、その後の夜間当直を担当することが、体力的に厳しく感じるようになります。また、以前は柿本先生以外に非常勤で勤務している医師が1名いたのですが、マネジメントの難しさにより退職してしまい、柿本先生にかかる負担が増大していました。
そのため、ここ数年は心臓系の執刀は行っておらず、比較的軽い処置となる睡眠時無呼吸症候群患者の口蓋手術などを中心に対応していましたが、オペの実施数減少に伴って収益性も低下傾向にありました。
医療法人を共同経営していた弟との対立により、債務超過状態に
石橋クリニックの収益性は黒字であったものの低下傾向にあり、財務面では厳しい状態でした。それは、以下のような事情があったためです。
15年前のクリニック開業時、医療法人石橋会は銀行から開業費として4億円を借り入れました。主な使途は、クリニック建物の建設費(土地は借地)や医療機器代です。
クリニックの開業費として、4億円はかなりの高額です。当初は10年で返済できる予定でしたが、想定外の事態に見舞われてしまいます。
実は当時の医療法人石橋会では、石橋クリニック以外にも内科診療が中心の石橋内科医院を運営していました。つまり、石橋クリニックは石橋会が運営する2院目のクリニックだったのです。そして、この石橋内科医院の収益や経営実績があったために、銀行も4億円という高額の融資に応じてくれたのでした。
医療法人石橋会は柿本先生が理事長を務めていますが、柿本先生の弟で内科医の佐藤先生も理事となっていました。そして石橋クリニックの開院後、同クリニックは柿本先生が院長、もともとあった石橋内科医院は佐藤先生が院長を務めるという役割分担をしていました。
ところが、石橋クリニックの開業から5年後に、医療法人石橋会の経営方針などをめぐって柿本先生と佐藤先生に対立が生じました。さまざまな話し合いを行ったのち、佐藤先生は石橋会の理事を退任することとなります。その代わりとして、石橋内科医院は事業譲渡の形で佐藤先生が譲り受けました。
その際、佐藤先生は医療法人への出資持分もあったため、出資持分の払戻金を含めた退職金として多くの額を法人から支払いました。この支払いをきっかけとして、医療法人石橋会の貸借対照表は、純資産がわずかにマイナスの債務超過状態に陥ってしまいました。
また、キャッシュフローも悪化したため、銀行融資の返済額を減らす返済条件の変更、いわゆるリスケジューリングをせざるを得なくなってしまったのです。
70歳を超えて負債の返済を続けていくより、M&A譲渡を決断
M&Aの検討を開始した際、融資の負債残高は2億円ほどでした。上記の事情に加えて収益低下傾向もあったので、これまで通りに返済を続けたとしても、完済までには10年以上かかりそうです。融資を受けている主体は医療法人ですが、その負債には理事長である柿本先生も個人保証をつけています。
70歳を過ぎて体力の衰えを感じはじめた柿本先生は、現在と同じように働いて長期的に融資を返済していけるかが不安になってきました。
医療法人のキャッシュフローでは融資返済を優先してきたため、柿本先生が受け取っている報酬も決して多い金額ではありません。
柿本先生は独身で子どももいませんでしたが、それだけに老後の生活資金面も心配になってきました。医療法人の後継者も決まっていません。
そのような不安を感じていることをメインバンクである花園銀行(仮称)の担当者に話したところ、年齢的なこともあるので医療法人をM&A譲渡して債務を整理してはどうか、という提案を受けたのです。柿本先生は、前向きに検討してみることにしました。
【買い手側】積極的なM&A譲り受けで急成長する医療法人あおば会
私たちは、花園銀行を通じて柿本先生のご紹介を受け、M&Aの仲介を依頼されました。
2億円の負債残高や債務超過などの条件があると聞くと、通常はかなり売り手に不利なイメージを持たれるでしょう。しかし、私たちが下記のような点を前面に出して買い手を募ったところ、多くの買い手候補からオファーが得られました。
- 19床を持つ希少な有床診療所であり、クリニックの建物や設備もしっかりしていて当面活用可能である点。
- 手術数や病床稼働率の減少により収益も落ちているが、それらを回復可能な診療体制を構築できれば、高い収益性が見込まれる点。
- 同クリニック隣接エリアの市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)の指定が、近い将来に外される予定であり、人口増加が見込まれる点。
譲り受けの意欲を示す買い手は、個人・法人合わせて10者近くに上りましたが、最終的に買い手となったのが、医療法人あおば会(仮称)です。
あおば会は、設立から10年ほどと歴史は浅いものの、M&Aを積極的に活用した拡張路線により、関東・東海エリアで20院以上の病院やクリニックを運営している急成長中の医療法人です。多くの買い手候補からオファーを受けた中で、最終的にあおば会との契約に至った理由は、医療に対する対応力に加えて同会の財務力が大きな理由でした。
■■■よく読まれている記事■■■
資金と医師の2つの問題をクリアして承継の実現へ
石橋会は出資持分のある医療法人であるため、M&Aのスキームとしては医療法人の持分譲渡+(医療法上の)社員交替という一般的な方法になります。
譲渡される持分の対価については、石橋会が債務超過、つまり貸借対照表上の純資産がマイナスであるため、原則的には「ゼロ」と評価されます。
ただし、石橋会の負債2億円は、新たに石橋会を運営していく買い手が引き受けて返済することになります。仮に持分の対価をゼロと評価して譲渡したとしても、実質的には、買い手は2億円で石橋会を譲り受けたのと同じということです。(ただし本事例では、持分の対価額も若干支払うことにしました。詳細は後述します。)
その際の主債務者は石橋会ですが、柿本先生も連帯保証人となっているため、柿本先生の保証債務を外すためには、債権者である花園銀行の承諾を得なければなりません。
もとより、この案件は花園銀行から相談を受けたものなので、花園銀行の意向を無視して進めるわけにはいきません。そして、債務を買い手に移行するには、主に4つの方法が考えられます。
- 連帯保証人を買い手に変更する
- 買い手の法人が新たに花園銀行から融資を受ける(石橋会としての負債は返済する)
- 買い手が他行から融資を受け、石橋会の負債を返済する
- 買い手が自己資金を用いて石橋会の負債を返済する
いずれにしても、買い手に花園銀行が納得できる信用力があるか、または2億円を用意できる財務力が必要になります。そして最大のポイントとして、M&Aの条件を詰める最終段階にならなければ、1~4のどの方法を用いることができるのか、はっきり見通せない点があります。
そのため、どの方法を用いることになった場合でも資金が調達できる信用力と財務力が買い手に求められました。
先に述べたように買い手候補の手は多く挙がったのですが、この信用・財務上の点から、あおば会がベストな買い手となりました。「当てにしていた資金調達方法がダメだったから、M&Aもご破算に」となることは、全ての関係者にとって避けたい事態です。
M&Aでは、その種の資金調達トラブルで破談になることは、決して珍しくありません。実際、本件もその懸念が現実化する一歩手前だったのです。
想定していた花園銀行からの借り換えが不可になり、買い手の自己資金を拠出
当初は花園銀行と売り手および買い手を交えた話し合いの中で、口約束レベルではあるものの、2のあおば会への融資という方向で話が進められていました。
ところが、最終契約に近い段階で、花園銀行からあおば会への融資が難しい状況となりました。2億円となると支店の決裁権限を超えますが、本部の決裁が取れなかったという理由でした。
そこで一悶着あったものの、結局あおば会は一部を他行からの融資を受けつつ、大半を自己資金で拠出して、花園銀行へ2億円の借入を返済することとしました。
本件はあおば会にそれだけの財務的な余力があったため最終契約に至りましたが、もしそうでなければ、破談になってしまっていたことでしょう。売り手の財務状態に鑑みて、財務力のある買い手を選定するという方針は、正しかったのです。
M&A後も売り手の理事長は、当面そのまま残留することに
本件で検討すべき事項として、資金的な問題と合わせて、M&A後の医療提供と収益向上面の課題もありました。
あおば会は主に整形外科を中心として病院の展開をしており、循環器で院長を務められる人材がグループ内にはいなかったのです。その点については、M&A後数年間は柿本先生が理事長かつ院長として留任するということで合意できました。柿本先生は、いわゆる「雇われ理事長」になるということです。
そこで、あおば会は債務超過であるため価値がゼロである医療法人持分に、1,000万円ほどの価格をつけて譲り受けることとしました。つまり、柿本先生との契約金のような意味合いと捉えることができます。
柿本先生にとっては、本来であれば自分が返済しなければならなかった2億円の債務保証がなくなった上に、1,000万円の譲渡対価が得られました。
また、今後数年間は慣れた職場で診療を続けられることとなりました。加えて、あおば会からの資金拠出により石橋会のキャッシュフローが改善され、柿本先生に支払われる報酬もM&A前より増額となり、柿本先生は大満足でした。
一方、あおば会にとっては循環器内科の現場管理を柿本先生に任せつつ、新たに整形外科を掲げることにしました。整形外科にはグループ内の医師を勤務させ、病床稼働率を上げれば収益性を高めることができます。いずれは循環器内科で柿本先生の後継となる医師も採用する予定です。
理想の後継者と出会う承継を、あなたにも。
エムステージでは、医師の理念や地域への想いを尊重した、最適な医業承継をお手伝いしています。
>医院継承をエムステージ医業承継サポートに相談する(無料)
本事例のポイント
最後に、本事例のポイントをまとめます。
①多額の負債があり債務超過の医療法人でも、M&A譲渡は可能
売り手法人に多額の負債があったり、債務超過状態であったりすると「再生案件」と呼ばれて、一般的なスキームでのM&Aが難しくなるケースもあります。
しかし、そのような財務状況でも、売り手の持つ収益力などのポテンシャルをしっかりと伝えることができれば、買い手とのマッチングは可能です。
②融資の返済スキームを複数パターン立案できたこと
医療機関のM&Aでは、売り手の求める医療理念や医療技術の水準にふさわしい買い手であることが重要です。
しかし、多額の負債のある案件では、買い手の資金力も重要なポイントになります。
本件も、買い手が複数のパターンで資金調達が可能であることをあらかじめ確認できたことが、最終契約に至るまでの重要な要素となりました。
③M&A後の医療提供体制の構想についても、合意できたこと
19床を持つ規模の大きいクリニックであったため、M&A後の収益改善のポイントは、いかに病床の稼働率上げていくかにありました。
その点で、売り手の柿本先生に当面残留してもらいつつ、買い手が得意とする診療科を増やすといった、柔軟な医療提供の構想で合意できたこともポイントとなりました。
本件のように、債務超過にまで陥ってしまい頭を悩ませている場合は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。解決策が見つかるかもしれません。
※案件情報の秘匿のため一部改編しています
医業承継の「実現力」を求めるなら、エムステージ。
高額スキームや複雑な家族構成、理念重視の買い手選定まで──医療に特化したM&A支援で、あなたの承継を成功へと導きます。
>医院継承をエムステージ医業承継サポートに相談する(無料)