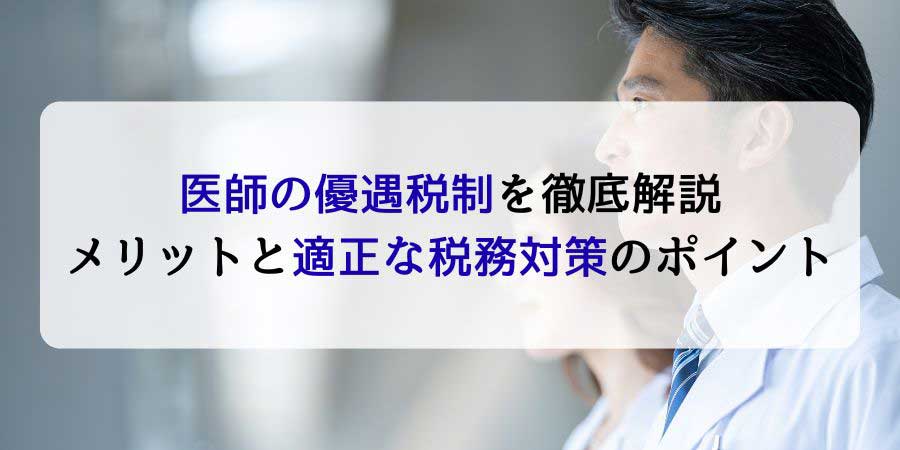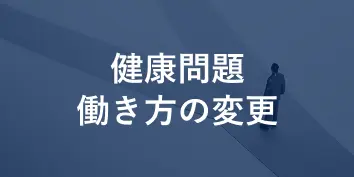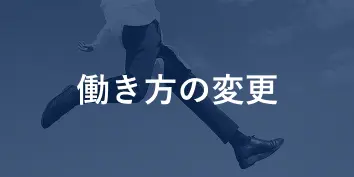減価償却明細書の書き方とは?確定申告の添付義務や注意点を解説

目次
クリニックの経営では建物をはじめに、医療機器など数多くの固定資産を取得します。
これらの資産は「減価償却」という会計処理が必要になり、その管理には「減価償却明細書」という書類が重要な役割を果たします。
しかし減価償却明細書について「作成方法がよくわからない」「確定申告で提出しなければならないのか?」といった疑問を持たれるクリニック経営者の方も多いでしょう。
本記事では、減価償却明細書の基本的な内容から作成方法、医療機関特有の注意点まで、わかりやすく解説しています。
減価償却明細書を適切に作成し、税務調査への備えや経営状況の正確な把握につなげましょう。
減価償却明細書とは
減価償却明細書とは、事業で使用する固定資産の減価償却費を計算し、その内容を一覧で記録した書類のことです。
減価償却とは建物や医療機器などの固定資産を取得した際、その取得費用を耐用年数にわたって分割して経費計上する会計処理を指します。
たとえば耐用年数が6年のCT装置を300万円で取得した場合、減価償却費として毎年50万円ずつ経費計上できる税負担の軽減措置です。
減価償却明細書には、主に以下のような情報が記載されます:
- 資産の名称(CT装置、超音波診断装置など)
- 取得年月日
- 取得価格
- 耐用年数
- 償却方法(定額法または定率法)
- 当期の減価償却費
- 未償却残高
固定資産台帳との違い
減価償却明細書と混同されやすいものに「固定資産台帳」があります。
固定資産台帳は、減価償却の対象となるすべての固定資産の情報を「網羅的に記録する帳簿」です。
一方で減価償却明細書は、その固定資産台帳の情報をもとに「減価償却費の計算過程を具体的に示した書類」です。
| 固定資産台帳 | 減価償却明細書 |
| 固定資産の取得から廃棄・売却まで、資産の詳細な履歴を記録法人の場合は会社法により10年間の保管義務がある | 減価償却費の計算に特化した書類税務申告時の根拠資料や償却資産申告で使用 |
固定資産台帳は資産の「全体像」を把握するもので、減価償却明細書は「減価償却費の計算過程」に焦点を当てた役割の違いがあります。
確定申告で減価償却明細書の添付義務は無い
確定申告において、減価償却明細書の添付は原則として義務ではありません。
青色申告決算書には「減価償却費の計算」という欄があり、ここに必要事項を記載するだけで問題なく、減価償却明細書の添付は不要です。
減価償却明細書の添付が必要になるケース
確定申告で原則として添付義務がない減価償却明細書ですが、以下のケースでは添付が必要になります。
- 法人が少額減価償却資産の特例制度を受ける場合
- 各自治体への償却資産の申告時
それぞれ詳しく解説します。
法人が少額減価償却資産の特例制度を受ける場合
医療法人が「少額減価償却資産の特例制度」を利用する場合、法人税の確定申告で減価償却明細書の添付が必要になります。
“この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。”
出典:国税庁|中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
少額減価償却資産の特例制度は、30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できるので、医療法人にとっても特に活用機会の多い制度と言えます。
【30万円未満の資産となる一例】
- パソコンやタブレット端末
- 小型の医療機器(血圧計、体温計、聴診器など)
- 事務機器(プリンター、複合機など)
- 什器備品(診察台、椅子など)
この特例を適用することで、取得した年度に全額を損金算入でき、医療法人の税負担軽減につながります。
なお個人の開業医の場合は前述した通り、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の項目に必要事項を記載するだけで問題なく、減価償却明細書の添付は不要です。※
出典:国税庁|「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について
各自治体への償却資産の申告時
毎年1月31日までに行う「償却資産の申告」では、各自治体に減価償却明細書(償却資産申告書)の提出が必要となる場合もあります。
参考:東京都主税局|固定資産税(償却資産)
この申告自体は、所得税や法人税とは別の固定資産税に関するものなので、事業用の償却資産を所有している場合は必ず行わなければなりません。
医療機関の場合、医療機器や什器備品などが申告対象となります。
医療機関の資産で減価償却の対象になるもの・ならないもの
医療機関が所有する資産には、減価償却の対象となるものと、ならないものがあります。
誤った償却をしないためにも、それぞれを明確に把握しておきましょう。
減価償却の対象になるもの
医療機関が所有する中で、減価償却の対象となる主な資産は下記のとおりです。
| 項目 | 主な対象資産 |
|---|---|
| 建物 | 診療所や病院の建物そのもの |
| 医療機器 | CT装置やMRI装置超音波診断装置X線撮影装置心電図計内視鏡人工呼吸器手術台その他10万円以上の医療機器 |
| 什器 | 診察台待合室の椅子やテーブル受付カウンターパソコン複合機エアコン冷蔵庫 |
参考:国税庁|減価償却のあらまし
減価償却の対象にならない
下記の資産に関しては、減価償却の対象にはなりません。
【土地】
土地は基本的に、時間の経過による価値の減少は無いと考えられているため、減価償却の対象外です。そのため、診療所の敷地や駐車場用地などは減価償却ができません。
【10万円未満の消耗品や備品】
取得価額が10万円未満の資産は、取得時に全額を経費計上できるため、減価償却の対象外です。たとえば少額の事務用品や体温計、注射器なども該当します。
【単価が20万円未満の資産】
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、「一括償却資産」として3年間で均等償却する方法を選択できます。たとえば、18万円のパソコンを取得した場合、3年間にわたって毎年6万円ずつ減価償却費として計上可能です。この方法のほうが、償却資産税の申告対象外となるメリットがあります。
出典:国税庁|減価償却のあらまし
減価償却明細書を作成する理由
基本的に確定申告において義務ではない減価償却明細書を、わざわざ作成するのは主に3つの理由があるからです。
- 計算ミスを防止するため
- 税務調査に備えるため
- 経営状況を正確に把握するため
それぞれ詳しく解説します。
計算ミスを防止するため
減価償却明細書があれば、一つひとつの資産をきちんと管理できるので計算ミスが防げます。
複数の固定資産がある場合、それぞれの償却方法や耐用年数が異なるため、手作業で計算するとミスが発生しやすくなります。
【発生しやすいミス】
- 耐用年数の設定間違い
- 償却率の計算間違い
- 未償却残高の計算間違い
減価償却明細書を作成することで、計算過程が明確になり、正確に減価償却費を算出できます。
税務調査に備えるため
税務調査が行われる際には、税務署から減価償却費の計算根拠を問われる可能性もあります。
その際に減価償却明細書を作成しておけば、すぐに提示ができて説明もスムーズです。
医療機関は高額な医療機器を多数保有しているため、減価償却費の金額も大きくなる傾向にあります。
そのため税務調査では、特に減価償却の内容に関しても重点的にチェックされるので、減価償却明細書の保管が重要です。
経営状況を正確に把握するため
減価償却明細書を作成することで、クリニックの経営状況をより正確に把握できるようになります。
たとえば、どの医療機器がいつ減価償却終了となるか、買い替え時期の目安を立てることが可能です。
また適切な減価償却費の計算によって、医療機関の損益状況を正確に把握できます。
特に医療機関は高額な医療機器を多数保有しているため、これらの資産状況を正確に把握することは、健全な経営を維持するうえで欠かせません。
減価償却費の計算方法は2種類
減価償却費の計算には、主に「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。
どちらの方法を使用するかは個人事業主と法人で異なり、また資産の種類によっても決まっています。
| 個人事業主 | 法人 | |
| すべての資産について定額法(医療機器や車両、什器備品については、税務署に届出書を提出することで定率法を選択可能) | 原則定率法となる資産 | 必ず定額法となる資産 |
| 医療機器・車両・什器備品 | 建物・建物附属設備(エレベーターなど)ソフトウェア | |
それぞれの計算方法を詳しく解説します。
定額法
定額法は毎年同じ金額の減価償却費を計上するため、計算が簡単で理解しやすいのが特徴です。
【定額法の計算式】
| 年間減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 |
【具体例】
600万円のMRI装置(耐用年数6年)の場合
| 年間減価償却費 = 600万円 × 0.167※ = 100.2万円 |
※定額法の償却率は国税庁の「減価償却資産の償却率等表」を参照。
定額法は毎年同じ金額の減価償却費が計上されるため、長期的な資金計画を立てやすいのがメリットです。
定率法
定率法は、未償却残高に一定の率を乗じて減価償却費を計算する方法です。
そのため取得初年度の減価償却費が最も大きく、年々減少していくのが特徴です。
【計算式】
| 年間減価償却費 = 期首未償却残高 × 定率法の償却率 |
【具体例】
600万円のMRI装置(耐用年数6年)の場合
| 1年目:600万円 × 0.333※ = 199.8万円2年目:400.2万円 × 0.333 = 133.3万円3年目:266.9万円 × 0.333 = 88.9万円 |
※定率法の償却率は国税庁の「減価償却資産の償却率等表」を参照。
定率法の場合、初期の減価償却費が大きいため、取得初年度の節税効果が高いのがメリットです。
個人の開業医の場合は「医療機器・車両・什器備品」に関しては定率法も選択できます。
医療法人の場合は、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法のみとなります。
減価償却明細書に記載する項目と書き方
減価償却明細書には償却資産の詳細がわかるように、様々な項目を正確に記載しなければなりません。
ここでは減価償却明細に記載する、主な項目の概要を解説します。
科目
科目には資産の種類を表す「勘定科目」を記載します。
医療機関でよく使用される科目は以下のとおりです。
- 建物
- 建物附属設備
- 構築物
- 医療機器
- 器具備品
- 車両運搬具
- ソフトウェア
資産名
資産名には、具体的な資産の名称を記載します。
医療機器の場合は、機種名まで詳しく記載することが望ましいです。
【資産の名称記載例】
- CT装置(◯◯社製××型)
- 超音波診断装置(△△社製××型)
- 電子カルテシステム
- 診察台(内科用)
取得年月
資産を取得した年月を記載します。
医療機器などの場合は「使い始めた日」が基準となります。
たとえばCT装置を導入した場合。
3月:購入契約を締結して代金を支払う
4月:機器が病院に納入される
5月:設置工事や調整作業を実施
6月:動作確認や安全検査が完了し、実際に患者の診療で使用開始
上記の場合、取得年月は「6月」と記載します。
取得価格
取得価格には、資産を取得するために支払った金額を記載します。
つまり分割払いであったとしても、購入した価格を記載します。
また設置費用や運送費などが発生していた場合には、それらも含めて記載しなければなりません。
未償却残高
前期末時点での未償却残高を記載します。
つまり購入した年の場合は、取得価額と同額になります。
耐用年数
税法で定められた資産の法定耐用年数を記載します。
医療機器の主な耐用年数は以下のとおりです。
| 6年 | 内視鏡CT装置MRI装置心電図計X線撮影装置超音波診断装置 |
出典:国税庁|耐用年数
上記は「新品」で購入した場合の耐用年数です。
中古で購入した場合には、下記の方法(簡便法)で耐用年数を算出します。
法定耐用年数をすべて経過している場合:法定耐用年数 × 20%(最低2年)
法定耐用年数の一部を経過している場合:(法定耐用年数 – 経過年数)+ 経過年数 × 20%
償却率
選択した償却方法(定額法または定率法)に応じた償却率を記載します。
購入した年によって償却率が異なるため、減価償却資産の償却率等表を参照にして、正確に記入する必要があります。
月数
当期中に減価償却資産を事業で使用した月数を記載します。
期中取得の場合には、月数按分が必要です。
【具体例】
4月決算の医療法人の場合
| 取得日 | 月数 |
| 4月1日 | 12(4月〜翌年3月) |
| 10月1日 | 6(10月〜翌年3月) |
| 1月15日 | 3(1月〜3月) |
月の途中で取得した場合でも、その月に事業で使用を開始していれば、その月を1か月として計算します。
当期償却費
当期に計上する減価償却費の金額を記載します。
期の途中に購入した資産に関しては、年額を12で割って月数を乗じた金額を記載します。
【期の途中で購入した場合の登記償却費の計算例】
600万円のMRI装置(耐用年数6年、定額法)を10月1日から使用
- 年間減価償却費:600万円 × 0.167 = 100.2万円
- 使用月数:6か月
- 当期償却費:100.2万円 × 6/12 = 50.1万円
期末簿価
期末簿価とは、取得価額からこれまでに計上した減価償却費の累計額を差し引いた残額のことです。
つまり帳簿上における、その資産の残っている価値を表しており、期末時点での帳簿価額(未償却残高)を記載します。
翌期の期首未償却残高となり、翌期の減価償却計算の基礎となります。
医療機関が減価償却明細書を作成する際の注意点
減価償却明細書を作成する際には、いくつかの注意点があります。
ここでは特に医療機関が注意しなければならない点を3つ解説します。
医療機器などの取得年月は「使い始めた日」を記載する
減価償却の開始時期は「購入した日」ではなく、「実際に事業で使い始めた日」を基準とします。
“「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます”
出典:国税庁|事業の用に供した日
たとえば3月にCT装置を購入し、設置工事や調整などを経て、実際に使用したのが6月だった場合、減価償却の取得年月は「6月」です。
「購入したけど実際に使い始めたのは数か月後だった」というケースは注意しなければなりません。
適切な減価償却期間を設定する
資産の種類ごとに定められた法定耐用年数に基づき、適切な減価償却期間を設定する必要があります。
耐用年数が長すぎると毎年の償却費が少なくなり、短すぎると税務署から指摘を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
関連記事:減価償却期間が長いメリットとは?期間の設定と見直しのタイミングについても解説
償却方法は原則変更ができない
一度選択した償却方法(定額法または定率法)は、原則として変更できません。
変更したい場合には税務署への届出が必要となりますが、認められない場合もあります。
償却方法は慎重に選択しましょう。
償却途中に医療法人成りした場合は新たに耐用年数を設定する
個人のクリニックから医療法人化した場合、個人から法人への資産移転が発生します。
この際に償却途中の資産価額と残存している耐用年数を、新たに設定しなければなりません。
医療法人成りは税務上複雑な処理が発生するため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:減価償却明細を作成して経営状況を明確にしましょう
減価償却明細書は確定申告での添付義務はありませんが、適切に作成することで計算ミスの防止や税務調査への備え、経営状況の正確な把握が可能になります。
特に医療機関は高額な医療機器も多いため、減価償却費の計算が重要です。
また、適切な減価償却の管理は、将来的に医院継承を行う場合の承継価格の算定においても重要な要素となります。
医院継承は準備期間が1年以上必要になることもある大きな決断です。
いざというときにスムーズに進められるように、あらかじめ専門家と関係を築いておくことも重要です。
将来的な医院継承に関して少しでもご興味がありましたら、医療分野に詳しい私たち「エムステージマネジメントソリューションズ」までお気軽に無料ご相談ください。
▶医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。
この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計50件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。